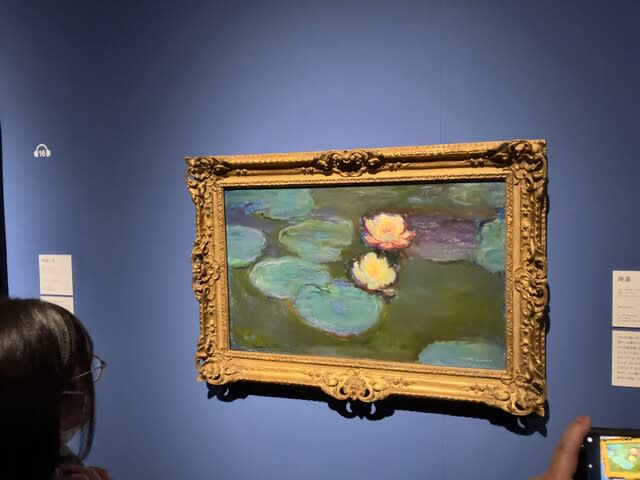ダニエル・クレイグのボンド3作目、「007スカイフォール」をテレビで録画して観た。2012、米、監督サム・メンデス、原題Skyfall。第1作目「カジノロワイヤル」は非常に面白かったが、第2作「慰めの報酬」はちょっと期待外れだった。その上で今回の第3作目はどうか、一度観たことがあるが、テレビで放映してたのでまた観たくなった。

各国のNATOの工作員を記録したMI6の情報が奪われ、ボンドは犯人パトリスを追いつめるが、新人女性エージェントのイヴ(ナオミ・ハリス)の誤射で橋の上から谷底へと落ち、死亡扱いににされてしまう。その直後、パトリスによりMI6本部が爆破される。
その後ボンドは再びMのもとへ復帰、パトリスを追って上海に行くが、殺してしまい手がかりを失う。パトリスの所持品のカジノのチップをヒントにマカオに向かい、カジノでパトリスの仲間らしい女性・セヴリン(ベレニス・バーロウ)を知り、彼女から黒幕は元MI6エージェントであったラウル・シルヴァ(ハピエル・バルデム)を突き止める。
シルヴァはMに恨みを持っていた。格闘の末、シルヴァを拘束したが、MI6の本部から逃亡される。Mが議会でその責任を追及されている時、シルヴァが急襲したたため、ボンドはMを連れて今は住む者のないスコットランドの彼の生家「スカイフォール」へ逃れ、シルヴァを誘い込み、そこで最後の決戦に臨む。

相変わらず話が複雑で、予習をしていないと映画が理解できない。その上で、この映画の感想を述べてみよう。
- 今回の第3作目は、第2作目よりもだいぶ面白かった。映画冒頭のイスタンブールのグランバザールでの格闘シーンは迫力あったし、その後のカーチェイス、列車の上での格闘シーンも面白かった。
- 舞台もイスタンブール、ロンドン、上海、マカオ、スコットランドなど魅力的な場所が選ばれている。マカオは行ったことがないが、それ以外は行ったことがあるところなので、見ていた楽しかった。
- Mが死亡し、その後任になった情報国防委員会の新委員長であるギャレス・マロリー(レイフ・ファインズ)は当初ボンドから典型的な官僚と非難されていたが、議会襲撃時に自らも銃を取り防戦し、負傷するなど、官僚らしからぬ実践力を見せ、ボンドからも一目おかれるようになるのが面白い。

楽しめました。