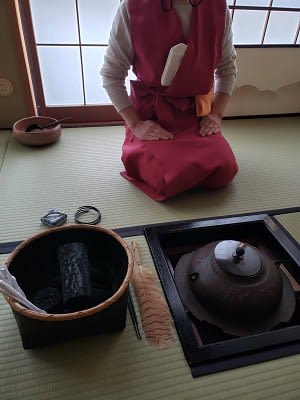初風炉の稽古まで二週間の休みです。
炉用の道具を片付けて、風炉の準備をします。
炉を塞ぎ、風炉を出します。
炭、炭道具、茶碗、香合、蓋置、柄杓、釜、等入れ替えます。

風炉は電気のものも用意しました。

十二単

小手鞠

卯の花・春壽菊

紫蘭
どの花も咲ききってしまい、初風炉までは持ちそうにありません。
困った。

タニウツギが咲き始めたので、これは使えるかな?
茶花には毎度苦労します。
炉用の道具を片付けて、風炉の準備をします。
炉を塞ぎ、風炉を出します。
炭、炭道具、茶碗、香合、蓋置、柄杓、釜、等入れ替えます。

風炉は電気のものも用意しました。

十二単

小手鞠

卯の花・春壽菊

紫蘭
どの花も咲ききってしまい、初風炉までは持ちそうにありません。
困った。

タニウツギが咲き始めたので、これは使えるかな?
茶花には毎度苦労します。