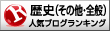無量寺(和歌山県串本町)
長澤芦雪(ながさわろせつ)が本州最南端の潮岬のある南紀・串本の無量寺の襖に描いた虎が、私は好きだ。
虎や龍は、日本の障壁画のモチーフとしてよく描かれている。虎は中国や朝鮮半島に生息していることが日本でも古くから知られており、“強いもの”の象徴である。龍は仏教の守護神である八部衆の一人であり、水の守り神でもある。
江戸時代以前の日本の絵師は生きている虎を見たことはないので、中国の絵画や敷物として輸入されていた虎の皮を見て、想像力を如何なく発揮して描いていたようだ。想像で描いたからであろうか、もしくはモチーフとしての演出を計算したのか、実際の虎よりも目が大きく丸長に描かれることが多い。獲物を負う鋭い眼光というよりも、神秘的に見える。
芦雪の無量寺の虎も実に目が大きい。獲物に目を付けまさに飛びかかるタイミングをうかがっているポーズで見る者を睨みつけているが、なぜか愛嬌がある。この虎は襖三面ほぼ一杯に描かれており、かなり大きい。そのため襖の前に座った寺を訪れる客人を威圧しないように計算したのか、胴体は細身で足がやたら長い。眼もご多分に漏れず大きくパッチリしているが、神秘的には見えず、虎ではなく猫に見えて仕方がない。視線が怖くないからだ。
芦雪は、江戸時代半ばの京都画壇のスーパースター・円山応挙の高弟の一人で、師の親しみやすさと静けさが同居したストイックな表現とは異なり、いたずら心を感じさせるところに特徴があると私は思う。彼が生きた18世紀後半の京都は、師の他にも曾我蕭白・伊藤若冲・与謝蕪村・池大雅といった現代の人気絵師を多く輩出した時代だった。そんな多くの絵師がいた中でも円山派は京都での人気は抜群で、応挙の弟子は千人近くいたと弟子の伝記に残されている。
芦雪は当時の絵師としては珍しく武家出身で、自己顕示欲が強かったようだ。そのため周囲の人に反感を買いやすかったのか、師からの破門説、死に至っては毒殺説がある。芦雪の画風には、そうした性格に起因するやもしれないが、人を魅了する「奇才」を生まれながらに持っていたことは間違いないであろう。
芦雪が串本の無量寺で襖絵を描いたのも、師の応挙の名代として派遣されたからだ。応挙もそれだけ芦雪の腕を認めていたと考えられる。芦雪は無量寺だけでなく、串本町古座の成就寺、白浜町富田の草堂寺、田辺市の高山寺など、南紀の海岸線沿いの各所に270点もの作品を残した。これらは無量寺の虎のように、写実を重視した師の画風から逸脱して自由奔放に描かれたものが多く、芦雪にとってはこの上ない旅だったことが想像に難くない。
芦雪が京に戻った後、南紀の寺に残された作品は地元の人々によって大切に守られてきた。無量寺にも1961年に地元の協力によって作品を公開する美術館が建てられた。みやこの最先端文化を間近に見られることへの人々の感謝の気持ちが、芦雪が残した作品から感じられる。無量寺の虎の眼は、私にはやんちゃ坊主に見えて仕方がない。いつ何度見ても愛くるしいのだ。心が和む。
芦雪や多くのスーパースターが京都で活躍していた頃、江戸では「大小絵暦」、現在で言う絵・写真付きのカレンダーが知識人の間で流行しており、そのニーズに応えるため多色刷りの錦絵(にしきえ)が明和2(1765)年に開発された。現代にイメージされるフルカラーの浮世絵が登場したことで、暦に使うのではなく、役者の宣伝といったメディアとして多様に使われるようになり、江戸が文化でも中心的な地位を築くようになる。京都画壇の絶頂期は、文化面での東京一極集中が始まった時代でもあったのだ。
日本や世界には、数多く「ここにしかない」名作がある。
「ここにしかない」名作に会いに行こう。
東京美術の「もっと知りたい」シリーズ。
画家を知るにはもってこいの一冊。
無量寺
休館日 なし(例外が発生する可能性もあるので訪問前にご確認ください)
公式サイト http://muryoji.jp/index.html