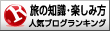賑やかな祇園の近くにこんな空間があります
建仁寺(けんにんじ)は臨済宗の開祖・栄西(ようさい)が鎌倉時代初期の1202(建仁2)年に京都で初めて開いた禅寺です。祇園の繁華街のすぐ南の拝観しやすい至近距離にあり、現在の祇園の街づくりに大きな影響を与えた寺でもあります。また日本で最も有名な屏風と言える「風神雷神図」を所有するほか、数々の障壁画の傑作でも知られています。
とても静かで大きな空を望め、京都を感じさせる庭が祇園のすぐ近くにあることも驚きです。
建仁寺は日本最古の禅寺と思われがちですが、最古は博多の聖福寺(しょうふくじ)で1195(建久6)年のことです。
建仁寺の建立には鎌倉幕府2代将軍・頼家の援助がありました。鎌倉幕府は自らに協力的な寺を京都に作りたかったのでしょう。寺名に創建時の元号が付けられていますが、これには天皇の特別な勅願が必要です。時の天皇と鎌倉幕府の駆け引きの産物であったこともうかがえます。
また当時京の都では天台宗・真言宗が強大な勢力で、新興宗教である禅宗が寺を開くのは大きな抵抗を受けました。そのため天台・真言・禅の三宗兼学の道場として出発し、既存勢力に配慮しています。
創建当初は大変な苦労がありましたが、室町時代になると幕府は禅寺を厚く保護し、五山文学の重要拠点として栄えました。「建仁寺の学問面(がくもんづら)」と京都市民にニックネームで呼ばれているのはこのためです。
明治の廃仏毀釈では境内のほぼ半分を政府に上納することになります。上納したエリアは現在の境内の北側から四条通までの間、花街の情緒を色濃く残す花見小路近辺です。
四条通の南側は、女子教育施設として設立された「女紅場(にょこうば)」がまとまって土地を所有しました。そのため四条通南部は雑居ビルが乱立するような乱開発を避けられ、風情のある街並みを残すことになりました。女紅場は現在も、舞妓・芸妓の教育施設として存続しています。

風神雷神図の前はいつも人でいっぱい
建仁寺は本坊を中心にいくつかの塔頭が取り巻いていますが、拝観は別々です。建仁寺の中心にあたる施設が「本坊」で、書院・方丈と法堂を廻る拝観コースが組まれています。
【公式サイト】 本坊の拝観可能エリア
本坊拝観で一番人気は、やはり俵屋宗達の「風神雷神図」です。きわめて精巧なレプリカですので常時展示されています。本物は京博に寄託されており、数年に一回くらいどこかの展覧会でお目にかかれる程度です。
建仁寺は京都の有名寺院では珍しく、室内外や絵画作品のほとんどが写真撮影OKです。「風神雷神図」は絶好のインスタ映えするモチーフになっています。
【公式サイトの画像】 海北友松「雲竜図」
方丈は、安土桃山時代に毛利の外交僧として知られた安国寺恵瓊(あんこくじえけい)が広島から移築したものです。障壁画が必見です。安土桃山時代のスーパースターの一人・海北友松(かいほうゆうしょう)の作で、親しかった安国寺恵瓊から方丈移築の際に製作を依頼されたものです。
堂々とした龍はとてもダイナミックで、襖からまさに飛び出てくるような迫力があります。しかしその目は優しく、仏法や水の守護神として方丈を包み込んでいるように感じさせます。こちらもレプリカですが、すばらしい京都の禅寺の室内空間を体験できます。

方丈庭園には時間を忘れて座れます
方丈南側の庭は、祇園の喧騒が近いとは思えないほど静かです。白砂と木々の緑のバランスに加えて大きな青い空を望むことができ、とてもすがすがしい気分になれます。時間を忘れるような空間がこんな便利なところにあるとは本当に大感謝です。ただし気持ち良すぎて居眠りしないでください。

思わず納得する立て札
行きやすいところにありすぎるのか、案外見逃しがちなことは否めません。同じ禅寺でも天竜寺ほどは混雑していません。お勧めする価値はとても大きい禅寺です。
こんなところがあったのか。
日本にも世界にも、唯一無二の「美」はたくさん。
迷ったら古寺巡礼シリーズを
建仁寺 本坊
http://www.kenninji.jp/
原則休館日:行事実施日
※仏像や建物は、公開期間が限られている場合があります。
「お寺・神社・特別公開」カテゴリの最新記事
 あの本能寺は今どうなっているか?_光秀と信長の夢の跡
あの本能寺は今どうなっているか?_光秀と信長の夢の跡 黄不動の彫像、世界最古のビザ_大津 三井寺の至宝が特別公開
黄不動の彫像、世界最古のビザ_大津 三井寺の至宝が特別公開 世界最高峰の天平彫刻と静かに向き合える_東大寺 戒壇堂 四天王
世界最高峰の天平彫刻と静かに向き合える_東大寺 戒壇堂 四天王 里山風景の中に美少年のような十一面観音_京田辺 観音寺
里山風景の中に美少年のような十一面観音_京田辺 観音寺 南山城に不思議な魅力の白鳳仏_カニがいっぱい蟹満寺
南山城に不思議な魅力の白鳳仏_カニがいっぱい蟹満寺 福岡 宗像大社_大陸との交流が封印された沖ノ島は素晴らしい世界遺産
福岡 宗像大社_大陸との交流が封印された沖ノ島は素晴らしい世界遺産 今しか見れない仁和寺の魅力_観音堂&御殿 特別公開 7/15まで
今しか見れない仁和寺の魅力_観音堂&御殿 特別公開 7/15まで 京都の”端っこ”はやはり素晴らしい_嵯峨野 愛宕念仏寺 ほのぼの石仏
京都の”端っこ”はやはり素晴らしい_嵯峨野 愛宕念仏寺 ほのぼの石仏 琵琶湖疎水の脇にたたずむ安祥寺、驚きの国宝美仏が伝わる
琵琶湖疎水の脇にたたずむ安祥寺、驚きの国宝美仏が伝わる 京都 大覚寺 王朝文化を伝える美仏と書_「天皇と大覚寺」展 5/13まで
京都 大覚寺 王朝文化を伝える美仏と書_「天皇と大覚寺」展 5/13まで