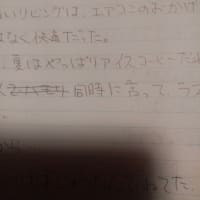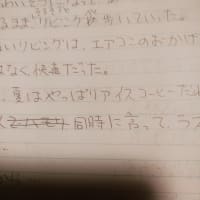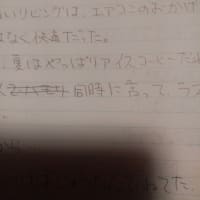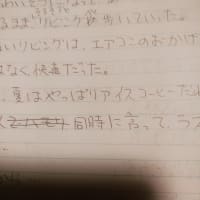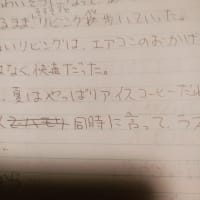言いながらも、諒は不安を覚えている。
また「別れて」とか嫌な条件を出されたらどうしよう…
しかし麻也は自分の腕をつかむ諒の手に自分の手を重ねて恥ずかしそうに、
「…こういうこと…」
と、頬を赤らめる。
諒は思わず身を乗り出して、
「え、いいの?」
「でも諒は大変だよね…?」
「ううん、全然。麻也さんとまた楽しくも喧嘩もありので一緒に暮らせるっていうなら、俺最高だよ」
(もしかして、マンションに暮らせるのかな)
「じゃあよろしくね。俺も体が良くなるように頑張るから」
「いやあんまり頑張らないで。ゆっくり静養してよ」
「諒の笑顔が一番の薬だから供給よろしくね」
麻也の穏やかな笑顔に誘われてしまい、諒は、
「麻也さんたら、もー、じゃあ早速…」
と、唇を奪おうとしていると…ドアがノックされて勝手に入ってきたのは社長と須藤と鈴木だった。
「諒、やっぱりここにいたのか」
「電話が通じないから心配したんですよ」
3人とも諒が引きずっていたラブラブモードにはお構いなしだ。
しかし社長はすぐに真面目な表情になり麻也を見すえて、
「麻也、諒から聞いたと思うけど、東京ドームでやらないかって話が来た」
するとどうしてか諒の方にも社長は厳しい目を向け、
「二人とも今日すぐに答えるとは言わないよ」
その一言は諒と麻也にとって意外だった。
すると社長はさらに、
「ドームは名誉だけど、そのステータスを維持するのは大変だろ? だからその決心が固まってからでいいよ」
「あ…」
それはどうしてか二人とも忘れていたことだった。
「まさかお前ら一生の記念に一回だけ立ちたいっていうわけじゃないだろ?」
言われてみれば確かにそうだ。
しかし社長は二人が一瞬黙ってしまったのを見て不安になったらしく、
「おいおい一回で終わらせるつもりだったのか?」
「いえ、考えたことがなかっただけで…何しろ急な話だったし…」
それは諒の本心だった。
先輩バンドが何度もやっているのを知っていたはずなのに、毎日の忙しさばかりに追われて忘れていたのだ。
社長は、
「ドームやったっていう肩書きは一生ついて回るからだよ。落ちぶれることは許されないんだ」
その言葉の重みに諒は黙り込んだ。
そして麻也が意地だけで引き受けなければいいなと思った。