|
『俳句四季』10月号 |
四季の美
良夜 草深昌子(青草)
みどり児に宛てて文書く良夜かな 昌子
難産の末に生れた孫を一か月ほど我が家で預かったことがある。朝から晩まで、泣いて泣いて泣き通しであった。火の付いたような泣き声には全くお手上げであった。
泣きながらも、じいっと考え込むような、何か深く見つめるような表情は、赤子にしてはちょっと怖いほどである。心配が昂じて、一家うち揃って病院へ連れて行ったが、赤子は泣くのが仕事と一笑に付されてしまった。
「一人の赤ん坊に、ぞろぞろと大のおとなが取り巻いて、ゆすったり、あやしたり、
あたふたしているのがいけないのです、赤ん坊はよくわかっていて、わざと困らせているのですよ」と見知らぬ夫人に叱られる始末。
生後一か月に満たない命に不安をかきたてられ、誰かに助けてもらいたいのは若きママより年老いた婆の方であった。
目覚めたる赤子の頬のふくらみて
かがやくごとき欠伸となりぬ 伊藤俊郎
秋風の赤子に眉の出できたり 昌子
赤子は生後二か月ともなると、オーオー、ウーウーと声を上げて上機嫌となった。
手足をバタバタさせ、ついには喉を鳴らして、顔じゅうを真っ赤にして乳を飲んでいる。
全身全霊で飲んでいる。そしてふっと、眉をひそめたりするではないか。
人は生まれ落ちたときからひとり、独りで戦っている。
私の好きな画家小倉遊亀が百五歳の長寿を全うされたのは、この頃であった。
「何はあれ、自分の力のありったけを尽くしたい。絵の上のみならず、嘘を言わず、
言い訳をせず、へこたれず、生のままにやっていくこと。画家の絵描き臭はこまりもの。
いつまでも素人としての初心さ、新鮮さで生きてゆきたい」と語ったのは晩年のいつ頃のことであったろうか。
かの大胆にもデフオルメされた裸婦の絵のタイトルは「月」また「良夜」である。
雲去れば雲来る望の夜なりけり 昌子
――これは十五夜との対面の句。雲一つない大月夜ではなく、どちらかと言えば雲は多い方である。大きな雲がつぎつぎにあらわれてはどこかへ消え望月を大空へ残してゆく。
望月の従来の情趣は一句から一掃され、代わりに満月をつぎつぎに追いかけるダイナミックな雲の運動をいきいきとつかんでいる――大峯あきら先生からいただいた最後の選評である。
俳人大峯あきらのポエジーの原点は、
芭蕉の「見る処花にあらずといふ事なし。思ふ所月にあらずといふ事なし」であった。
「月とか花とかいうのは景色ではなく、個体を超えた大きな命、命そのもののリズムである。
全ての生き物はこの根源的なリズムから逃れることはできない」と説かれた。
満月を見上げると思わず手を合わせるようになったのは、いつの頃からであろうか。
今は亡き師も、父も母も夫も、誰も彼も、月の命に生きてひとつ、皓皓たる光を放ってやまない。
青草俳句会
月今宵昭和の書籍片したり 伊藤 波
月光の子に引かれゆく駱駝かな 小原旅風
無月とな管球アンプに灯いれむ 伊藤欣次
百年の縁の木目や月祀る 山森小径
眠る前もいちど仰ぐ今日の月 石堂光子
名月や俳句人生一筋に 鈴木一父
ざつくりと家計簿つける良夜かな 古舘千世
月光のハチ公像に立ちにけり 米林ひろ
月代や舞台に上がるトウシューズ 加藤かづ乃
病窓の一つ一つに今日の月 佐藤健成
波寄せて過去か未来か月の道 松井あき子
花嫁の荷をとく母の良夜かな 奥山きよ子
月を背に一人踊るや芝に影 漆谷たから
となり家に瓜抱へゆく夕月夜 二村結季
七沢の月今生となりしかな 河野きなこ
臥待の月は山よりのぼりけり 間 草蛙
満月や兎はどこと子に問はれ 福山玉蓮
芝の上にわが影濃ゆき月今宵 石原虹子
月明のあたり一面真白なり 市川わこ
宵闇の葉擦れの音の街路かな 黒田珠水
名月や動くもの無き路地の奥 佐藤昌緒
門灯のまだついてゐる望の夜 堀川一枝
読み了へて静かに月を仰ぎけり 柴田博祥
海岸の巌に鑿あと月明り 川井さとみ
四海波静かなりけりけふの月 松尾まつを
(東京四季出版「俳句四季」令和元年10月号所収)










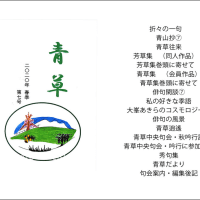



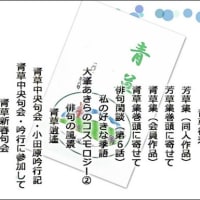
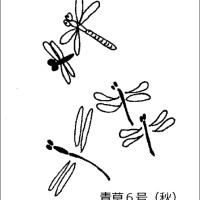




※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます