「青草」2020年春季(第7号)が令和2年2月に発刊されました。
さらに頁を増やして、内容の充実を計りました。
その一部をご紹介いたします。

青山抄(7) 草深昌子
欄干を跳んで蛙や秋の風
たまに来てすつかり秋の道であり
子規の忌の霞が関を過ぎりけり
底紅に看板出して鍛冶屋かな
今しがた蛇の失せたる臭木の実
寝姿の釈迦ある寺や新豆腐
秋夕べ地べたのやうな海の色
その人は遥か蜻蛉の群るるなか
秋暮れて一つ糸瓜を長くせり
豊の秋鴉のこゑのただ阿房
一亭は水に浮きたるやや寒う
宵月のニセアカシアの実と思ふ
ふと濠にさざなみたてて柳散る
大手門出でて大路や十三夜
幹太くなまめく鮎の下るころ
薔薇のほか無きが如くに秋の苑
あめんぼの大きくまはす水澄めり
部屋の名に山また川や雁渡る
たれかれと目の合ふ美男葛かな
小春日の珈琲買ひに行つたきり
(「俳壇」「俳句界」に発表を含む)
青草往来 草深昌子
芭蕉が『おくのほそ道』の旅に発ったのは元禄二年、西行の五百回忌の年である。令和元年は三百三十年を迎えるというので、都内で芭蕉展があった。芭蕉の真蹟はもとより芭蕉を慕った人々の書画が展示された。
野をよこにむま引むけよほとゝきす はせを
落款の「を」は意気揚々と撥ね上がっている。これに画を付けた森川許六の馬のふんばりも頼もしい。
馬からふと思い出されたのが、竹西寛子が、与謝蕪村の「奥之細道図」を褒め上げ、馬の尻尾の振り方までいいと書いていたことである。なるほど那須野の図など、馬上の芭蕉は飄々とありながら曾良と心を通わせているさまが偲ばれて、筆の先の先まで芭蕉への敬慕の念が滲み出ているものであった。
ふる池やかはつ飛込水の音 はせを
芭蕉の筆致は柔和でありながら、筆の入れかたや止めにはメリハリが利いていて筆は一息に走っている。
書道に疎いにもかかわらず、いちいち引き込まれたのは、その筆跡が俳句の内容と切っても切れぬ関係につながっているからであろう。
事実、芭蕉の書風は、俳風の展開に伴って変わっていったという。命をかけて推敲した一句一句の情は、まこと真摯に一字一字に乗り移っているのであった。
芭蕉展を出ると、旧友の姿が思い浮かんだ。ばったり出くわすたびに、「今日もこれですか?」と、左の手のひらを短冊に見立てて突き出すと、右手に筆をすべらす仕草を大げさにして見せるのである。俳句という文芸は今も矢立を手にした芭蕉と結びついてしまうのかと、恥かしくも笑ってしまうのであったが、実はこの即興こそが俳句の根本ではなかったか。
昨今は、筆はおろかペンさえも遠のき、パシャパシャとパソコンに打ち込むばかり、そんな私に友人は発破をかけてくれているのかもしれない。
俳句は芭蕉の文学であることを再認識するにいたって、せめて句帖には心のこもった文字を書き付けねばならないと気付かされたものである。










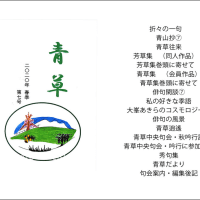



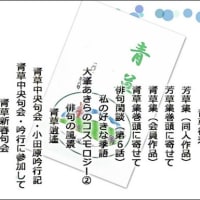
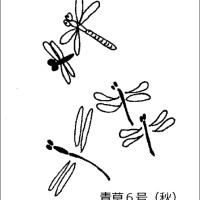




※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます