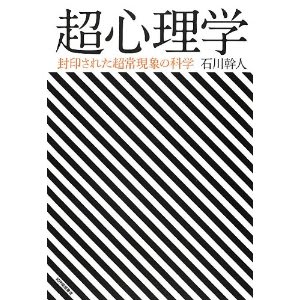語り部のアヴァンです!
山中先生、やりましたね~。お祝いに、「旅するマーメイドの神話」第一部人魚ナオミ篇第7章のドクトール・マッド登場のエピソードを再送させていただきます。アメリカ留学中に、利根川進先生がノーベル賞を受賞して、元気をいただいたことを思い出します。
本当に、今回は日本全体が元気をいただきました。心からお祝いを申し上げます。
________________________________
その日、マクミラはミシガン州に出かけた。
まだ30才代半ばの若さでゾンビーランド責任者に就任した、魔道斉人(まどう・さいと)博士と話し合いを持つためだった。かつては日本のある旧帝国大学で将来を嘱望される天才医学者だったが、「フランケンシュタイン計画」として知られる禁断のプロジェクトをおこなって大学を追われることになったのであった。
彼は、学内の倫理委員会の許可なしに、脳死患者の肉体で人体実験を繰り返した。もっとも脳死は人間の死であると主張して、それは「人体実験」とは言えないと自己弁護したらしいが・・・・・・
魔道は、中央棟の理事長室で待っていた。
ジェフとマクミラは、三匹の盲導犬、キルベロス、カルベロス、ルルベロスを連れて、エレベータを出るとドアをノックした。
「プリーズ、カムイン! 」
男が、完璧な英語で答える。
「おそくなってごめんなさい。こちらから遅い時間を指定しておいて」
マクミラのハスキーボイスが、日本語で答えた。
黒革のハーフコートに、レザージーンズを着た男が振り返った。
第7章―2 魔道とマッド
うっかりすると殺し屋と間違われかねないアウトフィットだったが、知的な顔立ちを見ればカレッジプロフェッサーのように見えないこともなかった。
「こちらこそ、辺鄙な山奥にご足労願って恐縮です。日本語がお上手ですね。一度、早い時期に貴方に会っておきたかったもので」
魔道を一目見た3匹が、うなり始めた。
「ヌーヴェルバーグ嬢は、どこにいらっしゃるにも3匹の盲導犬(盲導犬はSeeing Eye dog)をお連れと聞いていましたが、どうやらどう猛犬(seemingly excited dog)の間違いでしたか?」
「いいえ、盲導犬はつねに『親愛なる犬』ですわ。どうぞ、マクミラとお呼びください」
「わかりました。マクミラ、ここからは英語でお話ください。以前、ボルチモアで5年研究生活を送ったので、私もいちおうのコミュニケーションには困りません」
「いちおうのコミュニケーションですか・・・・・・」
一瞬、マクミラは冥界での神官時代を思い出した。
静かにするよう指示されて、今はおとなしくしているが、3匹はうなるのを止めただけでいつでも飛びかかれる姿勢を取っている。
「さっそく聞き難いことを伺いますが、アカデミックの世界を追われることになったいきさつをお聞かせいただければと思います」
「ご遠慮なく。長い話で、あなたが退屈しなければよろしいのですが」
「いいえ、これ以上興味深い話はないはずですわ・・・・・・フランケンシュタイン計画」
マクミラの口調が急に変わって、言った。
「だけどその前に、あなたの本当の人格に出てきてもらいましょうか」
「私の本当の人格とは?」
「わたしの心眼はごまかせないわ。他人の節穴はごまかせてもね。それにキル、カル、ルルもわかっているようだわ」
再び、うなり始めた3匹の盲導犬がだんだんと興奮していく。
「何をおっしゃっているのか、私にはわかりかね・・・・・・ウッ、頭が痛い・・・・・・」
突然、苦しみだした魔道の顔がゆがむ。
フッフッフッ! 最初からわかっていたな、とさっきとは別人の声が答えた。
整えられていた髪が逆立ち、両眼が鬼火のように燃え上がったかと錯覚するほど、力に満ちあふれた男がそこにいた。
「儂が魔道の影の人格、ドクトール・マッドじゃ!」
「こうこなくては。ミシガンくんだりまで来たかいがないわ。さあ、革フェチさん。いったい魔道とマッドとどちらがフェッチ(註、fetchは、死の直前に現れるといわれる生き霊)か教えてもらおうかしら」
青白い顔のまま、みるみるマクミラの唇に赤みが射してくる。
その時だった。キル、ルル、カルの周りに小さい爆弾でも破裂したような音がして、3匹が1匹の強大な魔犬ジュニベロスに変化した。
第7章―3 ネクローシスとアポトーシス
「儂の力を試してみるか?」
「あなた、不思議な波動ね。やさしさや憐れみを持たないくせに、悪意や傲慢さもない。そのくせ、とてつもない凶暴さを秘めている。上陸寸前の台風、爆発寸前の活火山、あるいはメルトダウンが始まりかけた原子力発電所とでも言えばよいかしら?」
「マクミラよ、気をつけて口を聞くがよい。今の儂は、脳髄のパワーが全開になっておる。かつて冥界の神官だったかどうか知らぬが、最高の英知を獲得した儂に対して気安い物言いではないか」
「気をつけるのはどちらの方? どちらにしても、人間の英知などたかが知れているのではないかしら」
そう言いながら、マクミラが背中から真っ赤な二条の鞭を取り出した。
彼女とマッドは、一触即発の雰囲気だった。
ジュニベロスの三首の口からもゆっくりと、だが着実に瘴気(しょうき)がはきだされて周りにただよっていく。
ジェフが、毅然と言う。「ドクトール、無礼ではないか? 初対面のレディに。これ以上、失礼があるなら私とケルベロスの息子たちが相手をするぞ」
今にも飛びかからんばかりのジュニベロスに気圧されたのか、マッドが言う。
「ふん、久しぶりに表に出たところにケンカ腰で、カッとなっただけじゃ。お転婆娘が鉾を収めるなら、儂にも、大人げない態度をとる理由はない」
「いいでしょう。わたしは、本性を隠して様子を見ようとする態度が気に入らなかっただけ。納得できるプランを提示するなら、ヌーヴェルバーグ財団は望むとおりの支援をしましょう。お互い駆け引き無しと、いこうじゃないの」
ジェフは、やれやれという心境だった。大切なマクミラに、こんなところでケガでもされては冥主プルートゥに会わせる顔がない。
「よかろう。話してやろうではないか。フランケンシュタイン計画、ふざけた名前がマスコミによってつけられたものだが。あれは今から11年前だった・・・・・・」
第7章―4 フランケンシュタイン計画
儂が目指していたのは、死人を別の存在として生き返らせることだったのじゃ。雷の晩につなぎ合わせた死体に電流を流すといった、非科学的方法ではない。
儂が目をつけたのは、アポトーシスと呼ばれるいらなくなった細胞が消えて、新しい細胞に取って変わられる過程じゃった。たとえば、オタマジャクシのしっぽが無くなってカエルの足が生えたり、醜い芋虫が美しい毒蛾に変態するのがそうじゃ。
人間も例外ではない。
胎児も、子宮の中で数千万年の人類の進化の歴史を繰り返す。受精した卵は、まず海洋生物に近い姿から、魚、両生類、爬虫類の姿を経て、だんだんとカバのような哺乳類の姿を経て、やっと人間らしい形になっていく。
生物の細胞は、アポトーシスと呼ばれる死を繰り返している。ネクローシスという病気によって細胞群の集団内で起こる受動的な崩壊過程と違って、アポトーシスは、細胞群の中で散発的に起こる古い細胞が新しい細胞に取って代わられる「積極的な細胞死」の自壊過程と考えられる。なぜなら身体は、細胞が別の形態に変化するのでなく、新たな細胞にとって変わられることでしか変態できないのじゃ。ほとんどの学者は、そのため不要になった細胞が自発的に死んで、きちんと除去されることが必要だと考えた。
しかし、儂は、これを本末転倒ではないかと疑った。
細胞死を発生させるのは、内部、まして外部からの誘因ではなく、変態パターンの必然性があるのではないかと考えた。ネクローシスが、エネルギーを長い時間をかけて漸次進行するのに対して、アポトーシスは、短期間に段階的に進行するしエネルギーを必要とする。必要な新細胞が生まれるために、古いじゃまな細胞を除去する一つの連続したプロセスこそアポトーシスなのではないか。それは単なる細胞死でなく、新旧細胞交代の一つのつながったプロセスではないのか? たとえば、カエルに足が生えるにはオタマジャクシのしっぽがなくならなければいけない理由があるのではないか?
この新旧細胞の交代メカニズムを解明すれば、人間を人間以前だった形態に戻したり、さらに人間を次の段階に変態させることが可能ではないかと考えたのじゃ」
第7章―5 ゾンビーソルジャー計画
「人間の身体は60兆個の細胞からなっているが、細胞の種類はたったの二百種類しかない。それが連絡を取り合って、秩序の取れた状態を生みだしている。
不要になったり、身体に害を与えるため「死ね」という指令を受けた細胞は、あらかじめ増殖や分化と同じように、すでに遺伝子に書き込まれている「自殺」のプログラムを起動させる。
身体自体が一つの組織で、組織のトップにいて指令を出すのが脳だとしたら、まだ我々の知らない指令系統が存在するのではないか? なぜなら人間の脳で、使われているのは10から30パーセントにすぎないと言われている。
もし残りのプログラムを活用できるように、かかっているプロテクターをはずせれば・・・・・・人間を従来の科学では想像もできない存在に作り替えられるのではないか?
まさに神の業の領域だ。
若かった儂は、このアイディアに夢中になった。
儂は何日も大学病院に泊まり込んでは、寝食を忘れてアポトーシスのコントロールに取り組んだ。研究は、遅々として進まなかった。仲間たちからも、そんなものが見つかればノーベル医学賞ものだよ、と冷やかされた。
あっという間に5年が過ぎていた。
嘲笑った学者の中には、30億あるDNAの遺伝子情報を読み込む「ヒトゲノム計画」を提唱する愚か者もいたが、あんなものは砂漠にまぎれこんだ一粒のダイヤを捜すのにも等しい。だいたい、ヒトゲノムの内、95パーセントはがらくたで、遺伝子を司るのは5パーセントほどしかないし、あいつらには読み込んだDNAをどのように操作するかの指針さえもない。
だいたい60兆もの細胞のどこを、どの程度まで差し替えることができると思っているのか? 早い時期の病気の診断や予防が可能になるというが、あんなものは保険業界や医療業界が得をするだけの代物に、巨額の税金をつぎ込むという暴挙を国家レベルで競っておるだけではないか。
そんな時だった。ヌーヴェルバーグ財団が資金を出すから、米国の名門私立大学の医学研究所にこないかと誘われたのは。儂は、天にも昇る心地だった。すでに日本の徒弟制度的な人間関係の中で独創的な研究を続けるのには疲れ果てていた。
開闢以来の秀才だった儂に、大学院時代こそ周りも期待したが、いつまでたっても出口どころか入り口さえ見えてこない研究に没頭する儂を、彼らは陰でマッド・サイエンティストと呼んでいたのじゃ」
第7章―6 転機
「6年前に魔道が、ニューヨーク州アルバニーの邸宅でヌーヴェルバーグ・シニアに会ってから儂の人生が始まった。
彼は、魔道に生命のすべての謎を解き明かす神導書アポロノミカンを見せようと言った。ヌーヴェルバーグが神導書を開いた瞬間、彼の頭の中のプロテクターが吹っ飛んで脳髄が100パーセントの割合で機能しだした。しかし、それは一人の人間が受けとめられる限度を遙かに超えていた。
その瞬間、誰かが叫んでいた。
だが、その叫びは、魔道自身のものじゃった。
知ってしまった知識の重みに耐えかねて、魔道は倫理や道徳心といったくだらない感傷を越えた存在、第二の人格であるこの儂、ドクトール・マッドを生みだした。儂は、魔道が寝静まっては起き出して脳死状態の死体を使っては、さまざまな実験を続けた。儂は、一度、活動停止した脳を再起動させて、ねらった命令を細胞に与えるさまざまな薬品や手術を試した。
もう少しで、研究の糸口がつかめそうになった時じゃった。学内から情報が漏れて、儂は身を隠さねばならなくなって、今お主の目の前にいるというわけじゃ。
マクミラよ、これがここまでの経歴に関する話よ。
研究の目的?
儂が研究したいのは、ゾンビーソルジャー計画じゃ。
人体をさまざまに変化させたゾンビ戦闘員を作ってみたいのじゃ。思考しないから恐れも知らず、傷ついても戦闘能力を失わず、最初から死んでいるから殲滅されるまで闘い続ける。彼らは、理想的なコンバッタントだとは思わないかね?
すでに気づいているのだろうが、人類の最大の脅威は人口問題だ。資源、難民、環境、国境を巡る問題さえそうだが、現代社会がかかえる重要な問題は、突き詰めればすべて人口が原因になっている。
必死になって寿命を延ばそうとしている先進国をよそに、途上国では内戦、貧困、飢餓、伝染病によって毎日数千、数万の人間たちが死んでいる。ゾンビーソルジャーは、期待通りに世界に混乱を招いてくれるだろう。人間が死ねば死ぬほど彼らの潜在的なメンバーが増えるとなれば、一石二鳥だとは思わないかね?
これ以上、あなたに協力するにはひとつ条件がある。
なに、実験結果の公表は無理だと?
バカを言っては困る。世俗的な名誉に対する興味など、とうに失っておるわ。儂が興味を持っているのは、自分の理論が正しいのか否かを検証することだけだ。
研究には完璧を期したい。ついては、中西部の極右団体を使ってパイロット・スタディを行いたい。アポロノミカンには、こんな一節があった。
・・・・・・こころざしをおなじゅうする者
南風の地につどいて戦いの宴に身をささげよ
十字架の戦士たちと競う瞬間
炎がすべてを包み
死への旅路が終わりをつげ
はじまりの旅が幕を切って落とされる・・・・・・
どうじゃ、カンザス州のどこぞの大学のキャンパスで試してみては?」
ランキング参加中です。楽しまれた方は、バナーをクリックしていただけるとうれしいです。

 にほんブログ村
にほんブログ村



 にほんブログ村
にほんブログ村