
妖怪というと、今では水木先生の作品に出てくる妖怪のイメージが強い。
だが、それは、たとえ古来から伝えられてきた妖怪でもあっても、先生の作品の中に出てきているのは、いわゆる「水木妖怪」であり、水木先生の作品の中で独自に性格づけさせられたり、独自に容姿を描かれたものが多い。
同じ妖怪でも、水木作品の中でのキャラと、それ以外の世界・・例えば伝承の中・・・でのキャラは違う場合は多いはず。
そのへんの対比みたいなものを知ってみたいなと思って買った本が、この本だった。
そういう点も多少描かれてはいたが、もう少しその辺は掘り下げてほしかった気もする。
まあ、妖怪というものは、人間の想像力が生んだ存在であることが多いことを考えれば、その対比を描くには限界もあるのだろう。
そういう対比を描くには、それぞれの妖怪の伝承の地を実際に旅して、現地の妖怪ゆかりの地の写真を撮ったり、現地での言い伝えがどんなものであるかをもっともっと紹介すれば、もっとよかったのではないだろうか。
取材費はかさむかもしれないけど(笑)。
そうなると、日本全国妖怪旅行記・・そんな感じの本になってしまうが、そんな本があってもいいんじゃないかなあ。
それにしても、こういう水木妖怪とは違う妖怪関係の本を読んでても、同じ名前の妖怪が出てくると、つい水木妖怪を思い浮かべてしまう。
いかに水木妖怪が浸透しているか・・ということを実感する。
水木先生も、元々は江戸中期に生きた浮世絵師・鳥山 石燕の妖怪画を大いに参考にされているが、その妖怪を現代においてこれほど浸透させた功績からいっても、水木先生は現代の鳥山 石燕とでも呼べるかもしれない。
で、この本に話を戻せば・・
この本、水木作品で初めて妖怪に興味を持ち、水木作品以外ではあまり妖怪のことを知らない方には、「水木作品を離れた妖怪」にも興味を持つようになるきっかけになるかもしれない。
この本がきっかけで、水木作品以外での妖怪の姿をあれこれ調べてみることになるかもしれない。
ただ、これまである程度妖怪関係の文献を読んできてる人には、「知ってることが多い」と思われてしまうかもしれない。
そういう意味では、水木作品を離れた妖怪への入門編・・・そう捉えれば、いい「きっかけ」になりそうな1冊だ。


















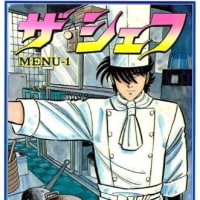









※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます