みなさま、おはようございます。
今日も、堅い話ばかりで申し訳ないのですがお付き合いください。
今日の話では、国鉄の貨物駅を、八百五十二駅を四百五十七にするという大合理化案について質問が行われています。
言わば、縮小再生産の合理策なのですが、拠点が減少することで全体の取扱量が減少するのは仕方のない事なのですが、もう少し協同体制というか、互いに保管しあうものがっても良かったのかなという気がしたりします。
特に集約輸送となると、今まで鉄道貨物で輸送されていた部分がトラック輸送になるわけですからその分道路整備を行う必要が生じます。
動力に対するエネルギー効率を考えれば鉄道は最初の固定経費が大きいものの定量的な輸送量があれば専用線の輸送を含めて今一度見直されても良いようなそんな気がしますね。
私の私見はさきおき、ひとまずご覧くださいませ。

○野坂委員 十分特段の配慮をされるように要求をして、この問題については一応終わります。
次は、五十九年の二月、国鉄の貨物駅を、八百五十二駅を四百五十七にするというかつてない大合理化案についてまず質問をしたいと思うのであります。
日本国有鉄道法の一条と二条をごらんいただきますと、公共の福祉を増進することを目的として日本国有鉄道を設立すると、第一条はそう書いてあります。第二条には、いわゆる商法の規定に定める商事会社ではない、ちょっと略しておりますけれども、そういうことであります。そういう方向で国鉄は進むというふうに考えてよろしゅうございますか。国鉄の総裁と運輸大臣にそれぞれ御答弁をいただきます。
○高木説明員 私どもの運営基準が公共的なものであるということでなければならぬことは法律上も明らかでございますし、私どももそう考えております。ただその場合に、公共的というのは全く採算と無関係かというと、やはり効率的運営ということが法律上明らかになっておるわけでございまして、何が、どの程度のものが公共的運営であり、どの程度のものが効率的運営であるかという点については非常にむずかしい問題があります。やはりある種の効率性があって初めて公共性が成り立ち得るのではないかという議論が最近非常に強くなっておるわけでございまして、貨物につきましても、貨物固有経費を賄える程度に運営していこうということは、決してそれで採算がとれたということにならないわけでございますが、やはりそれは公共的役割りということもございますから、全体としては採算がとれてなくてもいいのではないか、ただ貨物固有経費で採算がとれないようでは、これは余りにも効率性がないのではないかということで今度の案を考えているわけでございます。
○長谷川国務大臣 改めて日本国有鉄道法の第一章「総則」一条を拝見しますと、「その他一切の事業を経営し、能率的な運営により、これを発展せしめ、もつて公共の福祉を増進することを目的」とする。こういう、能率的な問題と公共の福祉、こう書いてあります。
○野坂委員 最後の締めは公共の福祉の増進を目的とするということが書いてあります。今度の合理化案は公共の福祉の増進の大きな役に立っておる、こういうふうにお考えですか。総裁いかがですか。
○高木説明員 現在大変な赤字になっておるわけでございます。そして、それは結局何らかの形で国民全体の負担において処理をしなければならぬということになりますと、そこまで赤字がどんどん出てしまっておるという現状は公共的福祉に奉仕したということにならないというふうに考えるわけでございまして、したがって、固有経費で赤字が出ないようにという程度のところが現在その第一条の精神を実現し得る線ではないかとわれわれは考えておる次第でございますが、これについてはいろいろ御批判があることは承知をいたしております。
○野坂委員 かつて国鉄当局と国鉄労働組合とで貨物の合理化問題について確認をされた事項があ
ります。「貨物取扱駅の集約の実施にあたっては、地域の輸送事情を勘案することとし、関係市町村及び県の意向について尊重する。」「貨物取扱駅の集約の実施にあたっては、荷主及び荷主関係団体の理解を得ることとし、集配距離の延伸による荷主の経費負担増にならないよう措置する。」過去は大体こういう確認事項がされてきております。この確認事項を総裁としてはいまも堅持をしたいとお考えになっておりますか、放てきをしようと考えておりますか。
○高木説明員 そっくりそのままでいけるという状態ではないと考えております。さりとて放棄をするということでもないわけでございまして、やはり現状に即した考え方で進めるべく、荷主さんとの間でも極力お話を進めてまいりますし、組合との間でもその議論を詰めてまいりますが、そっくりそのままという状態ではない。なぜならば、その申し合わせをいたしました時点と今日では全く様子が変わってきておりまして、ますます貨物の量が減ってきておるという現状を考えながら、やはりある種の変更を加えながら、しかし何としてもそれは基本的には関係市町村なり荷主さんと十分話を詰めてという精神を持ち続けながら進めてまいりたいと思います。
○野坂委員 時間がありませんから先に参ります。
四月一日の業界紙に、「五九・二以降の国鉄貨物営業体制が公表されて以来、本社貨物局に対する荷主、地元関係者らの陳情が相次いでいる。」と書いてあります。「このほど同局が自民党へ報告のため問題点を整理したところによると、」云々それぞれ項目が書いてありますから多くを申し上げません。何件程度陳情がありましたか、そしてその内容をわれわれに公表していただきたい、この二点について伺いたい。
○橋元説明員 先生のおっしゃいました資料と若干食い違うかもしれませんが、四月十六日現在で陳情者の件数が百四十四件ございました。
件数の内容でございますが、輸送ルートを確保してもらいたい、あるいは貨物取り扱いの存続を願いたい、あるいは専用線の存続または補償を願いたい、あるいは五十八年Xの見直しを要請する、その他ございまして、内容的には、件数をちょっと違った面で見ますと百四十四件ございます。とりわけ化成品についての御陳情が多いわけでございますが、これはちょうど同じ百四十四件という数字になっております。公表後いろいろな反響が実はございました。陳情はいま申し上げたような形をとったものでございまして、それ以外にもいろいろございますが、それぞれの具体的な内容はちょっと省略させていただきます。
○野坂委員 いま橋元常務理事がお話しになりましたように、日本化学工業協会、特に化成品工業協会というのはこの輸送の維持確保問題について厳しい陳情がありますね。たとえば火薬や液体の塩素、こういうものは一体どうやって送るんだ。あるいは通産省もおいでになりますが、古河鉱業の足尾銅山問題がありますね。あるいは麒麟麦酒やキッコーマンの大量輸送に対する動き、先ほど同僚委員が言いました超重量電気機器輸送の維持確保について、こういうたくさんの諸君たちの問題がある。農林省の場合は、北海道の種バレイショを車扱いではなしに送るということになればこれは全滅をする、こういう状態もある。米は集荷体制はばらばらである。ばらばらであって一カ所に集まる。飼料や肥料は一カ所から出るけれども着地はばらばらである。こういう関係でダイヤの改正と輸送システムはできるけれども運賃の計算ができていない。きわめて重大な問題であるというふうに私は理解しております。それらの点について、それぞれ通産省なり農林省、どういうお考えであるか、このダイヤ問題についてそれぞれの考え方を述べていただきたい。
○青木説明員 お答えいたします。
農林物資関係で国鉄輸送依存度の比較的高いもの、ただいま先生の御指摘のありましたように政府米あるいは肥料関係、飼料関係、また一部生鮮食料品等ございます。私ども国鉄の貨物合理化計画につきましては、全体として先ほど来御議論をいただいておりますような背景の中での取り組みでございますから、そういう方向についての理解は十分していかなければならないというふうに存じてはおりますけれども、農林物資につきましては、何と申しましても品目によりましては、生鮮食料品と、ただいま先生から御指摘ございました種芋のような場合につきましては、まさに生き物でございまして、合理化計画の推進に当たりましては具体的な荷の特性、そういったことにつきまして十分関係当局の御配慮をいただきたい、こういうふうに存じているわけであります。現在関係農業団体、また、私ども行政サイドにおきましてもそれぞれの部局におきまして、この辺の影響につきましては地域によってかなりそういう度合いが開く性質の問題だと理解しておりますので、そういう実情につきまして十分把握に努めておりますとともに、現に具体的に一部のものにつきましては、そういう関係当局にも御相談をさせていただいておるわけでありまして、十分そういう農林物資の特性を踏まえまして、支障を来さないように私ども行政サイドからも十分努力してまいりたい、こういうふうに存じております。
○小川説明員 通産省につきまして御答弁申し上げます。
この貨物線の問題につきましては国鉄からもいろいろお話を伺いまして、私どもの所管物資でも特に化学品関係などにつきましては、危険物というような問題もございまして、なかなかむずかしい問題がございます。
この問題に関しましては、第一に、各現場におきまして荷主と国鉄の各担当のところと十分お話いただけるというふうに伺っておりまして、そういう各荷主とのお話を十分詰めるようにということでお願いしております。それから、そういう問題の中にも、必ずしも各現場現場で解決できない、国鉄の全体の基本方針の問題、あるいは運輸省の問題というようなこともあろうかと思います。そういう問題につきましては、私どもの方に各業界から、それぞれの所管部局を通じましてその声を吸い上げておりまして、そういう問題をまとめまして、国鉄本社あるいは運輸省の方に具体的にどういうふうにやっていただくかというようなことをお願い申し上げているところであります。
以上でございます。
○野坂委員 委員長も大臣もお聞きいただきましたように、通産省の考え方は、商工委員会でも議論になっておりますが、通産大臣もいまお話がありましたように、もっと運輸省と話し合っていかなければならぬ、こう言っております。農林省も生鮮食料品等を取り扱っておるから、まだ詰めはない、こういうお話であります。そういう状況と、百四十件に上る陳情、請願が出ておるというこの現実。したがって、四月には下案の会議が終わったけれども、ダイヤやシステム化だけを進めて、運賃等が決まっていないために荷主もまたこれに対応できない、こういう状況が今日発生をしておることは御承知のとおりだと思います。
そこで、今度のダイヤ改正の中で考える車扱い等につきましても、北海道なんかはもう北海道だけなんですね。私の出身の米子管理局でも、大阪に一日に一車、東京に首都圏で二車、九州はゼロ、仙台に物を送ろうとしても送れない。東京で一遍終わって、それでまた仕立てが違ってくる。九州にも送れない。こういうまことに不便なかっこうになっておる。だれでもどこでも送れるというものではなくて、四百五十七駅が全部取り扱いをしてくれるか、そこに向けて発送ができるかというとそうじゃない。そうですよ、運輸大臣。したがって、いま各省庁からお話があったし、たくさんの皆さん方の陳情があった、こういうことを考えてみますと、このダイヤ改正の五十九年二月というのはきわめて問題であると言わざるを得ません。
ただ、千九百億円のヤード系の赤字、直行系は二百億円の黒字が出る、だからヤード系をやめてしまえばそれで利益が出るのではないか、固有経
費を賄えるのではないかという安易な考え方は利用者のニーズにそぐわない。また利用者は、それだけで、運賃は割り安になるという抽象論だけで具体性がない。こういう点を勘案してみると、拙速主義はとらないで、慎重にやっていかなければならぬではないのか、こういうふうに私は思いますが、大臣はいかがですか。もし大臣がお答えできないならば、国鉄総裁にお答えをいただきたい。
○高木説明員 一口で申しますと、ヤード系の輸送をやめるということに尽きるわけでございますけれども、これは容易ならぬことでございます。非常に大きな影響を及ぼすであろうことは前々から承知をいたしておりました。したがって、この問題が論議になりましたのは昭和五十年代の初めからでございますが、今日まで踏み切れなかったわけでございます。しかし、どうにも需要が減ってまいりましたのでこの際踏み切ったわけでございますが、その際大きな影響があるであろうということは覚悟をいたしております。したがって、その影響、摩擦を最小限にとどめなければならぬと考えておるわけでございまして、私自身もその種のことについてのお客さんにはなるべくお会いをいたしておりますし、地方におきましてもそれぞれよくお話を伺うように申しつけてございます。それによって実態をだんだんと理解をいたしまして、それの御迷惑を、ゼロというわけにはいかないわけでございますが、最小限にするにはどうしたらいいかということで、一方においてダイヤの組み方、列車の走らせ方についていろいろ具体的に考えながら、いまお示しのように、最も大事なことは運賃関係の問題でございますので、この運賃関係をどうしたらよろしいかということの研究が、率直に申してまだ十分できておりませんために大変混乱を起こしておる、御迷惑をかけておるという実態でございますから、これについての取り組みを急ぎまして、もう少し具体的によくお話ができるような体制をつくってまいりたい。いずれにしましても、来年の二月までには間に合うように最大限の努力をまずすることを今日の段階では考えたいというふうに思っております。
今日も、堅い話ばかりで申し訳ないのですがお付き合いください。
今日の話では、国鉄の貨物駅を、八百五十二駅を四百五十七にするという大合理化案について質問が行われています。
言わば、縮小再生産の合理策なのですが、拠点が減少することで全体の取扱量が減少するのは仕方のない事なのですが、もう少し協同体制というか、互いに保管しあうものがっても良かったのかなという気がしたりします。
特に集約輸送となると、今まで鉄道貨物で輸送されていた部分がトラック輸送になるわけですからその分道路整備を行う必要が生じます。
動力に対するエネルギー効率を考えれば鉄道は最初の固定経費が大きいものの定量的な輸送量があれば専用線の輸送を含めて今一度見直されても良いようなそんな気がしますね。
私の私見はさきおき、ひとまずご覧くださいませ。

○野坂委員 十分特段の配慮をされるように要求をして、この問題については一応終わります。
次は、五十九年の二月、国鉄の貨物駅を、八百五十二駅を四百五十七にするというかつてない大合理化案についてまず質問をしたいと思うのであります。
日本国有鉄道法の一条と二条をごらんいただきますと、公共の福祉を増進することを目的として日本国有鉄道を設立すると、第一条はそう書いてあります。第二条には、いわゆる商法の規定に定める商事会社ではない、ちょっと略しておりますけれども、そういうことであります。そういう方向で国鉄は進むというふうに考えてよろしゅうございますか。国鉄の総裁と運輸大臣にそれぞれ御答弁をいただきます。
○高木説明員 私どもの運営基準が公共的なものであるということでなければならぬことは法律上も明らかでございますし、私どももそう考えております。ただその場合に、公共的というのは全く採算と無関係かというと、やはり効率的運営ということが法律上明らかになっておるわけでございまして、何が、どの程度のものが公共的運営であり、どの程度のものが効率的運営であるかという点については非常にむずかしい問題があります。やはりある種の効率性があって初めて公共性が成り立ち得るのではないかという議論が最近非常に強くなっておるわけでございまして、貨物につきましても、貨物固有経費を賄える程度に運営していこうということは、決してそれで採算がとれたということにならないわけでございますが、やはりそれは公共的役割りということもございますから、全体としては採算がとれてなくてもいいのではないか、ただ貨物固有経費で採算がとれないようでは、これは余りにも効率性がないのではないかということで今度の案を考えているわけでございます。
○長谷川国務大臣 改めて日本国有鉄道法の第一章「総則」一条を拝見しますと、「その他一切の事業を経営し、能率的な運営により、これを発展せしめ、もつて公共の福祉を増進することを目的」とする。こういう、能率的な問題と公共の福祉、こう書いてあります。
○野坂委員 最後の締めは公共の福祉の増進を目的とするということが書いてあります。今度の合理化案は公共の福祉の増進の大きな役に立っておる、こういうふうにお考えですか。総裁いかがですか。
○高木説明員 現在大変な赤字になっておるわけでございます。そして、それは結局何らかの形で国民全体の負担において処理をしなければならぬということになりますと、そこまで赤字がどんどん出てしまっておるという現状は公共的福祉に奉仕したということにならないというふうに考えるわけでございまして、したがって、固有経費で赤字が出ないようにという程度のところが現在その第一条の精神を実現し得る線ではないかとわれわれは考えておる次第でございますが、これについてはいろいろ御批判があることは承知をいたしております。
○野坂委員 かつて国鉄当局と国鉄労働組合とで貨物の合理化問題について確認をされた事項があ
ります。「貨物取扱駅の集約の実施にあたっては、地域の輸送事情を勘案することとし、関係市町村及び県の意向について尊重する。」「貨物取扱駅の集約の実施にあたっては、荷主及び荷主関係団体の理解を得ることとし、集配距離の延伸による荷主の経費負担増にならないよう措置する。」過去は大体こういう確認事項がされてきております。この確認事項を総裁としてはいまも堅持をしたいとお考えになっておりますか、放てきをしようと考えておりますか。
○高木説明員 そっくりそのままでいけるという状態ではないと考えております。さりとて放棄をするということでもないわけでございまして、やはり現状に即した考え方で進めるべく、荷主さんとの間でも極力お話を進めてまいりますし、組合との間でもその議論を詰めてまいりますが、そっくりそのままという状態ではない。なぜならば、その申し合わせをいたしました時点と今日では全く様子が変わってきておりまして、ますます貨物の量が減ってきておるという現状を考えながら、やはりある種の変更を加えながら、しかし何としてもそれは基本的には関係市町村なり荷主さんと十分話を詰めてという精神を持ち続けながら進めてまいりたいと思います。
○野坂委員 時間がありませんから先に参ります。
四月一日の業界紙に、「五九・二以降の国鉄貨物営業体制が公表されて以来、本社貨物局に対する荷主、地元関係者らの陳情が相次いでいる。」と書いてあります。「このほど同局が自民党へ報告のため問題点を整理したところによると、」云々それぞれ項目が書いてありますから多くを申し上げません。何件程度陳情がありましたか、そしてその内容をわれわれに公表していただきたい、この二点について伺いたい。
○橋元説明員 先生のおっしゃいました資料と若干食い違うかもしれませんが、四月十六日現在で陳情者の件数が百四十四件ございました。
件数の内容でございますが、輸送ルートを確保してもらいたい、あるいは貨物取り扱いの存続を願いたい、あるいは専用線の存続または補償を願いたい、あるいは五十八年Xの見直しを要請する、その他ございまして、内容的には、件数をちょっと違った面で見ますと百四十四件ございます。とりわけ化成品についての御陳情が多いわけでございますが、これはちょうど同じ百四十四件という数字になっております。公表後いろいろな反響が実はございました。陳情はいま申し上げたような形をとったものでございまして、それ以外にもいろいろございますが、それぞれの具体的な内容はちょっと省略させていただきます。
○野坂委員 いま橋元常務理事がお話しになりましたように、日本化学工業協会、特に化成品工業協会というのはこの輸送の維持確保問題について厳しい陳情がありますね。たとえば火薬や液体の塩素、こういうものは一体どうやって送るんだ。あるいは通産省もおいでになりますが、古河鉱業の足尾銅山問題がありますね。あるいは麒麟麦酒やキッコーマンの大量輸送に対する動き、先ほど同僚委員が言いました超重量電気機器輸送の維持確保について、こういうたくさんの諸君たちの問題がある。農林省の場合は、北海道の種バレイショを車扱いではなしに送るということになればこれは全滅をする、こういう状態もある。米は集荷体制はばらばらである。ばらばらであって一カ所に集まる。飼料や肥料は一カ所から出るけれども着地はばらばらである。こういう関係でダイヤの改正と輸送システムはできるけれども運賃の計算ができていない。きわめて重大な問題であるというふうに私は理解しております。それらの点について、それぞれ通産省なり農林省、どういうお考えであるか、このダイヤ問題についてそれぞれの考え方を述べていただきたい。
○青木説明員 お答えいたします。
農林物資関係で国鉄輸送依存度の比較的高いもの、ただいま先生の御指摘のありましたように政府米あるいは肥料関係、飼料関係、また一部生鮮食料品等ございます。私ども国鉄の貨物合理化計画につきましては、全体として先ほど来御議論をいただいておりますような背景の中での取り組みでございますから、そういう方向についての理解は十分していかなければならないというふうに存じてはおりますけれども、農林物資につきましては、何と申しましても品目によりましては、生鮮食料品と、ただいま先生から御指摘ございました種芋のような場合につきましては、まさに生き物でございまして、合理化計画の推進に当たりましては具体的な荷の特性、そういったことにつきまして十分関係当局の御配慮をいただきたい、こういうふうに存じているわけであります。現在関係農業団体、また、私ども行政サイドにおきましてもそれぞれの部局におきまして、この辺の影響につきましては地域によってかなりそういう度合いが開く性質の問題だと理解しておりますので、そういう実情につきまして十分把握に努めておりますとともに、現に具体的に一部のものにつきましては、そういう関係当局にも御相談をさせていただいておるわけでありまして、十分そういう農林物資の特性を踏まえまして、支障を来さないように私ども行政サイドからも十分努力してまいりたい、こういうふうに存じております。
○小川説明員 通産省につきまして御答弁申し上げます。
この貨物線の問題につきましては国鉄からもいろいろお話を伺いまして、私どもの所管物資でも特に化学品関係などにつきましては、危険物というような問題もございまして、なかなかむずかしい問題がございます。
この問題に関しましては、第一に、各現場におきまして荷主と国鉄の各担当のところと十分お話いただけるというふうに伺っておりまして、そういう各荷主とのお話を十分詰めるようにということでお願いしております。それから、そういう問題の中にも、必ずしも各現場現場で解決できない、国鉄の全体の基本方針の問題、あるいは運輸省の問題というようなこともあろうかと思います。そういう問題につきましては、私どもの方に各業界から、それぞれの所管部局を通じましてその声を吸い上げておりまして、そういう問題をまとめまして、国鉄本社あるいは運輸省の方に具体的にどういうふうにやっていただくかというようなことをお願い申し上げているところであります。
以上でございます。
○野坂委員 委員長も大臣もお聞きいただきましたように、通産省の考え方は、商工委員会でも議論になっておりますが、通産大臣もいまお話がありましたように、もっと運輸省と話し合っていかなければならぬ、こう言っております。農林省も生鮮食料品等を取り扱っておるから、まだ詰めはない、こういうお話であります。そういう状況と、百四十件に上る陳情、請願が出ておるというこの現実。したがって、四月には下案の会議が終わったけれども、ダイヤやシステム化だけを進めて、運賃等が決まっていないために荷主もまたこれに対応できない、こういう状況が今日発生をしておることは御承知のとおりだと思います。
そこで、今度のダイヤ改正の中で考える車扱い等につきましても、北海道なんかはもう北海道だけなんですね。私の出身の米子管理局でも、大阪に一日に一車、東京に首都圏で二車、九州はゼロ、仙台に物を送ろうとしても送れない。東京で一遍終わって、それでまた仕立てが違ってくる。九州にも送れない。こういうまことに不便なかっこうになっておる。だれでもどこでも送れるというものではなくて、四百五十七駅が全部取り扱いをしてくれるか、そこに向けて発送ができるかというとそうじゃない。そうですよ、運輸大臣。したがって、いま各省庁からお話があったし、たくさんの皆さん方の陳情があった、こういうことを考えてみますと、このダイヤ改正の五十九年二月というのはきわめて問題であると言わざるを得ません。
ただ、千九百億円のヤード系の赤字、直行系は二百億円の黒字が出る、だからヤード系をやめてしまえばそれで利益が出るのではないか、固有経
費を賄えるのではないかという安易な考え方は利用者のニーズにそぐわない。また利用者は、それだけで、運賃は割り安になるという抽象論だけで具体性がない。こういう点を勘案してみると、拙速主義はとらないで、慎重にやっていかなければならぬではないのか、こういうふうに私は思いますが、大臣はいかがですか。もし大臣がお答えできないならば、国鉄総裁にお答えをいただきたい。
○高木説明員 一口で申しますと、ヤード系の輸送をやめるということに尽きるわけでございますけれども、これは容易ならぬことでございます。非常に大きな影響を及ぼすであろうことは前々から承知をいたしておりました。したがって、この問題が論議になりましたのは昭和五十年代の初めからでございますが、今日まで踏み切れなかったわけでございます。しかし、どうにも需要が減ってまいりましたのでこの際踏み切ったわけでございますが、その際大きな影響があるであろうということは覚悟をいたしております。したがって、その影響、摩擦を最小限にとどめなければならぬと考えておるわけでございまして、私自身もその種のことについてのお客さんにはなるべくお会いをいたしておりますし、地方におきましてもそれぞれよくお話を伺うように申しつけてございます。それによって実態をだんだんと理解をいたしまして、それの御迷惑を、ゼロというわけにはいかないわけでございますが、最小限にするにはどうしたらいいかということで、一方においてダイヤの組み方、列車の走らせ方についていろいろ具体的に考えながら、いまお示しのように、最も大事なことは運賃関係の問題でございますので、この運賃関係をどうしたらよろしいかということの研究が、率直に申してまだ十分できておりませんために大変混乱を起こしておる、御迷惑をかけておるという実態でございますから、これについての取り組みを急ぎまして、もう少し具体的によくお話ができるような体制をつくってまいりたい。いずれにしましても、来年の二月までには間に合うように最大限の努力をまずすることを今日の段階では考えたいというふうに思っております。










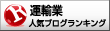
















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます