「黄金の羅針盤」 ライラシリーズ第1巻で世界観をつかむ
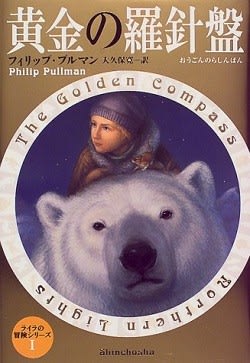
「黄金の羅針盤」 (ライラの冒険シリーズ 1) フィリップ・ブルマン著 大久保 寛(訳) 新潮社 1999年発行
映画は第1巻を作って終わりになるようだ
エラゴンと似ている・・
以下は第2巻まで発表された時の書評採録です
黄金の羅針盤」「神秘の短剣」と二作品が訳されているライラシリーズは子供向けとはいえない。ファンタジーだが、夢は無い。(ファンタジーだから何らかの「夢」を持っていなければいけないということは無い)著者のフィリップ・ブルマンは大学では英文学を教えるかたわら小説、芝居の脚本、絵本などを発表。ビクトリア時代を背景とした小説を書いている。この作品は発表されるや話題となり、多くの賞を受けたとある。だが、今世紀最後の大ファンタジーと書けば大げさな気がする。腰巻にいわく「『指輪物語』『ナルニア国物語』『はてしない物語』に熱中したすべての人に―」とあるが、それらとは明らかに毛色が違う。面白いが「大」とつくほどの哲学がなさそうな気がするのだ。
シリーズ三作目を読んでみないと断定は難しいところがある。大人と子ども、無辜なるものの持つエネルギーは、人類を救う力を秘めている、とか、解き明かされたとき見えてくる主張があるのかも知れない。シリーズというより、完結する一話の上、中、下巻といったほうが良いように、そ れぞれはクライマックスを迎えて終わっている。面白くないわけではない。が、子どもに読み聞かせるかといえば、他に読む本が多くあるし、奨めるべき本が数多あるだろう。
大人が面白い読み物を求めるとき、この物語には今までに無い新鮮味があり、筋立ての妙がある。熊人間(ただの喋る白熊?)が出てくるし、魔女も、魔法もある。ファンタジーなのだが、その枠を越えているようでもある。
こうした物語に通底する要素として、主人公が特別な印を持っているか、特別なものの所持者として選ばれた者であるということが挙げられると思うが、ポッターには印が、ライラには所持者としての特殊な能力が与えられており、伝統に適っている。しかし、両者とも今までの類型のファンタジーとは一線を画しているように思える。(ファンタジーという概念自体が難しく、非現実的な要素を含むものの総体をそう呼ぶとしての話である。)
ポッターのシリーズは、開明された現代では衰退の一途を辿る「魔法世界」を、現代のロンドン、イギリスにみごとに再構成して描き出している。魔法を信じないマグル、それこそが笑われてしかるべき。マグル代表のダーズリー氏の滑稽さは、空想の世界に時間を取られることを惜しみ、現実に汲々とする現代人のそれということか。魔法があるということは、学校の授業がつまらないということと同じぐらい確かなものだと読者に思わせる、作者の力量がある。童話にありがちな「この物語では魔法があたりまえということにしてありますからそのようにお願いします」という注書きが必要とされない。もともと子ども向きなのだから、どんな不思議なこともご承知置きくださいといった、作者の手抜きが無い。子ども向きということを、格を下げることと解釈して手抜きをした本は、子どもからも見下される。子どもなりに辻褄や合理性を気にかけ、説明を求めながら物語を聞き、読んでいるもののようだ。
ライラシリーズは、SF小説のようでもある。平行世界に住む少年と少女の出会い。その重なる世界を支配する現象を解き明かすための冒険。異世界の交点となる世界の存在は、ナルニア国物語の「魔術師のおい」を連想させる部分もあるが、切り離されることができないダイモン、エーテルを思わせるダストなどファンタジーの面目躍如たる道具立てに溢れていながら「希望」がない。道が険しく、どれほど過程が苦しくとも、探求の最後に「安住」を期待させるものが多い中で、この物語にはそれがない。主人公は、二人とも不幸な家庭を背負い、追い立てられるように、使命としての旅に出る。その旅はオズの魔法使いのようなものではなくて、ストリートチルドレンを想起させるような過酷さがある。読んでいるうちは面白く、部分部分は感心し良くできているが、全体としては心に残らない。三作目がすべてを決めるのだろうが、今のところの評価は微妙なところがある。それを狙って書いているだろう作者の試みがいままでにない感じをあたえるのだろうか。

第3作「琥珀の望遠鏡」を読んだ後では今一つ
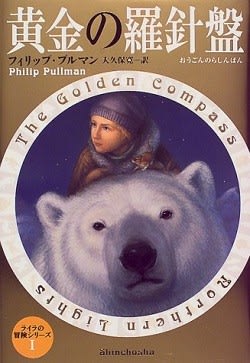
「黄金の羅針盤」 (ライラの冒険シリーズ 1) フィリップ・ブルマン著 大久保 寛(訳) 新潮社 1999年発行
映画は第1巻を作って終わりになるようだ
エラゴンと似ている・・
以下は第2巻まで発表された時の書評採録です
黄金の羅針盤」「神秘の短剣」と二作品が訳されているライラシリーズは子供向けとはいえない。ファンタジーだが、夢は無い。(ファンタジーだから何らかの「夢」を持っていなければいけないということは無い)著者のフィリップ・ブルマンは大学では英文学を教えるかたわら小説、芝居の脚本、絵本などを発表。ビクトリア時代を背景とした小説を書いている。この作品は発表されるや話題となり、多くの賞を受けたとある。だが、今世紀最後の大ファンタジーと書けば大げさな気がする。腰巻にいわく「『指輪物語』『ナルニア国物語』『はてしない物語』に熱中したすべての人に―」とあるが、それらとは明らかに毛色が違う。面白いが「大」とつくほどの哲学がなさそうな気がするのだ。
シリーズ三作目を読んでみないと断定は難しいところがある。大人と子ども、無辜なるものの持つエネルギーは、人類を救う力を秘めている、とか、解き明かされたとき見えてくる主張があるのかも知れない。シリーズというより、完結する一話の上、中、下巻といったほうが良いように、そ れぞれはクライマックスを迎えて終わっている。面白くないわけではない。が、子どもに読み聞かせるかといえば、他に読む本が多くあるし、奨めるべき本が数多あるだろう。
大人が面白い読み物を求めるとき、この物語には今までに無い新鮮味があり、筋立ての妙がある。熊人間(ただの喋る白熊?)が出てくるし、魔女も、魔法もある。ファンタジーなのだが、その枠を越えているようでもある。
こうした物語に通底する要素として、主人公が特別な印を持っているか、特別なものの所持者として選ばれた者であるということが挙げられると思うが、ポッターには印が、ライラには所持者としての特殊な能力が与えられており、伝統に適っている。しかし、両者とも今までの類型のファンタジーとは一線を画しているように思える。(ファンタジーという概念自体が難しく、非現実的な要素を含むものの総体をそう呼ぶとしての話である。)
ポッターのシリーズは、開明された現代では衰退の一途を辿る「魔法世界」を、現代のロンドン、イギリスにみごとに再構成して描き出している。魔法を信じないマグル、それこそが笑われてしかるべき。マグル代表のダーズリー氏の滑稽さは、空想の世界に時間を取られることを惜しみ、現実に汲々とする現代人のそれということか。魔法があるということは、学校の授業がつまらないということと同じぐらい確かなものだと読者に思わせる、作者の力量がある。童話にありがちな「この物語では魔法があたりまえということにしてありますからそのようにお願いします」という注書きが必要とされない。もともと子ども向きなのだから、どんな不思議なこともご承知置きくださいといった、作者の手抜きが無い。子ども向きということを、格を下げることと解釈して手抜きをした本は、子どもからも見下される。子どもなりに辻褄や合理性を気にかけ、説明を求めながら物語を聞き、読んでいるもののようだ。
ライラシリーズは、SF小説のようでもある。平行世界に住む少年と少女の出会い。その重なる世界を支配する現象を解き明かすための冒険。異世界の交点となる世界の存在は、ナルニア国物語の「魔術師のおい」を連想させる部分もあるが、切り離されることができないダイモン、エーテルを思わせるダストなどファンタジーの面目躍如たる道具立てに溢れていながら「希望」がない。道が険しく、どれほど過程が苦しくとも、探求の最後に「安住」を期待させるものが多い中で、この物語にはそれがない。主人公は、二人とも不幸な家庭を背負い、追い立てられるように、使命としての旅に出る。その旅はオズの魔法使いのようなものではなくて、ストリートチルドレンを想起させるような過酷さがある。読んでいるうちは面白く、部分部分は感心し良くできているが、全体としては心に残らない。三作目がすべてを決めるのだろうが、今のところの評価は微妙なところがある。それを狙って書いているだろう作者の試みがいままでにない感じをあたえるのだろうか。

第3作「琥珀の望遠鏡」を読んだ後では今一つ



























※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます