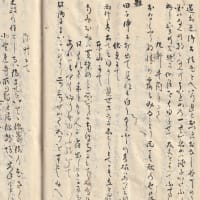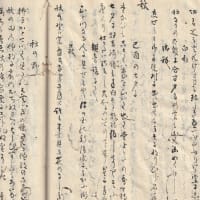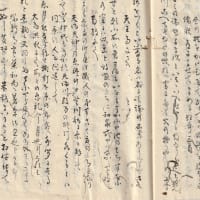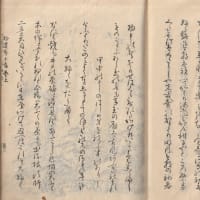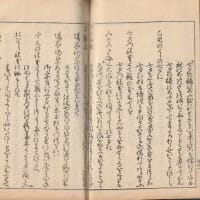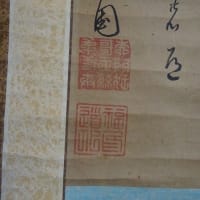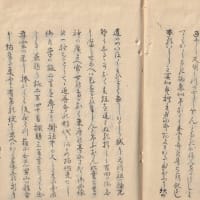おりづるタワーには一度も行ったことがなかった。旧市民球場跡地の利権がらみの人たちが慰霊碑から原爆ドーム方向の高さ制限を主張している折しも、千七百円も払って上から原爆ドームや平和公園を眺めるというのは気が進まなかった。しかし先日、太田和彦さんの居酒屋百選で太田さんがこのおりづるタワーを訪れた回を見て、展望台から阿武山の写真を撮ってみたいと思った。そして今週、カープ、サンフレッチェ、ドラゴンフライズの公認グッズ持参で入場料千円というのを見て、チャンスを伺っていた。
昨日19日は父が入院している病院で退院支援のYさんに時間を取ってもらっていて、そして栄養のチームの回診がある曜日だった。Yさんは退院に向けて吸引機や電動ベッドなどの準備を急ぎましょうというお話。その流れで栄養のM先生に退院後の食生活について尋ねたら、口からの食事が始まったばかりでまだまだ食事をステップアップしないといけないのに、退院後を語るのは早過ぎると怒られた。M先生は中学高校の同級生で他の先生には聞きにくいことも聞ける。食の細い父の退院後はかなりの苦戦を予想している。今は早く退院したいから残さず食べているが、帰ったらおそらく食べないだろう。父は鍋物が煮えるのを見ながら焼酎を飲む特技を持っていて、気づいたら何も食べていない。あとで食うと言いながら、もう薬を飲んだ、歯を磨いたと言って食べない。それで、こないだまで出ていた濃厚流動食を焼酎で割って飲ませて良いかという究極の質問を用意していたのだけど、今日のところはやめておいた。
前置きが長くなったが、栄養の回診が終わったのが14時前、耳の遠い父に説明したあと、14時半ごろ病院を出て、西広島行きの3番の電車で原爆ドーム前まで乗った。広島に住んでいても、原爆ドーム前の電停はあまり利用しない。旧市民球場に野球を見に行くときも、ほとんど紙屋町で買い物して行くからここでは降りず、帰りは混んでいるから乗りにくかった。覚えているのは昭和五十年の秋、日本シリーズが初めて広島であった日、火曜日であったが通っていた私立中学の授業は昼で打ち切りとなり、チケットを持っていた私は掃除当番を阪神ファンのK君に代わってもらって走って坂を下り古江から電車に乗って原爆ドーム前で降りて試合前の君が代に間に合った。ひょっとすると、この電停を利用するのはそれ以来かもしれない。PASPY(広島地区の交通系カード)を使い出してからはもちろん初めてだから履歴を貼っておこう。

(広島駅から病院までの広島バス31号線は未登録となっている)
この原爆ドーム前電停付近はなぜか土がむき出しで線路に雑草が生えていた。調べたら6年前の菓子博に合わせて芝生化とあるが、ぱっと見雑草である。

信号待ちでホームから北を見たら、カープの記念碑の向こう、県立体育館と基町高層住宅の間に阿武山が見えた。地上から見えるのにわざわざお金払って・・・とも思ったけれど、ここまで来たら行くしかない。

おりづるタワーの入り口は電車通りではなくて原爆ドーム側にあった。サンフレグッズを見せて千円の割引券を買って入場ゲートをくぐると女性係員がエレベーターで展望台に行く他に、歩いて登る方法があると教えてくれた。「450メートルの緩やかな散歩道です」とにっこり笑って言われたもので、思わずそちらを選択してしまった。たしかに緩やかなスロープをぐるぐる10回まわって、阿武山の写真を撮るために立ち止まったせいもあって全然きつくはなかった。最初は球場跡地の向こう高層住宅に隠れていたが、4層あたりで阿武山山頂が顔を出した。


一層ずつ阿武山を見ながら登って、こちらの散歩道で正解だったとこの時は思った。ところが、このあと思わぬ落とし穴が・・・とにかく順番に阿武山の写真を紹介しよう。広島城と阿武山の回で阿武山を玄武として広島城下が設計されたという論文を紹介した。正確には、阿武山と広島城天守を結んだラインを朱雀大路とした。それで広島城の東西南北は少し北東にずれているというものだった。しかしクレド方向から見る限り、お堀と平行に走る道の延長線上は阿武山山頂よりもすこし東にずれているように思えた。それで広島城と堀端の道と阿武山を意識しながら写真を撮った。こちらから見ても、やはり堀端の道の円頂はほんの少し山頂から東にずれているようにみえる。しかし、広島城天守をはじめ広島城下町が北東方向に傾いているのは事実なので、まだ結論を出すのは早い。次は広島城天守から見てみたいと思う。以下同じ写真のように見えるが、高さが増すだけではなく、もう一つ変化があるのだけれどおわかりだろうか。サイズを小さくして並べておこう。







10回めぐって最上階の展望台「ひろしまの丘」に着いた。ここは写真を撮るにはネットが写ってしまうのだけど、風が吹いて気持ちよかった。そして一回りしてからもう一度阿武山を見てびっくり、阿武山方向から黒煙が上がっている。落とし穴と書いたのはこのことで、上に並べた写真の2枚目にはすでに煙の上がり始めが確認できる。行きをエレベーターで昇っていれば、展望台はしばらく煙のない状態で阿武山を眺められたかもしれない。

これは白島あたりが火事だろうか、帰りのバスセンターから高陽方面行のバスは新白島から白島北町を通る。通行止めにならないだろうかと心配したが、実際バスに乗ってみると煙はいつまでたっても北にあり、バスが小田地区に降りる道の手前でも煙は阿武山方向でそこでやっと川内のあたりと特定できた。わりと阿武山の近くからの「のろし」だったわけだ。川内といえば、広島菜の特産地で、広島菜畑の向こうに阿武山を望める場所はお気に入りの散歩コースだ。大変な住宅火災だったようだが人的被害はなかったのが不幸中の幸いだった。

(2017日10月、安佐南区川内の広島菜畑より権現山、阿武山を望む)
話を展望台に戻して、広島別院から武田山方面と原爆ドーム平和公園方面の写真も載せておこう。2枚目の左端には弥山も写っている。


平和公園や原爆ドームを上から見る必要性を私はあまり感じない。100円プラスのおりづるの壁も足元が透明なのは苦手なので辞退した。しかし展望台「ひろしまの丘」は空があって山があって川があって風が吹いていて、私の故郷が確かにそこにあった。13階の展望台といえば大したことはなさそうだったけど、中々やるもんだと思った。広島は今、カープが空前の好景気で街の経済を支えている。しかしもしブームが去ったらどうなるのか少し心配になる。やはり、新しいチャレンジは常に必要だろう。通常の千七百円はちと高いと思うけれど。