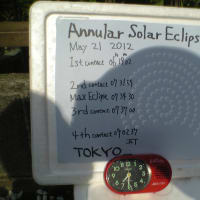『アナ・トレントの鞄』
クラフト・エヴィング商会【著】 坂本 真典【写真】
新潮社 (2005/07/30 出版)
とくに気に入ったもの:
エッジの小さな劇場
稲妻の先のところ
「手乗り象」の絵葉書
ARROW THROUGH ME
やはり「手乗り象」の絵葉書が気に入ったらしいヒト/2006-04-24
「この絵葉書を発見したのが大女の研究者だった」のひとことでスイッチが入ってしまう。
(どこかに書いたような気もするので不安なのだが)同様の発想があったもんでね。
小さい頃、この番組を見ていて考えたリクツ。
nhk.or.jp/おかあさんといっしょ 『ブーフーウー』
“(1)ぬいぐるみ、(2)人間が入る着ぐるみ、(3)ギニョール(棒とピアノ線で操る人形)の3種類を用意。ぬいぐるみを置くと、次の瞬間、カメラが着ぐるみに切り替わってサボテンをバックに動き出す。”のくだり。
おねえさんが小さなぬいぐるみをかばん(箱だと思っていたぞ)から出すと、ヒトが入った着ぐるみに切り替わり、終わりにはまた同じぬいぐるみ人形をしまう、という趣向ね。
「子供だましじゃねえか!」と思ったわけよ、コドモがね。
かばんに出し入れする人形と、明らかに中にヒトが入っていると思われる途中の劇部分は別物であろう、と推定せざるを得ない!と主張するわけね、幼児の分際で。
うまくは説明できないんだけど。
テレビ局側は「同じ人形がずっと継続しているのですよぉー」と視聴者(コドモ)を欺こうとしているようだが、その手に乗るもんか!ってわけ。
で、上記テレビ局の意図は、小さなぬいぐるみが(中に人が入っているかのように)細かい動きができるのです、と装うことにあったと見られたわけだが、もう一つ、サカサマの可能性として、「人形は人間の等身大の大きさであり、おねえさんが巨人である」可能性を考慮する必要はあるだろうか?というわけ(笑)。
まあその可能性はなかろうという結論に達したのだけれど。
そんなこと、大人に説明しても分かってもらえないだろうということで黙っておったけどさ。
これはさ、「手乗り象」の絵葉書の発想と同じなのよね!
ところで、アカイさん(NHKアーカイブス解説人?)がおねえさんと記載していたのでそれに従ったが、南面堂は「おばさん」と認識していたぞ。
子供から見た「おねえさんとおばさんの線引き」はなかなか興味深い(かつ残酷な)テーマだがな。
自分の母親よりも年長とみられる人物をおねえさんと呼ぶことには抵抗があるわけだな。
クラフト・エヴィング商会【著】 坂本 真典【写真】
新潮社 (2005/07/30 出版)
とくに気に入ったもの:
エッジの小さな劇場
稲妻の先のところ
「手乗り象」の絵葉書
ARROW THROUGH ME
やはり「手乗り象」の絵葉書が気に入ったらしいヒト/2006-04-24
「この絵葉書を発見したのが大女の研究者だった」のひとことでスイッチが入ってしまう。
(どこかに書いたような気もするので不安なのだが)同様の発想があったもんでね。
小さい頃、この番組を見ていて考えたリクツ。
nhk.or.jp/おかあさんといっしょ 『ブーフーウー』
“(1)ぬいぐるみ、(2)人間が入る着ぐるみ、(3)ギニョール(棒とピアノ線で操る人形)の3種類を用意。ぬいぐるみを置くと、次の瞬間、カメラが着ぐるみに切り替わってサボテンをバックに動き出す。”のくだり。
おねえさんが小さなぬいぐるみをかばん(箱だと思っていたぞ)から出すと、ヒトが入った着ぐるみに切り替わり、終わりにはまた同じぬいぐるみ人形をしまう、という趣向ね。
「子供だましじゃねえか!」と思ったわけよ、コドモがね。
かばんに出し入れする人形と、明らかに中にヒトが入っていると思われる途中の劇部分は別物であろう、と推定せざるを得ない!と主張するわけね、幼児の分際で。
うまくは説明できないんだけど。
テレビ局側は「同じ人形がずっと継続しているのですよぉー」と視聴者(コドモ)を欺こうとしているようだが、その手に乗るもんか!ってわけ。
で、上記テレビ局の意図は、小さなぬいぐるみが(中に人が入っているかのように)細かい動きができるのです、と装うことにあったと見られたわけだが、もう一つ、サカサマの可能性として、「人形は人間の等身大の大きさであり、おねえさんが巨人である」可能性を考慮する必要はあるだろうか?というわけ(笑)。
まあその可能性はなかろうという結論に達したのだけれど。
そんなこと、大人に説明しても分かってもらえないだろうということで黙っておったけどさ。
これはさ、「手乗り象」の絵葉書の発想と同じなのよね!
ところで、アカイさん(NHKアーカイブス解説人?)がおねえさんと記載していたのでそれに従ったが、南面堂は「おばさん」と認識していたぞ。
子供から見た「おねえさんとおばさんの線引き」はなかなか興味深い(かつ残酷な)テーマだがな。
自分の母親よりも年長とみられる人物をおねえさんと呼ぶことには抵抗があるわけだな。