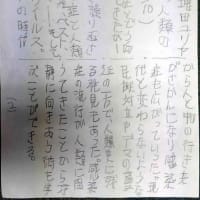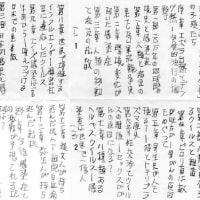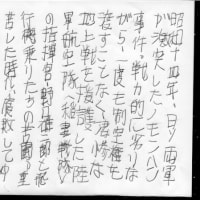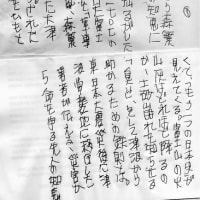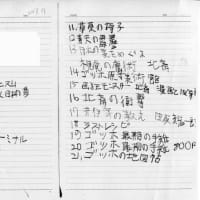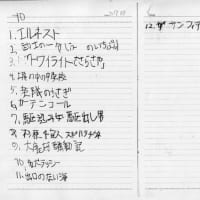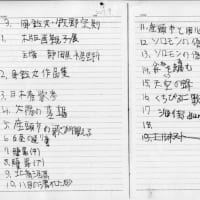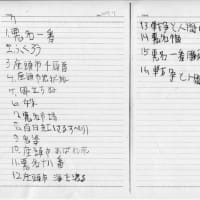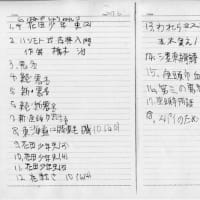増田院長記
○「あの戦争は何だったのか」(保阪正康著、新潮社)を読んで以来、心にくすぶっていることがある。あの戦争の究極的破綻に行きついた淵源は何だったのか?著者は直接的には「2・26事件」による暴力のテロであり、遠因としては夜郎自大化した日清日露以来の対外膨張の国策にあったと見る。私もこの文脈に沿って考えたことを若干披露した。特に日露の勝利が逆に奢りを招き、破綻していった。しかし、日露までは良くて日露後が悪いのか?典型的な司馬史観がそうである。
○ここに、「民族とは何か」(関曠野著、講談社現代新書)という好著がある。もう5年前に出版された本である。著者とは友人を挟んで1度会ったことがある。ともかく秀才である。著者の初めての学究的成果である「プラトンと資本主義」という専門書を読んだが、とても歯が立たなかった。懐かしい名前なので、とりもとりあえず購入してみたのだが、新書版ということもあり、分かりやすく書いてある。しかし、扱っている内容は難しい。しかし、最終章の「日本人は民族たりうるか」という章は誰でも読めて、誰もが著者の問題提起に対して自問自答することができる。これが冒頭のあの戦争の淵源を考える上でヒントとなる。
著者は江戸時代末期の開国をめぐる時期は日本人がひとつの民族となる絶好のチャンスだったと述べる。江戸幕府の権威が落ちて、諸大名列侯による話し合いでことを決める風潮ができていた。話し合いによって国の進路を決めるーこれこそ民族が形成される重要な契機であるという。
徳川慶喜の幕府も大政奉還して1大名の列に下った。公武合体の路線が引かれていた。ところが、今では「偽勅」であることが分かっているーつまり、ニセの天皇の勅命で、大久保利通と岩倉具視らはクーデターを敢行し、討幕へ踏み切る。明治維新とはこの無理が通れば道理が引っ込むというクーデターであったと断じる。ニセの勅命による錦の御旗。
このときから、天皇は政治的な利用の対象であった。そして、イデオロギーとして尊皇攘夷が利用された。明治国家とは正統性の欠けた分、それを補うための権威作りが必要とされた。それが天皇主権である。
「王政復古のクーデターが作りだした明治国家は、天皇主権を大義名分として薩長の人間が同胞に対して占領軍のように振舞う国家だった。」ちなみに永井荷風はこの明治国家が大嫌いだった。夏目漱石もそのように見える。鴎外も官に使えながら、遺言には位階勲章を一切拒否し、石見の森新太郎として死すことを望んだ。明治の国家に反発する空気は根強い。
「高位の軍人や官僚から村長や校長に到るまで天皇に連なるエリートの地位を維持すること自体が国家の至上目的になった。この国は上からの近代化によって封建社会ではありえないような大衆の動員や資源の集中を実現しながら、この増大した権力の統制は自らの地位にしか関心のない少数のエリート層のかけひきに委ねられていた。この国家には、思想も理念も人民の同意を得た国家目標もなく、とりわけ日本の開国の意味を問うという課題を中断し天皇主権で自足してしまっために、国際政治上の原則をもたなかった。このことが帝国の破滅の種を播く。」
著者は「なぜ征韓論だったのか」という節の中で次のように述べる。「クーデターで成立した政権に世論の支持などある筈もなく、そのうえ財政や軍事の面でも当時の明治政府の足元はぐらついていた。それだけに政府は権力の正統性の問題にはひときわ敏感にならざるをえなかったろう。そうした状況の中で同じ中国文明圏に属し儒教国としては先輩格とも言える韓国に国書の受け取りを拒否されることは、維新と明治政府の正統性に対して大きな打撃となりうるものだったのだろう。ゆえに維新と明治国家の正統性は、日本国内ではなく韓国においてテストされねばならないことになる。そこから征韓論が出てくる。」
本日はここまで。明日は続き。
○「あの戦争は何だったのか」(保阪正康著、新潮社)を読んで以来、心にくすぶっていることがある。あの戦争の究極的破綻に行きついた淵源は何だったのか?著者は直接的には「2・26事件」による暴力のテロであり、遠因としては夜郎自大化した日清日露以来の対外膨張の国策にあったと見る。私もこの文脈に沿って考えたことを若干披露した。特に日露の勝利が逆に奢りを招き、破綻していった。しかし、日露までは良くて日露後が悪いのか?典型的な司馬史観がそうである。
○ここに、「民族とは何か」(関曠野著、講談社現代新書)という好著がある。もう5年前に出版された本である。著者とは友人を挟んで1度会ったことがある。ともかく秀才である。著者の初めての学究的成果である「プラトンと資本主義」という専門書を読んだが、とても歯が立たなかった。懐かしい名前なので、とりもとりあえず購入してみたのだが、新書版ということもあり、分かりやすく書いてある。しかし、扱っている内容は難しい。しかし、最終章の「日本人は民族たりうるか」という章は誰でも読めて、誰もが著者の問題提起に対して自問自答することができる。これが冒頭のあの戦争の淵源を考える上でヒントとなる。
著者は江戸時代末期の開国をめぐる時期は日本人がひとつの民族となる絶好のチャンスだったと述べる。江戸幕府の権威が落ちて、諸大名列侯による話し合いでことを決める風潮ができていた。話し合いによって国の進路を決めるーこれこそ民族が形成される重要な契機であるという。
徳川慶喜の幕府も大政奉還して1大名の列に下った。公武合体の路線が引かれていた。ところが、今では「偽勅」であることが分かっているーつまり、ニセの天皇の勅命で、大久保利通と岩倉具視らはクーデターを敢行し、討幕へ踏み切る。明治維新とはこの無理が通れば道理が引っ込むというクーデターであったと断じる。ニセの勅命による錦の御旗。
このときから、天皇は政治的な利用の対象であった。そして、イデオロギーとして尊皇攘夷が利用された。明治国家とは正統性の欠けた分、それを補うための権威作りが必要とされた。それが天皇主権である。
「王政復古のクーデターが作りだした明治国家は、天皇主権を大義名分として薩長の人間が同胞に対して占領軍のように振舞う国家だった。」ちなみに永井荷風はこの明治国家が大嫌いだった。夏目漱石もそのように見える。鴎外も官に使えながら、遺言には位階勲章を一切拒否し、石見の森新太郎として死すことを望んだ。明治の国家に反発する空気は根強い。
「高位の軍人や官僚から村長や校長に到るまで天皇に連なるエリートの地位を維持すること自体が国家の至上目的になった。この国は上からの近代化によって封建社会ではありえないような大衆の動員や資源の集中を実現しながら、この増大した権力の統制は自らの地位にしか関心のない少数のエリート層のかけひきに委ねられていた。この国家には、思想も理念も人民の同意を得た国家目標もなく、とりわけ日本の開国の意味を問うという課題を中断し天皇主権で自足してしまっために、国際政治上の原則をもたなかった。このことが帝国の破滅の種を播く。」
著者は「なぜ征韓論だったのか」という節の中で次のように述べる。「クーデターで成立した政権に世論の支持などある筈もなく、そのうえ財政や軍事の面でも当時の明治政府の足元はぐらついていた。それだけに政府は権力の正統性の問題にはひときわ敏感にならざるをえなかったろう。そうした状況の中で同じ中国文明圏に属し儒教国としては先輩格とも言える韓国に国書の受け取りを拒否されることは、維新と明治政府の正統性に対して大きな打撃となりうるものだったのだろう。ゆえに維新と明治国家の正統性は、日本国内ではなく韓国においてテストされねばならないことになる。そこから征韓論が出てくる。」
本日はここまで。明日は続き。