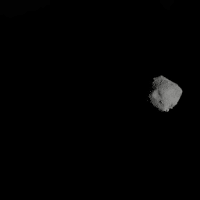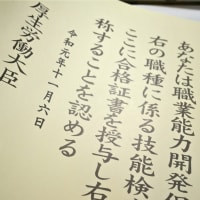「聖書」において、人の始まりはアダムとされているので、「聖書」の論理空間では、人間のはじまりをアダムという一点にまで遡ることができる。
明解な原点たる「ご先祖様」。
この論理空間では、書かれていることのすべては「真」なのであるからして、座標の原点たるこの一点は論理の根幹。この原点を超越的に保証するのが「神」というわけである。超越者はあらゆるマトリックスのオリジンを保証する。
ぼんやりと思ったことがあるのだけど、ウィトゲンシュタインの論理空間っていうのは「旧約聖書」的だな、と。まったく別の話なんだけど(^o^;)
さて( ・ิω・ิ)b
人類の原点たるアダムは「罪」の原点でもある。「原罪」「オリジナル・シン」とは、「罪」の「原点」というだけではなくて、「原点」が「罪」と不可分である論理空間を展開する。旧約聖書の論理空間では「罪」が所与の条件なのだ。その「贖い」たるべき何ごとかがいずれ与えれるという「予告」、「原福音」は、なぜかイヴに告げられる。「原罪」と「原福音」の位置にはズレがある。
アダムは神が造り給いし創造物であるので、アダムその人を、あるいはアダムから取られた「骨」で造られたイヴを、「神様」とすることは、まずはあり得ない。
どこかにそういう異端も存続しているらしいのだけど。。。様々な信仰のカタチの上で、どういった扱われ方をされているか、あいにく詳しくは存じ上げず(^ω^ゞ
しかしながら。
この世に存在する被造物が創造主たる神に並ぶことはもちろん、連なることもない。
これが「八百万の神々の国」、日本においてはだいぶ様子が違ってくる。
「ご先祖様」について遡ると、由緒正しき系図のあるなしなどには一切関わらず、たいてい日本人でありさえすれば、「神代」の「神様」にまで遡れることになっている。ただし、すでにして「八百万」。遡行しうる原点としての「神」が「八百万」いらっしゃるのである。
神々の生まれについて、明確に保証する神々がいる。
特権的にイザナギ・イザナミの男女二神を原点として置くとしても、すでにして原点は2つ。
原点が複数であることもさることながら、原点たる「神々」もまた「神々」によって生み出された存在。なので、真に超越者を見るには造化三神にまで遡らなければならない。ただ、あらわれて、すうっと隠れる。造化三神は現れてすぐにお隠れになられるので、常に側にいて論理を保証してくれたりはしない。何が正しいとか、何が間違っているとか。何が善で、何が悪か。そういうことは何も言わない。つきっきりで、「ああせい、こうせい」とか、まったく言わない。
ここに、論理空間を制御する論理がない。
いや。
論理で語らないことが始原の神々であることの証と捉えることはできるか。
あ!
まったく言わない、っていうのは少し言いすぎた(^^ゞ
ごくごくたまに、ホントにたま〜に、アドバイス的なことや、命令同然の提案をすることはあった。
そう言えば、イザナギ・イザナミにアドバイスを求められて、お答えになっておられましたな(*‘ω‘ *)
「神代」にあって、「神々」は相互に浅からぬ関係にあるので、いろんな意味でつながっている。対立する「神々」こそ、敵対を避けるべく、その血統を交えたりする。「記紀」の真偽はともかくとして、「記紀」の時代を生き延びた人々によってその後の日本が形作られたわけなので、「神話」の時代から見て、はるか未来の「現代」に生きる日本人は、少なくとも当時を生きた「神々」の子孫ということで、全体的にふわっと包みこまれている。
考えてみれば、それは必然というか、当然というか。仮に、現代において、ひとつの「家」のオリジンがまったく追えないとしても、現在にまで血統が繋がっているのであれば、それすなわちほとんど無数の、別の「家々」との関係があったことを明確に意味する。
ひとつの「家」が存続し続けるために、いったいどれほどの「家々」と関係を結ぶことになるのだろうか?
正直、考えただけでめまいがする(^o^;)
神話にまで遡れる「家々」。
日本国民の「すべて」がそうだとするのは言い過ぎとしても、神話とまったく関係ないという方が、確率論的に難しいのである。
当時に滅びてしまったのなら、その流れを汲む人たちは現在に存在できない、これは道理。
「今、続いている」「今、生きている」ということが、「神代」からのつながりを保証してしまう。
今、この世に生きて在るということ。これを遠く遡れば、「神々」によるなんらかの解決なしにはあり得なかった存在なのだ。その確かな証として僕らが存在し、現在に至る、というわけである。
「八百万の神々の国」にあっては、「ご先祖様」が「神様」であること自体は、あまりにもありふれていて、ことによるとあたりまえに過ぎているのかもしれない(^o^;)
「八百万の神々」の子孫たる僕らに、その自覚があるかどうかはさておき(^ω^ゞ
日本の状況をより複雑にしているのは、神仏習合によるところが大きい。
人が生まれればお宮参りをし、神の御前に祈りを捧げ、人が亡くなればお葬式でお経を詠んでもらって、阿弥陀如来に往生を祈る。極楽浄土に転生を果たすだけでなく、仏としての生まれ変わりを祈る。
本地垂迹説に基づく神仏習合が全国に実質的に広まった頃の平安時代にあって、どうした解釈をもって人々は異なる論理空間を重ね合わせていたのだろうか?
死に際して、仏として生まれ変わることを祈りつつ、「ご先祖様」であるところの「神様」もまたお祀りしているという多重性を、自分たちの自然として受け入れるのには、鷹揚さとか、おおらかさとかいった、そういう国民的性格をもって説明するにしても、それはだいぶあいまいに過ぎていて、説明できているとはちょっと言えない。
仏教や神道よりももっと古い、ある種の説明原理を包摂してしまえるような、ぐっと深いところの、別種の原始信仰、別種の原始オカルト哲学というべき背景があってこそ、鷹揚さも、おおらかさも存分に発揮されたのではないか?
こんな想像はする。
それはどんな世界観だったか?想像してみるのは、楽しい。
縄文文化には、確かに日本文化にまで伝わったと思われる祭祀のカタチが認められる例もある。有史以前の人の営みが何らかのカタチで、例えば祭祀の細かいルールなどに息づいていることは確かなのである。
そういう下地なしに、文化的ななにかを包摂するというのは難しいと思うのだ。
いずれにせよ、受容のベースメントをかたちづくっていた心的フィールドにおいて、神と仏は対立せずに「神仏」として、二重性、多重性、同時性のままに存在することを、「自然」とした。
いや。対立はした。
長く、所によっては激しく。
ただ、時間をかけて「平和的解決」をはかったのだ。
「神々の世界」と「仏の世界」が同時に存在する論理空間を日本人の心が「自然」とすることにも、それ相応の時間が必要だった。
さて。「神」であろうと、「仏」であろうと、「ご先祖様」を「ご先祖様」として敬うことはあっても、自分の「身内」っていう感覚で捉えられるか?というと、それには別種の強い想像力、あるいは強固な習慣が必要になるだろう。一緒に暮らした直近の「ご先祖様」ならともかく、百年前の「ご先祖様」と交歓するのだってなかなかに難しい。千年前、二千年前、万年前の、お顔を想像することさえ難しい「ご先祖様」を「身内」とする感覚、これを可能にするのは、もはや「祈り」しかあるまい。これは心理的な思いとか、そういうことを言っているのではない。技術的に、テクニカルに、今に至るまでそれしかないのだ。
日々の「祈り」こそが唯一の道となるだろう。
「祈り」は、具体的であるかもしれないし、抽象的であるかもしれない。その人その人による。また、そうであるべきだとも思う。
個人的になんだけど、僕はよく西行の歌を共感をもって思い出す。
何事の おわしますかは 知らねども かたじけなさに 涙こぼるる
お詣りしていると、なにかの拍子についつい思い出してしまうので、あわてて手を合わせ直すことも度々なんだけど(^ω^ゞ
ある意味、僕にとってはこういう心情が「原点」というか。
「原点」というべきなにかに思いを馳せるに相応しい作法があるとすれば、西行の歌にはそれがあるように思う。
それは、説明したり、証明したり、保証したりするようなものではない、とも思う。論理を超えちゃってるところにあるもの。
「語り得ないもの」、それを知るからこそ祈るんじゃないのか?
なんかわからんけど泣いちゃうような、そんな思いにこそ、共感したい。
明解な原点たる「ご先祖様」。
この論理空間では、書かれていることのすべては「真」なのであるからして、座標の原点たるこの一点は論理の根幹。この原点を超越的に保証するのが「神」というわけである。超越者はあらゆるマトリックスのオリジンを保証する。
ぼんやりと思ったことがあるのだけど、ウィトゲンシュタインの論理空間っていうのは「旧約聖書」的だな、と。まったく別の話なんだけど(^o^;)
さて( ・ิω・ิ)b
人類の原点たるアダムは「罪」の原点でもある。「原罪」「オリジナル・シン」とは、「罪」の「原点」というだけではなくて、「原点」が「罪」と不可分である論理空間を展開する。旧約聖書の論理空間では「罪」が所与の条件なのだ。その「贖い」たるべき何ごとかがいずれ与えれるという「予告」、「原福音」は、なぜかイヴに告げられる。「原罪」と「原福音」の位置にはズレがある。
アダムは神が造り給いし創造物であるので、アダムその人を、あるいはアダムから取られた「骨」で造られたイヴを、「神様」とすることは、まずはあり得ない。
どこかにそういう異端も存続しているらしいのだけど。。。様々な信仰のカタチの上で、どういった扱われ方をされているか、あいにく詳しくは存じ上げず(^ω^ゞ
しかしながら。
この世に存在する被造物が創造主たる神に並ぶことはもちろん、連なることもない。
これが「八百万の神々の国」、日本においてはだいぶ様子が違ってくる。
「ご先祖様」について遡ると、由緒正しき系図のあるなしなどには一切関わらず、たいてい日本人でありさえすれば、「神代」の「神様」にまで遡れることになっている。ただし、すでにして「八百万」。遡行しうる原点としての「神」が「八百万」いらっしゃるのである。
神々の生まれについて、明確に保証する神々がいる。
特権的にイザナギ・イザナミの男女二神を原点として置くとしても、すでにして原点は2つ。
原点が複数であることもさることながら、原点たる「神々」もまた「神々」によって生み出された存在。なので、真に超越者を見るには造化三神にまで遡らなければならない。ただ、あらわれて、すうっと隠れる。造化三神は現れてすぐにお隠れになられるので、常に側にいて論理を保証してくれたりはしない。何が正しいとか、何が間違っているとか。何が善で、何が悪か。そういうことは何も言わない。つきっきりで、「ああせい、こうせい」とか、まったく言わない。
ここに、論理空間を制御する論理がない。
いや。
論理で語らないことが始原の神々であることの証と捉えることはできるか。
あ!
まったく言わない、っていうのは少し言いすぎた(^^ゞ
ごくごくたまに、ホントにたま〜に、アドバイス的なことや、命令同然の提案をすることはあった。
そう言えば、イザナギ・イザナミにアドバイスを求められて、お答えになっておられましたな(*‘ω‘ *)
「神代」にあって、「神々」は相互に浅からぬ関係にあるので、いろんな意味でつながっている。対立する「神々」こそ、敵対を避けるべく、その血統を交えたりする。「記紀」の真偽はともかくとして、「記紀」の時代を生き延びた人々によってその後の日本が形作られたわけなので、「神話」の時代から見て、はるか未来の「現代」に生きる日本人は、少なくとも当時を生きた「神々」の子孫ということで、全体的にふわっと包みこまれている。
考えてみれば、それは必然というか、当然というか。仮に、現代において、ひとつの「家」のオリジンがまったく追えないとしても、現在にまで血統が繋がっているのであれば、それすなわちほとんど無数の、別の「家々」との関係があったことを明確に意味する。
ひとつの「家」が存続し続けるために、いったいどれほどの「家々」と関係を結ぶことになるのだろうか?
正直、考えただけでめまいがする(^o^;)
神話にまで遡れる「家々」。
日本国民の「すべて」がそうだとするのは言い過ぎとしても、神話とまったく関係ないという方が、確率論的に難しいのである。
当時に滅びてしまったのなら、その流れを汲む人たちは現在に存在できない、これは道理。
「今、続いている」「今、生きている」ということが、「神代」からのつながりを保証してしまう。
今、この世に生きて在るということ。これを遠く遡れば、「神々」によるなんらかの解決なしにはあり得なかった存在なのだ。その確かな証として僕らが存在し、現在に至る、というわけである。
「八百万の神々の国」にあっては、「ご先祖様」が「神様」であること自体は、あまりにもありふれていて、ことによるとあたりまえに過ぎているのかもしれない(^o^;)
「八百万の神々」の子孫たる僕らに、その自覚があるかどうかはさておき(^ω^ゞ
日本の状況をより複雑にしているのは、神仏習合によるところが大きい。
人が生まれればお宮参りをし、神の御前に祈りを捧げ、人が亡くなればお葬式でお経を詠んでもらって、阿弥陀如来に往生を祈る。極楽浄土に転生を果たすだけでなく、仏としての生まれ変わりを祈る。
本地垂迹説に基づく神仏習合が全国に実質的に広まった頃の平安時代にあって、どうした解釈をもって人々は異なる論理空間を重ね合わせていたのだろうか?
死に際して、仏として生まれ変わることを祈りつつ、「ご先祖様」であるところの「神様」もまたお祀りしているという多重性を、自分たちの自然として受け入れるのには、鷹揚さとか、おおらかさとかいった、そういう国民的性格をもって説明するにしても、それはだいぶあいまいに過ぎていて、説明できているとはちょっと言えない。
仏教や神道よりももっと古い、ある種の説明原理を包摂してしまえるような、ぐっと深いところの、別種の原始信仰、別種の原始オカルト哲学というべき背景があってこそ、鷹揚さも、おおらかさも存分に発揮されたのではないか?
こんな想像はする。
それはどんな世界観だったか?想像してみるのは、楽しい。
縄文文化には、確かに日本文化にまで伝わったと思われる祭祀のカタチが認められる例もある。有史以前の人の営みが何らかのカタチで、例えば祭祀の細かいルールなどに息づいていることは確かなのである。
そういう下地なしに、文化的ななにかを包摂するというのは難しいと思うのだ。
いずれにせよ、受容のベースメントをかたちづくっていた心的フィールドにおいて、神と仏は対立せずに「神仏」として、二重性、多重性、同時性のままに存在することを、「自然」とした。
いや。対立はした。
長く、所によっては激しく。
ただ、時間をかけて「平和的解決」をはかったのだ。
「神々の世界」と「仏の世界」が同時に存在する論理空間を日本人の心が「自然」とすることにも、それ相応の時間が必要だった。
さて。「神」であろうと、「仏」であろうと、「ご先祖様」を「ご先祖様」として敬うことはあっても、自分の「身内」っていう感覚で捉えられるか?というと、それには別種の強い想像力、あるいは強固な習慣が必要になるだろう。一緒に暮らした直近の「ご先祖様」ならともかく、百年前の「ご先祖様」と交歓するのだってなかなかに難しい。千年前、二千年前、万年前の、お顔を想像することさえ難しい「ご先祖様」を「身内」とする感覚、これを可能にするのは、もはや「祈り」しかあるまい。これは心理的な思いとか、そういうことを言っているのではない。技術的に、テクニカルに、今に至るまでそれしかないのだ。
日々の「祈り」こそが唯一の道となるだろう。
「祈り」は、具体的であるかもしれないし、抽象的であるかもしれない。その人その人による。また、そうであるべきだとも思う。
個人的になんだけど、僕はよく西行の歌を共感をもって思い出す。
何事の おわしますかは 知らねども かたじけなさに 涙こぼるる
お詣りしていると、なにかの拍子についつい思い出してしまうので、あわてて手を合わせ直すことも度々なんだけど(^ω^ゞ
ある意味、僕にとってはこういう心情が「原点」というか。
「原点」というべきなにかに思いを馳せるに相応しい作法があるとすれば、西行の歌にはそれがあるように思う。
それは、説明したり、証明したり、保証したりするようなものではない、とも思う。論理を超えちゃってるところにあるもの。
「語り得ないもの」、それを知るからこそ祈るんじゃないのか?
なんかわからんけど泣いちゃうような、そんな思いにこそ、共感したい。