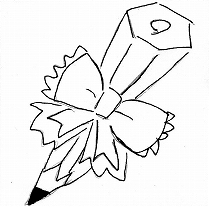今日は『橋の日』です。
由来は...お分かりですね。そう、語呂合わせです。
1986(昭和61)年、宮崎市の湯浅利彦さんの提唱により制定されました。私たちの生活と文化に深く根付いてきた川や橋とふれあい、郷土を想う心を培うことなどを目的としています。なんとテーマソングまで作っちゃったそうです。
国土のほとんどが山で、川も島も多い日本では、橋を架けて各地と交流を深めてきた歴史があります。そんな日本の三奇橋と呼ばれる橋をご紹介します。.
①甲州の猿橋
山梨県大月市の甲州街道にかかる全長29mの橋です。一説によると、推古天皇の時代(620年ごろ)からあったと言われています。どんな橋かというと、橋脚がないそうです(・・?)
岸の岩盤に穴を開けて刎木(はねぎ)を斜めに差し込み、川の上に突き出して、さらにその上に同様の刎ね木を突き出し、下の刎ね木に支えさせ、この上に板を敷いて橋にしたもので、こういう橋を刎橋というらしいです。

②防州・岩国の錦帯橋
山口県岩国市の錦川に架けられている木造の橋です。延宝元年(1673年)に城と城下町を繋ぐためにかけられました。川の中に飛び飛びに島を作り、そこに石垣で橋台を強固にした連続アーチ橋がかかっています。

③祖谷のかずら橋
実は3つ目は複数の候補があります。現存していませんが、富山県にかかる木造刎橋の愛本橋、木曽の桟(かけはし)。あとは栃木県日光への入口、大谷川に架かる神橋と徳島県三好市にあるかずら橋です。バリエーション豊かにしようと思ったので、かずら橋をここでは紹介します。
かずら橋は、長さ45mのシラクチカズラで作られた吊り橋です。植物で作られた吊り橋です。シラクチカズラというのは、山に自生するマタタビ科の植物で腐食に強いそうですが、3年に一度掛け替えが行われています。
ちなみにここに行ったことがある友人は、「こえーわ」とひとこと感想を漏らしてました(笑)

※写真はこちらのホームページから。