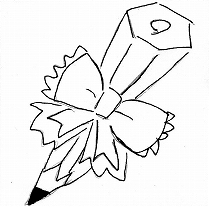今日は『民放テレビスタートの日』らしいです。
1953(昭和28)年8月28日午前11時20分、日本テレビが民間放送として初めてテレビ放送を開始したことにちなんで制定されました。
20日にNHK創立記念の記事を書きましたが、8月はそういう月なんでしょうかね?
NHKの放送開始、すなわち日本初のテレビ放送開始は2月1日だったようです。
テレビ放送は始まりましたが、当時のテレビの値段は29万円と大変高価でした。
初任給の約45倍だったらしいので、今の感覚に直すと20万×45=900万ぐらい。はあ?????? 無理無理無理無理。
そのため盛り場や駅、公園などに設置された街頭テレビに集まってみんなで楽しんでいたそうです。
日本経済の成長や技術革新による価格低下により、白黒テレビはやがて「電気冷蔵庫」と「電気洗濯機」と並んで3種の神器と称され、家庭に普及しました。
ちなみにその後の60年代には「カラーテレビ」「エアコン(クーラー)」「自動車(カー)」の頭文字をとって3Cが登場しました。
ここまでは小中学校でも習いますが、ではその次は何だったのか気になりませんか?
諸説ありますがこちらの記事によると、
○平成3種の神器:デジタルカメラ、薄型テレビ、DVDレコーダー
○令和3種の神器:4K/8Kテレビ、冷蔵庫、ロボット掃除機
まあ令和は始まったばっかりですので、今後何年続くか分かりませんが、また10年20年すれば「令和 新・3種の神器」みたいのが登場するんでしょうね〜。