実用英検準1級レベルの基礎が不安定なまま準1級に「合格させられた」結果、実用英検1級一次では何と八回も落ちてしまったことはここのブログで何度も書きました。実は英検1級二次でも二回落ちていますので、合格するまで合計十回落ちたことになります。
実用英検1級一次対策に関しては準1級レベルの基礎を固めることが合格への必要条件になります。二次は何とも窮屈な試験で「2分間のスピーチ」というのが私にとっての鬼門でした。まず一回目は、一分経過の際にタイマーが出した小さな音を終了の合図と勘違いしてスピーチをあわてて締めくくってしまって「不合格B」、二回目は快調だったものの結論に題意を逸脱したコメントを加えるというミスにより二点差で不合格、三回目は陳腐な内容をよどみなく時間いっぱいまで話してQ&Aも無難にこなし、かなり余裕の点差での合格でした。
今を遡ること十年前でも「スピーチを何本も暗記して臨む」という対策はありました。しかし落ちたら浪人生活を強いられるような試験でもないので、シャドウイングを毎日やる以外の対策は講じていませんでした。強いて第三回目合格の要因を考えると、二次受験資格を得てから一年間の間(当時は一年に二回の実用英検)に「実用英検1級一次合格」→「国連英検特A級一次合格」まで英語力を伸ばしたことがあったのかもしれません。ただ、実用英検1級二次はかなり運にも左右される試験で、「スピーチを何本も暗記して臨む」という邪道が横行している実態を英検協会が知っているのであれば、早急に改善策を講じるべきだと思います。ちなみに知人のプロ翻訳者は実用英検1級二次で三度落とされたため見限って受験をやめたと話していました。一次で通訳・翻訳者が落ちるといったことはまず考えられませんけれども二次は性悪と言いますか水物で、プロ翻訳者が落ちることもあるようです。
国連英検二次は相性が良く、B級から特A級までそれぞれ一回で合格しています。B級はニュースに関する世間話程度で済んだため楽でした。A級と特A級はまず間違いなく「日本の常任理事国入りの是非」が問われると予想できたので、「日本のような政治レベルの低い国は常任理事国になるべきではない」という主張と論拠を用意して臨み、試験官の突っ込みをしのぎ切って合格しました。特A級の面接では時事知識においてミスがいくつかあった上、国連に対する批判もかなり展開したにもかかわらず合格となり、懐の深さを感じました。時間通りにスピーチを終了させるといった官僚的側面を持つ実用英検よりも、自説を論理的に説明することが重視される国連英検がもっともっとメジャーになることを私は願っています。
追記
実用英検二次でも国連英検二次でも、六年間在籍した仙台トーストマスターズクラブでの英語スピーチ、ディベート訓練はとても役に立ちました。トーストマスターズクラブは世界組織で、日本国内にも支部がたくさんあります。英検対策を超えた英語力アップが可能と思われますのでおすすめです。
実用英検1級一次対策に関しては準1級レベルの基礎を固めることが合格への必要条件になります。二次は何とも窮屈な試験で「2分間のスピーチ」というのが私にとっての鬼門でした。まず一回目は、一分経過の際にタイマーが出した小さな音を終了の合図と勘違いしてスピーチをあわてて締めくくってしまって「不合格B」、二回目は快調だったものの結論に題意を逸脱したコメントを加えるというミスにより二点差で不合格、三回目は陳腐な内容をよどみなく時間いっぱいまで話してQ&Aも無難にこなし、かなり余裕の点差での合格でした。
今を遡ること十年前でも「スピーチを何本も暗記して臨む」という対策はありました。しかし落ちたら浪人生活を強いられるような試験でもないので、シャドウイングを毎日やる以外の対策は講じていませんでした。強いて第三回目合格の要因を考えると、二次受験資格を得てから一年間の間(当時は一年に二回の実用英検)に「実用英検1級一次合格」→「国連英検特A級一次合格」まで英語力を伸ばしたことがあったのかもしれません。ただ、実用英検1級二次はかなり運にも左右される試験で、「スピーチを何本も暗記して臨む」という邪道が横行している実態を英検協会が知っているのであれば、早急に改善策を講じるべきだと思います。ちなみに知人のプロ翻訳者は実用英検1級二次で三度落とされたため見限って受験をやめたと話していました。一次で通訳・翻訳者が落ちるといったことはまず考えられませんけれども二次は性悪と言いますか水物で、プロ翻訳者が落ちることもあるようです。
国連英検二次は相性が良く、B級から特A級までそれぞれ一回で合格しています。B級はニュースに関する世間話程度で済んだため楽でした。A級と特A級はまず間違いなく「日本の常任理事国入りの是非」が問われると予想できたので、「日本のような政治レベルの低い国は常任理事国になるべきではない」という主張と論拠を用意して臨み、試験官の突っ込みをしのぎ切って合格しました。特A級の面接では時事知識においてミスがいくつかあった上、国連に対する批判もかなり展開したにもかかわらず合格となり、懐の深さを感じました。時間通りにスピーチを終了させるといった官僚的側面を持つ実用英検よりも、自説を論理的に説明することが重視される国連英検がもっともっとメジャーになることを私は願っています。
追記
実用英検二次でも国連英検二次でも、六年間在籍した仙台トーストマスターズクラブでの英語スピーチ、ディベート訓練はとても役に立ちました。トーストマスターズクラブは世界組織で、日本国内にも支部がたくさんあります。英検対策を超えた英語力アップが可能と思われますのでおすすめです。











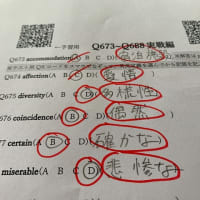


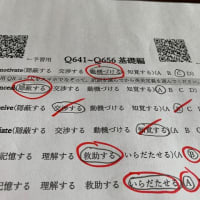

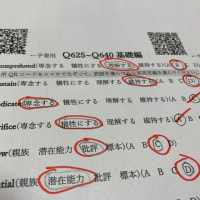





10年ほど前に、英検に関する掲示板で際立って役に立つコメントを
投稿されていた方が印象に残り、
このたびこちらのブログを運営されていると気づいて、
勉強法に関する記事をすべて読ませていただきました。
当時と同じく本当に示唆に富む記事ばかりでありがとうございます。
当方 TOEIC920を取ったことがありますが、
模擬試験の類をたくさん解いてテクニックを磨いただけで
相応の中身が全く伴っていないレベルです。
準1級は無対策で通ると思いますが、1級は1次で落ちると思います。
何かの資格試験を目指したりはしておりません。
ここからが本題です。
トーストマスターズクラブのことでお尋ねさせてください。
参加しはじめるのに最適なレベルは、英検1級1次試験をクリアできるくらいのレベルと考えているのですが、
どのようなレベルに到達したら参加するべきか、
ひとこと頂けませんでしょうか。
地元の複数のトーストマスターズクラブを見学に行ったことがあります。
即興で行うミニスピーチのコーナーを除けば、
筋書きの決まった演劇を見ているようで、どうにも違和感を持って帰宅してしまいました。
スピーチする人はともかく、それを講評する人、司会者その他、「当日はこう言う」という内容を練ってきており、
それを一言一句リピート再生するような感じだったからです。
対話というか、言葉のキャッチボールの応酬
というものをほとんど感じない会合ばかりでした。
(トーストマスターズとはこういうのが普通なのでしょうか)
トーストマスタースに関して私もほぼ同じ違和感を感じて、在籍6年でやめてしまいました。 「筋書きの決まった演劇」とは言い得て妙ですね。
ただ、ネットの発達のおかげで、言葉のキャッチボールの応酬を伴うトーストマスターズが可能になったと思います。
時間ができたらトーストマスターズに復活してスピーチをブログにアップして読者と丁々発止のやりとりをしてみたい、といったことを考えています。
英語レベルは準1級一次合格できれば十分だと思います。私のスピーチ原稿を和訳してアップしたサイトをURLをクリックしてご覧頂ければ幸いです。
私がトーストマスターズを見学したのは2010-13年で,
昔と事情が変わっているかもしれませんが
そのとき見学した地元の2つのクラブでの感想です。
A) スピーチに対しての講評は、プレゼンテーションの仕方だけに集中し、
スピーチ内容自体については何も触れない。
たとえば「指紋を押すことなかれ」を例にとりますと、
「具体的な例が複数配置されていてわかりやすかった」
「ちょうど良い声の大きさがよかった」
といった講評がある一方で、講評者は(その他の参加者も)「指紋をおすことをどう思うか」という、スピーチの核心部分については完全にノータッチです。
B) 上と関連しますが、スピーチの核心部分について出席者があれこれ対話する、言葉のキャッチボールをする、ということがないので、つまらない。
一般社会では、小学校の校長先生が全校児童を前に校庭でスピーチをするような、一方通行の言いっぱなしの場面は少ないです。
テーマ(「指紋を押すこと」について)にあれこれと参加者の意見を出しあえば、参加者の人生を豊かにするようなアイデア、発想が身につき、それは英語力の向上以上に大切で、かつ面白いことでもあると思うのですが、それがない。
NHKで"cool japan"という、毎回テーマを決めて外国人が意見を出しあう番組をやっていますが、ああいったことはできないものだろうかと思っています。
会員になった者だけが見れるクローズドのサイトの部分があるので、
そこでは行われているのかもしれません。
C) 参加人数が多く、大きな会場でもマイクを使わないので、聞き取りづらい。
英語を聞き取るのは日本語よりもセンシティブで集中力を要する作業です。
広い部屋で声がこだまして発言者の声が聞き取りつらいですし、
会の間に、廊下をだれかが談笑しながら歩くような会場でも、マイクなしなのは困ります。
(台湾で見学したトーストマスターズはマイクを使っていました。)
D) 5分を超えるような長いスピーチでも、スピーチ原稿か、レジュメの配布がない
個人的には近所の会場に毎回通うより、
近隣の韓国や台湾の会場へ年に1,2回、お金と時間をかけてでも通うほうが、
得るものがあるような気がします。
6年も通われているようでしたら、
「トーストマスターズをこんな風に活用するとよい」 「私はこんな風に活用してきた」
といった視点で
体験談も交えて記事にしていただけたら、とても参考になると思います。
ようやくトーストマスターズ活動を再開しました。
**************
A) スピーチに対しての講評は、プレゼンテーションの仕方だけに集中し、
スピーチ内容自体については何も触れない。
たとえば「指紋を押すことなかれ」を例にとりますと、
「具体的な例が複数配置されていてわかりやすかった」
「ちょうど良い声の大きさがよかった」
といった講評がある一方で、講評者は(その他の参加者も)「指紋をおすことをどう思うか」という、スピーチの核心部分については完全にノータッチです。
**************
といったご指摘全く同感でありまして、内容に踏み込まないことをモットーとする古参メンバーも少なからずいます。それでは面白くないのでネットを通してトーストマスターズの変革をもくろんでいます。
ディストリクトディレクターの東 公成さんが書いた「トーストマスターズインターナショナルは、セックス、政治、宗教をスピーチのトピックとして取り上げるのを禁止していません。」(http://tmaz.cocolog-nifty.com/tm_diary/2007/10/post_52c5.html)というブログ記事は面白いです。
コメント欄に書き込まれているように、「政治、宗教ネタ禁止は昔からよく言われてますが、根拠はなさそうですね。誰かが言い始めたことが広く流布されているのが現状のようです。」といったconformityが横行しているのがトーストマスターズの現実です。