第一章 理理趣経とはどんなお教か
古くから理趣経が秘伝として、その内容を一般に公開しなかったのは、そのような表面的な理解で早合点してしまわれるかたがいるのを恐れてのことなのです。
日本の密教は教相と事相の二つに分かれています。教相とは教義的、思想的なものであり、事相とは実践的、行動的なものであります。密教というのは、この二つがそろわないと十分とはいえません。
秘密には二種類あって、「如来の秘密」と「衆生の自秘」だと、「弁顕密二教論」(空海)には書いてあります。
相手がそこまで程度が進んでいないから、教えるとかえって相手のためにならないから秘密にしておくということ。これが秘密の一つの意味です。(「如来の秘密」)
もう一つの「衆生の自秘」とは何かというと、すべてはオープンになっているのですが、受け取るほうの目がかすんで見えない、という意味です。
本書では、かくすことはかくさなければいけないが、理解することは理解していただくという方向で、書き進めていきたいと思います。もちろん、実践に関する面は、ここで問題にすべきことではありません。
だから「般若の知恵」のあちらの岸に到りついた、悟りに至る状態、悟りの状態、般若波羅蜜多というのはそういう悟りの状態を表します。般若理趣経というのは、般若波羅蜜、そういう悟りに達する方法を書いたお経となります。
ところが、仏教でいう大楽という言葉は、裏に苦をもたない楽だということです。……。小さなものに対する大きなものではなくて、かけがえのないという意味なのです。
三昧耶経―悟りの境地
般若経(大乗仏教の代表的な経)の突然変異が般若理趣経。
般若経→一切空を説く。「色即是空、空即是色」
空とは何かというと、分別ということを否定することなのです。
分別というのは、分ち別つことです。だから、自分と他人を分ち別つ、自分と外界のものをすべて区別してしまう。仏教では、これはいけないのです。本来、みな一つなのです。
大乗仏教というのは、やはり否定面より肯定面に特徴があります。
龍樹→空を主題とした「中観哲学」についての権威者。「中論頌」「十二門論」「大智度論」(大般若経に対する注釈書)
形より心だとなつてくるのが大乗仏教だとお考え下さい。
維摩経(維摩居士)
在家の維摩居士は大乗仏教の理想像のようなものです。
阿羅漢(小乗仏教)というのは、自分だけが修行してその結果を手に入れる。小乗というのは一人用の乗り物です。大乗仏教というのはそうではない。みんなでいく。
一番わかりやすいのですが、これは一歩誤ると大層危険です。わかりやすいといえば、これほどわかりやすいことはない。こういう非常に危険な要素が、密教経典、特に理趣経の中には、ふんだんに説かれているため、ある程度の段階にまで達していない人には説いてはいけない、秘密だということになっています。相手の目がかなりの程度育っていないとセックスのことしか書いていない経典だと、好奇心で見られることになります。本来のものをつかまずに、表面的にそれを理解してしまう。そういう例が多いのです。
第二章 理趣経ができあがるまで
密教をどのようにとらえるかによって密教の起源の問題もだいぶ違ってきます。
密教というのは、多くの材料からすぐれたものを選別したり、一つの原理が中心になって他の原理とか材料を切り捨てていくのではなく、一切の物をほとんど無差別的に抱き込み、そのあと
何らかのシステムを作り上げるタイプです。ほとんどの東洋思想は、どちらかといえばこういった傾向をもっています。それは、異質なものを切り捨て、純粋なものだけを残して、それを育て上げていく西洋思想のようなタイプではありません。
密教というのは、現実に存在するすべてのものを何もかも包みこんで、、それらを一定の原理によって、全体的にシステム化していく。こういったところに特色があります。ですから密教の起源といっても、材料があちらこちらに転がっていますので、どこからはじめていいのかわからないわけです。
紀元前二千年ごろに興ったインド・アーリア文化以前のインダス文明にヨーガのきざはしあり。(密教起源?)
洋の東西を問わず古代民族にとって、呪術は科学だったのです。……。古代人にとっては、同じ方法をくり返すことで同じ結果が出てくるという科学のやり方と、呪術のやりかたはまったく一緒なのです。
真言密教の祖師の一人 一行禅師(天文学者でもあった)
大日経と金剛頂経は、弘法大師が日本に密教をもたらし真言密教の教学と実践法を樹立する基礎になった、重要な経典となりました。
初期の密教経典は仏説といって歴史的人物である釈尊の説いたものとなつていますが、大日経や金剛頂経になると、教主が実在性のない教理的な性格をもつ大日如来に変わります。
……といった三密の融合した修法の体系が中期密教経典に現われてきます。
般若経の空の思想を、密教の代表的な経典である金剛頂経の積極的な現実肯定の思想でもって、再構成した経典が理趣経であるといってよいでしょう。
不空の「大楽金剛不空真実三昧耶経」つまり「般若理趣経」は七六三年から七七一年の間に訳されたもので、、現在、真言宗の常用経典となっています。
「般若理趣釈」(不空訳)は弘法大師と伝教大師の対立の因となった。
第三章 理趣経の構成
ふつう仏教の経典は呉音で読みます。呉は揚子江流域。七世紀以降日本に唐文化の進入(洛陽長安)で漢音がはいってきました。……。それまで呉音で伝わっていた仏典の読み方を、漢音で統一しようということで理趣経などは漢音で読むわけです。
理趣経の構成→灌頂・合殺(かつさつ)・廻向が平安末成立。
理趣経というのは前と後に付加句、おまけがついたことになる。本文は今の「如是我聞」のところから「皆大歓喜信受行」のところまでだと、考えていただいていいわけです。
仏教の経典は通常三つに分けられます。序文、正宗分(本文)、流通分(功徳)、の三つに分けるのがふつうのやりかたです。
大日経や金剛頂経のうち初会にあたる真実小摂経に経典を読誦する功徳についてはまったく触れられておらず、理趣経にはそれが書かれているためだと思います。読んで功徳があると書いてあるお経がはじめて常用経典になる資格があるのです。
これら両経(大日経・真実摂経)は読誦する経典ではなくて、修法するための経典だからです。密教経典というのは、本来、修法の手引きであって、それを読んで功徳にあずかるという性質はもっておりません。
でも大日如来は釈尊のように、人間としてこの世に生まれてきた歴史上の人物ではありません。仏教の教理の上から生まれてきた仏さまです。
だから、釈尊の悟られた真理そのものを仏さまと考えた、それが大日如来ということです。
法身・応身・報身
「法身は説法せず」というのが仏教界の常識だったわけです。
こういう説に対して弘法大師は「法身は説法する」と大胆にいってのけたのです。これが弘法大師の教えの中では、仏教の他の宗派と大きく違う点です。
法身はいつも説法しているのだけれど、我われは、それを受け取る力がないだけの話だと。
自分のほうの能力さえ整えられれば、法身の説法を受け取ることができる。
自性法身・受用法身・変化法身
大日如来があまりに完全で、とらえるのに何か手がかりがいる。ですから、完全無欠の大日
如来の性格を四つに分けて「阿閦・宝生・無量光(阿弥陀)・不空成就」の四仏にしたわけです。
理法身(客体的な存在・ノエシス)は何かというと、大日経の世界、胎蔵マンダラです。
智法身(主体的な存在・ノエマ)は、金剛頂経の世界、金剛界マンダラです。
*理趣経の論理展開は直線的ではなく、複層的というか重層的。
第四章 序分の内容
「是の如く私が聞きました」→「如是我聞」
釈尊が亡くなって百年ほどたつと、結集(けつじゅう)というのが行われました。結集というのは、お弟子さんたちが集まって「私はこう聞きました」ということを、それぞれの専門家が間違いのないようにまとめようじゃないかといって開かれた会議のことです。
「薄伽梵」(ばくがぼん)→サンスクリット語バガヴァット(bhagavat)
「大毘盧遮那如来」→非常によく輝くもの→大日如来
大日如来の大は、、昼、夜なしに輝くという意味の大であります。
金剛界の五仏=五智如来
大日如来・阿閦・宝生・無量光・不空成就
マンダラというのは、……非常に論理的になっている。
金剛手菩薩(意志堅固)
観自在菩薩(慈悲深い)
虚空蔵菩薩(大きな気性)
金剛拳菩薩(ぐらぐしない)
文殊師利菩薩(知恵に優れる)
纔発心転法輪菩薩(発心即説法)
虚空蔵菩薩(幅広供養)
摧一切摩菩薩(一切摩摧破)
大日如来の教え→文義巧妙・純一円満・清浄潔白
第五章 理趣経の全体像
一切法の清浄句の門を説きたもう(十七の清浄句)
いわゆる妙適清浄の句、是れ菩薩の位なり
仏教でいう清浄とは、意識的に自と他を区別しないことです。自分と他人との間に枠をこしらえず、自分と他人と大自然が一体であるという前提に立つことを清浄という言葉で表しているわけです。
「十七の清浄句」に続いて、清浄句の功徳の書かれている句に移ります。密教経典の中でこのように功徳を説いている経典は、理趣経の外には非常に少ないのです。密教経典は修法する、拝むための作法が書いてある経典が主で、拝むための経典はプロの行者向けなのです。
このように経典読誦の功徳について触れた経典が、密教経典の中では理趣経のほかにはあまり見あたらないというのはなぜかというと、理趣経のもとが般若経という大乗経典であるためです。
「金剛手よ、もしこの清浄出生の句の般若理趣を聞くことあらば、いまし菩提道場に至るまで一切蓋障、および煩悩障、法障、業障、たとえ広く積習するも必ず地獄等の趣に堕せず。たとえ重罪を作るとも消滅せんこと難からず。もし能く受持して日々に読誦し作意思惟せば即ち現生に於て、一切法平等の金剛の三摩地を証して、一切の法に於て皆自在を得、無量の適悦歓喜を受け、十六大菩薩生を以って、如来と執金剛との位を獲得すべし」
清浄というのは浄らかなという意味ではなく、自他、あるいは自分と宇宙との区別をつけない、一体化している、むずかしくいえばマクロ=コスモスとミクロ=コスモスが一つであることを表します。これはヨーロッパ近代の考えかたとはまっこうから対立します。
ヨーロッパ近代社会では、我というものを確立することが大事であるとされました。ところが仏教では、我を確立すると同時にそれが全体の中の一つであること、大宇宙の中に自分が入っていく、大宇宙を自分の中に入れていく、この二つが一つであることを自覚することが悟りであると考えます。
「出生」は仏さまが何かを生み出すのではなくて、もともと現実世界に存在しながらかくされていたものを出現させることです。
「たとえ広く積習するも」
我われは倫理、道徳が最上と思っていますけれど、理趣経というのはもっと高い段階なのです。自分を全体の中に融合させて、まったく自分をなくしてしまって全体の中で自分を生かし、全体を自分の中に生かす境地が最高のものである。
「おれが、おれが」という自分へのこだわりをなくして、生きとし生けるものが全部一つだという、仏と自分が一つであるから自分自身も仏であるという自覚を持たなければいけないということです。
仏教でいう自由は自在ということですから、自分を残していたら自由にも自在にもなれません。自分を大きな世界に同化し、飛び込んでしまい、自分の我を残さず自由自在になる。
こういう意味で、不空訳の理趣経は、それまでの玄奘訳などからみると、非常に密教化、あるいは内面化している、仏教思想によって裏付けされているといえます。
義平等とは宝生如来の悟りですが、義というのはサンスクリット語のアルタ(artha)という言葉を訳したものです。アルタとは、〈意味〉と〈利益〉の両方の意味をもちますので、義平等は利益を説こうという意味です。利益とは何かというと、それぞれの生きとし生けるあらゆる人のもっている、かけがえのない価値・値打を説いています。
第六章 八如来の教え
理趣経の各段は、説き手がそれぞれ別の仏となっております。
理趣経は本来は死んだ人に対してとなえるものではなく、生きている人に向けていかに生きていくべきかという問題提起をしているお経であります。
第三段には釈迦如来が出てきます。釈迦如来は仏教の開祖ですが、ここではふつうのお釈迦さまというだけではなく、大日如来になって説くという形になります。聞き手は金剛手菩薩ですが、この金剛手菩薩も本来は釈迦如来であります。お釈迦さまが金剛手菩薩の形となって出てきて聞き手となり、全体をまとめるという形です。
釈尊は仏教の開祖でありますが、密教になってくると釈尊をたてずに大日如来をたてます。
大日如来と釈尊が同じものか、違うものか、千年もかかって議論されてきました。ところが、解答はちゃんと書かれているのです。「金剛頂経」という金剛界マンダラのもとになるお経があって、このお経の中に釈尊をいう、「一切義成就菩薩」が出てきます。
シッダールタ→漢訳すると義成就
五相成身観という修行を順次やることで、一切義成就菩薩は大日如来になりました。
金剛頂経には一切義成就菩薩がいかにして大日如来になったか、そしてこのようにして大日如来になった状態が金剛界マンダラであるということが説かれています。ですから、釈尊は五相成身観を実践することで大日如来の境地に達したということです。
あるいは釈尊より、大日如来の教えはもつと根源的なもので、釈尊は大日如来の悟りの境地を自分で身につけることによって永遠の真理を身につけたのであるということになります。
戯論、戯れの論とは何かというと、ものを差別して対立的に見る、分別をもってものを見ることです。
理趣経というのは非常に上級クラスの経典でありますから、初級クラス(世間的な道徳・倫理レベル)のことを求めてくるとみなここでひっかかってしまう。
「欲をもつのだったらもっと大きなものにしていけ、次元を超えろ」ということです。
「この理趣を聞きて受持し作意思惟することあらば、一切の自在と一切の智智と一切の事業と一切の成就を得る」
もう隠居してもいいといわれても、「私はまだやることがあるのだ、世の中の人が苦しんでいるかぎり、隠居できない」(無住処涅槃)
まず生きているということが前提にあって、生きているものがどうするべきかを説くのが理趣経です。
分別というのは煩悩ですから、煩悩(執着・とらわれ)を断ち切るにはどうしたらよいかということです。
すべての現象世界の根源、おおもとであります。この根源的真理を言葉で表現すると、何をいっても「だめだ」と否定をくりかえさなければなりません。これはいわゆる八不(はっぷ)という形で、生でも滅でもない、垢でも浄でもない、増でも減でもないというような対立する概念をどんどん切っていきます。そうしないと本来のものにいきつけないということです。
こういうふうに空・無相・無願というのは、私たちの執着を文殊菩薩の剣で否定していくやりかたです。執着を逃れ知恵を獲得するには、この三つの解脱門を通らなければなりません。……密教ではこういう否定だけではいけません(大乗仏教は否定だけ)。否定して否定しつくしたところに光明が出てきます。
この平等は……イコールという意味の平等ではなく、自分と仏さまが別々のようにみえるけれども本質的に違わないという意味です。理趣経に出てくる平等とはそういう意味です。
纔発心転法輪菩薩の表わしている意味は、長いこと一生懸命修行して先生になるのではなくやろうと思ったとたん、その姿を見てまわりの人が影響を受けるということです。
第九段の本論では、行為をもってする供養を四種類に分けます。すなわち、菩提心を起こすこと、一切衆生を救済すること、妙典を受持すること、般若波羅蜜多を受持し、読誦し、自ら書き、他に教えて書かせ、思惟し、修習することなどです。
理趣経の精神をしっかり受持して世の中に処していくことが仏さまを供養することになります。
ここに説かれている(金剛舞菩薩の悟りの境地)ことは、自分を捨てて他人のために体を動かしてつとめることが供養になる、般若の教えを日常生活の中で実践していく、般若の教えを自分の中にしっかり身につけていくこと、こういったことが本来の供養だということです。
忿怒大笑の心、忿怒の境地をとことんまでおしつめていけば、結局、大きく笑うということになります。
ですから小さなものをつぶしてしまうのではなく、見かたを変えて小さなものを大きなものからもう一度見直してみようではないかということを理趣経は説いています。
理趣経は四を基本にして四の倍数で構成されてきました。……。理趣経は「金剛頂経」の系統ですが、金剛頂経ではなんでも四でまとめて考えますので、理趣経もこのような構成になっています。
「薄伽梵の一切平等を建立する如来」
加持というのは……もともとは力を加える、プラスして何かを加えていくということです。
「お加持を受ける」というのは向こうにまかせっ放しでやってもらう、力が加わってくるということです。ところが弘法大師はそれではいけないとおっしゃった。仏さまが影を私たちの心に映すことが加であり、それに対して私たちの心が仏さまの影を映して感じとることが持ということなのです。ですから加持というのはこの二つの力が一つになってはじめて成り立つのであって、まかせっぱなしではだめなのです。向うから伝わってくる力を感じて受け取ってはじめて感応が成り立つのです。
生きているものが有情です。ところが日本語になると、情というのは情緒と同じになってしまいます。漢語ではもともと「生きているもの」という意味なのです。
「大日如来が一切の生きとし生けるものに加持をなす般若の教えをお説きになった」
加持するというのはどういうことかというと、生きとし生けるもの・有情が「自分はだめなやつだ、ぼんくらでロクなことをしないとみな思っている」と悩んでいると、これに仏さまが力を加えて「本当の自分の姿はこうである」ということに気づかせてくれることです。
大自然の中に自分が包まれていると同時に、大自然を自分の中に持っているのです。これが如来蔵、仏性ということです。
自分に仏性があるから、一切有情が仏さまになれるのです。ただ気付かないだけのことです。これが普賢菩薩の一切の我です。
「灌頂を受ける」というのは結局、価値に目覚めるということになります。
「金剛手よ、もしこの理趣を聞きて受持し読誦し其の義を思惟すること有らば彼れは仏菩薩の行に於いて皆究竟することを得ん」としめくくられます。ここの部分も玄奘訳の古い理趣経(「般若理趣分」)では、「悟りを得る」などの言葉が使われています。ところが不空訳の「般若理趣経」では、肝心なところになると「悟りを得る」ということも捨てておいて、とにかく「究竟に到達するのだ」と説きます。窮極に到達すれば、悟りを得ることは二のつぎ、三のつぎになってしまいます。窮極が最終目的で、その中には人びとを救うということまですべて含めているのです。
自分が全体となり、全体が自分であるということです。これが平等であり、般若の教えということになります。
理趣経は理屈で理解するのではなく、マンダラそのものを観想して自分と一つになるのが最終目標です。
「真言行者が」ということは、いいかえれば「私たちが」ということですから、「私たちがどうあるべきか」ということをここに教えていると考えてください。
結局、人間の生、生きているということの根源に立ちかえってもう一度考え直してみようではないか、というお経なのです。
「彼岸にいってはいけない」→大乗仏教の菩薩道
百字の偈→理趣経の精神を端的に言い表している。
理趣経の最高の理想が最後に百字の偈という形でしめくくられているのです。
お経はここで終わりますが、この後に付加分があります。この部分は後で日本でつけ加わったもので合殺(かつさつ)といいます。「毘盧遮那仏」と八回くり返されます。
理趣経というのは頭で理解するものではないということです。分別して「これがわかった」という受け取りかたをしてもらったのでは十分ではありません。理趣経がわかるというのはその精神がわかるということです。理趣経の精神を理解するためには、真言行を実践しながら、その神髄をつかみとることが必要になってまいります。
理趣経の各段の中にはそれぞれマンダラがありますが、瞑想の中でこれらのマンダラを観想していかなければなりません。それらのマンダラを観ずることによって、理趣経の各段が、頭ではなく、体でわかっていくという理解のしかたが大切なのです。
*平成二十九年十月二十六日抜粋終了。
*本読みの必読書です。
*字句のひっくり返りがありました。













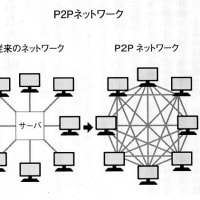
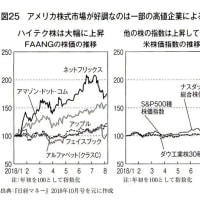

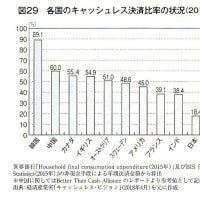
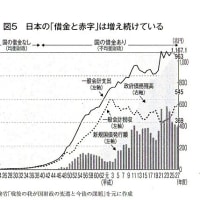

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます