
今回のお題は、たまたまパソコン内に貯め込んだ大量の写真を整理していた時に気になった一枚の写真から。

神奈川神社庁が製作した鳥居の種別ポスター
住吉は、柱が四角なのでこの図だけでは伝わらないし、両部は伝えたい意図は、わかるがこの図だけで果たして理解できるのか?また、唐破風、奴禰鳥居などかなりレア度高めな鳥居も掲載されていて鳥居マニアの端くれとしては、突っ込みどころがあって、なかなか興味深いポスターなのだが、ここで着目したいのは、八幡鳥居と春日鳥居が掲載されているところ

鳥居の種類(転載:鳥居WIKIより加工)
両鳥居の特徴を紹介するWEB掲載記事を読むと大方以下のような説明がされている。
【八幡鳥居】
鳥居の形式の一つ。円柱・貫・島木・笠木・額束からなるが、笠木・島木に反り、増しがなく、先端を斜めに切ったもの。
「反り、増しがなく」つまり直線であると同位であり図を見たまま表現している。
【春日鳥居】
基本構成は明神鳥居と変わらないが、笠木の両端が反らずに平坦な直線になっている。また、笠木と島木の木口が垂直に切り落とされている点が特徴。
(引用:コトバンクより)
春日と八幡の違いは、笠木と島木が直線で構成され木鼻の切口が斜めか垂直かの違いだけで、掲載された図をそのまま表現しているだけである事がわかる。
もちろん、今でこそ春日、八幡鳥居ともに名称はメジャーどころの鳥居ではあるのだが、ではそれぞれの総本山でもある奈良市の春日大社、大分宇佐市の宇佐八幡、京都八幡市の石清水八幡宮へ赴けば、図と同じ形状の鳥居を見ることが出来るのか?と、言う話になるのだが、実は図の形状とは、全く異なっているのだ。
早速、代表的なそれぞれの神社の一の鳥居を観て頂こう。

春日大社(奈良県奈良市 )一の鳥居

宇佐神宮(大分県宇佐市)一の鳥居

石清水八幡宮(京都府八幡市)一の鳥居
各鳥居ともに、笠木には反り増しが見られ定義されている鳥居とは異なるものとなる。
全国に分社する春日神社、八幡神社その多くで見られる鳥居も、殆どが明神型であって他は特に特徴が見られない。
疑問なのは、他の鳥居は、ほぼ鳥居の型を踏襲しているのに、なぜ春日と八幡だけ異なるのだろうか?
実は、これも旧ブログ「日々平穏」で過去に幾度か記事にした事があるのだが春日・八幡鳥居は、江戸時代(享保年間)に書かれた宮大工らが手本とする雛形本に掲載されているだけで元々「春日・八幡鳥居は存在していなかった」と、言うのがどうやら真相であるようだ。
WEB記事などで見る鳥居の説明記事は、昭和初期に活躍され鳥居研究の第一人者で、鳥居の様々な考察と基本体系の礎を築いた根岸榮隆著「鳥居の研究」が基本となっている。
彼は、黒木鳥居が鳥居の基本形であるならば、その系譜から明神鳥居が派生したと考え、その橋渡し的な役目を担うのが、図にあるような神明型の八幡鳥居(前期型)と春日鳥居であると推測した。
だが、全国を探せど実例が見つからず次第に彼は、本当に実在していたのか懐疑的になる。
結局彼の出した答えは、現在模索中で決定的な結論が出て来ない限り今のところ保留とする。と、お茶を濁す始末
しかし何としてでも鳥居の系譜にこだわる彼は、木鼻の切口が斜めで、笠木に反りが生じているものを“後期八幡型”と区分しその代表的な実例が石清水八幡宮のものと結論付けた。
だが、全国を探せど実例が見つからず次第に彼は、本当に実在していたのか懐疑的になる。
結局彼の出した答えは、現在模索中で決定的な結論が出て来ない限り今のところ保留とする。と、お茶を濁す始末
しかし何としてでも鳥居の系譜にこだわる彼は、木鼻の切口が斜めで、笠木に反りが生じているものを“後期八幡型”と区分しその代表的な実例が石清水八幡宮のものと結論付けた。
春日大社で見られる現在の一の鳥居も「建て直し以前までは、春日鳥居の型を踏襲していた」と、言う説もあるが出所は定かではない。
近年の研究者によって根岸のこれら説は否定され
- 八幡・春日鳥居は、あくまでも宮大工の雛形本から、独り歩きしたものであって実在しない。
- 神明から明神系へと繋ぐ橋渡し的な存在であるというのは根岸の捏造思い込みである。
- 鳥居は、進化の系譜などはなくスタートから神明・明神であった。
と、言うのがどうやら真相であるようだ。
※かく言う自分自身も根岸の説をそのまま信じて、八幡鳥居の前期、後期と考察を続けてきたのだが、改めて本稿でまとめ訂正させて頂く。
しかしながら、では、図にあるような神明造りの春日・八幡両鳥居は実際には存在しないのか?と、言う話になるのだが実は、建立年はずっと新しくはなるが図の形状を手本とするような両鳥居が出現している。


春日神社(東京都目黒区三田)

春日神社(京都府京都市西京区桂春日町)

世田谷八幡宮(東京都世田谷区宮坂)
以上の様に様々な形状のある鳥居の中で、春日・八幡だけが特異な存在である事が理解して頂けたと思う。
そもそも存在していなかった鳥居を独自の推論で「あった」と、断言してしまった根岸の功罪は大きい。
本来ならば、存在していないわけであるから鳥居の種別から抹消すべきであり、ましてや神社庁も注釈も入れずそのまま掲載しているのはおかしい。
だが後世に忠実に再現しているものが出現しているわけで「春日・八幡鳥居」としての種別は、残しておいてもいいのかもしれない。
☞関連記事:




















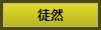



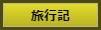
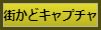

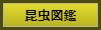


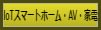

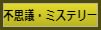
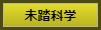
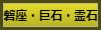


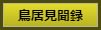
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます