「お疲れさまです」問題を掘り下げた記事を見つけました。面白いので、記録しておきます。
**********
目上の人に「お疲れさまです」は間違いなのか
同じことでも言い回しで印象は変わる
大ナギ 勝:ムービングオフィス代表
東洋経済ONLINE 2015年8月16日
今、「お疲れ様です」という言葉が、大きな波紋を呼んでいます。
7月26日放送の『ヨルタモリ』(フジテレビ系)でタモリさんが「子役が誰彼かまわず『お疲れ様です』と言って回るのはおかしい」という出だしから「『お疲れ様』というのは、元来、目上の者が目下の者にいう言葉。これをわかっていないんですね」と力説しました。週刊ポスト誌をはじめ、一部のメディアでこの発言を記事化したためにあちらこちらで物議をかもしています。
さらに、その発言を受けて、民放連(日本の民間ラジオ・テレビ業者が所属する団体)が子役に「お疲れ様」と言わせないよう申し入れをすべきだとまで提言したとのこと。しかし、この記事の読者の皆さんもきっと違和感を覚えた人も大勢いると思います。
研修で教えている内容とは?
近年、各研修会社でのビジネスマナー講習では「『ご苦労さま』は目上の人から目下の人に使うのに対し、『お疲れさま』は同僚、目上の人に対して使うもの」と、研修講師から教わっているはずです。
文化庁のサイト平成17年度版「国語に関する世論調査」の結果を参考にすると
4.仕事が終わったときに、どのような言葉を掛けるか(以下原文のまま)
仕事後に掛ける言葉<問5>(12ページ)
― 相手の職階が上だと、約7割が「お疲れ様(でした)」。相手の職階が下だと「御苦労様(でした)」が増加―
会社で仕事を一緒にした人たちに対して、仕事が終わったときに何という言葉を掛けるかを、自分より職階が上の人の場合と自分より職階が下の人の場合について尋ねた。
(1)一緒に働いた人が、自分より職階が上の人の場合
〔全体〕結果を多い順に示すと、以下のとおり(「その他」「わからない」は省略)
「お疲れ様(でした)」が約7割で、「御苦労様(でした)」、「ありがとう(ございました)は、ともに1割台にとどまっている。
「お疲れ様(でした)」……69.2%
「御苦労様(でした)」 ……15.1%
「ありがとう(ございました)」……11.0%
「どうも」……0.9%
何も言わない……0.6%
(2)一緒に働いた人が、自分より職階が下の人の場合
〔全体〕結果を多い順に示すと、以下のとおり(「その他」「わからない」は省略)
「お疲れ様(でした)」が5割強で、「御苦労様(でした)」は3割台半ばとなっている。(1)で尋ねた自分より職階が上の人の場合と比べると、「お疲れ様(でした)」の割合が16ポイント、「ありがとう(ございました)」の割合が6ポイント低くなり、「御苦労様(でした)」の割合が21ポイント高くなっている。
「お疲れ様(でした)」……53.4%
「御苦労様(でした)」……36.1%
「ありがとう(ございました)」……5.0%
「どうも」……2.8%
何も言わない……0.5%
この結果を見ても、目上の人に対しては7割近い人が「お疲れ様」という言葉を使用して、すでに十分に浸透しているのがわかります。ここまで浸透していると、その言葉を使用しないで挨拶をするのにはどうしたらよいのか迷ってしまいます。
「お疲れ様」はすでに浸透している
その言葉の持つ「本来の意味」や「由来」を理解している人にすれば、部下や後輩が先輩や上司に対して、その労をねぎらう声掛けをすること自体、(たとえ建前論だとしても)本来はあるべきではない姿だと立腹されるのも当然といえば当然です。
ただ、文化庁がこのような調査をすること自体、その時代に応じての「言葉の使い方」や「言葉の選択」の仕方に変化が表れていることを確認し、対応していくために必要とされているからにほかなりません。
もう30年以上も前になりますが、筆者自身のことを思い出してみても、当時の新入社員研修で、すでに「『ご苦労さま』は目上の人から目下の人に、『お疲れさま』は同僚、目上の人に」と、研修講師から教わった記憶は鮮明に残っています。学生から社会人になりたてで、「お疲れ様でした」という言葉に新鮮さを覚え、毎日、嬉々として使っていたものです。
ところがある時、外回りから帰ってきた先輩に「お疲れ様でした」といつものように元気に声掛けした時のことです。「まだ、午前中だから疲れていないよ」という言葉を返されてしまい困惑してしまいました。それ以来、正しいのだろうなと思いながらも、「お疲れ様」という言葉を目上の人に対して使うことはなくなりました。
その代わりに、場面、場面に応じて「ありがとうございます。」というお礼のひとことを添えて、万能の「言い回し」を考えたものです。
「お疲れ様」を言い換えるなら
「おはようございます。朝早くから、(私たちの指導のために)ありがとうございます。今日もよろしくお願いします」という朝の挨拶から始まり、夜であれば、「遅くまで、ありがとうございます(今日はお先に失礼します)」。
また、昼間であれば「お帰りなさいませ。(暑いなかでの、)外回りありがとうございます」など、上司、先輩に対して「お疲れ様」というねぎらうひと言ではなく、その時どきの状況に応じたひと言(例のような「おはようございます」「よろしくお願いします」など)のあたりまえの挨拶に「ありがとうございます」という感謝の言葉で気持ちを表します。
このように何気なく使う日常の挨拶の中で、きちんと気持ちを表現し続けることで、良好な人間関係が築き上げられます。
(その時「ありがとうございました」は、完了形の言い回しになってしまい、それを使い続けると、いつしか縁を切ってしまうように響きますから、極力現在形の「ありがとうございます」を使用します。)
また、同じく文化庁のサイト平成24年度版「国語に関する世論調査」には、「お疲れ様」という言葉以外でも、コミュニケーションについての興味深い結果がでています。
1. 人とのコミュニケーションについて (以下原文のまま)
誰かに話をしていて、自分の言いたかったことが、相手にうまく伝わらなかったという経験があるか、ないか<問2>(P.7)
― 6割以上の人が「ある(計)」と回答―
〔全体・年齢別〕誰かに話をしていて、自分の言いたかったことが、相手にうまく伝わらなかったという経験があるか、それとも、ないかを尋ねた。
「よくある」と「時々ある」を選んだ人を合わせた「ある(計)」は63.4%、「余りない」と「ない」を合わせた「ない(計)」は36.3%であった。
年齢別に見ると、「ある(計)」の割合は、16歳から50代までは、6割台半ばから7割前後となっている。また、60歳以上では、5割台半ばとなっている。
自分の言いたいことが伝わらなかった理由<問2付>(P.7)
― 「自分の話し方に問題がある」と考える人の割合は、若い年代で高い傾向―
〔全体〕問2で「ある(計)」を選択した人(63.4%)に、伝わらなかった理由を尋ねた。結果は以下のとおり。
・どちらかと言えば、自分の話し方に問題があることが多いと感じる……55.0%
・どちらかと言えば、相手の聞き方に問題があることが多いと感じる……8.6%
・どちらとも言えない……35.9%
・わからない……0.5%
〔年齢別〕年齢別に見ると、すべての年代で、「どちらかと言えば、自分の話し方に問題があることが多いと感じる」と回答した人の割合が最も高くなっている。
中でも、16~19歳では8割、20~30代では6割台後半となっており、40代以上に比べて高くなっている。一方、「どちらかと言えば、相手の聞き方に問題があることが多いと感じる」と回答した人は、60歳以上を除くすべての年代で1割に達していない。
人とのコミュニケーションにおいて、重視すること<問4> (P.13)
― 6割台半ばの人が「相手との人間関係を作り上げながら伝え合うこと」と回答―
〔全体〕人とのコミュニケーションにおいて、「相手との人間関係を作り上げながら伝え合うこと」と「根拠や理由を明確にして論理的に伝え合うこと」のどちらを重視するかを尋ねた。
「相手との人間関係を作り上げながら伝え合うこと」と回答した人が6割台半ば、「根拠や理由を明確にして論理的に伝え合うこと」と回答した人が1割台半ばという結果であった。また、「相手や状況によって異なるので、どちらかひとつには絞れない」と回答した人も1割台半ばであった。
・「相手との人間関係を作り上げながら伝え合うこと」の方を重視する……65.1%
・「根拠や理由を明確にして論理的に伝え合うこと」の方を重視する……15.0%
・相手や状況によって異なるので、どちらかひとつには絞れない……14.9%
・どちらも重視していない……3.7%
・わからない……1.4%
〔年齢別〕年齢別に見ると、すべての年代で「(a)相手との人間関係を作り上げながら伝え合うこと」を重視すると答えた人の割合が高くなっている。特に、20代から40代では7割前後となっており、ほかの年代に比べて高い。また、「(b)根拠や理由を明確にして論理的に伝え合うこと」を重視していると答えた人の割合はどの年代でも1割台となっている。そのうち、60歳以上では、18.2%となっており、ほかの年代に比べて高い。
こうしてみると、6割以上もの多くの人が、誰かに話をしていて、「自分の言いたかったことが、相手にうまく伝わらなかった」という経験をしています。
そして、年齢が若ければ若いほど、「自分の話し方に問題がある」と感じ、更に若ければ若いほど「相手との人間関係を作り上げながら伝え合うこと」を重視しているのが解ります。
よりよい「言葉」や「言い回し」で想いを伝える
同じ思いも言い回しによっては、心に刺さる「しびれるひと言」になります。「今回の成功は部長のおかげです」
より
「部長の下で成功できたことはわたしの誇りです」
こんな言葉で言われたら上司冥利に尽きます!
「言葉の選択」によって人を変え、そして、その言葉によって自分を変える。 自分が発する言葉で、部下のやる気を引き出したり、ネガティブな上司や取引先の態度をガラッと変えたりできます。結果として、相手に対する自分の印象が変わり、自分の評価が高まり、自分自身のモチベーションも上がります。
コミュニケーションにおいて、よりよい「言葉」「言い回し」を選択できるようになると、あなたの「想い」が、上司や部下、取引先にしっかりと伝わるようになります。そんな勉強をするのには遅いも早いもありません。夏休みの今の時期がチャンスかもしれません。
**********
提案されている「ありがとうございます」を使うのは悪くないと思うのですが、筆者の用法だとわざとらしい気もします。
朝なら「おはようございます。今日もよろしくお願いします」でよいでしょうし、相手が帰社したときには「お帰りなさい」で十分で、付け加えるなら、「外、暑かったでしょう」ぐらいでよいと思います。もちろん、帰りは「お先に失礼します」で文句はつけられません。
要するに、「お疲れ様でした」を使わないだけで、「こいつ、できるな」と上司・先輩は思ってくれるのではないでしょうか。
美しい日本語、やっぱり勉強しないといけません。













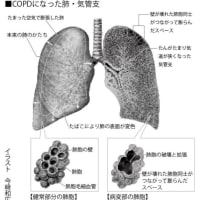
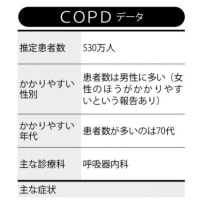




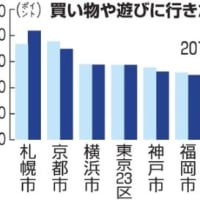






おっしゃるように、代わりの言葉のほうが好ましいと思います。
日本語は焦点をぼかした言い回しが多いような気がします。
昔からの文化なのかもしれませんが、グローバルな視点から見ると、よろしくないのかもしれません。