東日本大震災が、福島県の子供たちの生活と身体に大きな影響を与え続けています。
**********
福島の子の肥満、高止まり 震災で運動不足や生活変化(朝日新聞) - goo ニュース
調査は毎年、全国の幼稚園児と小中高校生の5~17歳の一部を抽出して実施。身長ごとに決められた標準体重を20%以上、上回る「肥満傾向」の子どもの割合を全国平均と福島県を比べると、9歳で8・14%と15・07%、13歳で8・42%と14・43%、17歳で9・48%と13・11%。震災後の2012年度以降、多くの年齢で福島県が1位を占める状況が続いている。
文科省によると、冬に雪が積もる東北地方はもともと肥満傾向の子が多いが、震災後の福島県は特に割合が高い。放課後の外遊びが制限されたり、一部地域で登下校の距離が短くなったりといった生活環境の変化が原因とみられるという。体育の改善に取り組んでいるが、担当者は「効果が出るには時間がかかる」としている。
「肥満児」福島で依然多く 屋内遊び習慣化が一因 文科省調査(産経新聞) - goo ニュース
全国の幼稚園と小・中・高校で「肥満傾向」と判断される子供の割合が3年連続で10%以下となったことが23日、文部科学省の平成26年度学校保健統計調査(速報値)で分かった。全国的に子供たちに“スリム体形”が定着する一方、福島県では東日本大震災以降、肥満傾向が依然、高いままであることも判明。県教育委員会は「子供たちが屋外を避け、テレビゲームなど屋内での遊びが習慣化したことが一因とみられる」と分析している。
調査は全国の幼稚園と小・中・高校で昨年4~6月に行った健康診断の結果から、5~17歳の男女約70万人を抽出して実施。身長別などの標準体重より20%以上重い「肥満傾向」の子供たちの割合を出現率として算出した。
各学年の男女別割合を前年度と比べると、男子は計7学年(小2、4、5、中2、3、高2、3)で0・01~1・18ポイント、女子は計5学年(小3、4、6、中1、高2)で0・07~0・57ポイントそれぞれ下降。文科省は「子供の生活習慣病を心配する親世代が食生活に気を使っているためではないか」と分析している。
福島県では計8学年で0・03~2・31ポイント上昇し、小中の計6学年で全国1位となるなど前年度に引き続き肥満傾向児の多さが目立つ。98%の学校で屋外活動の制限は解除され、震災前と同じ状況に戻っているが、改善が進んでいない。県教委は「今後は家庭と連携し、生活習慣の改善に努めたい」としている。
本県、全国平均上回る 子どもの肥満傾向改善されず(福島民報) - goo ニュース
県が発表した肥満傾向児の割合は【表】の通り。
本県男子の肥満傾向児の割合は9歳が17・34%と、県内の各年齢で最も高くなった。女子は13歳が13・78%で最高となった。6、7、9歳と11~13歳の6つの年齢で、全国で最も高い割合だった。
県教委は、東京電力福島第一原発事故に伴う屋外活動の制限やスクールバスによる通学などが、子どもの運動や生活の習慣に影響しているとみている。
子どもの健康維持に向けて、県教委は27年度、小学4年から高校1年の児童生徒と、保護者、教職員の3者が子どもの運動や生活習慣の課題を共有する手帳「自分手帳(仮称)」を作製する。家庭と連携した運動不足の解消を目指す。公立小学校の体育の授業にスポーツトレーナーらの専門家を派遣する事業も展開する。














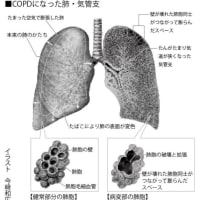
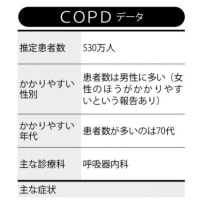




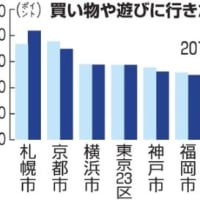





※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます