こういうことが裁判になるのだから、日本は平和です。それでも、この結果でホッとしました。
**********
国旗国歌訴訟「合憲」 都教委など安堵広がる 「ごく妥当な判決」(産経新聞) - goo ニュース
2011年1月29日(土)08:00
「当然の判決だ」。卒業式、入学式で教職員らが起こした混乱の正当性を否定した28日の東京高裁の逆転判決。東京都教育委員会など教育関係者の間には、安堵(あんど)の雰囲気が広がったばかりか、1審判決への改めての批判が出た。一方、原告の教員らは「裁判所はひどいところだ」と、逆転判決に納得がいかない様子だった。
◇
東京都の石原慎太郎知事は28日の定例会見の中で、「国歌や国旗に対する国民の反応や現象は日本だけちょっと奇異。判決は大変結構だと思っています。ごく妥当だ」と話した。
大原正行教育長も「主張が認められたことは当然のことと考える。今後とも、学校における国旗・国歌の指導が適正に行われるよう取り組んでいく」とのコメントを発表した。
厳粛な卒業式や入学式の実施のため、都教委ではこれまで、国歌斉唱や起立を拒んだ教員たちに毅然(きぜん)とした態度で臨んできた。
通達を出した平成15年度に懲戒処分を受けた教員数は179人。同種の事案での全国の処分者の9割以上を占めたこともある。
しかし、最近では斉唱時の起立を拒む教員は激減。東京都の21年度の処分者はわずか5人になった。国旗の持ち去りや引き下ろし、表立っての式典妨害など「実力行使」は影を潜めている。
正常化が進んだ背景には、東京都日野市の小学校で音楽教諭が国歌のピアノ伴奏を拒み戒告処分とされたことに関した、職務命令をめぐる訴訟で19年2月、職務命令を合憲とする最高裁判決が出るなどしたことがある。各地での同種訴訟でも教員側の敗訴が相次いでいる。
ただ、東京都に限らず各地の一部の教員らは、「起立の義務はない」と校長らに「予防訴訟」を提起したり、学校が不起立教員の名前を教委に報告することを「個人情報の違法収集だ」として訴えを起こしたりするなど、あの手この手の「裁判闘争」を続けている。支援組織によるホームページを通じて訴訟の経過報告や集会の案内、カンパ要請をしながら支持を呼びかける活動が一般的だ。
北九州市では校長が式典前に「心を込めて歌うように」と教員に命じたところ、「内心の自由を侵害した」と裁判になるなどしている。
こういった現状について、公立学校での校長経験を持つ、埼玉県狭山ケ丘高校の小川義男校長は「国旗や国歌をめぐってここまで係争が相次ぐのは日本だけの光景。国家や同胞といった者への感覚、意識がいかに希薄になっているかを象徴的に示す裁判ともいえる」と指摘。そのうえで、「学校行事という公的な場で『俺は立つ』『私は立たない』などと始まれば儀式など成り立つはずがない。そもそも違憲だと判断した1審東京地裁の判決自体がおかしな判決だった」と話している。
**********
今日の社説を見ると、読売・産経が今回の判決を全面支持していますが、朝日は反対。毎日・東京・日経は触れていません。その朝日の社説を記録しておくとしますか。あきれ果てるないようですが。
**********
君が代判決―少数者守る司法はどこへ
数々の演劇賞を受賞した永井愛さん作・演出の喜劇「歌わせたい男たち」(2005年初演)は、卒業式の日を迎えた都立高校が舞台だ。
教育委員会の指示通りに式を進めようと必死の校長。君が代斉唱の時、起立しないと決めている教師。そんな葛藤があることを知らぬまま、ピアノ伴奏を命じられた音楽講師……。
根はいい人ばかりなのに、みな消耗し、傷つき、追いつめられていく。
芝居の素材になった都立高校で働く教職員ら約400人が、君が代の際に起立斉唱したり伴奏したりする義務がないことの確認や慰謝料を求めた裁判で、東京高裁は請求をすべて退ける判決を言い渡した。「起立や伴奏を強制する都の指導は、思想・良心の自由を保障した憲法に違反する」とした一審判決は取り消された。
極めて残念な判断だ。ピアノ伴奏を命じることの当否が争われた別の訴訟で、最高裁は07年に合憲判決を言い渡している。高裁はこの判例をなぞり、斉唱や伴奏を命じたからといって個々の教職員の歴史観や世界観まで否定することにはならない、だから憲法に違反しないと結論づけた。
判決理由からは、国民一人ひとりが大切にする価値や譲れぬ一線をいかに守り、なるべく許容していくかという問題意識を見いだすことはできない。「誰もがやっているのだから」「公務員なのだから」と理屈を並べ、忍従をただ説いているように読める。
それでいいのだろうか。
私たちは、式典で国旗を掲げ、国歌を歌うことに反対するものではない。ただ、処分を科してまでそれを強いるのは行き過ぎだと主張してきた。
最後は数の力で決まる立法や行政と異なり、少数者の人権を保護することにこそ民主社会における司法の最も重要な役割がある。最高裁、高裁とも、その使命を放棄し、存在意義を自らおとしめていると言うほかない。
近年、この問題で都の処分を受ける教職員は減っている。違反すると、罰は戒告、減給、停職と回を追って重くなるうえ、定年後の再雇用が一切認められなくなるからだ。そんな脅しと損得勘定の上に粛々と行われる式典とは何なのか。いま一度、立ち止まって考える必要があるように思う。
国旗・国歌法が制定された99年、当時の有馬朗人文相は国会で「教員の職務上の責務について変更を加えるものではない」と言明し、小渕恵三首相も「国民の生活に何らの影響や変化が生ずることとはならない」と述べた。
ところが現在、教職員ばかりか、生徒や保護者、来賓の態度をチェックする動きが各地で報告されている。
今回の高裁判決が、こうした息苦しさを助長することのないよう、社会全体で目を凝らしていきたい。
**********
国家としての見えない紐帯というものをぶち壊したい朝日新聞。この論法だと、個人はすべて社会の中で自由を許され、勝手し放題でよいということになります。そんなムチャクチャな。
アメリカや中国・韓国でもし国旗掲揚や国歌斉唱のときに立ち上がらなかったり、国歌を唄うことを拒絶したりしたら、反逆罪に問われるでしょう。日本だけ異常なのです。それもこれも、朝日みたいな日本の国柄を貶める新聞が存在するからです。
国旗に敬意を表し、国歌を唄う。当然のこと。何も息苦しくはありません。目を凝らす必要もありません。日本人として当たり前のことを当たり前にやるべきです。













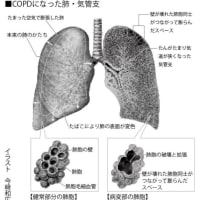
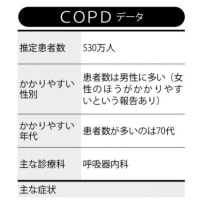




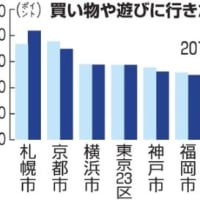





※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます