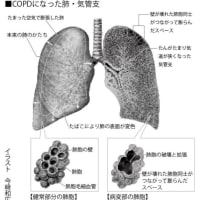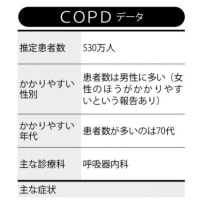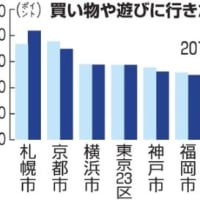先週末2月26日と27日の二日連続で、毎日新聞が禁煙治療についての社説を載せています。
26日: 社説:視点 禁煙治療 依存症の軽重、無視する子供っぽさ=論説委員・北村龍行
27日: 社説:視点 禁煙治療 おせっかいの功と罪、広がる依存癖が心配=論説委員・三木賢治
違う論説委員が、同工異曲を2日連続で行うというのも奇異な感じがしますが、内容も首を傾げるものです。そこでひと言いわせてもらうことにしました。
今日は、26日の社説を取り上げさせてもらいます。まずは、原文をご一読ください。
**********
社説:視点 禁煙治療 依存症の軽重、無視する子供っぽさ=論説委員・北村龍行
06年度の診療報酬改定で「ニコチン依存症管理料」が認められた。保険が適用されるということは、その症状が公的に「病気」とみなされる、ということだ。まるで「喫煙は病気」のような雰囲気になってきた。
しかし、喫煙が病気ということではない。禁煙しない人に保険は適用されない。自分で禁煙した人にも保険は適用されない。自分では禁煙できずに、医師の治療を求めた場合にのみ保険が適用され、病気とみなされるのだ。
では、その病気とは何か。ニコチン依存症である。世界保健機関によれば依存症とは「ある薬物の精神効果を体験するため、また退薬による苦痛から逃れるために、その薬物を継続的あるいは周期的に摂取したいという強迫的欲求を常に伴う行動や、その他の反応に特徴づけられる状態」とある。
ある薬物を継続的、周期的に摂取したいという欲求と、その欲求を満たすための反応や行動という二つの要素が示されている。欲求を持つのは本人の問題だが、その欲求を満たすための反応や行動は、周囲の人々の災厄や犯罪につながる恐れがある。
その依存症にも「乱用」と「依存症」があり、たばこや酒などの嗜好(しこう)品の場合の「乱用」は健康、社会生活を破たんさせるほど摂取すること、「依存症」は「使用していない時に離脱症状、禁断症状がでる状態」とされる。
たばこに「乱用」があるだろうか。ごく少数の例外を除けば、たばこ代のために犯罪を働いたり、破産したりはしない。喫煙のために仕事をしくじったり、たばこで友人関係が破たんしたりもしない。健康面での問題は残るが、たばこが社会生活を破たんさせるとは考えにくい。
「依存症」はどうだろう。離脱症状や禁断症状はあるが、禁煙社会化するなかで喫煙者はすでに、可能な時と場所でしか喫煙しなくなっている。離脱・禁断症状は喫煙者によって克服されている。
ニコチンは依存症を生む。しかし、それが本人あるいは周囲に及ぼす影響は、アルコールや他の薬物に比べて明らかに低い。喫煙率が下がり続けているが、非喫煙者と禁煙者の増加によるものだ。禁煙者の増加自体が、たばこの依存症が重くないことを証明する。さらに、たばこの害は科学的に証明されていると主張するなら、たばこの販売自体の禁止を主張すべきだろう。依存症だからといって、影響の軽重も考えずに病気扱いするのは、正義のためなら人を傷つけてもいいと考える子供にも似て、社会的成熟に欠ける。
かつて喫煙者が、間接喫煙被害者の苦痛に鈍感であったことは事実だ。しかし、すべての喫煙者を医師の診療なくして禁煙できない人とみなして病人扱いする風潮には、かつての喫煙者の鈍感さに通じるものがある。
毎日新聞 2006年2月26日 東京朝刊
**********
前半はよしとして、太字で示した後半の4段落が納得できません。段落ごとに物申させていただきます。
**********
たばこに「乱用」があるだろうか。ごく少数の例外を除けば、たばこ代のために犯罪を働いたり、破産したりはしない。喫煙のために仕事をしくじったり、たばこで友人関係が破たんしたりもしない。健康面での問題は残るが、たばこが社会生活を破たんさせるとは考えにくい。
**********
たばこに「乱用」はないと主張する北村氏です。しかし、果たしてそうでしょうか。
「ごく少数の例外を除けば、たばこ代のために犯罪を働いたり、破産したりはしない」と言いますが、「ごく少数の例外」が重要なこともあるはずです。第一、少年非行の第一歩は、喫煙から始まるものではないでしょうか。若年層の喫煙を無視してよいのでしょうか。
「喫煙のために仕事をしくじったり、たばこで友人関係が破たんしたりもしない」とおっしゃる意味が分かりません。
もはやスモーカーお断りの企業も増えてきていますし、スモーカーを恋人や配偶者にしたくないという人も増えているのです。この現実をどのようにお考えなのでしょう。
つまり、多くのタバコを吸わない人から見れば、喫煙者はタバコを「乱用」しているように見えるのだということです。
**********
「依存症」はどうだろう。離脱症状や禁断症状はあるが、禁煙社会化するなかで喫煙者はすでに、可能な時と場所でしか喫煙しなくなっている。離脱・禁断症状は喫煙者によって克服されている。
**********
信じられない発言です。「喫煙者はすでに、可能な時と場所でしか喫煙しなくなっている」とは、どこを見ておっしゃっているのでしょうか。禁止条例が存在するのに、歩きタバコはなかなか減らないのが現実です。これこそ「依存症」の喫煙者が相当数存在するという証明ではないでしょうか。
**********
ニコチンは依存症を生む。しかし、それが本人あるいは周囲に及ぼす影響は、アルコールや他の薬物に比べて明らかに低い。喫煙率が下がり続けているが、非喫煙者と禁煙者の増加によるものだ。禁煙者の増加自体が、たばこの依存症が重くないことを証明する。さらに、たばこの害は科学的に証明されていると主張するなら、たばこの販売自体の禁止を主張すべきだろう。依存症だからといって、影響の軽重も考えずに病気扱いするのは、正義のためなら人を傷つけてもいいと考える子供にも似て、社会的成熟に欠ける。
**********
いやはや、この段落も独断に満ち溢れています。
「ニコチンは依存症を生む。しかし、それが本人あるいは周囲に及ぼす影響は、アルコールや他の薬物に比べて明らかに低い」とは、どういうことでしょう。受動喫煙の害を無視されるのでしょうか。
「禁煙者の増加自体が、たばこの依存症が重くないことを証明」しているとおっしゃいますが、依存症の問題はその軽重ではなく、依存症が存在するということではないのでしょうか。やめたいのにやめられない人がいる現実をどう見るかなのです。その人たちが、安価に禁煙治療を受けたいと言ったとしたら・・・。
「依存症だからといって、影響の軽重も考えずに病気扱いするのは、正義のためなら人を傷つけてもいいと考える子供にも似て、社会的成熟に欠ける」という最後の文にいたっては、ゴウ先生、よく理解できません。
ニコチン依存症であると認定されて治療を受けるということが、社会的差別を受けると北村氏はお考えなのでしょうか?
ゴウ先生は、そんなことはない気がします。タバコをやめるために禁煙治療を受けていると会社でカミングアウトする社員を、好意的に受け入れない会社があるとは思えないのです(JTは別ですが)。
さらに、「正義のためなら人を傷つけてもいいと考える子供」というたとえは、だれが見ても穏当な言い方ではありません。もう少し慎重な言い回しが必要ではないでしょうか。
**********
かつて喫煙者が、間接喫煙被害者の苦痛に鈍感であったことは事実だ。しかし、すべての喫煙者を医師の診療なくして禁煙できない人とみなして病人扱いする風潮には、かつての喫煙者の鈍感さに通じるものがある。
**********
これでは、あたかもいまの喫煙者が常に周囲に気配りしてタバコを吸っている印象があります。しかし、上述したように、それは正しくありません。相変わらず、スモーカーのほとんどはわれわれ「間接喫煙被害者の苦痛に鈍感」なのです。
ともあれ、禁煙治療の善悪は別として、タイトルにも見られるような(「子供っぽさ」)少々品位に欠ける発言には苛立ちを覚えます。
喫煙者が、タバコを吸わない人のことをきちんと考えて、公共の場での喫煙を一切しないようになってくれてからの発言であるならば、耳を傾けます。
しかし、現在日々受動喫煙の被害を浴びている人間としては、北村氏のこの社説はなんともやりきれないものです。
北村氏がスモーカーであるかどうか知りません。しかし、もしそうであるならば、1ヶ月ほどおやめになってみてはいかがでしょう。それでも、ここでお書きのような考えがお変わりにならなければ、またお吸いください。
もしタバコをお吸いにならないのだとしたら、もう少しきちんと禁煙治療の具体的欠陥をお示しいただきたいと思います。
26日: 社説:視点 禁煙治療 依存症の軽重、無視する子供っぽさ=論説委員・北村龍行
27日: 社説:視点 禁煙治療 おせっかいの功と罪、広がる依存癖が心配=論説委員・三木賢治
違う論説委員が、同工異曲を2日連続で行うというのも奇異な感じがしますが、内容も首を傾げるものです。そこでひと言いわせてもらうことにしました。
今日は、26日の社説を取り上げさせてもらいます。まずは、原文をご一読ください。
**********
社説:視点 禁煙治療 依存症の軽重、無視する子供っぽさ=論説委員・北村龍行
06年度の診療報酬改定で「ニコチン依存症管理料」が認められた。保険が適用されるということは、その症状が公的に「病気」とみなされる、ということだ。まるで「喫煙は病気」のような雰囲気になってきた。
しかし、喫煙が病気ということではない。禁煙しない人に保険は適用されない。自分で禁煙した人にも保険は適用されない。自分では禁煙できずに、医師の治療を求めた場合にのみ保険が適用され、病気とみなされるのだ。
では、その病気とは何か。ニコチン依存症である。世界保健機関によれば依存症とは「ある薬物の精神効果を体験するため、また退薬による苦痛から逃れるために、その薬物を継続的あるいは周期的に摂取したいという強迫的欲求を常に伴う行動や、その他の反応に特徴づけられる状態」とある。
ある薬物を継続的、周期的に摂取したいという欲求と、その欲求を満たすための反応や行動という二つの要素が示されている。欲求を持つのは本人の問題だが、その欲求を満たすための反応や行動は、周囲の人々の災厄や犯罪につながる恐れがある。
その依存症にも「乱用」と「依存症」があり、たばこや酒などの嗜好(しこう)品の場合の「乱用」は健康、社会生活を破たんさせるほど摂取すること、「依存症」は「使用していない時に離脱症状、禁断症状がでる状態」とされる。
たばこに「乱用」があるだろうか。ごく少数の例外を除けば、たばこ代のために犯罪を働いたり、破産したりはしない。喫煙のために仕事をしくじったり、たばこで友人関係が破たんしたりもしない。健康面での問題は残るが、たばこが社会生活を破たんさせるとは考えにくい。
「依存症」はどうだろう。離脱症状や禁断症状はあるが、禁煙社会化するなかで喫煙者はすでに、可能な時と場所でしか喫煙しなくなっている。離脱・禁断症状は喫煙者によって克服されている。
ニコチンは依存症を生む。しかし、それが本人あるいは周囲に及ぼす影響は、アルコールや他の薬物に比べて明らかに低い。喫煙率が下がり続けているが、非喫煙者と禁煙者の増加によるものだ。禁煙者の増加自体が、たばこの依存症が重くないことを証明する。さらに、たばこの害は科学的に証明されていると主張するなら、たばこの販売自体の禁止を主張すべきだろう。依存症だからといって、影響の軽重も考えずに病気扱いするのは、正義のためなら人を傷つけてもいいと考える子供にも似て、社会的成熟に欠ける。
かつて喫煙者が、間接喫煙被害者の苦痛に鈍感であったことは事実だ。しかし、すべての喫煙者を医師の診療なくして禁煙できない人とみなして病人扱いする風潮には、かつての喫煙者の鈍感さに通じるものがある。
毎日新聞 2006年2月26日 東京朝刊
**********
前半はよしとして、太字で示した後半の4段落が納得できません。段落ごとに物申させていただきます。
**********
たばこに「乱用」があるだろうか。ごく少数の例外を除けば、たばこ代のために犯罪を働いたり、破産したりはしない。喫煙のために仕事をしくじったり、たばこで友人関係が破たんしたりもしない。健康面での問題は残るが、たばこが社会生活を破たんさせるとは考えにくい。
**********
たばこに「乱用」はないと主張する北村氏です。しかし、果たしてそうでしょうか。
「ごく少数の例外を除けば、たばこ代のために犯罪を働いたり、破産したりはしない」と言いますが、「ごく少数の例外」が重要なこともあるはずです。第一、少年非行の第一歩は、喫煙から始まるものではないでしょうか。若年層の喫煙を無視してよいのでしょうか。
「喫煙のために仕事をしくじったり、たばこで友人関係が破たんしたりもしない」とおっしゃる意味が分かりません。
もはやスモーカーお断りの企業も増えてきていますし、スモーカーを恋人や配偶者にしたくないという人も増えているのです。この現実をどのようにお考えなのでしょう。
つまり、多くのタバコを吸わない人から見れば、喫煙者はタバコを「乱用」しているように見えるのだということです。
**********
「依存症」はどうだろう。離脱症状や禁断症状はあるが、禁煙社会化するなかで喫煙者はすでに、可能な時と場所でしか喫煙しなくなっている。離脱・禁断症状は喫煙者によって克服されている。
**********
信じられない発言です。「喫煙者はすでに、可能な時と場所でしか喫煙しなくなっている」とは、どこを見ておっしゃっているのでしょうか。禁止条例が存在するのに、歩きタバコはなかなか減らないのが現実です。これこそ「依存症」の喫煙者が相当数存在するという証明ではないでしょうか。
**********
ニコチンは依存症を生む。しかし、それが本人あるいは周囲に及ぼす影響は、アルコールや他の薬物に比べて明らかに低い。喫煙率が下がり続けているが、非喫煙者と禁煙者の増加によるものだ。禁煙者の増加自体が、たばこの依存症が重くないことを証明する。さらに、たばこの害は科学的に証明されていると主張するなら、たばこの販売自体の禁止を主張すべきだろう。依存症だからといって、影響の軽重も考えずに病気扱いするのは、正義のためなら人を傷つけてもいいと考える子供にも似て、社会的成熟に欠ける。
**********
いやはや、この段落も独断に満ち溢れています。
「ニコチンは依存症を生む。しかし、それが本人あるいは周囲に及ぼす影響は、アルコールや他の薬物に比べて明らかに低い」とは、どういうことでしょう。受動喫煙の害を無視されるのでしょうか。
「禁煙者の増加自体が、たばこの依存症が重くないことを証明」しているとおっしゃいますが、依存症の問題はその軽重ではなく、依存症が存在するということではないのでしょうか。やめたいのにやめられない人がいる現実をどう見るかなのです。その人たちが、安価に禁煙治療を受けたいと言ったとしたら・・・。
「依存症だからといって、影響の軽重も考えずに病気扱いするのは、正義のためなら人を傷つけてもいいと考える子供にも似て、社会的成熟に欠ける」という最後の文にいたっては、ゴウ先生、よく理解できません。
ニコチン依存症であると認定されて治療を受けるということが、社会的差別を受けると北村氏はお考えなのでしょうか?
ゴウ先生は、そんなことはない気がします。タバコをやめるために禁煙治療を受けていると会社でカミングアウトする社員を、好意的に受け入れない会社があるとは思えないのです(JTは別ですが)。
さらに、「正義のためなら人を傷つけてもいいと考える子供」というたとえは、だれが見ても穏当な言い方ではありません。もう少し慎重な言い回しが必要ではないでしょうか。
**********
かつて喫煙者が、間接喫煙被害者の苦痛に鈍感であったことは事実だ。しかし、すべての喫煙者を医師の診療なくして禁煙できない人とみなして病人扱いする風潮には、かつての喫煙者の鈍感さに通じるものがある。
**********
これでは、あたかもいまの喫煙者が常に周囲に気配りしてタバコを吸っている印象があります。しかし、上述したように、それは正しくありません。相変わらず、スモーカーのほとんどはわれわれ「間接喫煙被害者の苦痛に鈍感」なのです。
ともあれ、禁煙治療の善悪は別として、タイトルにも見られるような(「子供っぽさ」)少々品位に欠ける発言には苛立ちを覚えます。
喫煙者が、タバコを吸わない人のことをきちんと考えて、公共の場での喫煙を一切しないようになってくれてからの発言であるならば、耳を傾けます。
しかし、現在日々受動喫煙の被害を浴びている人間としては、北村氏のこの社説はなんともやりきれないものです。
北村氏がスモーカーであるかどうか知りません。しかし、もしそうであるならば、1ヶ月ほどおやめになってみてはいかがでしょう。それでも、ここでお書きのような考えがお変わりにならなければ、またお吸いください。
もしタバコをお吸いにならないのだとしたら、もう少しきちんと禁煙治療の具体的欠陥をお示しいただきたいと思います。