ウミガメの上に新種の生物が住んでいたなんて、何かいいですよねえ、ロマンとメルヘンを感じます。
**********
アカウミガメの甲羅に生息する新種の甲殻類が鹿児島県で発見され、浦島太郎にちなんで「ウラシマタナイス」と命名された。写真は新種と確認されたウラシマタナイスの雄(左)と雌=北海道大の田辺優航さん提供【時事通信社】
(時事通信)
アカウミガメの甲羅に生息する新種の甲殻類が鹿児島県で発見され、浦島太郎にちなんで「ウラシマタナイス」と命名された。北海道大の角井敬知講師や大学院生の田辺優航さんらの研究チームが見つけ、国際動物学誌ズータクサ電子版に論文が掲載された。
ウラシマタナイスは体長数ミリで、大きなはさみを持つ。詳しい生態は不明だが、脚から糸を出してカメの甲羅の上に管状の巣を作り、生活しているとみられる。
研究チームは2016年、鹿児島県・屋久島に産卵のため上陸したアカウミガメの甲羅から、微小生物を採取。詳しく調べたところ、口の特徴などからウラシマタナイスを新種と確認した。
ウミガメに乗って生活 新種の甲殻類「ウラシマ」と命名
朝日新聞 2017年11月28日16時25分
ウミガメの甲羅の上で暮らす新種の甲殻類を、北海道大の角井敬知(かくいけいいち)講師(系統分類学)らが発見した。甲羅に乗って海中を旅する浦島太郎の物語にちなんで、「urashima(ウラシマ)」の文字を含む学名をつけ、分類学の国際専門誌に発表した。
この甲殻類はタナイス目の一種。体長2~3ミリで、はさみを持つ。ウミガメに付着するフジツボなどを研究する日本工営中央研究所の林亮太研究員が甲羅に付着していた個体を採取して角井さんに送ったことが、新種発見のきっかけになった。
昨年5~6月に鹿児島県・屋久島で改めて調査を実施。砂浜に上陸したアカウミガメの甲羅上から採取し、体の構造を顕微鏡で詳しく調べた。その結果、脚や触角の特徴などが、既知のどの種とも異なることが分かった。
アカウミガメは国際自然保護連合(IUCN)のレッドリストで絶滅危惧種に指定されている。角井さんは「生物多様性を守るには、ウミガメだけでなく、小さな寄生生物にも目を向けることが大切だ」と話している。(合田禄)
**********
名前が「ウラシマタナイス」というのも、泣けます。どうせなら、「ウラシマタロウ」ではいけなかったのかとおもったら、「タナイス目」の一種ということで、こればかりは仕方ないようです。
なお、「タナイス」というのは、ロシアの有名なドン川(『静かなるドン』!)の旧名に由来するのだとか。生物学者がつける名前というのも、面白いものです。
ともあれ、アカウミガメともども、ウラシマタナイスも、いつまでも元気に生活していってほしいです。絶滅するのは、悲しすぎます。
発見された方々、その地道な努力に頭が下がります。がんばってください。










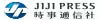




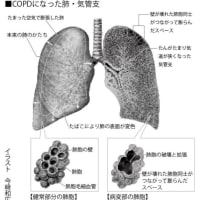
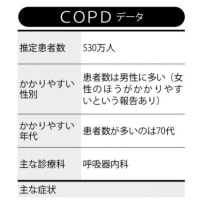




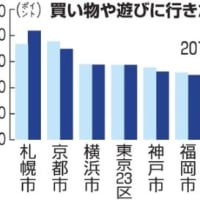





※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます