ドジョウ首相の所信表明演説が行われました。新聞は、どう評価するのだろうと思ったら、ほぼ同じ見出しで批判してきました。
産経・朝日・毎日が「覚悟」がないと文句をつけます。
産経: 所信表明演説 首相の「覚悟」感じられぬ
朝日: 2度目の所信―首相こそ覚悟を示せ
毎日: 所信表明演説 首相の覚悟いつ示す
読売だけは、「器量」に焦点。
読売: 所信表明演説 首相自身の「器量」も試される
ともあれ、ドジョウ首相が「安全運転」ばかりして実行力を示さないところに、国民のみならずマスコミも不満を抱いています。どうにかしてもらわないと。でも、ドジョウじゃ、無理かもしれません。
一日も早い解散総選挙を望みます。
以下、4紙の社説を記録しておきます。
**********
【主張】所信表明演説 首相の「覚悟」感じられぬ
2011.10.29 04:13
東日本大震災に加え、産業空洞化や東シナ海での中国の活動活発化など内外の危機を抱えた時期だからこそ、最高指導者の国のかじ取りが注視される。
2度目となる野田佳彦首相の所信表明演説は、それを明らかにする好機だったはずだ。だが、「安全運転」ばかりが目立ったのは極めて残念である。
首相が明確な針路を示さなければ、国政の停滞は打開できない。冒頭で掲げた「政治家の覚悟と器量」を問われているのは首相自身であることを自覚すべきだ。
本格復興のための約12兆円にのぼる第3次補正予算案は、震災から7カ月半でようやく提出された。だが、復興財源を増税で確保する姿勢は変わらない。「国家の信用が問われる」などと説明したが、なぜ国民に負担を求めなければならないのかの理由は、十分明かされないままだ。
焦点の環太平洋戦略的経済連携協定(TPP)の交渉参加は、「しっかり議論し、できるだけ早く結論を出す」と、前回の演説から一歩も進んでいない。
歳出削減と税外収入確保に「断固たる決意で臨む」のは至極当然である。遅きに失したが首相らの給与をカットし国会の定数削減を求めるなど、政治家自らが身を削る姿勢は見え始めた。政権公約である国家公務員総人件費の2割削減にも早急に着手すべきだ。
米軍普天間飛行場移設問題では「日米合意を踏まえつつ、沖縄の負担軽減を図る」という従来の見解を繰り返すだけだった。27日に沖縄県の仲井真弘多知事と初めて会談した際、知事から沖縄訪問を要請されても答えなかった。
民主党政権が目指した県外移設論とその頓挫こそが、沖縄の辺野古移設反対論を拡大した。中国海軍の活動活発化により、沖縄海兵隊などの抑止力の意義は高まっている。民主党の失政を謝罪し、日米合意への理解を求める努力の先頭に首相が立たねばならない。
前回の演説で「経済社会の血液」と指摘した電力の安定供給についての言及がなかったのも問題だ。停止中の原発を再稼働させるとの方針は、党内外の反発を恐れて後退してしまったのか。
TPP問題をはじめ、首相が政治生命を懸けて決断しなければならない課題は山積している。今後の国会論戦を通じて、「覚悟」を示してもらいたい。
所信表明演説 首相自身の「器量」も試される(10月29日付・読売社説)
野田内閣の発足から2か月近くになる。首相はいつまでも安全運転の姿勢では済まされない。
野田首相が衆参両院本会議で、所信表明演説を行った。臨時国会の課題として、震災復興、原発事故の収束、日本経済の立て直しの3項目を挙げ、今年度第3次補正予算案と関連法案の早期成立を訴えた。
さらに、「私たち政治家の覚悟と器量が問われている」と述べ、与野党の国会議員に、協力と結束を繰り返し呼びかけた。
そう言う以上、首相自身が、時には敢然とリスクを取る「覚悟」と、重要課題を着実に前に進めていく「器量」を率先して行動で示すことが求められる。
東日本大震災から7か月以上が経過したのに、復旧・復興作業は大幅に遅れ、原発事故周辺地域の除染作業も滞っている。歴史的な円高に歯止めをかける対策も、効果を上げていない。
与野党は、補正予算案と関連法案を一日も早く成立させなければならない。民主、自民、公明の3党協議では、復興財源の増税の期間や品目などで隔たりがあるが、メンツにこだわらず歩み寄り、合意点を探るべきだ。
首相は9月中旬の最初の所信表明演説では、政策課題を網羅的に取り上げた。今回は、臨時国会の課題に絞り、演説の分量も減らした。その意図は理解できる。
しかし、喫緊の課題では踏み込んだ対策を示さず、社会保障と税の一体改革や原子力発電所の再稼働問題に言及しなかったのは、物足りなかった。
環太平洋経済連携協定(TPP)への参加問題についても、首相は、「できるだけ早期に結論を出す」と述べるにとどまった。
交渉参加の事実上の期限であるアジア太平洋経済協力会議(APEC)が11月中旬に迫る中、民主党内では依然、参加賛成派と反対派が激しく対立している。
そろそろ首相が自ら指導力を発揮し、参加表明を決断する時だ。その際、民主党内だけでなく、国民全体に正確な情報を提供し、参加のメリットを示して、理解を求める必要がある。
それには、市場開放に耐えられるだけの農業強化策を加速するなど、TPP参加を実現するための具体的な戦略が欠かせない。
消費税率引き上げや、米軍普天間飛行場の移設などの困難な課題についても同様だ。問題解決に向けて、日程を組み、布石を打ち、閣僚や官僚をきちんと使いこなす首相の手腕が試されよう。
(2011年10月29日01時17分 読売新聞)
2度目の所信―首相こそ覚悟を示せ
朝日新聞
震災復興、原発事故の収束、日本経済の再生に向け、第3次補正予算と関連法を一日も早く成立させる。野党との「共同作業」で責任を果たしたい。
野田首相がきのうの所信表明演説に込めたメッセージは、単純明快だ。
東北には冬の足音が近づく。速やかに被災者の生活を再建し、将来に希望が持てる環境を整える。それが政治の仕事だ。
その財源として、首相は時限的な増税を求めた。
「欧州の危機は対岸の火事ではない」「(日本で)きょう生まれた子ども1人の背中に700万円を超える借金がある」
首相が語った財政への危機感は、私たちも共有する。歳出削減や増収策を徹底しても、なお足りない部分を国民が分かち合うのはやむを得まい。自民、公明両党と復興増税の期間などの詰めの協議を急ぐべきだ。
それにしても、である。
9月以来、2度目の首相の所信表明なのに、あまりにも首相の覚悟が見えない。「安全運転」はわかるが、これで政治が動くのかと心配になる。
典型例が環太平洋経済連携協定(TPP)交渉への参加問題だ。前回の演説はこうだった。
「しっかりと議論し、できるだけ早期に結論を出します」
あれから1カ月半、政府・与党も野党も議論してきた。すでに野田政権が交渉参加の方向で意見集約をめざしているのは、誰の目にも明らかだ。
それなのに今回はこうだ。
「引き続き、しっかりと議論し、できるだけ早期に結論を出します」
これはつまり、党内調整が大詰めを迎えているいま、自分が余計な発言をすることで波風を立てたくない、ということか。
この態度は明らかに国会演説の意義を軽視している。国民への説明を避けているに等しい。
国民注視の原発・エネルギー政策の方向性もまだ抽象的だ。政治家が身を切る覚悟を強調しながら、定数削減の具体策は与野党任せである。臨時国会のテーマではないとして、社会保障には触れもしない。
しかし、就任2カ月の首相に求められているのは、国民に率直に信念を訴え、理解と支持を得ることだ。それが政策を収斂(しゅうれん)する力にもなる。
首相は演説の冒頭と結びで、全国会議員に政治家の「覚悟と器量」を求めた。それなら、まず首相が示すべきだ。
20年以上の早朝の街頭演説を政治活動の原点という首相ならば、もっと「言葉の力」を見せてほしい。
社説:所信表明演説 首相の覚悟いつ示す
今度の臨時国会が抱える課題を簡潔に分かりやすい言葉で国民に訴えてはいたが、肝心な話になると自らの考えは鮮明にしない--。野田佳彦首相の所信表明演説は、そんな物足りなさが残った。
各党間の議論が煮詰まらないうちに首相が方向性を決めつけては話がまとまらなくなるというのが、ひたすら低姿勢で臨む野田首相流ではあろう。だが、就任後、約1カ月半経過し、所信表明演説も2回目だ。東日本大震災の復旧・復興と原発事故の収束、そして国際的な経済危機にどう立ち向かうのか。この日、首相は「私たち政治家の覚悟と器量が問われている」と与野党議員に呼びかけたが、そろそろ自分の覚悟を具体的に示していかないと首相としての器量にも疑問符がつくことになる。
例えば首相は第3次補正予算案の財源について「政府全体の歳出削減と税外収入の確保に断固たる決意で臨む」としたうえで、復興増税に理解を求めた。復興債の償還期限など今後の与野党協議の焦点となる事項に関し、具体的に言及しなかったのは、野党への配慮と思われる。
ただし、演説で「今日生まれた子ども1人の背中には、既に700万を超える借金がある」と語ったように、首相は今の国の財政に人一倍危機感を持っているはずだ。そうであるなら、なぜ税と社会保障の一体改革、つまり消費税引き上げ問題に一言も触れなかったのか。
多くの国民は復興増税にとどまらず、消費税や社会保障の行方に関心を持っている。今国会の議案ではないとはいえ、何らかの形で首相の考えを示してもらいたかった。
深刻な政治対立テーマになりつつある環太平洋パートナーシップ協定(TPP)の交渉参加問題に至っては「引き続きしっかりと議論し、できるだけ早期に結論を出す」と素っ気なく語るのみだった。
民主党内でも反対論が日に日に強まっているが、首相が交渉参加に極めて前向きなのは疑いないところだ。首相の周辺からは「反対論には多くの誤解がある」といった不満も聞こえる。ならば、せめてTPP参加がどれだけ、この国にとってプラスになるのか、あるいはマイナス点は何なのか、論点を示すくらいはすべきではなかったか。
週明けからは代表質問が始まる。首相は今後、国会論戦を通じて自らの考えを明らかにしていくつもりなのだと、ここは信じることとしよう。当面、衆院解散・総選挙はありそうもない状況だ。与野党ともに腰を落ち着けて、国の将来を見すえた議論をしてもらいたい。そんな国会となるよう先導していくのも首相の器量というものだ。
毎日新聞 2011年10月29日 2時32分













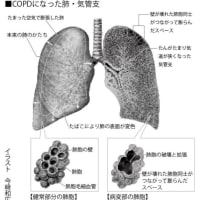
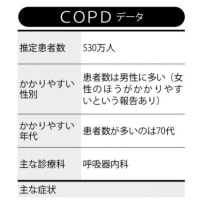




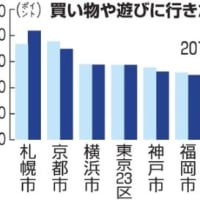





現実の内容は、「世の中は、、、、、」の内容であり、理想の内容は、「あるべき姿」の内容である。これは非現実である。
日本語には時制がなく、日本人は現実 (現在) と非現実 (過去・未来) の世界を独立させて並行して言い表すことが難しい。
非現実 (理想) に向かうための現実対応策が語れない。
現実から理想へと一足飛びに内容が飛ぶ。言霊の効果のようなものか。その過程が明確にされない。
時制を考慮することなく自分の思った内容を述べようとすると、現実肯定主義派と空理空論 (曲学阿世) 派のどちらかに分かれることになる。
これでは政治音痴は止まらない。
両者は話が合わない状態に陥り、議論ができない。そこで、悪い意味での数合わせで、民主的に、物事を決するしかないことを日本人は心得ている。
だから、多数がとにかく足並みをそろえる大連立の構想には意味があると考えられているのであろう。
守旧派の世界は理想的ではないが、過不足なく成り立っている。革新派の世界は穴だらけで成り立たないことが多い。
安心と不信の背比べである。だから、政治家は静観が多く、意思決定には手間を取る。
静観には現在時制を働かせるだけで十分であるが、意思決定に至るには意思(未来時制の内容)の制作が必要になる。
意思の制作に未来時制が必要であるということは、自分が意思を作って示すことも他人から意思を受け取ることも難しいということになる。
つまり、社会全体が意思疎通を欠いた状態のままでとどまっているということである。
それで、勝手な解釈に近い以心伝心が貴重なものと考えられている。
時代に取り残されるのではないかという憂いが常に社会に漂っている。
英米人の政治哲学に基づいて次々と繰り出されてくる条約締結の提案には、ただたじろぐばかりである。
自分たちには、哲学がない。理想もなければ、それに向かって踏み出す力もない。
筋道を明らかにされることのない指導者からの励みの要請に民は閉塞感を持っている。玉砕戦法のようなものか。
だから、我々は耐え難きを耐え、忍び難きを忍ぶ必要に迫られることになる。
http://www11.ocn.ne.jp/~noga1213/
http://page.cafe.ocn.ne.jp/profile/terasima/diary/200812