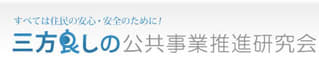「ワシもう帰る」
「呑まなきゃやってられんわ」
「明日二日酔いやけどゴメンね」
なんて言葉を吐いて会社をあとにしたのは数日前。
結局のところヤケ酒にはならず、そのセリフの原因となった事柄を女房殿に二言三言話すと、あとはいつもとそんなに変わらぬ、いやいつも以上にくつろげる酒になった。
思い起こせば長いあいだ、しびれるほど呑んでその日をリセットするのが日課だった。
プレッシャーやら思いどおりにならないこと。それらの憂さを酒で晴らそうとするのが常だった。
いつのころからだろう。そんなに遠い過去ではないはずだ。ヤケ酒は極力呑まないと思い定めた。
呑むんだったら、楽しい酒を呑みましょう。うれしい酒を呑みましょう。ときに淡々と、ときにはしゃいで。とにもかくにも、陰々滅々とした酒は排しましょう。
もちろん、哀しい酒もあっていい。ヤケ酒もあっていい。だがそれは、わたしがわたし自身に向けたものではなく、誰かが哀しいとき誰かが自棄になったときに付き合う酒としてあってわたしのなかで初めて酒となる。わたし自身のヤケ酒は極力つつしむが、もし「ヤケ酒につきあってくれ」という他人がいれば、積極的に付き合わうのが正しい酒呑みだ。
そんなふうな考えと行為は、いつのまにか習い性となってしまったようで、「よし今日は自棄になって呑む、シビレルまで呑む」と思い込んでも、そんな酒は持続せず、そんなときには特に、つとめて楽しいつとめて明るい酒へと転換してしまう自分がいる。とかナントカ、そんなことを考えながら一杯、また一杯。「オレも少しはまともな人間に近づいてきたか?」などと自問自答しつつもう一杯。その夜の酒はいつもに増してくつろげるものとなった。
「ああ、これこそがヤケ酒がダメな理由(わけ)だな」と得心した話がある。
釈迦だ。
つい最近、『非常識な読書のすすめ』(清水克衛、現代書林)という本で知った。
紹介する。
ある日突然、矢がバーンと飛んできて胸を射貫かれたとします。無防備なところに飛んできたわけですから、その矢は避けようがありません。でも、次に飛んでくる第二の矢は、人間の知恵で避けられる、というのです。
(略)
重要なのは、第二の矢は現実ではない。非現実だということです。第二の矢はあくまで脳内でつくり出されるバーチャルなものに過ぎません。
ですから、第一の矢は避けられませんが、第二の矢は避けられます。苦痛を感じても、それに対する嫌悪感が生じるのを遮断できればいいのです。快楽も苦痛もただのデータだと受け止められれば、心が動じることはありません。
(略)
人のせいにして怒っているより、自分に今できること、自分が生み出せることを考えて、そこに全力を注ぎましょう。
第二の矢を避けるセンスが大事です。知恵さえあれば、第二の矢は避けることができるし、チャンスに変えることさえできるのです。
(Kindle版位置No.1413~1443)
酒はいい。じつにいい。
だがこわくもある。ヤケ酒がまさにそれだ。
ヤケ酒というものは、脳内でバーチャルなものをつくり出し、自ら進んで「第二の矢」に当たるように自らを仕向ける自爆行為に他ならない。そこからは、第二の矢を避けるセンスも知恵も生まれないし、もちろんのこと、それをチャンスに変えることもでき得ない。
呑むんなら楽しい酒を、明るい酒を。
とはいえ人生そんな単純なものではない。哀しく暗い酒になることもあるだろうが、そのときは、自らのなかに湧き上がる負の感情を増幅させることなくひとり静かに淡々と呑むべし。
正しい酒呑みとはそういうものだと、近ごろとみにそう思う。
(あ、いいんですよ、若いアナタは。それもこれも経験です。どんどんやっちゃってください。さんざんやらかしてきた還暦前のオジさんが、さんざんやらかした末に腹に入った結論です)
(あ、それともうひとつ。この先もし、アナタの眼前に自棄になってくだを巻くわたしがいたら、ゴメンね、といってスキンヘッドをボリボリ掻くしかない。どうぞ見逃してやってください ^^;)
2016.07.04
こっちのほうがわかりやすいかな?っていうことで加筆。
【第二の矢】
http://www.soto-kanto.net/image/radio/220403.pdfより
今からおよそ2600年前のインド。 ある日お釈迦さまは、弟子たちに質問をされました。 「いまだ正しい教えを聞いたことがない人も、すでに正しい教えを聞き、それ を学ぶ人も、喜びを感じたり、苦しさを感じたりする。 では、正しい教えを聞いたことがない人と、正しい教えを聞き、学ぶ人とは、 どこが違うのだろうか。」
この質問に弟子たちは答えることができませんでした。お釈迦さまは、二つの矢の たとえをもってその違いをお話になりました。
「いまだ正しい教えを聞いたことがない人は、 第一の矢を身体で受け、さらに第二の矢を心で受けるようなものである。 第一の矢とは、身体で感じるということである。 第二の矢とは、執着する心である。正しい教えを聞きそれを学ぶ事がない為に喜びを感じればそれに執着する心が生まれ、また、苦しさを感じれば怒りの心が生まれ、結果、煩悩に囚われてしまう。だが、正しい教えを聞きそれを学ぶ人は、第一の矢を受けるが、第二の矢を受けることがないのである。喜びを感じても、それに執着する心が生まれることがない。また、苦しさを感じても、怒りの心が生まれないので、結果、煩悩に囚われることがないのである。」
お釈迦さまも私たちと全く同じ感覚を持っていたということが分かります

↑↑ クリックすると現場情報ブログにジャンプします
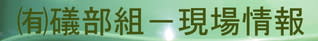
有限会社礒部組が現場情報を発信中です
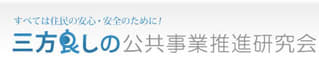
発注者(行政)と受注者(企業)がチームワークで、住民のために工事を行う。

にほんブログ村