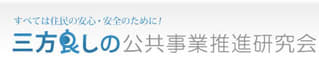カレーのことなどを書いてみたいと思う。
新潟万代シティバスセンターのカレーのことである。
「昼メシどうします?」
三方良しの公共事業推進研究会の研修会および理事会出席のため新潟へと向かう往路、伊丹空港でいっしょになった友人にそう訊かれたわたしは、ちゅうちょなく「カレー」と答え、そのあとすぐ「バスセンターの」とつけ足した。
その彼には若年の同行者が二人。
「おい、君ら、もうしわけないけど初めての新潟メシは立ち食いや」
こと「食う」ということに関して、少なくとも他人さまと同行するときは、まっ先にアレを食いたいだのコレを食うだのと自己主張をすることがほとんどないわたしは、その言葉を聞いて「なんと自己中心的な発言だったのだろう」と少しばかり反省したがまあいい。それはそれだ。わたしは未だ食したことがないにせよ名にし負う新潟名物だ。「初めての新潟メシ」にして何の不足があるだろう、と気を取り直しタクシーに乗り込む。バスセンターのカレーを食べにタクシーで行く。なんという贅沢だろう。
途中、思いついたようにくだんの友人が言った。
「あ、もうしわけないけどひとりで行ってもらってかまいません?コイツらにはへぎ蕎麦でも食わしたりますわ」
「あ、ええよ。そうやね、初めての新潟メシが立ち食いカレーっていうのはどうもね。へぎ蕎麦なら会場の近くに須坂屋っていう店があるからそこがいい。」
ということで万代シティ前で彼らと別れタクシーを降りたわたし。融けかけた雪を踏みしめドアを開けると、「万代そば」という看板がかかった一角があった。時間は12時半過ぎ。食券自動販売機の前には4人ほどが並んでいた。
二人連れの片割れのオジさんが若者に訊く。
「なんにする?」
「ぼくはカレー、大盛り」
「じゃあオレはミニカレーと〇〇蕎麦だな」
ざっと店内(といっても立ち食いのオープンスペースだが)を見わたすと、半分以上の人がカレーを食べている。若年のころより、「アレを食おう」と決めて食い物屋に行くとついつい別のものを食べてしまうという奇妙な癖があるわたしだが、今回はちゅうちょなく一点買い。カレーの食券を買いふたたび行列に並んだあと店員さんにわたすとすぐさま品物が出てきた。

そのヴィジュアル、匂い、・・・
「完璧じゃないか」と独りごち少し離れたカウンターに陣取った。隣りにはわたしより少しだけ若そうな女性の2人づれ。会話から推察すると観光客らしい。「オイシいね、うんオイシいね」と会話をはずませながらご満悦の体だ。期待で胸がふくらむ。待て待て落ち着けと水を一杯。そのあとおもむろにカレーを口に運ぶ。
「?」
ひと口目で生じた少しばかりの違和感を打ち消そうとたてつづけにスプーンを口に運んだ。だが、違和感はますます増大し、すぐに確信に変わった。
「コノカレーハウマクナイデハナイカ」
そう、うまくないのである。そうなると、誰それという芸能人が絶賛したとか、なんというTVプログラムで放映されたとかいう貼り紙がやたらと空疎なものに見えてしまう。そんななか、ゆっくりとそして黙々と、スプーンを口に運んでは周りを見回すという動作を繰り返しながら、初めてのバスセンターカレーを食べ終えると、「ごちそうさま」と返却口のおニイサンに言いながら、内心では「もう来ることはないだろうな」と思う。
もちろんのこと、味は好みである。そして、人の好みをとやかく言うほどわたしの舌が上等にできているわけではない。だがアレは・・・。いったいどういうことなのだろう。ドアを開け、歩道に残る雪を踏みしめながら考えた。答えは出ない。聞いてみるしかない。夕餉の会食で幾人かの地元民に問うてみた。
「アレってどうなの?」
驚いたことに「なに言ってんの、うまいでしょ?」という反応はひとつもない。皆おしなべて「アレはあんなもんなのだ」というような応え方をする。思い切って、さらに一歩踏み込んだ問いをぶつけてみた。
「うまくないでしょ?」
誰も否定しないなか、こんな答えをくれた人がいた。
「ウマいとかマズいとか、そんな次元のもんじゃなく郷愁の味。四国でたとえると”連絡船うどん”みたいなもんですよ」
「そうかパトリ(※)か」と膝を打ち、「な~るほどネ」と得心するわたし。
そういえば、今はなき”連絡船うどん”もうまくなかった。だが、宇高連絡船に乗るたびに食べていた。しかも毎回のように行列に並んでである。そして思い浮かべたのは、中高生時代に大好きだった”豚太郎の味噌ラーメン”。今となってはけっして「美味い」とは思わないアレもそうだ。都会に出て、初めて本物の味噌ラーメンを食ったときのうまさと衝撃と、それでもなお捨てきれなかった”豚太郎の味噌ラーメン”への愛着。たしかに、ウマいとかマズいとかで価値を云々してはいけない食べ物がある。そのような存在に対して、好悪の判断はともかく、ウマいとかマズいとかで評価してしまうという態度は不遜以外の何物でもないのではないか。そう思いはじめると、自分がやたらと恥ずかしくてたまらなくなってしまった。
帰路に着いた翌日、いつものように妻への土産「柿の種」を買おうと空港の売店に行く。すると、今までは気づくことがなかった「当店売り上げNo.1」というポップが目に飛びこんできた。そのワゴンにはレトルトの「バスセンターのカレー」が山積みにされていた。ふたたびむくむくと頭をもたげてくる疑念。
「郷愁の味ならわかる。パトリならわかる。だがなぜ土産なのだ。どうしてナンバーワンなのだ。どんだけの人がウマいウマいと言って食うのだコレを。。。」
いやいやだから、「ウマいとかマズいとかで価値を云々してはいけない食べ物なのだよアレは」と自分で自分に言い聞かせながらも釈然としないわたし。
バスセンターのカレー、それもこれもやあれやこれやの総てをひっくるめ、忘れられない味になった。そして、たぶんもう食べることはないだろうと確信し、おおぜいの人にそれを広言したにもかかわらず、なぜだかまたいつか食べたくなりそうな気がしてたまらない今なのである。
※パトリ
パトリとは、〈私〉が他ならぬ〈私〉であることの理由、つまり私が〈世界〉につながるための依って立つ地面のことである。パトリを足場にすることで 「〈世界〉に感染するための通路」(つまり第3象限のことである)は開かれる。
それは〈私〉が生まれ育った環境(育成環境)のことでもある。それは多くの場合、郷土や地域社会や学校や職業といった共同体性=種・中景のことであり、パトリとはパトリオティズム(愛郷主義)のことではあるが――それは国を愛するということを強要してはいない――。
(桃知利男『ももちどぶろぐ』2006年9月20日、より)

↑↑ クリックすると現場情報ブログにジャンプします
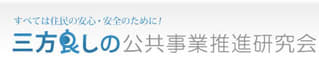
発注者(行政)と受注者(企業)がチームワークで、住民のために工事を行う。