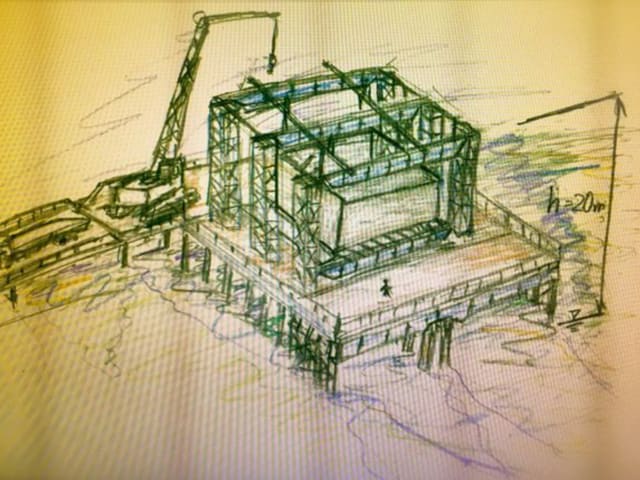オオタニさんの打棒がとまらない。
******
(『THE PAGE』05.27.5:40配信、より)
大リーグ公式サイトは「“ハードヒッティング・ショー”…大谷が117マイル(約188キロ)の本塁打をかっ飛ばす」との見出しを取り報じた。 記事は「打撃速度で、これまで最速だった115.2マイル(約185キロ)を上回り、彼のキャリアで最もハードヒッティングされた本塁打だった」と紹介。2015年にスタットキャストが導入されて以来、エンゼルスで最速だった本塁打で、今シーズンの本塁打では、フランチ―・コルデロ(レッドソックス)の118.6マイル(約191キロ)、ジャンカルロ・スタントン(ヤンキース)の118マイル(約190キロ)、ゲレーロJr.の117.4マイル(約189キロ)、マイク・ズニーノ(レイズ)の117.3マイル(約189キロ)、そしてスタントンの117.3マイル(約189キロ)に次いで6番目の最速本塁打だったという。
******
断っておくが、彼の活躍にイチャモンをつける気持ちなど微塵もない。
むしろその逆で、いつも凄いなぁと感嘆しながらテレビニュースの画面に映る同胞の若者を誇らしげに見るおじさんだ。
だが、それと同時に、近ごろではすっかり付き物となった観があるこの数字の羅列には、いつも、なんだかなぁと思ってしまう。
「いったいその数字のどこがおもしろいのかね?」
「どこのどいつがそんなものを知りたいのかね?」
いつもそう訊ねたい衝動にかられてしまう。
野球だけではない。
ことほど左様に、今という時代、渡る世間には数字があふれかえり、多くの人は数字に頼り切っている。
しばしば、なんだかとても不思議な感じがする。と同時に、心の奥底がざわざわっとしてしまうこともある。
「オマエのほうが不思議なんだよ」
もしもそう言われれば、返す言葉がない。
だからだろう。次のような文章に出会うと、思わず快哉を叫びたくなってしまうのだ。
******
技術が救世主だとか、過去に学ぶものはないとか、数字がすべてを物語るといったことを信じていると、やがて危険な誘惑の言葉にふらふらと吸い寄せられることになる。真実の断片をコツコツとつなぎ合わせる努力をせずに、特効薬を見つけようとしているようなものだ。(『センスメイキング――本当に重要なものを見極める力』クリスチャン・マスビアウ、Kindleの位置No.1021)
人間のあらゆる行動には、先の読めない変化が付き物なのだが、理系に固執していると、こうした変化に対して鈍感になり、定性的な情報から意味を汲み取る生来の能力を衰えさせることになる。世の中を数字やモデルだけで捉えるのをやめて、真実の姿として捉えるべきだ。(同No.200)
******
それとこれとを結びつけるのはコジツケだろうか。
いやいや、あながちそうとも言えないのではないだろうか。
数字とは切っても切り離せない仕事をしていながら、このようなことを書くのはいかがなものだろうか、という気がしないでもない。
しかし、近ごろのこのザマは、どうにも行き過ぎのような気がしてならない。
人間が人間という生物からどんどん離れていっているようで。
それはたしかに進歩なのかもしれないが、進化と呼ぶにはふさわしくないとわたしは思う。