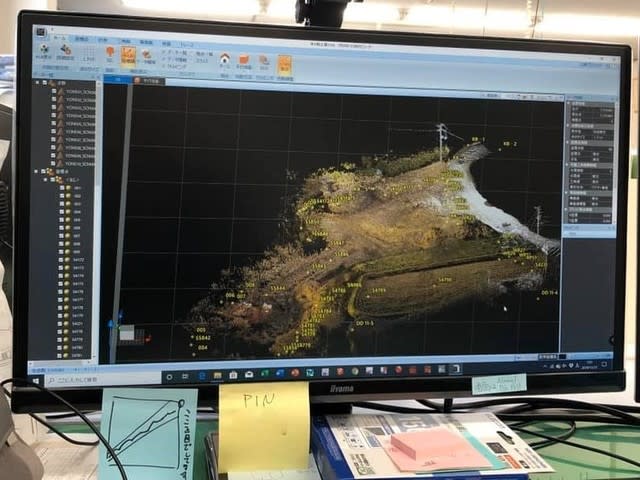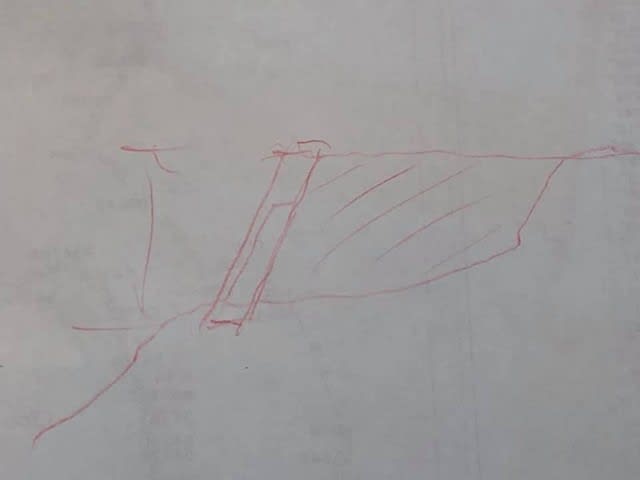きのうも書いたように、
設計変更で躯体のすべてが仕上がらなくなった旨を、地域の人たちや関係各所に伝えるための「工事だより」に、上のような3Dイメージをつくって載せるための画像だ。
そしてこれもきのう紹介したように、スケッチアップでつくっている。
ではこのあと、この構造物はどうなるのか?
その結果を、同じ「工事だより」上に載せなければならないのは当然のこと。
では、どのようなモデルにすればよいのか?
現在と未来(この場合は、ひと月先の未来とそれから3ヶ月ほど経過した未来)とを比較する場合、同じ土俵の上で異なる結果を表現するのがセオリーだろう。そのほうが読み手に理解しやすい。
しかし・・・
ここは少しひねってみることにした。

トレンドコアでつくった3Dモデルに、道路工事を担当したことがある技術屋にはおなじみの、「赤が実績」「青は計画」という色分けをしてみた。
そしてそれを、3DPDFでエクスポートし、加工をほどこしたものが上の画像だ。
つまり、

これが
次の工事では

こうなりますよ。
という比較である。
エラそうに開陳するほどのものではないし、CIMと呼ぶに値するほどの大層なものでもない(だから「ゆる〜いCIM」なのですが ^_-)
今日、言いたかったことはただひとつ。
ひとつのアプリケーションやひとつのツールに執着することなかれ。
また、ひとつのソフトウェアベンダーに依存するなかれ。
自分のアタマで考えて、自分の身体で実践してみると、おもしろいことができたりする。
以上、「ゆる〜いCIM」どころか、「ゆるすぎ〜るCIM」。
ごくごく些細なことから、あらためてそう思わされたので、備忘録(のようなもの)として。
↑↑ インスタグラム ーisobegumiー
↑↑ 土木のしごと~(有)礒部組現場情報