「自学ノート」は、呼び方を変えた「宿題帳」なのか。もしそうでないとすれば、その違いはどこにあるのだろうか。
いつ頃からか、職員室で「自学ノート」という言葉をよく耳にするようになった。私が以前勤務していた中学校でも、その前の学校でもよく使われていた。 生徒たちは、毎日「自学ノート」を学習係に提出し、担任が目をとおした(?)後、本人に戻されるようであった。「自学ノートの見本」として、優秀なノートをコピーした資料が配られることもあった。学級によっては、提出の有無や1日のページ数などを教室の掲示物としてグラフに書きこんでいるところもある。しかし、先生から呼び出されて、自学ノートの未提出を叱責されたり、約束のページが終わるまで放課後残ってやれと厳しく指導されたりしている場面もよく見かけた。
そんな時、先生の熱意はわかるが、本当に「その子のため」になっているのかと気になった。
▼自学ノートで不登校に?
自学ノートが苦痛で不登校になる生徒も出てきているのではないかと危惧する先生もいる。私も、確かにその危険性は否めないと思う。
本来、「自学ノート」とは、「自主的に学んだことをノートに整理したもの」であろう。それを先生に提出するということは、提出する生徒が自ら学ぶ上での疑問に答えてもらい、より発展的な学習へとつなぐためのアドバイスをもらうためではないのか。当然、その中で間違いや誤字などのチェックもなされ、表現の適切さやよりわかりやすくするための助言をもらい、「自学=自ら学ぶ」力を高めていくということではないのか。
自ら学ぶには意欲が必要である。中学生の多くはその意欲をもてず、学びから遠ざかることで苦悩から逃げているのではなかろうか。教えるプロである教師は、その意欲を引き出し、学びへとどう高めていくかに心血を注がなければならない。その知恵が、「自学ノート」の強制だとしたら浅薄であろう。習慣化することは、確かに人間の行動を変える手っ取り早い手段である。問題は、その生徒に応じた適切な強化となっているかということである。
前勤校では、「学習案内」の冊子を作成し、先生方の「学び方」の知恵を、生徒・保護者にわかりやすく伝えたいという取り組みを行った。年度当初、冊子を使ったオリエンテーションを実施し、そこから個に応じた学びの定着を支援していく教師の営みがスタートする。同時にそれを見守り支えていく家庭の意識も高めていくねらいなのだが、その効果を検証できないまま退いたのが残念である。
学習者の自主性を重んじるという「自学ノート」なら、係の生徒が集めてその量を競うようなやり方はそぐわないような気がする。もちろん、それを励みとして努力を続ける生徒も少なくないだろう。しかし、そうできるのは、おそらく家庭学習の習慣が身に着いており、「独り学び」ができる生徒たちであろう。教師が気になる、より重きをかけて支援する必要があるのは、そうではない生徒。つまり、「やる気がない」「宿題もしてこない」「忘れ物が多い」「放課後何回もやり直しをさせられている」「くらい表情で訴えている生徒たちである。
▼教師が見方を変えることから
では、どうやれば、そういう生徒に「自学ノート」と向き合わせられるだろうか。
それは、簡単である。教師が見方を変えることである。「自学ノート」が苦痛の種になっていて、担任の先生や教科担任の先生に合わせる顔がないと、暗い気持ちで登校している生徒にスポットライトを当て、支援の手を差し伸べようとする視点をもてばいい。これまで培ってき指導技術、実践力があれば、ターゲットとなる生徒の顔をじっと見ているだけで、妙案が浮かんでくるに違いない。
では、具体的に考えてみよう。
「自学ノート」を文字どおりにとらえてみる。「自ら学ぶ」ためのノート、「自ら学んだ」足跡を残すノート、「自ら学ぶ」方法を教えてもらえるノート、「自ら学んだ」ことをしっかり評価してもらえるノート、「自ら学ぶ」意欲がわいてくるノート、「自ら学ぶ」喜びが綴られるノート、「自ら学ぶ」自分の姿が見え学ぶ喜びを実感できる……、「自己肯定感」が高まるノートであろう。生徒の顔と見比べて教師が一つ一つ頭に思い浮かべてみると良い。
▼家庭での生活をイメージしてみる
もう一つの大切な観点として、家庭の支援をどのくらい得られるのかということが挙げられる。目の前の生徒は、家に帰ってからどのような生活をし、どのような家庭学習の積み重ねや歴史をもっているのだろうかとイメージしてみることである。
保護者が傍にいるのか。教えられるのか。理解はあるのか。きょうだいは何人で、上か下か、一人っ子か。落ち着いて学習できる環境か。机、学習用具や参考書、辞書・事典類は。インターネット環境は……と、学習者がノルマを果たそうと必死になって自学に取り組んでいる姿、あるいは、取り組めないで苦しんでいる姿をイメージしてみるとよい。
教師が生徒の心や生活の状況について思いを馳せることは、もっとも重要な資質である。
こう考えてくると、「自学ノート」にするなら、生徒がやってきた分でよしとすることである。つまり、「自己申告制」が最低の条件になる必要がある。もちろん、「やる・やらない」も含めてであり、「やらない子」を「やる子」にするのが教師の手腕である。
一人一人が様々な個性をもち、その個性を伸ばす教育を高らかに謳っている教師側にすれば、ある生徒が提出した自学ノート10頁と、別の生徒が提出した1行の軽重は計れないと思うのだが。
本来、自学ができるように指導することが教師の務めであり、自学が十分にできない生徒には、その子に合った学び方を指導する必要がある。その子がやれることを精一杯やってきた主体性をこそ、しっかりと認めてやるべきであり、引き出さねばならないことだと考える。
▼宿題は同じじゃないと不公平?
「課題は同じじゃないと不公平だ。」「子どもを差別してはならない。」「みな平等でなければ……」と、先生方は口に出す。
確かにそのとおりであるし、教育にとって欠くことのできない重要な視点であることに間違いない。ただ、その文言の意味するところについて、少し掘り下げて考えることも必要である。では、差別とは何だろうか。平等と均等は同じだろうか。
実は、前述の不公平論の多くは、子どもの側から出てくる幼い平等意識から発せられている。それを教師が口にする場合、「先生、なんでAさんだけいいんですか!」と問われて明確な答を出せない実践の曖昧さや、差別の現実から学びとれていない弱さがある。「人間はみんな違っている。一人一人が個性をもち、今を懸命に生きている。だから先生も精一杯勉強して、一人一人に応じて今やれる精一杯のことを探しているんだよ。」という教師の答を、「そうなんだ、先生は一人一人を、そして私を見てくれている」と受け止める「心」も、教室の中で同時に育てていかねばならないのである。
いつ頃からか、職員室で「自学ノート」という言葉をよく耳にするようになった。私が以前勤務していた中学校でも、その前の学校でもよく使われていた。 生徒たちは、毎日「自学ノート」を学習係に提出し、担任が目をとおした(?)後、本人に戻されるようであった。「自学ノートの見本」として、優秀なノートをコピーした資料が配られることもあった。学級によっては、提出の有無や1日のページ数などを教室の掲示物としてグラフに書きこんでいるところもある。しかし、先生から呼び出されて、自学ノートの未提出を叱責されたり、約束のページが終わるまで放課後残ってやれと厳しく指導されたりしている場面もよく見かけた。
そんな時、先生の熱意はわかるが、本当に「その子のため」になっているのかと気になった。
▼自学ノートで不登校に?
自学ノートが苦痛で不登校になる生徒も出てきているのではないかと危惧する先生もいる。私も、確かにその危険性は否めないと思う。
本来、「自学ノート」とは、「自主的に学んだことをノートに整理したもの」であろう。それを先生に提出するということは、提出する生徒が自ら学ぶ上での疑問に答えてもらい、より発展的な学習へとつなぐためのアドバイスをもらうためではないのか。当然、その中で間違いや誤字などのチェックもなされ、表現の適切さやよりわかりやすくするための助言をもらい、「自学=自ら学ぶ」力を高めていくということではないのか。
自ら学ぶには意欲が必要である。中学生の多くはその意欲をもてず、学びから遠ざかることで苦悩から逃げているのではなかろうか。教えるプロである教師は、その意欲を引き出し、学びへとどう高めていくかに心血を注がなければならない。その知恵が、「自学ノート」の強制だとしたら浅薄であろう。習慣化することは、確かに人間の行動を変える手っ取り早い手段である。問題は、その生徒に応じた適切な強化となっているかということである。
前勤校では、「学習案内」の冊子を作成し、先生方の「学び方」の知恵を、生徒・保護者にわかりやすく伝えたいという取り組みを行った。年度当初、冊子を使ったオリエンテーションを実施し、そこから個に応じた学びの定着を支援していく教師の営みがスタートする。同時にそれを見守り支えていく家庭の意識も高めていくねらいなのだが、その効果を検証できないまま退いたのが残念である。
学習者の自主性を重んじるという「自学ノート」なら、係の生徒が集めてその量を競うようなやり方はそぐわないような気がする。もちろん、それを励みとして努力を続ける生徒も少なくないだろう。しかし、そうできるのは、おそらく家庭学習の習慣が身に着いており、「独り学び」ができる生徒たちであろう。教師が気になる、より重きをかけて支援する必要があるのは、そうではない生徒。つまり、「やる気がない」「宿題もしてこない」「忘れ物が多い」「放課後何回もやり直しをさせられている」「くらい表情で訴えている生徒たちである。
▼教師が見方を変えることから
では、どうやれば、そういう生徒に「自学ノート」と向き合わせられるだろうか。
それは、簡単である。教師が見方を変えることである。「自学ノート」が苦痛の種になっていて、担任の先生や教科担任の先生に合わせる顔がないと、暗い気持ちで登校している生徒にスポットライトを当て、支援の手を差し伸べようとする視点をもてばいい。これまで培ってき指導技術、実践力があれば、ターゲットとなる生徒の顔をじっと見ているだけで、妙案が浮かんでくるに違いない。
では、具体的に考えてみよう。
「自学ノート」を文字どおりにとらえてみる。「自ら学ぶ」ためのノート、「自ら学んだ」足跡を残すノート、「自ら学ぶ」方法を教えてもらえるノート、「自ら学んだ」ことをしっかり評価してもらえるノート、「自ら学ぶ」意欲がわいてくるノート、「自ら学ぶ」喜びが綴られるノート、「自ら学ぶ」自分の姿が見え学ぶ喜びを実感できる……、「自己肯定感」が高まるノートであろう。生徒の顔と見比べて教師が一つ一つ頭に思い浮かべてみると良い。
▼家庭での生活をイメージしてみる
もう一つの大切な観点として、家庭の支援をどのくらい得られるのかということが挙げられる。目の前の生徒は、家に帰ってからどのような生活をし、どのような家庭学習の積み重ねや歴史をもっているのだろうかとイメージしてみることである。
保護者が傍にいるのか。教えられるのか。理解はあるのか。きょうだいは何人で、上か下か、一人っ子か。落ち着いて学習できる環境か。机、学習用具や参考書、辞書・事典類は。インターネット環境は……と、学習者がノルマを果たそうと必死になって自学に取り組んでいる姿、あるいは、取り組めないで苦しんでいる姿をイメージしてみるとよい。
教師が生徒の心や生活の状況について思いを馳せることは、もっとも重要な資質である。
こう考えてくると、「自学ノート」にするなら、生徒がやってきた分でよしとすることである。つまり、「自己申告制」が最低の条件になる必要がある。もちろん、「やる・やらない」も含めてであり、「やらない子」を「やる子」にするのが教師の手腕である。
一人一人が様々な個性をもち、その個性を伸ばす教育を高らかに謳っている教師側にすれば、ある生徒が提出した自学ノート10頁と、別の生徒が提出した1行の軽重は計れないと思うのだが。
本来、自学ができるように指導することが教師の務めであり、自学が十分にできない生徒には、その子に合った学び方を指導する必要がある。その子がやれることを精一杯やってきた主体性をこそ、しっかりと認めてやるべきであり、引き出さねばならないことだと考える。
▼宿題は同じじゃないと不公平?
「課題は同じじゃないと不公平だ。」「子どもを差別してはならない。」「みな平等でなければ……」と、先生方は口に出す。
確かにそのとおりであるし、教育にとって欠くことのできない重要な視点であることに間違いない。ただ、その文言の意味するところについて、少し掘り下げて考えることも必要である。では、差別とは何だろうか。平等と均等は同じだろうか。
実は、前述の不公平論の多くは、子どもの側から出てくる幼い平等意識から発せられている。それを教師が口にする場合、「先生、なんでAさんだけいいんですか!」と問われて明確な答を出せない実践の曖昧さや、差別の現実から学びとれていない弱さがある。「人間はみんな違っている。一人一人が個性をもち、今を懸命に生きている。だから先生も精一杯勉強して、一人一人に応じて今やれる精一杯のことを探しているんだよ。」という教師の答を、「そうなんだ、先生は一人一人を、そして私を見てくれている」と受け止める「心」も、教室の中で同時に育てていかねばならないのである。











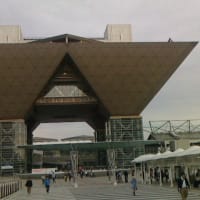
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます