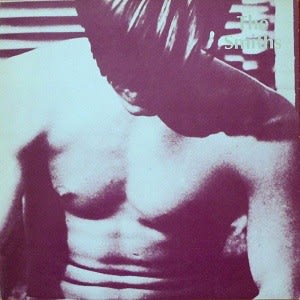ゲホゲホゲホ。2024年も終わりに近づく中、身辺の慌ただしさが災いしたのか、マイコプラズマ肺炎になりました。そんな最中、モリッシーの最新インタビューが出ていた。
“MORRISSEY SPEAKS ‐ An Exclusive Interview With Fiona Dodwell”
何人かが病状を心配しながら教えてくれましたが、私もゲホゲホゲホりながら読んでいました。秋の北米ツアーも問題なく無事終わり、モリッシーは元気だな、、、くらいしか、体力・気力がなかったので思わず、「モリッシーがマイコプラズマの人をなぐさめる」AI画像を生成して遊んでいました。ごめんなさい。
でもふと見たら、、、日本の音楽WEB情報アカウントなどがジョニー・マーとのことばかりフィーチャーした見出しがXに上がってきた。
ちょ、待てよ! ゲホゲホゲホ、、、、
と、いうことでちゃんとインタビューについてブログに書きたくなった。
MORRISSEY SPEAKS
An Exclusive Interview With Fiona Dodwell

このインタビューは合間合間にインタビュアーのフィオナの気持ちや地の文が入るので、そこも含め要約してみた。モリッシーが言いたいことの肝はここだろうなってとこは、赤で太くしておきます(勝手に判断)。
1 フィオナがモリッシーをインタビューした背景
モリッシーは、多くの人々やアンチに「語られる」が、自身が発言することはあまりない。かつて「ビッグマウス・ストライクス・アゲイン」という見出しで笑いものにされたが、実際には全くビッグマウスではなく、メディアの前では尊厳ある沈黙を守る人物だ。あんまり考えない人は、誰かの言ったことの二番煎じコピペジャーナリストによる歪んだメディアのストーリーに影響され、バイアスのかかった意見を持ってしまう。だから本人と話して、モリッシー自身の考えや信念を探りたい。
2 すでに録音されている未発表アルバムはどうなったか?
「ご存じの通り2枚あって、その2枚目は2023年の終わりにフランスで再録音され、新しいタイトルが付けられた。半分のトラックを削除し、新たに6曲を録音したので、2023年初めのアルバムとは異なる」とのこと。そのうちの1枚目“Bonfire of Teenagers”は、2021年の夏にはすでにリリース予定だったがリリースされていない。
3 なぜモリッシーを音楽業界は拒み続けているのか?
「レーベルはどちらのアルバムも素晴らしい高品質のポップアルバムだと言っているが、それらをリリースしたくない。『ガーディアン』の逆鱗に触れて、地獄の生活に陥りたくないからだ。『ガーディアン』による私への嫌がらせキャンペーンは今や世界的に知られている。レーベルがこの“Gotcha!“ジャーナリズムに巻き込まれたくないと考えていることを鑑みれば、このキャンペーンは効果的なようだ」
(‘‘Gotcha”ジャーナリズムとは、インタビュー対象者の人格や主張を意図的に不利に見せる映像や音声をとることを目的とした、罠にかけるようなメディアの取材手法、インタビュー方法のこと)
4 ‘‘Gotcha”ジャーナリズムとは何か?
「それは非常にウザい学生政治の一形態で、特定のメディアが自分たちの敵を決め、モリッシーやら、敵と見なされた誰もが言うことはすべて問題があるように見えるようにするものだ。この理由だけで自分は、英国ではある程度ブラックリストに入れられている。2020年初めだかに、母がラジオ4で『ガーディアン』の記者がしゃべってるのを聞いていた。その記者が『英国には嫌がらせという大きな問題がある』と言ったんで母はラジオに向かって、『そうよ!あんたのせいで!』と叫んでいた」
5 自由な言論の擁護者であるアーティストであることが災いした?
「問題は、私はずっと自由な言論の擁護者だったということだ。私は実際、他の方法では話せない。でも今や、自由な言論が英国とアイルランド全体で犯罪化され、その自由に頼っていた人々が閉め出されつつある…キャンセルされることは、現代版のリンチだよね?そして、その裏では、あなたの生活、生存能力、仕事相手との関係がすべて静かに攻撃され、最終的に機能しなくなる。キャンセルカルチャーの広がりとその深さ、そしてその残酷さを正確に研究したことはない。キャンセルされた人々は内心では、自殺寸前まで追い込まれていると言っても大げさじゃない」
6 なぜモリッシーは排除されるのか?
「そして、何のためにキャンセルするのか?国全体が同じ音楽、同じ本、同じコメディ、同じ政治、同じ映画を愛してくれることを願ってるってか?そんなことは決して起こらない!“Bonfire of Teenagers”は“The Queen is Dead”の現代版だが、それをどのレーベルもリリースしないという事実は、音楽業界がどれほど子どもじみて、怖がっているのかの表れだ」
「オープンマインドな意見を排除する最も簡単な方法は、彼らを人種差別者だと呼ぶことだ。なぜなら、反論に成功したとしても、その非難だけは永久につきまとってくる。その言葉を最初に使うだけで、相手は即死だ。もちろん、反論する機会も、自分を正当化する機会も与えられることはない。したがって音楽の世界では、従順であるがゆえにふわふわしたような奴らだけが生き残ることができる。私たちのように自分の考えを持っている者は、社会的に排除されなければならない」
7 スミスの再結成に対して賛成したのか?
「同意した。なぜなら、再結成する最後のチャンスのように感じたからだ。私たちはみんな歳をとり始めた。提案された再結成ツアーは、一生のように感じられるほど長い間スミスを聴いてくれた人たちに感謝の気持ちを伝える良い方法だと思った。マーに対する思い入れがあったわけではない。全く何もない」
8 ジョニー・マーに対してどう思っているか?
「彼は1980年代と同じように、今も不安で恐れているように感じる。でも、彼はスミスの守護者として孤立しているふりをすることで、より多くのメディアの賛美を得ている。私に対する不平を言って隅に座っている限り、彼はその台座に座っていられる。でも再結成が実現したら、その台座は消えることになる。彼は私を全く理解できないと言っているが、ステージに上がるたびに私の歌詞、私のボーカルメロディー、私の曲名を歌っている。これは偽善だか、自己欺瞞なンですか?彼は人々にモリッシーとマーのどっちを選ぶか二者択一を迫ってきた。私は彼の嫌味なコメントにはうんざりだ。30年以上黙って受け入れてきたんだ」
9 マーなんて関係なくて今の音楽キャリアを愛し満足していること
「私に関しては、残された時間はかなり限られている。しかし、マーの関与なしに自分で作り上げた音楽キャリアを絶対的に愛している。音楽は本当に人々を繋げる最後の手段だ。音楽を楽しんでいるのなら、それは人生を楽しんでいるということになる」
10 共感を感じるアーティストはいるか?
「クリフ・リチャード。なぜなら彼が裁判前なのに、メディアによる処刑の恐怖を経験したことをわかっているから(BBCは2014年、過去の子どもへの性的暴行容疑で警察がクリフ・リチャード宅を捜索する様子を、ヘリコプターを飛ばすなどして報道。証拠は見つからず起訴されなかった)。彼は50年以上にわたって60以上のヒットを出しながらも、どのラジオ局も彼の音楽を流さなかったという事実は不当だと感じる。ラジオは公共サービスであるべきだ。5年前、私は“Knockabout World”という曲を、クリフ・リチャードを思い浮かべながら書いた。そんなひどい状況の中で、彼がここまでやってきたことは、素晴らしいことだと思う」
(あーーー!だからこの曲は“Conglatulations”で始まるのか!クリフ・リチャードのヒット曲は「コングラチュレーションズ」)
Morrissey - Knockabout World (Official Audio)
11 今のバンドとライブについて
「今までで最強のバンドとライブクルーがいる。現在、アメリカでツアー中で、最高の気分だ。ジェシー・トバイアスは20年もの間一緒にいる。ライブ体験は今もユニークで、たくさんの人々を幸せにしている。最近のライブは最高だった。アーカンソー州リトルロック、アラバマ州バーミンガム、テネシー州ノックスビル、インディアナ州インディアナポリス…どこでも、ここ数年私が受けた過度な中傷を認識しているような人々から圧倒的な歓迎を受けた。私が歌うときにステージに上がろうとする観客を見ていると、困惑するが…同時に、音楽業界の誰にも興味を持ってもらえっこない」
「“白痴文化”は過ぎ去ると信じている。私たちは再び文化的自由を味わうことができる。私にとっては遅すぎるかもだが…骨は不死だ。私はペール・ラシェーズ(フランス、パリ東部の墓地)に横たわり、魂より『いいね』を送ろう(笑)」
12 モリッシーをインスパイアし続けているものは何か?
「私は決して自分の役目を離れたことはないと思う。考えるのも恐ろしい!私は自分の曲が大好きで、それらを聞くたびに愛校心のような誇りを感じる。ソロ作品は最大の誇りであり、喜びだ。これ以上のものを人生から求めることはできない。スミスの曲は力強いが、それらは若さに根ざしていたものだ。一方で、ソロの曲はマンチェスターを超えた世界を語っている。どうしてもそうしなければならなかった。多くの人が私に、マンチェスターで舞い踊る細い少年のままでいて欲しかったのは知っているが…この年齢でそれはバカげている」
(終わり)
モリッシーが、どんなに人にのぞまれていることはわかっても、その加齢だけが理由でなく、「スミス」なままでいられなくなった、そしてソロアーティストになった、なれた、思いが最後に出ていたことに改めて感動して、私の咳もマジ良くなってきた。モリッシーのこの一貫性、迷いなき自身、今しかない感、本当にすばらしい。
もうええでしょう!スミスとかマーとか!

よくないかw(言いたいだけ)
…最後の12「ソロの曲はマンチェスターを超えた世界を語っている」ですが、私の『お騒がせモリッシーの人生講座』のP126-127 のこの図が本人の言葉によって検証されたようでうれしいです♪