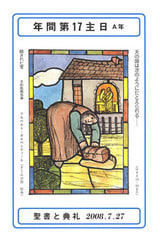
『聖書と典礼』表紙絵解説 (『聖書と典礼』編集長 石井祥裕)
2008年7月27日 年間第17主日 A年 (緑)
天の国は次のようにたとえられる……
(マタイ13・44より)
隠された宝
手彩色紙版画
アルベルト・カルペンティール (ドミニコ会 日本)
今回は、畑の宝を見つけた人のたとえを味わうときに眺める絵として、それぞれに鑑賞していただくこと以外に解説すべきことはない。
たとえ話のキーワードは、次の真珠のたとえと並べてみると、「持ち物をすっかり売り払って」にあることがわかる。そこから、神の国のかけがえのなさという教えが響いてくるが、同時に “探す” “見つける” というプロセスがその前提とされていることが興味深い。その場合、たくさんの数の中から、または広い畑の土地の中から “探す” のであり、一つの貴重なものを “見つける” のである。可能なかぎり時間をかけ、努力していると考えてもよい。このたとえの意味を味わうために、きょうの第一朗読は、関連する旧約聖書の箇所として神がソロモンに知恵を与えるところをあげている(列王記3・5、7-12)。知恵とは、知恵の書によれば「輝かしく、朽ちることがない」もの(知恵6・12)、“どんな宝石よりもまさるもの” (同7・9参照)である。このことを考え合わせると、ここの宝や真珠は、もちろん神の国だが、神のことば、神の知恵、救いの秘義全体、ひいてはキリスト自身を意味している、として味わっていくことができる。たとえを絵に表すことで、聖書の言葉やシンボルの互いのつながりにも目を向けていけるなら、それも絵の効果といえるだろう。










「宝」のみ言葉を読みますと、私は自然と同じマタイの「全世界をもうけても、自分の命を失ったら、それが何の役に立つだろう」を思います。「また、人は、命の代わりに何を与えることができよう」。この箇所は余りにも有名です。「私のあとに従おうと思うなら、自分をすて、自分の十字架をになって、私に従え。自分の命を救おうと思う者は、それを失い、私のために命を失う者は、それをうけるのである」(16の24~) 聖書一流のパラドックス、難解な箇所ですよね。魅力的で、私の心を逸らさせません。
「聖書と典礼」のご絵及び解説は、オリエンスから引っ張ってきたものなのです。以前は、教会から持ち帰ってデジカメで撮っていたのですけど。
今週28日(月)の旧約聖書の言葉は、エレミア13.1~、でした。主日には朗読されない箇所で、思わず耳をそばだてました。
“私は、こういうふうに、ユダの光栄と、イエルザレムの偉大な光栄とを、すり切らせよう。・・・もうなんのやくにもたたないこの帯のようになるだろう。”
旧約には旧約の含蓄がある、と痛感します。平日に修院でミサに与っていますが(休む日も多い♪)、いいものです。一般信徒の人も、何人かいます。ちょっと、関係ないこと、書きました。