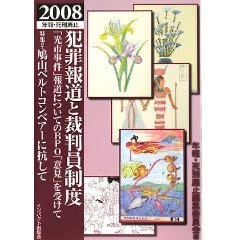
〈来栖の独白〉
被害者の1人の首を生きたまま電動のこぎりで切断、男性2人が殺害された事件。裁判員裁判初の死刑判決が横浜地裁で言い渡された(2010/11/16)。
被告人(人間)の更生可能性・犯罪行為の態様(残虐性)・裁判員の心的負担等々、多くの問題を提起した。
裁判員裁判だが、私には、多くの面から妥当でないとの思いが強い。死刑制度のある国で量刑まで選択、決定しなければならない裁判員制度は裁判員の負担が重すぎる。被告人の防御権という観点からも、僅かの審理時間で結論を出されるのは、不当である。
「命を議論する」「人間を観る」、これは、幾ら時間をかけても、かけすぎるということはない。くれぐれも拙速は、警戒されねばならない。
日本の裁判員裁判は、禁忌に踏み入った制度である。死刑という制度の是非、存廃が激しく争われる命の領域に、何の資格も有さず、昨日までは死刑についてなど考えてもみなかった人を出鱈目に引きずり込み、生殺与奪の判断を負わせる。被告人にしてみれば、たまたま選ばれただけの6名の民間人に、自分の命を左右されてしまう。
命が鴻毛の軽きに扱われるようになった。忌むべき制度だ。
.........................................
◆裁判員裁判で初の死刑判決/2人殺害.生きたまま電動のこぎりで切断/横浜地裁2010-11-16
◆プロの裁判官のみに裁かれたかった=審理不十分な裁判員裁判2010-04-13
--------------------------------------------------
◆実は、新しく始まるのは、裁判員・被害者参加裁判なのです=安田好弘弁護士2008-12-01
『年報死刑廃止08』【犯罪報道と裁判員制度】ー安田好弘弁護士の話抜粋
一つ理解していただきたいんですが、裁判員裁判が始まると言われていますが、実はそうではないのです。新しく始まるのは、裁判員・被害者参加裁判なのです。今までの裁判は、検察官、被告人・弁護人、裁判所という3当事者の構造でやってきましたし、建前上は、検察官と被告人・弁護人は対等、裁判所は中立とされてきました。しかし新しくスタートするのは、裁判所に裁判員が加わるだけでなく、検察官のところに独立した当事者として被害者が加わります。裁判員は裁判所の内部の問題ですので力関係に変化をもたらさないのですが、被害者の参加は検察官がダブルになるわけですから検察官の力がより強くなったと言っていいと思います。(中略)
司法、裁判というのは、いわば統治の中枢であるわけですから、そこに市民が参加していく、その市民が市民を断罪するわけですね、同僚を。そして刑罰を決めるということですから、国家権力の重要な部分、例えば死刑を前提とすると、人を殺すという国家命令を出すという役割を市民が担うことになるわけです。その中身というのは、確かに手で人は殺しませんけれど、死刑判決というのは行政府に対する殺人命令ですから、いわゆる銃の引き金を引くということになるわけです。
今までは、裁判官というのは応募制でしたから募兵制だったんです。しかも裁判官は何時でも辞めることができるわけです。ところが来年から始まる裁判員というのは、これは拒否権がありませんし、途中で辞めることも認められていません。つまり皆兵制・徴兵制になるわけです。被告人を死刑にしたり懲役にするわけですから、つまるところ、相手を殺し、相手を監禁し、相手に苦役を課すことですから、外国の兵士を殺害し、あるいは捕まえてきて、そして収容所に入れて就役させるということ。これは、軍隊がやることと実質的に同じなわけです。(中略)
裁判員裁判を考える時に、裁く側ではなくて裁かれる側から裁判員裁判をもう一遍捉えてみる必要があると思うんです。被告人にとって裁判員というのは同僚ですね。同僚の前に引きずり出されるわけです。同僚の目で弾劾されるわけです。さらにそこには被害者遺族ないし被害者がいるわけです。そして、被害者遺族、被害者から鋭い目で見られるだけでなく、激しい質問を受けるわけです。そして、被害者遺族から要求つまり刑を突きつけられるわけです。被告人にとっては裁判は大変厳しい場、拷問の場にならざるを得ないわけです。法廷では、おそらく被告人は弁解することもできなくなるだろうと思います。弁解をしようものなら、被害者から厳しい反対尋問を受けるわけです。そして、さらにもっと厳しいことが起こると思います。被害者遺族は、情状証人に対しても尋問できますから、情状証人はおそらく法廷に出てきてくれないだろうと思うんです。ですから、結局被告人は自分一人だけでなおかつ沈黙したままで裁判を迎える。1日や3日で裁判が終わるわけですから、被告人にとって裁判を理解する前に裁判は終わってしまうんだろうと思います。まさに裁判は被告人にとって悪夢であるわけです。おそらく1審でほとんどの被告人は、上訴するつまり控訴することをしなくなるだろうと思います。裁判そのものに絶望し、裁判という苦痛から何としても免れるということになるのではないかと思うわけです。
それからもう一つですけれども、従来から多数の冤罪被害者の人たちがいます。もう累々たる屍になっているだろうと思うんです。特に最近の冤罪というのは、強制的に自白させられて冤罪になるというような直接的な冤罪ではなくて、むしろ自ら積極的に認めざるを得ない、つまり屈辱的な冤罪の人たちがどんどん増えてきている。これは、ひとたび否認すれば100日200日と拘置所に入れられる。ひとたび否認すれば、反省していないということで、光市事件の彼のように一気に死刑にひっくり返る。そういう中にあって、結局認めざるを得ない。そして、そういうところで認めた人は、どういう心理状態に陥るか。自分自身を責めて生きていかざるを得ないわけです。そういう累々とした冤罪被害者の人たちは、自分が冤罪であるということさえも社会的に発言できない。悶々とした生活、情けない自分を受け入れながら生きていくだろうというふうに思うんです。
つまり、刑事司法は従来、本当は人を生かし、自由を守り、命を守り、そして名誉と財産を守るシステムだったはずのものが、実は人を破壊し、専ら人に苦痛を与える場所というふうになっているわけです。そういうものを防ぐために、少なくとも理性と法で支配される場、少なくとも事実が公正に評価される場、人が人として評価される場でなければならないのですが、ますますそれと逆行していく。その最たるものが裁判員裁判ではないかと思うんです。(中略)
そして、私が、一番最後に言いたいんですけど、実はこのBPOの意見書には半分憤りを持っています。私の怒りは何か、このふざけた報道は、すべて被告人に対する冒涜であるわけです。この報道の被害者は、実は被告人なわけです。この報道が、被告人に対する加害行為であること、言葉による暴力であり、リンチであり、虐待であることを一言も述べていない。被告人に対する理解を欠くとは指摘しているけれども、報道機関そのものが実は相手を傷つけている、侮辱している、冒涜している、名誉を毀損していると、しかもそれも徹底的に名誉を毀損しているということを、自己批判していない、自己批判に捉えていないというところが、私はこのBPOの結論の嫌いなところなんです。
つまり、この人たちはつまるところいわゆる文化人にしか過ぎないのではないか。優等生で、良識があって、あるいはいろんな教養の高い人たち、つまり善人なんでしょう。しかし、人から蔑まれ非難されたことがあるのだろうか。非難される側に立って考える、言い換えれば、報道される側に立って考えることができない、報道される側の痛みがまず頭に浮かばない人たちではないかなと、私は思うんです。
*強調(太字)は、来栖
.............................................................................................................
◆国家と死刑と戦争と【2】
皆さん方は、これまで死刑事件にかかわってこられておわかりと思いますが、事件を起こした人というのは、その起こした瞬間から、すでに自分の命を捨てています。1日も早く処刑されてこの世から消えることを彼自身は願っている。そういう中で、弁護人が一生懸命彼を励まし、一つ一つ事実について検証していこう、検察官が出してくる証拠について確認していこうよと呼びかけても、被告人からは「とにかく裁判を早く終わらせてくれ」と求められるわけです。そういうことを新しい法律が見越して、被告人がそういう状態にいる間に裁判を終わらせてしまおうというのが、この新しい法律の狙いです。ですから大道寺さんたちをはじめ、私たちが今まで死刑事件でたたかってきたことは、この裁判員制度の導入ということですべて禁止されてしまい「違法な行為」ということにされてしまったわけです。
..................................................
関連;「司法改革の行き先は現代の徴兵制?裁判員制度」安田好弘
「被害者参加制度12月施行」
「裁判員制度のウソ、ムリ、拙速」
死刑とは何か~刑場の周縁から
==========================================
◆クローズアップ2010:2人殺害・横浜裁判員裁判 死刑選択、負う市民
裁判員裁判で初めての死刑判決が16日、横浜地裁で言い渡された。昨年5月の裁判員制度開始から1年半。1日の耳かきエステ店員ら2人殺害事件の判決で、東京地裁は死刑求刑に対し極刑を回避したが、男性2人が殺害された今回の事件は、「行為の残虐性」が究極の刑罰を選択させた。一方、市民が法律の下、人の生命を奪う結論にかかわり、12年をめどに行われる制度の見直しや死刑制度の存廃を巡る議論を活発化させる可能性もある。【北村和巳、石川淳一】
◇「生きたまま切断」重視
「想像し得る殺害方法の中でも最も残虐な部類に属する」。横浜地裁の死刑判決が理由で最初に触れたのは、殺害方法の残虐性だ。池田容之(ひろゆき)被告(32)は、被害者の1人の首を生きたまま電動のこぎりで切断して殺害した。被害者2人が「最後に家族に電話させてほしい」と懇願しても聞き入れなかったが、これも「極めて冷酷」と批判した。
ともに2人が殺害された事件で検察側が死刑求刑した横浜地裁と東京地裁の裁判員裁判。東京地裁判決は無期懲役(確定)で、被告に対する判断は「生と死」で分かれた。
両判決とも、死刑選択の基準「永山基準」に基づき▽動機▽殺害方法の執拗(しつよう)性、残虐性▽事件後の情状--など9項目の論点に沿って死刑を適用すべきかどうか検討したと明記している。プロの裁判官だけの裁判と同じ枠組みだ。
殺害方法については東京判決も、被害者2人がナイフで何度も刺されたことから「残虐性は言うまでもない」と述べている。しかし、それ以上の言及はなかった。
動機についても認定が分かれた。横浜判決は「被害者2人とトラブルのあった者から、覚せい剤密輸の利権を得たいという極めて身勝手かつ利欲的な動機で、全く面識のない被害者を殺害しており、酌量の余地はない」と述べた。東京判決は耳かきエステ店への来店拒否が発端で身勝手としつつも「女性店員に強い好意を抱いていたのに拒まれ、うつ状態を悪化させての犯行。極刑に値するほど悪質とは言えない」とした。
ただし、東京の裁判員の1人は「永山基準は裁判官による裁判のもの。自分の気持ちを大事にした」と語った。それが反映されたとみられるのは、被告の反省に対する判決の指摘だ。「恋愛感情はないということにこだわり、相手に配慮しない言動は許し難い」としつつ「被告なりの反省の態度は相応に考慮すべきだ」として積極的に酌んだ。
一方、横浜の裁判員によると、永山基準を根拠に評議は進められていたという。判決は、被告が公判で遺族の証言を聞いた後、謝罪の意を表すなど内面の変化があるとしながら、「遺族の精神的苦痛を和らげるものとはなっておらず大きく評価できない」と指摘。被告に有利な事情に関しては、死刑回避の十分な理由に当たるかどうか判断すべきだとした山口県光市の母子殺害事件の最高裁判決(06年)に沿って「自首や反省といった事件後の情状について議論を尽くしたが、行為の残虐性や動機の悪質さなどと比較すると極刑回避の事情とは評価できない」と結論づけた。
横浜の事件が強盗殺人罪、死体損壊・遺棄罪に問われる一方、東京の事件は金目当てなどでなく、事件の性質も異なっていた。
◇重い負担、見直しの声
裁判員が死刑判決にかかわることは負担が大きく、論議の的になってきた。
国民の司法参加を導入する国のほとんどが、日本と同様に殺人などの重大事件を審理の対象としている。しかし、欧州や韓国などでは死刑が廃止・停止され、市民が死刑判断に加わるのは日本や米国の一部州など少数だ。
現役裁判官は「極刑は裁判官にも大きな負担で、国民に負わせていいかという議論はあるが、社会のルールを守る意識が強い人なら心理的負担は多少あっても意見を言うだろう」と語る。最高裁関係者は「死刑制度を持ち、法定刑も幅広い日本では市民が死刑選択に関与するのは避けられない。法曹三者が適切な運用をしていく必要はあるが、突き詰めれば、死刑制度の是非という問題になる」と話す。
制度開始から3年後に当たる12年をめどに裁判員制度は必要がある場合は見直される。死刑判決のあった16日、見直しについて有識者らが議論する法務省の「裁判員制度に関する検討会」の会合が開かれ、委員からは死刑判断の負担について意見が出された。
委員の1人の山根香織・主婦連合会会長は「死刑宣告が裁判員にとって過酷すぎるなら、対象範囲の見直しも検討対象になるかもしれない」と発言。座長の井上正仁・東京大大学院教授は「死刑も身近な問題として(市民に)考えていただくことが重要」と述べた。議論は来年以降に本格化するが、死刑判断をこのまま市民にさせてもいいのかどうかは、テーマの一つとして浮上する可能性もある。日本弁護士連合会では「死刑選択は裁判員6人と裁判官3人の全員一致を必要とすべきだ」との提言も出されている。
◇遺体写真「確認を」/被告の人間性「感じて」 検察側と弁護側、効果的立証狙う
結審まで6日間の審理では検察側、弁護側とも裁判員に配慮しながらも、それぞれの主張を効果的に印象づけようとする姿勢が際立った。
「求刑を先に述べます。被告を死刑に処すべきと考えます」。10日の論告で検察側は、通常は最後に行う求刑をいきなり冒頭に持ってきた。検察幹部は「先に言った方が裁判員に分かりやすいと思った」と説明したが、極めて異例の対応で、裁判員に死刑相当であることを強調したと言える。そして「被告が死刑にならないなら今後、我が国で死刑判決はあるのか」と結んだ。
1日の初公判では、白い表紙つきの資料を配布した。資料は、切断されて発見された遺体の一部の写真。「重要な証拠。無残なので表紙をつけているが、可能な方は確認してほしい」。30秒ほど時間を取り見てもらったが、まゆをひそめる裁判員が目立った。凶器の電動のこぎりも示され、作動させる状況を撮影した映像は音声を消して流された。
悪質性や残虐性を強調する立証。同じく死刑が求刑された耳かきエステ店員ら2人殺害事件の審理でも、裁判員の精神的負担を考慮して被害者2人の遺体写真6枚を白黒に変換して手元のモニターに映したが、評議などで見てもらうことを想定し、カラー写真も証拠提出した。
遺族感情の強さを打ち出したのも特徴だ。今回の公判では被害者2人の遺族の調書を詳細に朗読したうえ、4人の証人尋問や意見陳述を行った。これに対し弁護側は死刑適用は極めて慎重になるべきだとして、「ほんの少しでもためらう気持ちがあるなら回避しなければならない」と訴えかけた。結果の重大性などについては認めたうえで、「被告に人間性を感じていただきたい」と繰り返し、被告を前にした裁判員の心を揺さぶろうとした。
毎日新聞 2010年11月17日 東京朝刊
..................................................
死刑を廃止した国が多い。死刑制度はあっても…
死刑を廃止した国が多い。死刑制度はあっても執行を長く停止中の国も多い。世界的な流れをよそに死刑を執行中の国は、先進国では今や珍しい▼そのひとつ、日本では、死刑判決を書いた裁判官が法廷で言い渡している途中で涙声になり、被告に控訴を勧めたことがある。執行命令書への署名を拒んだ法相もいた。職務として関与する人たちの苦悩も、かくも深い▼「2010年11月16日」は、死刑制度に一般国民が組み込まれた日として記憶される。裁判員制度では初の死刑判決が横浜地裁の強盗殺人事件で言い渡された。裁判長は被告に控訴を勧めた。裁判員の心情をおもんばかったのかもしれない▼死刑判決にかかわる市民を、裁判員制度が増やしていくのは避けようがない。鹿児島地裁で審理中の強盗殺人事件のように、無罪を主張する被告に検察が極刑を求刑する展開が予想される裁判もある。裁判員の苦悩は深まる▼裁判員制度が始まって1年半が過ぎた。なぜ凶悪事件が主な対象なのか。「市民感覚」を期待するのであれば、民事裁判のほうがふさわしくないか。素朴な疑問に対する分かりやすい説明はどこまでなされてきただろう▼裁判員法は施行から3年後に見直す手はずになっている。死刑制度に市民を組み込むことの是非も問い直されるべきだ。死刑制度自体の是非をめぐる根幹の議論も要る。何も変わらないようなら世界から奇異の目で見られる。=2010/11/17付 西日本新聞朝刊「春秋」より抜粋









