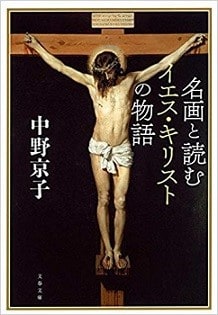〈来栖の独白 2019.12.12 Thu〉
何がきっかけだったのか、最近のことなのに思い出せない。が、このところ取りつかれたように遠藤周作さんの本を読んでいる。セブンイレブンへ注文し入荷の通知があると喜んで受け取りに行き、読む。
遠藤さん関連の本は『沈黙』その他、また『遠藤周作の世界』(武田友寿)といった具合で、過去にほとんど読んだつもりでいたが、そうではなかった。とりわけ、今読んでいるようなエッセーの類は目にしておらず、面白く、楽しくて仕方がない。「キリスト教」「カトリック」という共通項があるからだろう。
カトリック要理(?)について概ね了解しているつもりだが、私の頭の隅っこに引っかかっていることは、「自殺」についてである。カトリックは自殺を認めない。幸せな境遇で自殺する人なんていない、苦しみの最中にあってこそ自殺するのだろうが、カトリックは自殺を認めない。自殺とは、希望を捨てることだから、許さないのか。
遠藤さんの『人生の踏み絵』に自殺に関する叙述があった。
最近読んだ『名画と読むイエス・キリストの物語』の中の主の受難と重なり、ぐうの音も出なかった。
『人生の踏み絵』新潮文庫
P108~
やがて彼は結婚しますが、女房が苦痛を伴う病気に冒されます。病状ははかばかしくなく、不治を宣告される。彼女は死にたがっている。彼の顔を見るたびに、「死にたい」----なんて書いてないですよ、さすがにグリーンはBクラスだから。私はCクラスですから、私の小説なら「死にたい、死にたい」って書くだろうけど。今日はCクラスの説明で聞いてくださいね。毎日のように「死にたい、死にたい」と訴えてくるのが可哀そうで、生きていても何の希望もない妻のために、憐みの気持ちで毒を買ってくるんです。
『事件の核心』の場合も、スコービーは憐憫の業のせいで、警察副署長としての義務も怠り、(p109~)賄賂もついに取ってしまい、19歳の人妻と姦通し、妻を裏切ってしまう。そして、自殺というキリスト教の中で最大の罪の一つかもしれない罪を犯すことになる。
私の考えでは、絶望が最大の罪だと思っています。私の友人の神父なんて、「絶望以外の罪はないよ」とまで言っています。つまり自分の救いに対してまったく希望を失うこと以外に、罪というものはないと。自分の救いに対してまったく絶望した状態が地獄ですから、それ以外に許されない罪なんてないんだって、その神父は言っていました。
それはともかく、一応、自殺は禁じられています。なぜかと言うと、イエスは十字架をずっと背負ったまま、死んでいったじゃないかと。イエスは人生の十字架を背負ったら、決して途中で放り出さなかったじゃないかと。
つまり、重たい十字架を人生そのものだと考えるわけです。人生というのは、決して嬉しいものでも、楽しいものでも、魅力あるものでも、美しいものでもなくて、実にいやらしいものでしょ? みなさんもいろんな経験されておわかりでしょうけども、人生は汚らしいし、目を背けたくなるところがある。しかし決して、放り投げちゃいかんのだと。最後まで味わい尽くせと。それがやはり「イエスに倣いて」であり、(p110~)それが人生なんだ、というのがキリスト教の根本概念であります。自殺は、人生に対する愛情がないという考えに立っている。
どんな女房でも、ろくでもないし、あんまり美しくもなく、魅力もないんです。にもかかわらず、これを決して捨てたらいけないと、離婚を禁じているでしょ。これ、キリスト教会がそう言っている。私の女房は美しいし、魅力があるけどさ(会場笑)。
だから、離婚と自殺が禁止されているのは、そこには愛がないからです。魅力あるもの、美しいものなどに惹かれるのは情熱であって、愛じゃないと。しかし魅力のないもの、色褪せたもの、つらいものを、なお捨てないということが愛だ、というのがキリスト教の考え方です。だから、本当に人生って、オデキみたいなものですね。オデキみたいな人生だから、愛さないといけない。大切に味わわないといけない。あるいは、オデキみたいな女房だからこそ(会場笑)、捨てたらいけない。
例えば、『ボヴァリー夫人』などで有名なフローベールの短い小説に、こういうものがあります。冬の寒い夜、ある聖人が歩いていたら、体中にデキモノができている物乞いが道端に寝ていて、「寒い、寒い」と訴えて、聖人に「あなたの着ているマントをくれ」と言うから、マントをあげたんです。そしたら、「まだ寒いから服をくれ」と言うので、着ていた服をやった。それでも「寒いから下着をくれ」と言う。
(p111~)
聖人は下着も脱いで、裸になった。物乞いはなおも「まだ寒いから、私の体の上を抱いてお前の体で温めてくれ」と言うから、その聖人はデキモノだらけの体の上に乗って、一所懸命抱いてあげると、「もっと強く抱きしめてくれ」。それで、強く強く抱きしめていると、やがて光芒燦然たるイエス様になりましたという話なわけ。
私は大学の時、これを読まされて、「くっだらない小説! 日本でも光明皇后でこういう話があったわいな」と思った。奈良時代の光明皇后に似たような話があるんですよ。フローベールもくだらない話を書くなあと学生時代は思っていたけど、この年齢になると・・・この年齢って、もうちょっと早くからだなな。ああ、俺は読み方、間違っていたなと気づいた。デキモノだらけの体というのは、具体的に何病とかじゃなくて、人生そのものだと考えれば良かったんだね。
つまり、人生というものを、ずっと抱きしめろと。どんなに汚くても、途中で放棄したらいけない。この短編小説は「汚くて、寒くて、つらくて、面倒でも、それをずうっと抱きしめて、もっともっと抱きしめたら、やがて、人生が光芒燦然たるものになる。そうなるまで、抱きしめている」と言っているわけで、これはやっぱり日本の小説家には書けないでしょう。キリスト教感覚というものを植え付けられているフローベールだから書けた。フローベールは別にキリスト教作家とは呼ばれていないけれども、
(p112~)やはりキリスト教文化の中で暮らしているから書けたのでしょう。
キリスト教は、デキモノだらけの薄汚れた人生を途中で放棄したらいけないと、自殺を禁じている。その自殺をスコービーはやってしまいます。しかも、それは彼の業であった憐憫の情のために自殺してしまう。ちょうどテレーズが彼女の業であった非情の目、何にも酔えない、何もかも見てしまうという目のために、夫に毒を盛ったように。この二人の書き方は非常によく似ていますね。
書き方がよく似ているということは、モーリヤックとグリーンというこの二人のキリスト教作家も似ているところがある。業というか、自分のどうにもならないような衝動によって、われわれは罪を犯していきますが、そこで神さまが語りかけてくるのです。業なり罪なりの中にこそ、神さまが張り巡らせた罠があるという気持ちを、この二人のキリスト教作家はもっているのだと思います。
言い換えれば、この人生において無駄なものは一つもないんだと。全てのものには、神さまの罠が張り巡らされているのだからと。そして、その視点から、『事件の核心』を読みますと、モーリヤックがグリーンをヘタクソと言った気持ちもよく・・・。
* 中野京子著『名画と読むイエス・キリストの物語』 〈来栖の独白〉私は初めてイエスというお方が解り始めたようだ。
-------------------