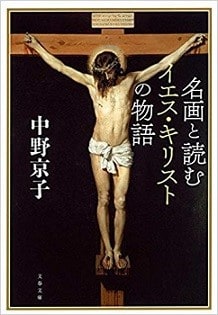
名画と読むイエス・キリストの物語 文春文庫
中野 京子 (著)
p128~
それは旧約聖書の「出エジプト記」に関連している。
紀元前13世紀ころ、エジプトで長く奴隷状態にあったユダヤ人がモーセに導かれて脱出し、ついに自由の民にもどったことを記念する祭りとされる。だが正確に言えば、脱出に先立つ血なまぐさい出来事が、「過ぎ越し」という言葉に示されている。つまりモーセは、自分たちユダヤ民族を虐げるエジプト人に災いをもたらしてほしいと神に祈り、聞き届けられ、エジプト人家庭の全ての長男が一夜にして急死する。その際ユダヤ人は自分たちに害が及ばぬよう、神の定めに従って雄の仔羊を殺し、家の門柱にその血を塗りつけておいた。長男の身代わりとしたのである。かくして神の裁きはユダヤ家庭を「過ぎ越し」、エジプト家庭にのみ下ったというわけだ。
過越祭はこれを再現して寿ぐ、生贄の祭りだ。奉納者はそれぞれ持参した仔羊ないし仔山羊か仔牛、あるいは鳩を(全て雄)、神殿の「祭司の庭」で、無傷かどうか祭司に調べてもらう。傷が見つかれば、神殿で売っている動物を新たに買わねばならない。良しとなると、犠牲となる動物の頭に手を置き、これによって自分の代わりと認められる。(p129~)それから祭壇の北側に用意された鉤付き台で殺し(仔羊なら四肢を縛って刃物で首を切り、鳩ならくびり殺す)、祭司にその血を祭壇の周りにふりかけてもらう。続いて皮を剥ぎ、ばらばらに裂き、内臓と足をきれいに洗う。それらは再び祭司の手により、神への捧げものとして祭壇の上で焼き尽くされ、罪の許しが得られた証となる。
現代日本人の視座からは、実に血なまぐさい祈り方としか言いようがない。動物たちはその鋭い感覚で、迫りくる死を予知するのであろう、不安がり、暴れもがき、逃げたがり、哀れな鳴き声をたてる。殺される瞬間には、もちろん断末魔の叫びを上げる。血しぶきが飛ぶ。自分の罪を全て小動物に贖わせる信仰深き者たちは、殺す時も解体時にもその血を顔に手に衣服に浴びる。また次から次へと祭壇にふりかけられる夥しい血は、真っ赤な川のように排水溝へ流れてゆく。蠅がたかる。脂肪が滴って火がはぜ、肉が焼け焦げて煙がのぼる。その間も、順番を待つ人々の祈りの声は途切れなく続く。
興奮した動物と人間の体が発する酸っぱいような刺激臭、汗と血と砂埃と汚れの混じった強烈な悪臭、生温かい内臓の臭い、肉の焼き尽くされる臭い・・・それらはどんなに香料が焚かれても完全に消えはしなかった。宗教に浸りきって生きている当時(p130~)の人々にとって、仔羊は可憐さを愛でる対象ではなく、自分のために血まみれで死すべき過ぎ越しの生贄にすぎない。古代的聖所は清らかさとは無縁で、生と死の混在するなまなましい血の空間だ。ローマ人がユダヤ人の体臭を嫌い、時に笑いの種にしたのも、この生贄の儀式がよく知られているからだろう。
それにしても神にいちいち動物を捧げるやり方は、貧しい者にとって多大な出費であったし、食料の無駄遣いとも言えた。自分の財産たる家畜を(ないしはわざわざその日に購入した動物を)、神殿で自らの手で解体せねば罪を赦されない(現代であれば司祭に告白する「懺悔」だけですむ)というのは、無闇な律法での縛りと同根だとイエスは感じていたのだろう、神殿に仔羊を捧げたことはなかった(儀式自体について何かを表明したこともなかったが)。
その代わりイエスが行おうとしていたのは、自らが「過ぎ越しの仔羊」「犠牲の仔羊」となることだった。ダヴィデやモーセやアブラハムのように、異邦人と戦って殺しまくるのではなく、「悪しき者に抵抗(てむか)ふな。人もし汝の右の頬をうたば、左をもむけよ」と教えたイエスは、ローマに反旗を翻す政治的活動にも関心がなかった。この世での自らの役割を、エルサレム神殿の台で、罪深い人間の身代わりとなって血を流すことと知っていた。過越祭にこだわった理由がそれだ。自らが人類の犠牲の仔羊となれば、
p132~
もうほんとうの動物たちを生贄にする必要もない。だから、3度にわたって使徒たちに語りきかせたのだ、エルサレムで何が待ち受けているかを------。
〈来栖の独白 2019.11.21 Thu〉
中野京子氏の著書によって、私は初めてイエスというお方が解り始めたようだ。あまりにも遅い。遅すぎるが。
「イエス」について、私には「神の子」という定義(?)が強すぎた。「人間」イエスというイメージは薄かった。しかし、中野氏はそのイメージから私を正してくれ、人間イエスに出会わせてくれ、イエスの痛みに気づかせてくれた。
イエスはゲッセマネで3度、山の上に行き、一人祈っている。
p161
「わが父よ、もし得(う)べくば此の酒杯(さかずき)を我より過ぎ去らせ給え」。酒杯とは、待ち受けている運命、受難そのものを指す。
なんと正直な吐露であろう。イエスは神に頼んだのだ、どうか助けてください、と。弟子に裏切られ、民衆に嘲られ、鞭打たれ、十字架上で苦悶の死を遂げる運命を、どうか避けさせてください、逃がしてください、許してください・・・。
神は答えなかった。無言であった。イエスはすでに選ばれており、それは変えようがない。神の沈黙、それが答えなのだ。ついにイエスは言った、「我が意(こころ)の儘にとにはあらず、御意のままに為し給へ」。
p162
「わが父よ、この酒杯もし我飲までは過ぎ去りがたくば、御意のままに成し給へ」。
「過ぎ去る」という言葉に、過越祭(すぎこしのまつり)が意識されている。かつて災いは仔羊の血を門に塗りつけたユダヤ人の家は過ぎ越してゆき、そうしなかったエジプト人の家に襲いかかった。今もしイエスが犠牲の仔羊の役割を担わなければ、神罰は人々の上を過ぎ越してゆかないだろう。ならばどんなに辛くとも、受難を引き受けねばならない。神の御心がそうならば従います、とイエスは言ったのだ。
〈来栖の独白〉続き
中野氏の著書で教えられたのは人間イエスについてばかりではない。実に多くを覚醒させられたが、イエスの行った「奇跡」についても、然りである。聖書を読むとき、私は「奇跡」に重きを置かなかった。大袈裟に書いているのだろう、くらいに受け止めていた。「重要なのは奇跡ではなく、イエスが愛してくださったということだ」と考えていた。「人のために命を捨てること、それよりも大きな愛はない」とイエスは身をもって教え、示してくださった。それに比べれば、奇跡など小さなことだ、と。
しかし、そうではないようだ。多くの奇跡を為したから、イエスは有名になり、群衆が騒いだ。そしてそれは十字架につながった。
『名画と読むイエス・キリストの物語』は3年前に読んだはずだが(傍線を引いたり、端を折り曲げたりして)、一体何を読んだのだろう。今回手に取って、目の覚める思い。一体、何を読んでいたのだろう。

ジョット〈ユダの接吻〉
またきてごらんになると、彼らはまた眠っていた。その目が重くなっていたのである。 それで彼らをそのままにして、また行って、三度目に同じ言葉で祈られた。それから弟子たちの所に帰ってきて、言われた、 「まだ眠っているのか、休んでいるのか。見よ、時が迫った。人の子は罪人らの手に渡されるのだ。立て、さあ行こう。見よ、わたしを裏切る者が近づいてきた」
そして、イエスがまだ話しておられるうちに、そこに、十二弟子のひとりのユダがきた。また祭司長、民の長老たちから送られた大ぜいの群衆も、剣と棒とを持って彼についてきた。イエスを裏切った者が、あらかじめ彼らに、「わたしの接吻する者が、その人だ。その人をつかまえろ」と合図をしておいた。

ピエトロ・ロレンツェッティ〈ユダの自殺〉
夜が明けると、祭司長たち、民の長老たち一同は、イエスを殺そうとして協議をこらした上、イエスを縛って引き出し、総督ピラトに渡した。
そのとき、イエスを裏切ったユダは、イエスが罪に定められたのを見て後悔し、銀貨三十枚を祭司長、長老たちに返して言った、 「わたしは罪のない人の血を売るようなことをして、罪を犯しました」 しかし彼らは言った、「それは、われわれの知ったことか。自分で始末するがよい」
そこで、彼は銀貨を聖所に投げ込んで出て行き、首をつって死んだ。
祭司長たちは、その銀貨を拾いあげて言った、「これは血の代価だから、宮の金庫に入れるのはよくない」。そこで彼らは協議の上、外国人の墓地にするために、その金で陶器師の畑を買った。そのために、この畑は今日まで血の畑と呼ばれている。
こうして預言者エレミヤによって言われた言葉が、成就したのである。 すなわち、「彼らは、値をつけられたもの、すなわち、イスラエルの子らが値をつけたものの代価、銀貨三十を取って、主がお命じになったように、陶器師の畑の代価として、その金を与えた」 (マタイによる福音書)
(使徒行伝 第1章)
ペテロはこれらの兄弟たちの中に立って言った、 「兄弟たちよ、イエスを捕えた者たちの手びきになったユダについては、聖霊がダビデの口をとおして預言したその言葉は、成就しなければならなかった。彼はわたしたちの仲間に加えられ、この務を授かっていた者であった。( 彼は不義の報酬で、ある地所を手に入れたが、そこへまっさかさまに落ちて、腹がまん中から引き裂け、はらわたがみな流れ出てしまった。そして、この事はエルサレムの全住民に知れわたり、そこで、この地所が彼らの国語でアケルダマと呼ばれるようになった。「血の地所」との意である。)」
そこで一同は、バルサバと呼ばれ、またの名をユストというヨセフと、マッテヤとのふたりを立て、祈って言った、「すべての人の心をご存じである主よ。このふたりのうちのどちらを選んで、ユダがこの使徒の職務から落ちて、自分の行くべきところへ行ったそのあとを継がせなさいますか、お示し下さい」 それから、ふたりのためにくじを引いたところ、マッテヤに当ったので、この人が十一人の使徒たちに加えられることになった。
◎上記事は[絵画で聖書]からの転載・引用です
.............









