上代の「言挙げ」という語については、これまでもたびたび論じられていた。本居宣長・古事記伝に、「さて許登は、言か、又事の意にてもあるべし、阿宜は、論などの阿宜にて、事のさまあるべきさまを、云々と挙て言立るを、言挙と云なり、」(国会図書館デジタルコレクションhttps://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1920821/147、漢字の旧字体等は改めた)とあり、言葉の理解は行き届いている。それが文脈的解釈に及ぶと途端に不明なところが現れる。ここでは最初に上代の文献例を網羅的に掲げ、「言挙げ」とは何か、その言葉の意図する真の姿について検討する(注1)。
「言挙げ」の諸例
①是に詔はく、「茲の山の神は、徒手に直に取りてむ」とのりたまひて、其の山に騰る時、白き猪、山の辺に逢へり。其の大きさ、牛の如し。爾くして、言挙げ為て詔はく〔爾為言挙而詔〕、「是の白き猪に化れるは、其の神の使者なり。今殺さずとも、還らむ時に殺さむ」とのりたまひて、騰り坐しき。是に大氷雨を零して、倭建命を打ち或はしき。此の白き猪に化れるは、其の神の使に非ずして、其の神の正身に当たれるに、言挙げに因りて惑はさえしぞ〔因言挙見惑也〕。(景行記)
②遂に身の所汚を盪滌ぎたまはむとして、乃ち興言して曰はく〔乃興言曰〕、「上瀬は是太だ疾し。下瀬は是太だ弱し」とのたまひて、便ち中瀬に濯ぎたまふ。(神代紀第五段一書第六)
③已にして素戔嗚尊、其の左の髻に纏かせる五百箇の統の瓊を含みて、左の手の掌中に著きて、便ち男を化生す。則ち称して曰はく〔則稱之曰〕、「正哉吾勝ちぬ」とのたまふ。(神代紀第六段一書第三)
④是の時に、素戔鳴尊、其の子五十猛神を帥ゐて、新羅国に降到りまして、曽尸茂梨の処に居します。乃ち興言して曰はく〔乃興言曰〕、「此の地は吾居らまく欲せじ」とのたまひて、遂に埴土を以て舟に作りて、乗りて東に渡りて、出雲国の簸の川上に所在る、鳥上の峯に到る。(神代紀第八段一書第四)
⑤乃ち称して曰はく〔乃稱之曰〕、「杉及び櫲樟、此の両の樹は、以て浮宝とすべし。檜は以て瑞宮を為る材にすべし。柀は以て顕見蒼生の奥津棄戸に将ち臥さむ具にすべし。夫の噉ふべき八十木種、皆能く播し生う」とのたまふ。(神代紀第八段一書第五)
⑥遂に出雲国に到りて、乃ち興言して曰はく〔乃興言曰〕、「夫れ葦原中国は、本より荒芒びたり。磐石草木に至及るまでに、咸に能く強暴る。然れども吾已に摧き伏せて、和順はずといふこと莫し」とのたまふ。(神代紀第八段一書第六)
⑦然して後に、母吾田鹿葦津姫、火燼の中より出来でて、就きて称して曰はく〔就而稱之曰〕、「妾が生める児及び妾が身、自づからに火の難に当へども、少しも損ふ所無し。天孫豈見しつや」といふ。(神代紀第九段一書第五)
⑧[日本武尊、]亦相模に進して、上総に往せむとす。海を望りて高言して曰はく〔望海高言曰〕、「是小き海のみ。立跳にも渡りつべし」とのたまふ。乃ち海中に至りて、暴風忽に起りて、王船漂蕩ひて、え渡らず。(景行紀四十年是歳)
⑨[筑紫国造磐井、]外は海路を邀へて、高麗・百済・新羅・任那等の国の年に職貢る船を誘り致し、内は任那に遣せる毛野臣の軍を遮りて、乱語し揚言して曰く〔乱語揚言曰〕、「今こそ使者たれ、昔は吾が伴として、肩摩り肘触りつつ、共器にして同食ひき。安ぞ率爾に使となりて、余をして儞が前に自伏はしめむ」といひて、遂に戦ひて受けず。驕りて自ら矜ぶ。是を以て、毛野臣、乃ち防遏へられて、中途にして淹滞りてあり。(継体紀二十一年六月)
⑩是の月に、或、馬飼首歌依を譖ぢて曰く、「歌依の妻逢臣讃岐の鞍の韉異なること有り。就而熟視れば、皇后の御鞍なり」といふ。即ち収へて廷尉に付けて、鞫問極切し。馬飼首歌依、乃ち揚言して誓ひて曰く〔乃揚言誓曰〕、「虚なり。実に非ず。若し是実ならば、必ず天災を被らむ」といふ。(欽明紀二十三年六月是月)
⑪穴穂部皇子、天下を取らむとす。 発憤りて称して曰はく〔発憤稱曰〕、「何の故にか死ぎたまひし王の庭に事へまつりて、生にます王の所に事へまつらざらむ」といふ。 (敏達紀十四年八月)
⑫言挙阜。右、言挙阜と称ふ所以は、大帯日売命の時、行軍したまふ日に、此の阜に御して、軍中に教令して曰はく、「此の御軍は、慇懃、な言挙為そ〔勿為言挙〕」とのたまふ。故、号けて言挙前と曰ふ。(播磨風土記・揖保郡)
⑬千万の 軍なりとも 言挙げせず〔言擧不為〕 取りて来ぬべき 男とそ思ふ(万972)
⑭この小川 霧そ結べる 激ちたる 走井の上に 言挙げせねども〔事上不為友〕(万1113)
⑮大方は 何かも恋ひむ 言挙げせず〔言擧不為〕 妹に寄り寝む 年は近きを(万2918)
⑯蜻蛉島 倭の国は 神からと 言挙げせぬ国〔言擧不為國〕 然れども 吾は言挙げす〔吾者事上為〕 天地の 神もはなはだ 吾が思ふ 心知らずや 行く影の 月も経ゆけば ……(万3250)
⑰葦原の 瑞穂の国は 神ながら 言挙げせぬ国〔事擧不為國〕 然れども 言挙げぞ吾がする〔辞擧叙吾為〕 言幸く 真幸く座せと 恙なく 幸く座さば 荒礒波 有りても見むと 百重波 千重波しきに 言挙げす吾は〔言上為吾〕 〈言挙げす吾は〔言上為吾〕〉(万3253)
⑱我が欲りし 雨は降り来ぬ かくしあらば 言挙げせずとも〔許登安氣世受杼母〕 年は栄えむ(万4124)
「言挙げ」についての現在の通説
岩波古語辞典に、「ことあげ【言挙げ】声高く言い立てること。……▷古くはコトアゲは禁忌とされた。危急・肝要の場合には言霊(だま)の力が求められて、コトアゲが行なわれた。」(500頁)、時代別国語大辞典に、「ことあげ[言挙・言上](名)ことばに出して言いたてること。コトと挙グの複合語の名詞形。サ変動詞を伴って用いられることが多い。ことばに出すことにより運命が左右されるという言霊信仰から、いたずらに言挙することは慎まれた。」(298頁)と、似たような解説が行われている(注2)。
言霊という概念について、言葉を発することによって何か呪的に作用するところがあるものと誤解している。言霊とは、人間の側に、言葉と事柄とを、同じコトであるようにしようとする勢いがあるために、まるで魂でもあるかのように感じられるという印象を語るものである。言挙げについても同様である。言葉で発すれば事柄もそのようになっていることが求められると思うがため、その波及する現象までも含めての考え方である。大きな声を出して言えば、多くの人が聞きとどけるところとなり、関係によって成立している社会のなかにあっては、実際にそうなる可能性が高まることは案外多いものである。目標を立てたら人に話してみるのが良いというのは、周りの人が関心を寄せて折に触れてアレはどうなった? と聞いてくることになり、なにかと自ら努力することになって、言ったコトが実際のコトに成るというケースが多くなるからである(注3)。
言霊という言葉に結実したように、ヤマトコトバにその事情が重んじられたのには、特にそれが無文字であったという性格が大きくかかわる。上代において、言葉には文字表記といった、内実を担保するものがなかった。言っていることしか定かにすることができないのだから、適当なことばかり言っていたら信用が失われて社会は成り立たなくなってしまう。全体に対する一人の信用ではなく、全体に対する全体の信用である。そうならないようにするためには、確かなことを皆が言いつづけ、その積み重ねによって全体を確かにしていく必要があった。言葉に発声することは、事柄に忠実でなければならなかったのである。それが言霊の真の正体であり、同様に、言挙げにも付いて回る性質であった(注4)。
そしてまた、発する言葉の一語一語も、声のレベルにおいて、それ自体言葉として正しいと順次証明していくことが求められた。言葉を発しながら、その言葉を(再)定義していく営みである。すなわち、確かなことを言っていくことはもちろんのこと、その言って行っている言葉が確かであることを証明することがその都度行われていたのである。この、自己言及的、二重拘束的な言語活動が、無文字時代のヤマトコトバの爛熟期にあった飛鳥時代の言葉づかいの特徴であった。
「言霊」や「言挙げ」という語について、外側に尾鰭を付けて過大視してはならない。仮に、言葉にはおしなべて呪力があるとするなら、そしてその呪力は神の怒りを受けるものでもあるとするならば、おちおち話をすることもできなくなる。神の全体主義におののいて箝口令が敷かれていたなどとは知られず、万葉集に見られるように多彩にして自由奔放に言葉をあやつっていた。効果を期待して言葉を発する「寿ひ」、「呪ひ」、「呪り」、「詛ひ」などとは異なり、「言挙げ」には呪力といった外的な要素の付与はない。そうではなく、言葉の使い方として、それ自体、自己拘束的になるように使っていたがために独特な効果が生まれていたのである。その一端は、「言霊」という語で表し得た。だから特別な言葉ではなく、コトという言葉がそのまま用いられている。「言挙げ」とは、事をあげつらうようにしながら大声で言うこと、そのことばかりをシンプルに示す語である。
②「上瀬は是太だ疾し。下瀬は是太だ弱し」という発語を「興言」としている目的は、イザナキが禊を中瀬ですると大きな声で宣言していることを指し示すためである。百歩譲っても、せいぜい言い訳している程度のことである(注5)。いま立っている地点が川の中流域であることを言い立てているだけである。水源や河口以外はみな中瀬であるとも言えようから、そういうこじつけをしていると考えられなくもないが、喫緊の課題に直面して特別な発声法を使うことによって、そこが上瀬でも下瀬でもなくなり流れが中庸に落ち着いたということではない。言ったことは事柄になるからというので、誰かが声を上げたらそれだけでたちどころに運河が貫通したという夢物語ではないのである。「上瀬」でもない、「下瀬」でもないと、ひとつひとつコトをアゲつらっている。そして、いろいろ検討した挙句に「中瀬」に決めたとしている。それ以上の意味合いはない。
万3250・3253番歌の「言挙げせぬ国」
万葉集の⑯⑰例において、先行研究のように、言挙げすることはタブー視されていたなどと重大視するには及ばない。言葉の表現技法と捉えられるものである。⑯「蜻蛉島 倭の国は 神からと 言挙げせぬ国」、⑰「葦原の 瑞穂の国は 神ながら 言挙げせぬ国」とあるのは、ヤマトの国は神意によってわざわざことさらに言い立てなくても済んでいる国であるとの謂いである(注6)。けれども、それは、日本が神国であるということではない。
予定調和的にうまいことかなっているから、わーわー騒ぐ必要がない、と言っている。国のあり方について言及しているわけではなくて、枕詞のような、修辞表現を使った言い回しがうまくできているということである。「蜻蛉島 倭の国」や「葦原の 瑞穂の国」である。ただの「倭の国」や「瑞穂の国」ではない。「蜻蛉島 倭の国」や「葦原の 瑞穂の国」と、すでに言葉に神意があらわれていて、形容表現として慣用化している。慣れっこになっているから、一(いち)からわーわー言い立てる必要がない。その言葉のアヤ的なところを「神からと」、「神ながら」と大げさに言っている。「蜻蛉島 倭の国」、「葦原の 瑞穂の国」といつもながらに続けて歌えばすべてを表現し尽くしているから、それ以上わーわー「言挙げせぬ」、そういう「国」なのだと、おもしろおかしく歌っている。国の成り立ちについて一介の下級役人の分際で評論できるものではなかろう(注7)。
⑯⑰の歌では、そんな前置きはともかくとして、これから私が申しあげますことには、というのを、「然れども 吾は言挙げす」、「然れども 言挙げぞ吾がする」と前置いている。前置きにつぐ前置きと、饒舌にすぎる前置きを置いているのは、要するに、中身のない話をしているからである。「神からと」、「神ながら」の「神」なるものは、枕詞のような修辞の言葉に宿っているのであって、世界の造物神などではない(注8)。言い得て妙だということを「神」に譬えている。たかだか万葉集のなかの二首に出てくるだけで“大きな”議論に持ちこむと、誤解に終わることになる。
古事記の「言挙げ」
言挙げは、わざわざ大声を出して言い放ち、それと規定してかかることが要点である。ありきたりの、当たり前のことについて、本来大声を出して言う必要はない。対して、どう判断したらいいか迷うような場合に強引に決めてかかろうとするとき、大きな声を出すことがある。世の中では、事態は声の大きな者の言うように動く傾向がある。
古事記の例の①では、ヤマトタケルは伊吹山の山麓で言挙げして、牛のような大きさの動物をただの猪だと決めてかかっている。「白猪、逢二于山辺一。其大如レ牛。」とあり、動物学的にはイノシシなのだが、文学的には山のウシ(主人)だから「如レ牛」と言っていて、よって神の「使者」ではなく「正身」なのであった。その場所は、イフキ(伊服岐)という名の山においてである。イフキとは、息吹(いふき)の意であり、息を吹く、呼吸すること、牛の息のそれは、温室効果ガスとして問題となっているゲップを指すであろうことは、話を聞いている人に機転が利けば思わず笑いが起きるほどのものである。名義抄に、「上気 アクヒ、オクヒ」とある。
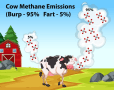 牛のメタン排出量を示す科学ポスター(https://jp.freepik.com/free-vector/science-poster-showing-cow-methane-emissions_5837852.htm)
牛のメタン排出量を示す科学ポスター(https://jp.freepik.com/free-vector/science-poster-showing-cow-methane-emissions_5837852.htm)
ゲップはあがってくるから、それに合わせてヤマトタケルは言挙げしているように設定されている。ゲップが、それと知らずに飲み込んでいたものが集まって一気に息として吹くように、イフキ山でそれと知らずに言挙げしている。「或(惑)」の原因はとてつもなく臭いゲップにある(注9)。
古事記のなかで唯一の言挙げの記事であるが、口頭言語としてふさわしく使われている。先行研究にあるような、伊吹山に地縁の神や氏族があったことを前提として物語られているわけではない(注10)。また、言挙げの誤用がヤマトタケルの身の不運を招いたというものでもない。
否定辞を伴う「言挙げ」
万葉集の「言挙げ」は、否定辞を伴うことが多い。⑯⑰の例は上に概観した。
⑬千万の 軍なりとも 言挙げせず〔言擧不為〕 取りて来ぬべき 男とそ思ふ(万972)
千万の敵軍がいても、あれこれと騒ぎ立てることもなく、討ち取って来るであろう男だと思う、と言っている。
⑭この小川 霧そ結べる 激ちたる 走井の上に 言挙げせねども〔事上不為友〕(万1113)
この小川は霧となって結んでくれている、激流となって走井のところの上に、言挙げしなくても、と言っている。
⑮大方は 何かも恋ひむ 言挙げせず〔言擧不為〕 妹に寄り寝む 年は近きを(万2918)
ふつうならどうしてこんなに恋しく思ったりしようか、つべこべ言わなくてもあなたに寄り添って寝るだろう年は近いのに、と言っている。
⑱我が欲りし 雨は降り来ぬ かくしあらば 言挙げせずとも〔許登安氣世受杼母〕 年は栄えむ(万4124)
雨が降ってほしいと思っていたら雨は降ってきたのだから、もはや大声を出して雨乞いの祝詞を唱える必要もない、今年は豊作だ、と言っている。
これらの例が「言挙げす」ではなく「言挙げせず」の形ばかりなのは、なによりそれが歌だからである。歌を歌うとは「言挙げす」ることである。大声を出して多くの人々に聞こえるように言っている。「言挙げ」のうち、拍子を付けた五・七・五・七・七音の発声が歌である。だから、歌のなかで「言挙げす」とあったら自明のことを言っていることになり、何を事立てているのかわからないことになる。いつも大声でまくしたてる人がいて、その人が、「次のことは声を大にして言いたい」などと言われても、ふざけるなよ、いつもうるさくてかなわないよ、ということになる。⑰⑱の例に「言挙げす」とあるのは、「言挙げせぬ国」と前提したなかで言っているから意が通る。
⑬で勇敢な武将であると褒める折に「言挙げせず」を登場させている。いま、歌を歌って顕彰しているけれども、そんな歌の性質である事立てて言うこととは無関係に、黙って討ち取って来るすごい男なのだとしている。
⑭で川にほとばしり流れている水汲み場のところに霧がたっていて、それと言挙げとが絡めて歌にされている(注11)。この発想は、①の古事記の例と同じである。伊吹山のことでイブキ(息吹)が連想され、言挙げという語を用いた説話に構成されていた。万1113番歌では、イブキ(息吹)は「霧〔白気〕」と表現されている。岩波古語辞典に、霧は、「息吹(き )。神話の世界では、息(き)と霧とは同じものとされ、生命の根源と見られていた。」(392頁)とある。言挙げしなくても、つまり、息吹をあげなくても、息吹と同じ意の「霧」となって立ち込めている。設定の場所を、大きな川ならあろうかもしれないところ、「小川」なのにそうなっているとしている。実景としてなのかはともかく、歌における言葉の使い方として機知に富んだ表現となり、自ら作った修辞に陶酔して歌っているわけである。
⑮で婚約している相手に対して、恋い焦がれていることを歌うために「言挙げせず」を登場させている。歌に伝えているのだから騒ぎ立てているのだが、婚約していて二人の将来は約束されているから騒ぎ立てる必要はないのである。わざわざ歌にしているということを訴えるために「言挙げせず」と言挙げしている。
⑱で雨は降ったのだから雨乞いのように声高にする必要もないのに、そのことを今、声高に歌にしているからその矛盾を述べるために「言挙げせず」を登場させている。
歌と言挙げとが同意であり、歌の文句に「言挙げ」という言葉を入れ込むことは自動的に矛盾、対立を惹起する。ただそれだけの理由で、万葉集の歌のなかに使われる「言挙げ」は否定辞を伴うケースばかりに目につくようになる。先行研究のように、「言挙げ」という語の意味合いが変遷して行って万葉集に現れている、ということではない。
播磨風土記の「言挙げ」
風土記に記される⑫の例は、神功皇后が言挙げをするなと言っているのにそこを「言挙阜」と名づけるのはおかしいとされてきた(注12)。そのような浅い認識の上に立って「言挙げ」についての緒論が行われている。皇后は軍中に対し、「言挙げをするな」と言挙げをしている。論理学的に幼稚でなければ「言挙阜」と名づけて何ら不思議ではない。皇后が何か他のこと、例えば「新羅を攻めるぞ」と「言挙げ」しているときには、その地は「新羅阜」などと名づけられるであろう。「言挙げ」に関して「言挙げ」しているから、コトアゲという名を冠した地名に据えてよくわかるのである。他の例を示すなら、「癖が強い」という言葉において、あるお笑い芸人が方言を交え、独特な、まさに癖が強い言い方をし続けると、その「癖が強い」という言葉はきらめきを帯び、彼の持ちネタとして人々に認知されるのである。
日本書紀の「言挙げ」
②についてはすでに述べた。③~⑥はスサノヲの言挙げである。スサノヲが「泣きいさち」(記上)る性格であったことはよく造形されている。夜郎自大的で、何でもかんでも大きなこととして披瀝したがる人物(神物)であった。③④⑥は自らを正当化する自分勝手な発語である。大きな声をあげて決めてかかっている。それを「言挙げ」としている。⑤は木材の種類をひとつひとつ挙げていって用途を述べている。それを「言挙げ」としている。
⑦のアタカシツヒメの「称」は、天孫のホノニニギが自分の子ではないだろうと疑ってかかったことに対して、天神の子であれば火のなかにいても焼かれないだろうと、古代の占法である「誓ひ」をした結果、焼かれなかったから、ほら、こういうことだ、と強く示しているところである。疑念を晴らしたところを大きな声を出して強調しているのである。対照的にホノニニギは、ぐうの音も出なかった。大きな声と無言との対比が際立っている。
⑧のヤマトタケルの例は、走水の浦賀水道は小さな海で、「立跳」すれば渡れるほどだと「高言」している。ジャンプのことを言わんとするには、発声自体から「高」く言うことがふさわしいだろう。言辞の内容を表明の様態に渡らせて然なりなのである。折しも、相模から上総へ「渡」ることが話題となっている。このような用法は、特に口頭語において顕著となる傾向がある。したがって、ヤマトタケルの「望海高言」の様子は、海に向かって大きな声を出しているだけのことで、見ている限りでは「海のバカヤロー」の亜種と考えても差し支えない。すなわち、話の当初においてヤマトタケルは、海神に向かって「言挙げ」していたわけではなかった。しかし、思うように渡れずに暴風にさらされたため、随行していたオトタチバナヒメは事の真相を探っている。そのときはじめて海神のことが持ちあがり、海神の心を宥められればうまくいくだろうと考えて彼女は人柱になっている。「言挙げ」という行為が、それ自体で直接的に何らかの問題を引き起こしたと読み取ることはできない。「言挙げ」の如何にかかわらず、間違った認識のもとに行動しているから災厄を被っている。②の「言挙げ」で中瀬での禊がかなったこととの違いは、論理学的に高度なレトリックで「言挙げ」したら、現実との間に乖離が生じてうまくできなかったというところにある。我々読者に求められているのは、「言挙げ」というメタ言葉が、括弧に括られる対象言語の発語にまで言語レベルを越えて浸潤していることを理解し、笑うことである。上代において、聞き手は笑って聞いて楽しく納得していたから、文字に書き取る時点まで伝わったものと考えられる(注13)。
⑨のツクシノイハヰの例は、今でこそ朝廷の使者になっているが、昔は同じ釜の飯を食った仲ではないか、それラフことになっており、道徳的秩序の欠如をことさらに問題視する姿勢で大声を発している。人聞きが悪いことを大声で言って、皆に薄情な奴だと思われて後ろ指刺されることを狙っている。その態度は「驕而自矜」と表されており、大柄だから声高なのはふさわしいのである。
⑩のウマカヒノオビトウタヨリの例では、身の潔白を主張するために「言挙げ」している。ウタヨリの妻の鞍の下に敷く韉は、皇后のものだという讒言があった。ために逮捕されたのであるが、そのとき「揚言誓曰」している。冤罪を晴らすことは古来難しい。弱々しく言っていたら聞いてもらえないと思うし、濡れ衣を着せた輩に対して腹も立って興奮気味に大声で訴えるようになる。この場面での「言挙げ」はその様子をうまく伝えており、「虚也。非レ実。若是実者、必被二天災一。」と言っている。ウタヨリが言いたいことは、「或」の言うことは嘘だということである。「或」の言い分は、「歌依之妻逢臣讃岐、鞍韉有レ異。就而熟視、皇后御鞍也。」であった。「或」は変だなあと思って「就而熟視」たら事の真相がわかったと主張している。ウタヨリはそれを否定するために「言挙げ」している。ひとつひとつアゲツラフことをしている。第一に「虚也。」である。第二に「非レ実。」である。なぜそうやってアゲツラフ形にしているか。「或」の言明に、「就而熟視」とあったからである。ツラツラ見ている。馬に鞍が装着されていて、それを馬のこちら側からも、あちら側からも見て確認したと言っている。馬は、人の、特にいわゆる日本人のような平面的な顔面(オモ)をしておらず、鼻が立っていて左右にツラツラな顔面(ツラ)をしている。だから、「就而熟視」という表現は当を得ていて、讒言はいかにも正しそうに思われたのである。それに対抗するためには、ウタヨリは、ツラツラに否定するためにアゲツラフように述べている。「虚也。」と「非レ実。」とは意味は同じであるが、「就而熟」に反論しているのである。そして、「非レ実。」という言葉を引き継ぐ形で、「誓」の言、「若是実者、必被二天災一。」と述べている。
⑪のアナホベノミコの例では、「発憤」して「言挙げ」している。どうして亡くなった王の殯宮にばかりお仕えして生きている王の側には仕えないのか、と大声で言っている。生きている王とはアナホベ自身のことを言わんとしている。話の仕方が理屈っぽい。亡くなった先王にはよく仕え、生きているこれからの王には仕えていない、だから、と三段論法に持ちこもうとしている。アゲツラフことの得意な弁護士の言い方に似ている。「発憤」していて、ムツカルと訓んでいる。ムツカルと大声になるのは、ムツ(睦)+カル(枯・涸・離)ために小声でひそひそ仲良く話すことがなくなり、角立ってツンケン話すために自然と声が大きくなったということであろう。お通夜をしている最中から相続のことを言い出す弁護士風の人間に睦ぶところはない。
おわりに
「神からと 言挙げせぬ国」、「神ながら 言挙げせぬ国」がどんな国かといえば、「蜻蛉島 倭の国」、「葦原の 瑞穂の国」であった。その形容修飾の見事さ、言語表現の巧みさを、「神からと」、「神ながら」と讃えていた。その構造を括弧で括って理解しやすくすると次のようになる。
⑯「蜻蛉島 倭の国」は、神からと 言挙げせぬ国。
⑰「葦原の 瑞穂の国」は、神ながら 言挙げせぬ国。
「蜻蛉島 倭の国」、「葦原の 瑞穂の国」と言った途端にすぐさま確認、評価して「神からと」、「神ながら」と言っている。もうそれで十分な表現だから、それ以上には「言挙げせぬ」としてふさわしい、そんな「国」なのだが、というのが歌の導入部の序詞的な言い回しであった。
このような言い方は、「言挙げ」という語を使うときに現れる性質、すなわち、声を出して言うとき、それはまさしく、「言挙げ」的に大きな声をあげて言うことになっているが、言っている言葉の音量が大きくなっていることにまつわりつくことと親和性がある。「言挙げ」という言葉は、論理学でいう、対象言語とメタ言語という言語レベルの間に混同が引き起こる、その現場にある言葉なのである。そのことに気づいていた上代の人たちは、「言挙げ」という言葉を論理学的におもしろいものとして巧みに扱っている。「……」と言挙げする、と言えば、「……」と大声で発語し、その言述の仕方はコトをあげつらうもので、いろいろな可能性をひとつひとつ潰していくような理屈っぽい言明をして、他を言いくるめようとする強弁的な傾向を示す。そればかりか、その発声やアゲツラヒは、「言挙げ」という言葉にブーメランのように帰ってきていて、言挙げの性質が「……」のレベルに介入、浸潤し、「……」が牛のゲップのあがってくることや、「……」に飛びあがる要素を含入させていたりしているのであった。それらの結果、コト(言)がコト(事)を導こうとする試みとして、あたかも「言挙げ」という“儀礼形式”が行われているのではないかとさえ疑われるほどであったのである(注14)。
言葉は使われることでその役目を果たし、使われている場においてのみ存在するものであり、数学の公式のように使われる前から控えているものではない。上代の人たちにとって「言挙げ」という言葉は、その言葉を使えば言語レベルを行き来することが可能だと承知していて、いろいろとおもしろいことを言い表せそうだと思って楽しんで使っていたものなのである。いま、記紀万葉に残されているのはその形跡である。彼らの言語感覚は、メタ言語の事情に通じていて、高度なレトリックを駆使するに十分な領域に達していたということである。われわれ現代人の言語能力は、枕詞を駆使することなど到底思いつかないように、後塵を拝する状況にある。
(注)
(注1)論考のなかには、日本書紀の例と万葉集の例を分けて読み、「言挙げ」の語史をたどる向きがある((注2)参照)。本稿では、「言挙げ」という語の全体像を確認することを目指す。結果的には、上代において「言挙げ」という語に変異は認められず、ただ一通りの解釈で理解が行き届く。「言挙げ」とは大声を出して言うことである。
日本書紀の例でコトアゲと訓むとした古訓は、①「為言擧而」(兼永筆本傍訓)、②「興言 古止安介」(日本紀私記乙本)、③「稱 」(弘安本傍訓)、⑤「稱之」(乾元本傍訓)、⑦「稱之 」(鴨脚本傍訓)、⑧「高言 古止安介」(日本紀私記丙本)、⑨「揚言 」(前田本傍訓)、⑪「稱 」(前田本傍訓)によっている。なお、本文内の説明では「言挙げ」と一括して表記するようにしているが、表記によって意味内容が変わるものではないことを重視してのことである。
(注2)角川古語大辞典に、「ことばに出して宣言すること。言霊(だま)のこもる重大な内容を負うことばを口外することによって、望ましい方向に事が実現するという考え方に従って、神を前にした祭式や誓言などの厳粛な場における重大な発言をいう。なすべきでないときにすれば、大きな災いを招くとして慎まれた。」(506頁)、古典基礎語辞典に、「言葉にして声高く言い立てること。古代、言葉を意味するコト(言)と出来事や人間の行為を表すコト(事)とはほとんど同じと考えられ、口に出して言った言葉とそれを現実の事柄にすることは区別が明確でなかった。自分の思うことを言葉に出してはっきり言うことによって人の吉凶が左右されるから、めったなことは口にすべきでないと考え、コトアゲすることは禁忌として避けられた。……自分の思うことを言葉に出してはっきり言うこと。言葉にしたことは現実になるという言霊だま信仰から、うかつに口に出すことは禁忌として避けた。」(499~500頁、この項、石井千鶴子)、大浦2014.に、「「言挙げ」とは、日常の言葉とは異なる様式によって、祈りをこめて言葉を発することであり、「言挙げ」の力によって「言」として発された内容が「事」として実現するという信仰である。ただし、言語呪術である「言挙げ」はむやみに行うものではなかった。右の歌[万3253]にもあるように、この国は基本的には「神ながら 言挙げせぬ国」なのであり、「言挙げ」はよほどの危機を乗り越えるために行われるものであったようである。」(142頁)とある。
これらの考え方は、言挙げを特殊な「言」、特に神に対する「言」ととらえ、そこに禁忌性をよみとった次田1924.以来続いている。「此[⑰⑱]の「言挙せぬ」を、……多くの用例から推し量ると、是は神の意志に反して、自己の意志を揚言する事を云つたものらしい。……[①の例]は、白猪を神の使者であると思つて、之を侮つて言挙し給うた為であつて、元来言挙する事は忌むべきものとされてるたやうである。……[古代]の宗教思想から右の物語を考察する時には、是は倭建命の御病の原因を、膽吹山の神に対つて言挙せられた結果であると考へられたものであると解釈する事が出来る。上代では病気にしても、不慮の災難にしても、悉く神意によつて起るので、それは神の意志に反抗したり、神威を汚したりした為であると考へられたのである。要するに神に対して言挙する事は、神意の表現である所の、託宣や夢告や卜占や誓約に反抗するのと均しく、神の怒を招くものとして深く忌み慎まれたものであるらしい。」(国会図書館デジタルコレクションhttps://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1918074/228、漢字の旧字体は改めた)。
太田1966.では、「呪術的実修もしくは観念としての「ことあげ」は、その原始的な相においては、何か特別な開口発声儀礼にかかわるものであったらしい」(230頁)と想定し、「ことあげする」と「ことあげしない」があることから、「「ことあげしない」ということが言い出されるためには、言語活動というものについての相当の体験と反省と思索とが必要だったに相違ないのである。」(235頁)として“言挙げ史”を展開している。吉井1977.では、「言挙げは、[記紀万葉時点からみて]過去において威力ある言葉による発生儀礼という歴史をもっていたかもしれないが、今、我々に残されたものによって考えるかぎりは、この行為は、個人的願望を、言語にひそむ力によって上位者に、実現するように願うという性質を強めていることを認めざるを得ないのである。」(218頁)としている。青木2015.は、紀のコトアゲについて整理している。「まず、コトアゲの文脈は、そのコトの内容を提示しつつ伝承のとじめ、あるいは伝承展開の中で重要な位置に配されていること。次に、相手の回答を促すような、対話性(問答性)をもった言ではないこと。そして、神の言という意識があるゆえに、人が発した場合、霊威がある言として禁忌性、反王権性が生じること、などである。このようにおさえていくと、日本書紀のコトアゲは、その呪性の喪失過程の中で意味づける方向とは別に、むしろ呪性を前提として、発言者と受け手のかかわりの中で説くこともできるのではなかろうか。」(379頁)。
通釈書、解説書でも様相は同じである。大系本日本書紀では、②について「興は、名義抄にオコル・オコスとあり、発する意。言葉に発する意。」((一)49頁)、⑧について「ここでは、大言壮語すること。」((二)97頁)、⑪について「言葉にはっきり出して語り論じること。アゲは、全容を上に示しあらわすこと。」((四)51頁)、新編全集本日本書紀では、②について「いざという時に、言霊だまの力を借りて、言い立てること。」(①49頁)、③について「このコトアゲは、反逆心のないことが誓約の結果分り、今度は言霊だまの力を借りて宣言することをさす。」(①73頁)、新編全集本古事記では、①について「「言挙」は、大声で言いたてること。言葉の呪力を働かせるための行為。言挙げの内容に誤りが含まれている時、言葉の力は逆に働いて、神を撃つはずの倭建命の力を無効にしてしまう。「言挙」自体がいけないのではない。」(231頁)、新編全集本風土記では、⑫について「あえて自分の意志を言葉に出して表現すること。言霊だまの力による実現を期待する行為。」(63頁)、多田2020.では、①について「言挙げとは、ある事柄を特殊な方法で言い立て、言葉の呪力を働かせる一種の言語呪術である。多くは、神に向けたある断定的な意思(誓言)の表明になる。危急存亡の際の言挙げは必須と考えられたが、一方でそれは、現実を乗り越え、打ち破るための非日常的な力の発動だから、不用意な言挙げはかえって危険視された。」(44頁)、新釈全訳日本書紀では、②について「ことばにだして言い立てる。ことばに発することに霊力を認めていた。」(111頁)、⑧について「自らを過信して大言すること。古訓コトアゲはことばに出して言い立てることで、ことばの霊力を発動させる行為。ことばが霊力を持つからこそ、不可能なコトアゲは災厄をもたらす。」(495頁)と注されている。
(注3)社会心理学に、予言の自己成就と呼ばれる。もちろん、必ずしもそうなるとは限らない。とはいえ、上代の人が、コト(言)とコト(事)とは別物との前提で、“作為”して言=事になるようにしようなどとは思わなかったものと思われる。別物であるなら別の言葉を“選択”していたであろうからである。
(注4)拙稿「上代語「言霊」と言霊信仰の真意について」参照。
(注5)伊藤1993.は、「「言挙」とは、人間がある目的達成の際、障害となるかもしれぬ既知・未知な対象への畏怖感を克服するために、その対象の属性をあらかじめ良い方向に意味づける「言」や劣位な素性のものと暴露する「言」に変換して、声高く発する対抗措置だったと言えよう。」(244頁)と広範な定義を施しているが、中瀬を前にしてそこで濯ぐと言って濯ぐ事をしている。障害となるものなどない。
(注6)吉井1977.は、「「神ながら」の語は、『万葉集』に「神ながら神さぶ」「神ながら思ほす」「神ながらしく」「神ながら愛づ」「神ながら治む」などの表現となって十八例の使用がある。……「神ながら」の語の用い方をみれば、おそらく柿本人麿によって創始されたと考えられるこの歌語が、……「やすみしし我が大君、高光る日の御子」の表現とともに、天武、持統朝における王権の神聖化と、これを支える高天原神話の形成に従って使用されはじめた、特異な内容を含む歌語であることに気づかざるをえないのである。」(220~221頁)とする。
筆者がこういった議論に同意できないのは、歌が、歌を作って歌う側ばかりではなく、歌われた途端に聞く側にも共有されるものであったからである。言葉を新しく創作して使うことは誰にでもできる。問題は、多くの人に受け入れられるかどうかである。内輪で盛り上がるといった局所的なその場限りのものではなく、聞いた人のほとんどがうまいことを言うねえと感心し、納得して世の中に歓迎されなければ言葉として広まり得ないのである。新しい言葉を教壇上から概念定義をレクチャーすることは皆無であったとは言わないが、歌が披露されるときにそんな事態は起こりえない。皇室、王族、豪族貴族の面々が、下級役人なのかさえ不明な柿本人麻呂から新しい言葉の説明を受けていたとは考えられない。二度聞きしなければわからない歌はまた皆無とは言わないが、広くフォロワーを獲得することはなく、つまりは新語が流行語となることはなく、ただ死語となっていったであろう。
(注7)柿本人麻呂には、吉野讃歌(万36~39)のように、国のありさまを持ち上げることがあるとされるが、天皇を持ち上げているのであって、勝手に国のありさまを評論するようなことはしていない。
(注8)西郷2006.は、「言挙げ」について解説する際、「神ながら」という語を施しているが誤用である。「不用意なコトアゲは不吉とされていた。しかし神ながらの自然的秩序が崩れてゆくにつれ、人は否応なくコトアゲするようにならざるをえない。次の歌にそのへんの消息がうかがえる、「葦原の、瑞穂の国は、神ながら、コトアゲせぬ国、然れども、コトアゲぞ我がする、言幸く、ま幸くませと、……コトアゲす我は」(万、一三・三二五三)。」(115頁、説明文の後半を割愛した)。
(注9)拙稿「ヤマトタケルの伊吹山の難」で、この話のなかの言葉の絡み合いについて詳細に分析している。
(注10)吉井1977.に、土着豪族の息長氏が「山の神」の背後にあるとする見方がある。そういう設定を置くことは誤りであるが、イフキ(息吹)にオキナガ(息長)氏が関係あるようになっていったのは、話をよく理解した人たちによるものと思われる。
(注11)この万1113番歌に「言挙げせねども」という句が使われていることについての解釈は、これまで見過ごされてきた。以下の注釈書では、古事記の、吹き棄つる気吹が霧になったという話を紹介しながら、言葉を中心に考えるのではなく、神話での展開を典故とするものかとしている。伊藤1996.に、「言挙げをすれば、その発声に伴う気息によって霧がかかるという信仰があったのであろうか。『古事記』上巻の天の真名井の誓約の段に、「吹き棄つる気息」が霧になったという話がある。霧がおのずからに湧き起こり立ちこもる現象に自然の威力を覚えた歌であろう。」(74~75頁)、多田2009.に、「アマテラスとスサノヲは、天の真名井で誓約を行っている。互いの物実が「吹き棄つる気息のさ霧」になったとある(「神代記」)。「霧」は、この伝承を意識したものか。恋の誓約を交わす場でもあったから、それへの意識もあるか。あるいは、恋の不成就の嘆きの息が「霧」になったか。」(34頁)とある。
(注12)太田1966.に、「「ゆめな言挙しそ」と言われたから「言挙の阜」なり「言挙の前」なりの名が生まれたというのは不自然であり、後人の解釈によって転生した伝承であることが難なく想像されるが、この所伝は原始的なことあげ観念をそのまま継承しているものではなく、新しい段階のそれを反映しているものと見られる。「言挙の阜」のほんとうの由来は、そこで何らかの開口発声を主要素とする宗教的儀礼もしくは呪術的行為が、恒例的に行なわれていたことにあったものと想像するのが自然で、その名の根拠があまり判然としなくなったころ、別個の由縁の附会がこころみられたものであろう。」(232頁)とある。吉井1977.では、「[神功皇后が]言挙げするな、というのは、後に言挙げしないことが美風と考えられたことによって、修正を受けたものと考えるのが妥当であろう。」(215頁)としている。
現代の研究において、最初に躓いてしまって踏襲されるとこのようなことになる。風土記の地名伝承は、地口的な地名譚にすぎない。地名自体、言葉自体についてああだこうだ言っているのであって、言挙げについて、しないことが美風かどうかといった判断など、考えに入れられるものではない。そのことは、他の地名の由来を語るときにもすべて当てはまる。「言挙阜」の名の本願については本文に述べたとおりである。
(注13)論理学の逆説の例に、「クレタ人は嘘つきだとクレタ人が言った」という有名な命題がある。クレタ人が嘘つきなら、「クレタ人は嘘つきだ」と言っているクレタ人の言は嘘であるから「クレタ人は嘘つき」ではないことになり矛盾が生じる。クレタ人の言が本当のことだとしたら、言っている内容の「クレタ人は嘘つき」であることとの間にこれまた矛盾が生じる。どうしても矛盾が生じるのである。伝承された人の名を冠してエピメニデスのパラドックス、また、自己言及のパラドックスとも呼ばれる。
それに照らすなら、「上代人は大声でものを言うと上代人が大声で言った」という命題を実現していることになる。このとき、論理学的には、正誤以前、意味をなさないというのが本当のところではあるが、逆説には陥っておらず、あたかも絶対的な真理であるかのようにさえ目されるものである。それがおもしろいから、「上代人は大声でものを言うと上代人が大声で言った」という文脈で、上代の人は「言挙げ」という言葉を使ったのであった。コトアゲとはコト(言)+アゲ(挙)の複合語以外のなにものでもない。コトアゲという複合語は、メタ言語がその論理的部分において「本質的に豊か(essential richness)」(タルスキ)であることにかなっている。
 言語レベルの混同を楽しむ表現の概念図
言語レベルの混同を楽しむ表現の概念図
(注14)「言挙げ」が記紀万葉に儀礼として扱われていないばかりか、令や式などに一切現れないことも、古代のそれが儀礼的、儀式的なものではなかったことを示唆してくれている。
(引用・参考文献)
青木2015. 青木周平『青木周平著作集 上巻 古事記の文学研究』おうふう、平成27年。
伊藤1993. 伊藤高雄「言霊の信仰」櫻井満監修『万葉集の民俗学』桜楓社、平成5年。
伊藤1996. 伊藤博『萬葉集釈注 四』集英社、1996年。
岩波古語辞典 大野晋・佐竹昭広・前田金五郎編『岩波古語辞典』岩波書店、1974年。
大浦2014. 大浦誠士「こと【言・事】」多田一臣編『万葉語誌』筑摩書房、2014年。
太田1966. 太田善麿『古代日本文学思潮論(Ⅳ)─古代詩歌の考察─』桜楓社、昭和41年。
角川古語大辞典 中村幸彦・岡見正雄・阪倉篤義編『角川古語大辞典 第二巻』角川書店、昭和59年。
烏谷2016. 烏谷知子『上代文学の伝承と表現』おうふう、2016年。
岸根2017. 岸根敏幸「古事記神話と言霊信仰(後編)─他者に幸禍をもたらす発言、および、「言挙げ」─」『福岡大学人文論叢』第49巻第3号、2017年12月。福岡大学機関リポジトリhttp://id.nii.ac.jp/1316/00004245/
古典基礎語辞典 大野晋編『古典基礎語辞典』角川学芸出版、2011年。
西郷2006. 西郷信綱『古事記注釈 第六巻』筑摩書房(ちくま学芸文庫)、2006年。
時代別国語大辞典 上代語編修委員会編『時代別国語大辞典 上代編』三省堂、1967年。
志水1995. 志水(城崎)陽子「言挙げ考」『目白学園女子短期大学研究紀要』第32号、1995年12月。
新釈全訳日本書紀 神野志隆光・金沢英之・福田武史・三上喜孝校注『新釈全訳日本書紀 上巻』講談社、2021年。
新編全集本古事記 山口佳紀・神野志隆光校注・訳『新編日本古典文学全集1 古事記』小学館、1997年。
新編全集本日本書紀 小島憲之・直木孝次郎・西宮一民・蔵中進・毛利正守校注・訳『新編日本古典文学全集2 日本書紀①』・『新編日本古典文学全集3 日本書紀②』小学館、1994・1996年。
新編全集本風土記 植垣節也校注・訳『新編日本古典文学全集5 風土記』小学館、1997年。
大系本日本書紀 坂本太郎・家永三郎・井上光貞・大野晋校注『日本書紀(一)』・『日本書紀(二)』・『日本書紀(三)』・『日本書紀(四)』岩波書店(ワイド版岩波文庫)、2003年。
多田1995. 多田一臣「言挙げということ─『万葉集』巻十三・三二五三~四を手がかりにして」『日本文学』第44巻第6号、平成7年6月。
多田2009. 多田一臣『万葉集全解 3』筑摩書房、2009年。
多田2020. 多田一臣『古事記私解Ⅱ』花鳥社、2020年。
タルスキ1987. アルフレッド・タルスキ、飯田隆訳「真理の意味論的観点と意味論の基礎」坂本百大編『現代哲学基本論文集Ⅱ ムーア タルスキ クワイン ライル ストローソン』勁草書房、1987年。(Alfred Tarski, “The semantic conception of truth and the foundations of semantics”, in Leonard Linsky (ed.), “Semantics and the Philosophy of Language : a collection of readings”, Urbana : University of Illinois Press, 1952.)
次田1924. 次田潤『古事記新考』明治書院、大正13年。
中村2012. 中村秀吉『パラドックス─論理分析への招待─』講談社(講談社学術文庫)、2012年。
樋口2016. 樋口達郎「神の発話と神への発話─「言挙」に関する一考察─」『倫理学』32号、2016年3月。つくばリポジトリhttp://hdl.handle.net/2241/00143848(『言霊と日本─言霊論再考─』北樹出版、2017年、所収)
吉井1977. 吉井巌『ヤマトタケル』学生社、昭和52年。
「言挙げ」の諸例
①是に詔はく、「茲の山の神は、徒手に直に取りてむ」とのりたまひて、其の山に騰る時、白き猪、山の辺に逢へり。其の大きさ、牛の如し。爾くして、言挙げ為て詔はく〔爾為言挙而詔〕、「是の白き猪に化れるは、其の神の使者なり。今殺さずとも、還らむ時に殺さむ」とのりたまひて、騰り坐しき。是に大氷雨を零して、倭建命を打ち或はしき。此の白き猪に化れるは、其の神の使に非ずして、其の神の正身に当たれるに、言挙げに因りて惑はさえしぞ〔因言挙見惑也〕。(景行記)
②遂に身の所汚を盪滌ぎたまはむとして、乃ち興言して曰はく〔乃興言曰〕、「上瀬は是太だ疾し。下瀬は是太だ弱し」とのたまひて、便ち中瀬に濯ぎたまふ。(神代紀第五段一書第六)
③已にして素戔嗚尊、其の左の髻に纏かせる五百箇の統の瓊を含みて、左の手の掌中に著きて、便ち男を化生す。則ち称して曰はく〔則稱之曰〕、「正哉吾勝ちぬ」とのたまふ。(神代紀第六段一書第三)
④是の時に、素戔鳴尊、其の子五十猛神を帥ゐて、新羅国に降到りまして、曽尸茂梨の処に居します。乃ち興言して曰はく〔乃興言曰〕、「此の地は吾居らまく欲せじ」とのたまひて、遂に埴土を以て舟に作りて、乗りて東に渡りて、出雲国の簸の川上に所在る、鳥上の峯に到る。(神代紀第八段一書第四)
⑤乃ち称して曰はく〔乃稱之曰〕、「杉及び櫲樟、此の両の樹は、以て浮宝とすべし。檜は以て瑞宮を為る材にすべし。柀は以て顕見蒼生の奥津棄戸に将ち臥さむ具にすべし。夫の噉ふべき八十木種、皆能く播し生う」とのたまふ。(神代紀第八段一書第五)
⑥遂に出雲国に到りて、乃ち興言して曰はく〔乃興言曰〕、「夫れ葦原中国は、本より荒芒びたり。磐石草木に至及るまでに、咸に能く強暴る。然れども吾已に摧き伏せて、和順はずといふこと莫し」とのたまふ。(神代紀第八段一書第六)
⑦然して後に、母吾田鹿葦津姫、火燼の中より出来でて、就きて称して曰はく〔就而稱之曰〕、「妾が生める児及び妾が身、自づからに火の難に当へども、少しも損ふ所無し。天孫豈見しつや」といふ。(神代紀第九段一書第五)
⑧[日本武尊、]亦相模に進して、上総に往せむとす。海を望りて高言して曰はく〔望海高言曰〕、「是小き海のみ。立跳にも渡りつべし」とのたまふ。乃ち海中に至りて、暴風忽に起りて、王船漂蕩ひて、え渡らず。(景行紀四十年是歳)
⑨[筑紫国造磐井、]外は海路を邀へて、高麗・百済・新羅・任那等の国の年に職貢る船を誘り致し、内は任那に遣せる毛野臣の軍を遮りて、乱語し揚言して曰く〔乱語揚言曰〕、「今こそ使者たれ、昔は吾が伴として、肩摩り肘触りつつ、共器にして同食ひき。安ぞ率爾に使となりて、余をして儞が前に自伏はしめむ」といひて、遂に戦ひて受けず。驕りて自ら矜ぶ。是を以て、毛野臣、乃ち防遏へられて、中途にして淹滞りてあり。(継体紀二十一年六月)
⑩是の月に、或、馬飼首歌依を譖ぢて曰く、「歌依の妻逢臣讃岐の鞍の韉異なること有り。就而熟視れば、皇后の御鞍なり」といふ。即ち収へて廷尉に付けて、鞫問極切し。馬飼首歌依、乃ち揚言して誓ひて曰く〔乃揚言誓曰〕、「虚なり。実に非ず。若し是実ならば、必ず天災を被らむ」といふ。(欽明紀二十三年六月是月)
⑪穴穂部皇子、天下を取らむとす。 発憤りて称して曰はく〔発憤稱曰〕、「何の故にか死ぎたまひし王の庭に事へまつりて、生にます王の所に事へまつらざらむ」といふ。 (敏達紀十四年八月)
⑫言挙阜。右、言挙阜と称ふ所以は、大帯日売命の時、行軍したまふ日に、此の阜に御して、軍中に教令して曰はく、「此の御軍は、慇懃、な言挙為そ〔勿為言挙〕」とのたまふ。故、号けて言挙前と曰ふ。(播磨風土記・揖保郡)
⑬千万の 軍なりとも 言挙げせず〔言擧不為〕 取りて来ぬべき 男とそ思ふ(万972)
⑭この小川 霧そ結べる 激ちたる 走井の上に 言挙げせねども〔事上不為友〕(万1113)
⑮大方は 何かも恋ひむ 言挙げせず〔言擧不為〕 妹に寄り寝む 年は近きを(万2918)
⑯蜻蛉島 倭の国は 神からと 言挙げせぬ国〔言擧不為國〕 然れども 吾は言挙げす〔吾者事上為〕 天地の 神もはなはだ 吾が思ふ 心知らずや 行く影の 月も経ゆけば ……(万3250)
⑰葦原の 瑞穂の国は 神ながら 言挙げせぬ国〔事擧不為國〕 然れども 言挙げぞ吾がする〔辞擧叙吾為〕 言幸く 真幸く座せと 恙なく 幸く座さば 荒礒波 有りても見むと 百重波 千重波しきに 言挙げす吾は〔言上為吾〕 〈言挙げす吾は〔言上為吾〕〉(万3253)
⑱我が欲りし 雨は降り来ぬ かくしあらば 言挙げせずとも〔許登安氣世受杼母〕 年は栄えむ(万4124)
「言挙げ」についての現在の通説
岩波古語辞典に、「ことあげ【言挙げ】声高く言い立てること。……▷古くはコトアゲは禁忌とされた。危急・肝要の場合には言霊(だま)の力が求められて、コトアゲが行なわれた。」(500頁)、時代別国語大辞典に、「ことあげ[言挙・言上](名)ことばに出して言いたてること。コトと挙グの複合語の名詞形。サ変動詞を伴って用いられることが多い。ことばに出すことにより運命が左右されるという言霊信仰から、いたずらに言挙することは慎まれた。」(298頁)と、似たような解説が行われている(注2)。
言霊という概念について、言葉を発することによって何か呪的に作用するところがあるものと誤解している。言霊とは、人間の側に、言葉と事柄とを、同じコトであるようにしようとする勢いがあるために、まるで魂でもあるかのように感じられるという印象を語るものである。言挙げについても同様である。言葉で発すれば事柄もそのようになっていることが求められると思うがため、その波及する現象までも含めての考え方である。大きな声を出して言えば、多くの人が聞きとどけるところとなり、関係によって成立している社会のなかにあっては、実際にそうなる可能性が高まることは案外多いものである。目標を立てたら人に話してみるのが良いというのは、周りの人が関心を寄せて折に触れてアレはどうなった? と聞いてくることになり、なにかと自ら努力することになって、言ったコトが実際のコトに成るというケースが多くなるからである(注3)。
言霊という言葉に結実したように、ヤマトコトバにその事情が重んじられたのには、特にそれが無文字であったという性格が大きくかかわる。上代において、言葉には文字表記といった、内実を担保するものがなかった。言っていることしか定かにすることができないのだから、適当なことばかり言っていたら信用が失われて社会は成り立たなくなってしまう。全体に対する一人の信用ではなく、全体に対する全体の信用である。そうならないようにするためには、確かなことを皆が言いつづけ、その積み重ねによって全体を確かにしていく必要があった。言葉に発声することは、事柄に忠実でなければならなかったのである。それが言霊の真の正体であり、同様に、言挙げにも付いて回る性質であった(注4)。
そしてまた、発する言葉の一語一語も、声のレベルにおいて、それ自体言葉として正しいと順次証明していくことが求められた。言葉を発しながら、その言葉を(再)定義していく営みである。すなわち、確かなことを言っていくことはもちろんのこと、その言って行っている言葉が確かであることを証明することがその都度行われていたのである。この、自己言及的、二重拘束的な言語活動が、無文字時代のヤマトコトバの爛熟期にあった飛鳥時代の言葉づかいの特徴であった。
「言霊」や「言挙げ」という語について、外側に尾鰭を付けて過大視してはならない。仮に、言葉にはおしなべて呪力があるとするなら、そしてその呪力は神の怒りを受けるものでもあるとするならば、おちおち話をすることもできなくなる。神の全体主義におののいて箝口令が敷かれていたなどとは知られず、万葉集に見られるように多彩にして自由奔放に言葉をあやつっていた。効果を期待して言葉を発する「寿ひ」、「呪ひ」、「呪り」、「詛ひ」などとは異なり、「言挙げ」には呪力といった外的な要素の付与はない。そうではなく、言葉の使い方として、それ自体、自己拘束的になるように使っていたがために独特な効果が生まれていたのである。その一端は、「言霊」という語で表し得た。だから特別な言葉ではなく、コトという言葉がそのまま用いられている。「言挙げ」とは、事をあげつらうようにしながら大声で言うこと、そのことばかりをシンプルに示す語である。
②「上瀬は是太だ疾し。下瀬は是太だ弱し」という発語を「興言」としている目的は、イザナキが禊を中瀬ですると大きな声で宣言していることを指し示すためである。百歩譲っても、せいぜい言い訳している程度のことである(注5)。いま立っている地点が川の中流域であることを言い立てているだけである。水源や河口以外はみな中瀬であるとも言えようから、そういうこじつけをしていると考えられなくもないが、喫緊の課題に直面して特別な発声法を使うことによって、そこが上瀬でも下瀬でもなくなり流れが中庸に落ち着いたということではない。言ったことは事柄になるからというので、誰かが声を上げたらそれだけでたちどころに運河が貫通したという夢物語ではないのである。「上瀬」でもない、「下瀬」でもないと、ひとつひとつコトをアゲつらっている。そして、いろいろ検討した挙句に「中瀬」に決めたとしている。それ以上の意味合いはない。
万3250・3253番歌の「言挙げせぬ国」
万葉集の⑯⑰例において、先行研究のように、言挙げすることはタブー視されていたなどと重大視するには及ばない。言葉の表現技法と捉えられるものである。⑯「蜻蛉島 倭の国は 神からと 言挙げせぬ国」、⑰「葦原の 瑞穂の国は 神ながら 言挙げせぬ国」とあるのは、ヤマトの国は神意によってわざわざことさらに言い立てなくても済んでいる国であるとの謂いである(注6)。けれども、それは、日本が神国であるということではない。
予定調和的にうまいことかなっているから、わーわー騒ぐ必要がない、と言っている。国のあり方について言及しているわけではなくて、枕詞のような、修辞表現を使った言い回しがうまくできているということである。「蜻蛉島 倭の国」や「葦原の 瑞穂の国」である。ただの「倭の国」や「瑞穂の国」ではない。「蜻蛉島 倭の国」や「葦原の 瑞穂の国」と、すでに言葉に神意があらわれていて、形容表現として慣用化している。慣れっこになっているから、一(いち)からわーわー言い立てる必要がない。その言葉のアヤ的なところを「神からと」、「神ながら」と大げさに言っている。「蜻蛉島 倭の国」、「葦原の 瑞穂の国」といつもながらに続けて歌えばすべてを表現し尽くしているから、それ以上わーわー「言挙げせぬ」、そういう「国」なのだと、おもしろおかしく歌っている。国の成り立ちについて一介の下級役人の分際で評論できるものではなかろう(注7)。
⑯⑰の歌では、そんな前置きはともかくとして、これから私が申しあげますことには、というのを、「然れども 吾は言挙げす」、「然れども 言挙げぞ吾がする」と前置いている。前置きにつぐ前置きと、饒舌にすぎる前置きを置いているのは、要するに、中身のない話をしているからである。「神からと」、「神ながら」の「神」なるものは、枕詞のような修辞の言葉に宿っているのであって、世界の造物神などではない(注8)。言い得て妙だということを「神」に譬えている。たかだか万葉集のなかの二首に出てくるだけで“大きな”議論に持ちこむと、誤解に終わることになる。
古事記の「言挙げ」
言挙げは、わざわざ大声を出して言い放ち、それと規定してかかることが要点である。ありきたりの、当たり前のことについて、本来大声を出して言う必要はない。対して、どう判断したらいいか迷うような場合に強引に決めてかかろうとするとき、大きな声を出すことがある。世の中では、事態は声の大きな者の言うように動く傾向がある。
古事記の例の①では、ヤマトタケルは伊吹山の山麓で言挙げして、牛のような大きさの動物をただの猪だと決めてかかっている。「白猪、逢二于山辺一。其大如レ牛。」とあり、動物学的にはイノシシなのだが、文学的には山のウシ(主人)だから「如レ牛」と言っていて、よって神の「使者」ではなく「正身」なのであった。その場所は、イフキ(伊服岐)という名の山においてである。イフキとは、息吹(いふき)の意であり、息を吹く、呼吸すること、牛の息のそれは、温室効果ガスとして問題となっているゲップを指すであろうことは、話を聞いている人に機転が利けば思わず笑いが起きるほどのものである。名義抄に、「上気 アクヒ、オクヒ」とある。
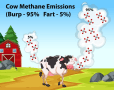 牛のメタン排出量を示す科学ポスター(https://jp.freepik.com/free-vector/science-poster-showing-cow-methane-emissions_5837852.htm)
牛のメタン排出量を示す科学ポスター(https://jp.freepik.com/free-vector/science-poster-showing-cow-methane-emissions_5837852.htm)ゲップはあがってくるから、それに合わせてヤマトタケルは言挙げしているように設定されている。ゲップが、それと知らずに飲み込んでいたものが集まって一気に息として吹くように、イフキ山でそれと知らずに言挙げしている。「或(惑)」の原因はとてつもなく臭いゲップにある(注9)。
古事記のなかで唯一の言挙げの記事であるが、口頭言語としてふさわしく使われている。先行研究にあるような、伊吹山に地縁の神や氏族があったことを前提として物語られているわけではない(注10)。また、言挙げの誤用がヤマトタケルの身の不運を招いたというものでもない。
否定辞を伴う「言挙げ」
万葉集の「言挙げ」は、否定辞を伴うことが多い。⑯⑰の例は上に概観した。
⑬千万の 軍なりとも 言挙げせず〔言擧不為〕 取りて来ぬべき 男とそ思ふ(万972)
千万の敵軍がいても、あれこれと騒ぎ立てることもなく、討ち取って来るであろう男だと思う、と言っている。
⑭この小川 霧そ結べる 激ちたる 走井の上に 言挙げせねども〔事上不為友〕(万1113)
この小川は霧となって結んでくれている、激流となって走井のところの上に、言挙げしなくても、と言っている。
⑮大方は 何かも恋ひむ 言挙げせず〔言擧不為〕 妹に寄り寝む 年は近きを(万2918)
ふつうならどうしてこんなに恋しく思ったりしようか、つべこべ言わなくてもあなたに寄り添って寝るだろう年は近いのに、と言っている。
⑱我が欲りし 雨は降り来ぬ かくしあらば 言挙げせずとも〔許登安氣世受杼母〕 年は栄えむ(万4124)
雨が降ってほしいと思っていたら雨は降ってきたのだから、もはや大声を出して雨乞いの祝詞を唱える必要もない、今年は豊作だ、と言っている。
これらの例が「言挙げす」ではなく「言挙げせず」の形ばかりなのは、なによりそれが歌だからである。歌を歌うとは「言挙げす」ることである。大声を出して多くの人々に聞こえるように言っている。「言挙げ」のうち、拍子を付けた五・七・五・七・七音の発声が歌である。だから、歌のなかで「言挙げす」とあったら自明のことを言っていることになり、何を事立てているのかわからないことになる。いつも大声でまくしたてる人がいて、その人が、「次のことは声を大にして言いたい」などと言われても、ふざけるなよ、いつもうるさくてかなわないよ、ということになる。⑰⑱の例に「言挙げす」とあるのは、「言挙げせぬ国」と前提したなかで言っているから意が通る。
⑬で勇敢な武将であると褒める折に「言挙げせず」を登場させている。いま、歌を歌って顕彰しているけれども、そんな歌の性質である事立てて言うこととは無関係に、黙って討ち取って来るすごい男なのだとしている。
⑭で川にほとばしり流れている水汲み場のところに霧がたっていて、それと言挙げとが絡めて歌にされている(注11)。この発想は、①の古事記の例と同じである。伊吹山のことでイブキ(息吹)が連想され、言挙げという語を用いた説話に構成されていた。万1113番歌では、イブキ(息吹)は「霧〔白気〕」と表現されている。岩波古語辞典に、霧は、「息吹(き )。神話の世界では、息(き)と霧とは同じものとされ、生命の根源と見られていた。」(392頁)とある。言挙げしなくても、つまり、息吹をあげなくても、息吹と同じ意の「霧」となって立ち込めている。設定の場所を、大きな川ならあろうかもしれないところ、「小川」なのにそうなっているとしている。実景としてなのかはともかく、歌における言葉の使い方として機知に富んだ表現となり、自ら作った修辞に陶酔して歌っているわけである。
⑮で婚約している相手に対して、恋い焦がれていることを歌うために「言挙げせず」を登場させている。歌に伝えているのだから騒ぎ立てているのだが、婚約していて二人の将来は約束されているから騒ぎ立てる必要はないのである。わざわざ歌にしているということを訴えるために「言挙げせず」と言挙げしている。
⑱で雨は降ったのだから雨乞いのように声高にする必要もないのに、そのことを今、声高に歌にしているからその矛盾を述べるために「言挙げせず」を登場させている。
歌と言挙げとが同意であり、歌の文句に「言挙げ」という言葉を入れ込むことは自動的に矛盾、対立を惹起する。ただそれだけの理由で、万葉集の歌のなかに使われる「言挙げ」は否定辞を伴うケースばかりに目につくようになる。先行研究のように、「言挙げ」という語の意味合いが変遷して行って万葉集に現れている、ということではない。
播磨風土記の「言挙げ」
風土記に記される⑫の例は、神功皇后が言挙げをするなと言っているのにそこを「言挙阜」と名づけるのはおかしいとされてきた(注12)。そのような浅い認識の上に立って「言挙げ」についての緒論が行われている。皇后は軍中に対し、「言挙げをするな」と言挙げをしている。論理学的に幼稚でなければ「言挙阜」と名づけて何ら不思議ではない。皇后が何か他のこと、例えば「新羅を攻めるぞ」と「言挙げ」しているときには、その地は「新羅阜」などと名づけられるであろう。「言挙げ」に関して「言挙げ」しているから、コトアゲという名を冠した地名に据えてよくわかるのである。他の例を示すなら、「癖が強い」という言葉において、あるお笑い芸人が方言を交え、独特な、まさに癖が強い言い方をし続けると、その「癖が強い」という言葉はきらめきを帯び、彼の持ちネタとして人々に認知されるのである。
日本書紀の「言挙げ」
②についてはすでに述べた。③~⑥はスサノヲの言挙げである。スサノヲが「泣きいさち」(記上)る性格であったことはよく造形されている。夜郎自大的で、何でもかんでも大きなこととして披瀝したがる人物(神物)であった。③④⑥は自らを正当化する自分勝手な発語である。大きな声をあげて決めてかかっている。それを「言挙げ」としている。⑤は木材の種類をひとつひとつ挙げていって用途を述べている。それを「言挙げ」としている。
⑦のアタカシツヒメの「称」は、天孫のホノニニギが自分の子ではないだろうと疑ってかかったことに対して、天神の子であれば火のなかにいても焼かれないだろうと、古代の占法である「誓ひ」をした結果、焼かれなかったから、ほら、こういうことだ、と強く示しているところである。疑念を晴らしたところを大きな声を出して強調しているのである。対照的にホノニニギは、ぐうの音も出なかった。大きな声と無言との対比が際立っている。
⑧のヤマトタケルの例は、走水の浦賀水道は小さな海で、「立跳」すれば渡れるほどだと「高言」している。ジャンプのことを言わんとするには、発声自体から「高」く言うことがふさわしいだろう。言辞の内容を表明の様態に渡らせて然なりなのである。折しも、相模から上総へ「渡」ることが話題となっている。このような用法は、特に口頭語において顕著となる傾向がある。したがって、ヤマトタケルの「望海高言」の様子は、海に向かって大きな声を出しているだけのことで、見ている限りでは「海のバカヤロー」の亜種と考えても差し支えない。すなわち、話の当初においてヤマトタケルは、海神に向かって「言挙げ」していたわけではなかった。しかし、思うように渡れずに暴風にさらされたため、随行していたオトタチバナヒメは事の真相を探っている。そのときはじめて海神のことが持ちあがり、海神の心を宥められればうまくいくだろうと考えて彼女は人柱になっている。「言挙げ」という行為が、それ自体で直接的に何らかの問題を引き起こしたと読み取ることはできない。「言挙げ」の如何にかかわらず、間違った認識のもとに行動しているから災厄を被っている。②の「言挙げ」で中瀬での禊がかなったこととの違いは、論理学的に高度なレトリックで「言挙げ」したら、現実との間に乖離が生じてうまくできなかったというところにある。我々読者に求められているのは、「言挙げ」というメタ言葉が、括弧に括られる対象言語の発語にまで言語レベルを越えて浸潤していることを理解し、笑うことである。上代において、聞き手は笑って聞いて楽しく納得していたから、文字に書き取る時点まで伝わったものと考えられる(注13)。
⑨のツクシノイハヰの例は、今でこそ朝廷の使者になっているが、昔は同じ釜の飯を食った仲ではないか、それラフことになっており、道徳的秩序の欠如をことさらに問題視する姿勢で大声を発している。人聞きが悪いことを大声で言って、皆に薄情な奴だと思われて後ろ指刺されることを狙っている。その態度は「驕而自矜」と表されており、大柄だから声高なのはふさわしいのである。
⑩のウマカヒノオビトウタヨリの例では、身の潔白を主張するために「言挙げ」している。ウタヨリの妻の鞍の下に敷く韉は、皇后のものだという讒言があった。ために逮捕されたのであるが、そのとき「揚言誓曰」している。冤罪を晴らすことは古来難しい。弱々しく言っていたら聞いてもらえないと思うし、濡れ衣を着せた輩に対して腹も立って興奮気味に大声で訴えるようになる。この場面での「言挙げ」はその様子をうまく伝えており、「虚也。非レ実。若是実者、必被二天災一。」と言っている。ウタヨリが言いたいことは、「或」の言うことは嘘だということである。「或」の言い分は、「歌依之妻逢臣讃岐、鞍韉有レ異。就而熟視、皇后御鞍也。」であった。「或」は変だなあと思って「就而熟視」たら事の真相がわかったと主張している。ウタヨリはそれを否定するために「言挙げ」している。ひとつひとつアゲツラフことをしている。第一に「虚也。」である。第二に「非レ実。」である。なぜそうやってアゲツラフ形にしているか。「或」の言明に、「就而熟視」とあったからである。ツラツラ見ている。馬に鞍が装着されていて、それを馬のこちら側からも、あちら側からも見て確認したと言っている。馬は、人の、特にいわゆる日本人のような平面的な顔面(オモ)をしておらず、鼻が立っていて左右にツラツラな顔面(ツラ)をしている。だから、「就而熟視」という表現は当を得ていて、讒言はいかにも正しそうに思われたのである。それに対抗するためには、ウタヨリは、ツラツラに否定するためにアゲツラフように述べている。「虚也。」と「非レ実。」とは意味は同じであるが、「就而熟」に反論しているのである。そして、「非レ実。」という言葉を引き継ぐ形で、「誓」の言、「若是実者、必被二天災一。」と述べている。
⑪のアナホベノミコの例では、「発憤」して「言挙げ」している。どうして亡くなった王の殯宮にばかりお仕えして生きている王の側には仕えないのか、と大声で言っている。生きている王とはアナホベ自身のことを言わんとしている。話の仕方が理屈っぽい。亡くなった先王にはよく仕え、生きているこれからの王には仕えていない、だから、と三段論法に持ちこもうとしている。アゲツラフことの得意な弁護士の言い方に似ている。「発憤」していて、ムツカルと訓んでいる。ムツカルと大声になるのは、ムツ(睦)+カル(枯・涸・離)ために小声でひそひそ仲良く話すことがなくなり、角立ってツンケン話すために自然と声が大きくなったということであろう。お通夜をしている最中から相続のことを言い出す弁護士風の人間に睦ぶところはない。
おわりに
「神からと 言挙げせぬ国」、「神ながら 言挙げせぬ国」がどんな国かといえば、「蜻蛉島 倭の国」、「葦原の 瑞穂の国」であった。その形容修飾の見事さ、言語表現の巧みさを、「神からと」、「神ながら」と讃えていた。その構造を括弧で括って理解しやすくすると次のようになる。
⑯「蜻蛉島 倭の国」は、神からと 言挙げせぬ国。
⑰「葦原の 瑞穂の国」は、神ながら 言挙げせぬ国。
「蜻蛉島 倭の国」、「葦原の 瑞穂の国」と言った途端にすぐさま確認、評価して「神からと」、「神ながら」と言っている。もうそれで十分な表現だから、それ以上には「言挙げせぬ」としてふさわしい、そんな「国」なのだが、というのが歌の導入部の序詞的な言い回しであった。
このような言い方は、「言挙げ」という語を使うときに現れる性質、すなわち、声を出して言うとき、それはまさしく、「言挙げ」的に大きな声をあげて言うことになっているが、言っている言葉の音量が大きくなっていることにまつわりつくことと親和性がある。「言挙げ」という言葉は、論理学でいう、対象言語とメタ言語という言語レベルの間に混同が引き起こる、その現場にある言葉なのである。そのことに気づいていた上代の人たちは、「言挙げ」という言葉を論理学的におもしろいものとして巧みに扱っている。「……」と言挙げする、と言えば、「……」と大声で発語し、その言述の仕方はコトをあげつらうもので、いろいろな可能性をひとつひとつ潰していくような理屈っぽい言明をして、他を言いくるめようとする強弁的な傾向を示す。そればかりか、その発声やアゲツラヒは、「言挙げ」という言葉にブーメランのように帰ってきていて、言挙げの性質が「……」のレベルに介入、浸潤し、「……」が牛のゲップのあがってくることや、「……」に飛びあがる要素を含入させていたりしているのであった。それらの結果、コト(言)がコト(事)を導こうとする試みとして、あたかも「言挙げ」という“儀礼形式”が行われているのではないかとさえ疑われるほどであったのである(注14)。
言葉は使われることでその役目を果たし、使われている場においてのみ存在するものであり、数学の公式のように使われる前から控えているものではない。上代の人たちにとって「言挙げ」という言葉は、その言葉を使えば言語レベルを行き来することが可能だと承知していて、いろいろとおもしろいことを言い表せそうだと思って楽しんで使っていたものなのである。いま、記紀万葉に残されているのはその形跡である。彼らの言語感覚は、メタ言語の事情に通じていて、高度なレトリックを駆使するに十分な領域に達していたということである。われわれ現代人の言語能力は、枕詞を駆使することなど到底思いつかないように、後塵を拝する状況にある。
(注)
(注1)論考のなかには、日本書紀の例と万葉集の例を分けて読み、「言挙げ」の語史をたどる向きがある((注2)参照)。本稿では、「言挙げ」という語の全体像を確認することを目指す。結果的には、上代において「言挙げ」という語に変異は認められず、ただ一通りの解釈で理解が行き届く。「言挙げ」とは大声を出して言うことである。
日本書紀の例でコトアゲと訓むとした古訓は、①「為言擧而」(兼永筆本傍訓)、②「興言 古止安介」(日本紀私記乙本)、③「稱 」(弘安本傍訓)、⑤「稱之」(乾元本傍訓)、⑦「稱之 」(鴨脚本傍訓)、⑧「高言 古止安介」(日本紀私記丙本)、⑨「揚言 」(前田本傍訓)、⑪「稱 」(前田本傍訓)によっている。なお、本文内の説明では「言挙げ」と一括して表記するようにしているが、表記によって意味内容が変わるものではないことを重視してのことである。
(注2)角川古語大辞典に、「ことばに出して宣言すること。言霊(だま)のこもる重大な内容を負うことばを口外することによって、望ましい方向に事が実現するという考え方に従って、神を前にした祭式や誓言などの厳粛な場における重大な発言をいう。なすべきでないときにすれば、大きな災いを招くとして慎まれた。」(506頁)、古典基礎語辞典に、「言葉にして声高く言い立てること。古代、言葉を意味するコト(言)と出来事や人間の行為を表すコト(事)とはほとんど同じと考えられ、口に出して言った言葉とそれを現実の事柄にすることは区別が明確でなかった。自分の思うことを言葉に出してはっきり言うことによって人の吉凶が左右されるから、めったなことは口にすべきでないと考え、コトアゲすることは禁忌として避けられた。……自分の思うことを言葉に出してはっきり言うこと。言葉にしたことは現実になるという言霊だま信仰から、うかつに口に出すことは禁忌として避けた。」(499~500頁、この項、石井千鶴子)、大浦2014.に、「「言挙げ」とは、日常の言葉とは異なる様式によって、祈りをこめて言葉を発することであり、「言挙げ」の力によって「言」として発された内容が「事」として実現するという信仰である。ただし、言語呪術である「言挙げ」はむやみに行うものではなかった。右の歌[万3253]にもあるように、この国は基本的には「神ながら 言挙げせぬ国」なのであり、「言挙げ」はよほどの危機を乗り越えるために行われるものであったようである。」(142頁)とある。
これらの考え方は、言挙げを特殊な「言」、特に神に対する「言」ととらえ、そこに禁忌性をよみとった次田1924.以来続いている。「此[⑰⑱]の「言挙せぬ」を、……多くの用例から推し量ると、是は神の意志に反して、自己の意志を揚言する事を云つたものらしい。……[①の例]は、白猪を神の使者であると思つて、之を侮つて言挙し給うた為であつて、元来言挙する事は忌むべきものとされてるたやうである。……[古代]の宗教思想から右の物語を考察する時には、是は倭建命の御病の原因を、膽吹山の神に対つて言挙せられた結果であると考へられたものであると解釈する事が出来る。上代では病気にしても、不慮の災難にしても、悉く神意によつて起るので、それは神の意志に反抗したり、神威を汚したりした為であると考へられたのである。要するに神に対して言挙する事は、神意の表現である所の、託宣や夢告や卜占や誓約に反抗するのと均しく、神の怒を招くものとして深く忌み慎まれたものであるらしい。」(国会図書館デジタルコレクションhttps://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1918074/228、漢字の旧字体は改めた)。
太田1966.では、「呪術的実修もしくは観念としての「ことあげ」は、その原始的な相においては、何か特別な開口発声儀礼にかかわるものであったらしい」(230頁)と想定し、「ことあげする」と「ことあげしない」があることから、「「ことあげしない」ということが言い出されるためには、言語活動というものについての相当の体験と反省と思索とが必要だったに相違ないのである。」(235頁)として“言挙げ史”を展開している。吉井1977.では、「言挙げは、[記紀万葉時点からみて]過去において威力ある言葉による発生儀礼という歴史をもっていたかもしれないが、今、我々に残されたものによって考えるかぎりは、この行為は、個人的願望を、言語にひそむ力によって上位者に、実現するように願うという性質を強めていることを認めざるを得ないのである。」(218頁)としている。青木2015.は、紀のコトアゲについて整理している。「まず、コトアゲの文脈は、そのコトの内容を提示しつつ伝承のとじめ、あるいは伝承展開の中で重要な位置に配されていること。次に、相手の回答を促すような、対話性(問答性)をもった言ではないこと。そして、神の言という意識があるゆえに、人が発した場合、霊威がある言として禁忌性、反王権性が生じること、などである。このようにおさえていくと、日本書紀のコトアゲは、その呪性の喪失過程の中で意味づける方向とは別に、むしろ呪性を前提として、発言者と受け手のかかわりの中で説くこともできるのではなかろうか。」(379頁)。
通釈書、解説書でも様相は同じである。大系本日本書紀では、②について「興は、名義抄にオコル・オコスとあり、発する意。言葉に発する意。」((一)49頁)、⑧について「ここでは、大言壮語すること。」((二)97頁)、⑪について「言葉にはっきり出して語り論じること。アゲは、全容を上に示しあらわすこと。」((四)51頁)、新編全集本日本書紀では、②について「いざという時に、言霊だまの力を借りて、言い立てること。」(①49頁)、③について「このコトアゲは、反逆心のないことが誓約の結果分り、今度は言霊だまの力を借りて宣言することをさす。」(①73頁)、新編全集本古事記では、①について「「言挙」は、大声で言いたてること。言葉の呪力を働かせるための行為。言挙げの内容に誤りが含まれている時、言葉の力は逆に働いて、神を撃つはずの倭建命の力を無効にしてしまう。「言挙」自体がいけないのではない。」(231頁)、新編全集本風土記では、⑫について「あえて自分の意志を言葉に出して表現すること。言霊だまの力による実現を期待する行為。」(63頁)、多田2020.では、①について「言挙げとは、ある事柄を特殊な方法で言い立て、言葉の呪力を働かせる一種の言語呪術である。多くは、神に向けたある断定的な意思(誓言)の表明になる。危急存亡の際の言挙げは必須と考えられたが、一方でそれは、現実を乗り越え、打ち破るための非日常的な力の発動だから、不用意な言挙げはかえって危険視された。」(44頁)、新釈全訳日本書紀では、②について「ことばにだして言い立てる。ことばに発することに霊力を認めていた。」(111頁)、⑧について「自らを過信して大言すること。古訓コトアゲはことばに出して言い立てることで、ことばの霊力を発動させる行為。ことばが霊力を持つからこそ、不可能なコトアゲは災厄をもたらす。」(495頁)と注されている。
(注3)社会心理学に、予言の自己成就と呼ばれる。もちろん、必ずしもそうなるとは限らない。とはいえ、上代の人が、コト(言)とコト(事)とは別物との前提で、“作為”して言=事になるようにしようなどとは思わなかったものと思われる。別物であるなら別の言葉を“選択”していたであろうからである。
(注4)拙稿「上代語「言霊」と言霊信仰の真意について」参照。
(注5)伊藤1993.は、「「言挙」とは、人間がある目的達成の際、障害となるかもしれぬ既知・未知な対象への畏怖感を克服するために、その対象の属性をあらかじめ良い方向に意味づける「言」や劣位な素性のものと暴露する「言」に変換して、声高く発する対抗措置だったと言えよう。」(244頁)と広範な定義を施しているが、中瀬を前にしてそこで濯ぐと言って濯ぐ事をしている。障害となるものなどない。
(注6)吉井1977.は、「「神ながら」の語は、『万葉集』に「神ながら神さぶ」「神ながら思ほす」「神ながらしく」「神ながら愛づ」「神ながら治む」などの表現となって十八例の使用がある。……「神ながら」の語の用い方をみれば、おそらく柿本人麿によって創始されたと考えられるこの歌語が、……「やすみしし我が大君、高光る日の御子」の表現とともに、天武、持統朝における王権の神聖化と、これを支える高天原神話の形成に従って使用されはじめた、特異な内容を含む歌語であることに気づかざるをえないのである。」(220~221頁)とする。
筆者がこういった議論に同意できないのは、歌が、歌を作って歌う側ばかりではなく、歌われた途端に聞く側にも共有されるものであったからである。言葉を新しく創作して使うことは誰にでもできる。問題は、多くの人に受け入れられるかどうかである。内輪で盛り上がるといった局所的なその場限りのものではなく、聞いた人のほとんどがうまいことを言うねえと感心し、納得して世の中に歓迎されなければ言葉として広まり得ないのである。新しい言葉を教壇上から概念定義をレクチャーすることは皆無であったとは言わないが、歌が披露されるときにそんな事態は起こりえない。皇室、王族、豪族貴族の面々が、下級役人なのかさえ不明な柿本人麻呂から新しい言葉の説明を受けていたとは考えられない。二度聞きしなければわからない歌はまた皆無とは言わないが、広くフォロワーを獲得することはなく、つまりは新語が流行語となることはなく、ただ死語となっていったであろう。
(注7)柿本人麻呂には、吉野讃歌(万36~39)のように、国のありさまを持ち上げることがあるとされるが、天皇を持ち上げているのであって、勝手に国のありさまを評論するようなことはしていない。
(注8)西郷2006.は、「言挙げ」について解説する際、「神ながら」という語を施しているが誤用である。「不用意なコトアゲは不吉とされていた。しかし神ながらの自然的秩序が崩れてゆくにつれ、人は否応なくコトアゲするようにならざるをえない。次の歌にそのへんの消息がうかがえる、「葦原の、瑞穂の国は、神ながら、コトアゲせぬ国、然れども、コトアゲぞ我がする、言幸く、ま幸くませと、……コトアゲす我は」(万、一三・三二五三)。」(115頁、説明文の後半を割愛した)。
(注9)拙稿「ヤマトタケルの伊吹山の難」で、この話のなかの言葉の絡み合いについて詳細に分析している。
(注10)吉井1977.に、土着豪族の息長氏が「山の神」の背後にあるとする見方がある。そういう設定を置くことは誤りであるが、イフキ(息吹)にオキナガ(息長)氏が関係あるようになっていったのは、話をよく理解した人たちによるものと思われる。
(注11)この万1113番歌に「言挙げせねども」という句が使われていることについての解釈は、これまで見過ごされてきた。以下の注釈書では、古事記の、吹き棄つる気吹が霧になったという話を紹介しながら、言葉を中心に考えるのではなく、神話での展開を典故とするものかとしている。伊藤1996.に、「言挙げをすれば、その発声に伴う気息によって霧がかかるという信仰があったのであろうか。『古事記』上巻の天の真名井の誓約の段に、「吹き棄つる気息」が霧になったという話がある。霧がおのずからに湧き起こり立ちこもる現象に自然の威力を覚えた歌であろう。」(74~75頁)、多田2009.に、「アマテラスとスサノヲは、天の真名井で誓約を行っている。互いの物実が「吹き棄つる気息のさ霧」になったとある(「神代記」)。「霧」は、この伝承を意識したものか。恋の誓約を交わす場でもあったから、それへの意識もあるか。あるいは、恋の不成就の嘆きの息が「霧」になったか。」(34頁)とある。
(注12)太田1966.に、「「ゆめな言挙しそ」と言われたから「言挙の阜」なり「言挙の前」なりの名が生まれたというのは不自然であり、後人の解釈によって転生した伝承であることが難なく想像されるが、この所伝は原始的なことあげ観念をそのまま継承しているものではなく、新しい段階のそれを反映しているものと見られる。「言挙の阜」のほんとうの由来は、そこで何らかの開口発声を主要素とする宗教的儀礼もしくは呪術的行為が、恒例的に行なわれていたことにあったものと想像するのが自然で、その名の根拠があまり判然としなくなったころ、別個の由縁の附会がこころみられたものであろう。」(232頁)とある。吉井1977.では、「[神功皇后が]言挙げするな、というのは、後に言挙げしないことが美風と考えられたことによって、修正を受けたものと考えるのが妥当であろう。」(215頁)としている。
現代の研究において、最初に躓いてしまって踏襲されるとこのようなことになる。風土記の地名伝承は、地口的な地名譚にすぎない。地名自体、言葉自体についてああだこうだ言っているのであって、言挙げについて、しないことが美風かどうかといった判断など、考えに入れられるものではない。そのことは、他の地名の由来を語るときにもすべて当てはまる。「言挙阜」の名の本願については本文に述べたとおりである。
(注13)論理学の逆説の例に、「クレタ人は嘘つきだとクレタ人が言った」という有名な命題がある。クレタ人が嘘つきなら、「クレタ人は嘘つきだ」と言っているクレタ人の言は嘘であるから「クレタ人は嘘つき」ではないことになり矛盾が生じる。クレタ人の言が本当のことだとしたら、言っている内容の「クレタ人は嘘つき」であることとの間にこれまた矛盾が生じる。どうしても矛盾が生じるのである。伝承された人の名を冠してエピメニデスのパラドックス、また、自己言及のパラドックスとも呼ばれる。
それに照らすなら、「上代人は大声でものを言うと上代人が大声で言った」という命題を実現していることになる。このとき、論理学的には、正誤以前、意味をなさないというのが本当のところではあるが、逆説には陥っておらず、あたかも絶対的な真理であるかのようにさえ目されるものである。それがおもしろいから、「上代人は大声でものを言うと上代人が大声で言った」という文脈で、上代の人は「言挙げ」という言葉を使ったのであった。コトアゲとはコト(言)+アゲ(挙)の複合語以外のなにものでもない。コトアゲという複合語は、メタ言語がその論理的部分において「本質的に豊か(essential richness)」(タルスキ)であることにかなっている。
 言語レベルの混同を楽しむ表現の概念図
言語レベルの混同を楽しむ表現の概念図(注14)「言挙げ」が記紀万葉に儀礼として扱われていないばかりか、令や式などに一切現れないことも、古代のそれが儀礼的、儀式的なものではなかったことを示唆してくれている。
(引用・参考文献)
青木2015. 青木周平『青木周平著作集 上巻 古事記の文学研究』おうふう、平成27年。
伊藤1993. 伊藤高雄「言霊の信仰」櫻井満監修『万葉集の民俗学』桜楓社、平成5年。
伊藤1996. 伊藤博『萬葉集釈注 四』集英社、1996年。
岩波古語辞典 大野晋・佐竹昭広・前田金五郎編『岩波古語辞典』岩波書店、1974年。
大浦2014. 大浦誠士「こと【言・事】」多田一臣編『万葉語誌』筑摩書房、2014年。
太田1966. 太田善麿『古代日本文学思潮論(Ⅳ)─古代詩歌の考察─』桜楓社、昭和41年。
角川古語大辞典 中村幸彦・岡見正雄・阪倉篤義編『角川古語大辞典 第二巻』角川書店、昭和59年。
烏谷2016. 烏谷知子『上代文学の伝承と表現』おうふう、2016年。
岸根2017. 岸根敏幸「古事記神話と言霊信仰(後編)─他者に幸禍をもたらす発言、および、「言挙げ」─」『福岡大学人文論叢』第49巻第3号、2017年12月。福岡大学機関リポジトリhttp://id.nii.ac.jp/1316/00004245/
古典基礎語辞典 大野晋編『古典基礎語辞典』角川学芸出版、2011年。
西郷2006. 西郷信綱『古事記注釈 第六巻』筑摩書房(ちくま学芸文庫)、2006年。
時代別国語大辞典 上代語編修委員会編『時代別国語大辞典 上代編』三省堂、1967年。
志水1995. 志水(城崎)陽子「言挙げ考」『目白学園女子短期大学研究紀要』第32号、1995年12月。
新釈全訳日本書紀 神野志隆光・金沢英之・福田武史・三上喜孝校注『新釈全訳日本書紀 上巻』講談社、2021年。
新編全集本古事記 山口佳紀・神野志隆光校注・訳『新編日本古典文学全集1 古事記』小学館、1997年。
新編全集本日本書紀 小島憲之・直木孝次郎・西宮一民・蔵中進・毛利正守校注・訳『新編日本古典文学全集2 日本書紀①』・『新編日本古典文学全集3 日本書紀②』小学館、1994・1996年。
新編全集本風土記 植垣節也校注・訳『新編日本古典文学全集5 風土記』小学館、1997年。
大系本日本書紀 坂本太郎・家永三郎・井上光貞・大野晋校注『日本書紀(一)』・『日本書紀(二)』・『日本書紀(三)』・『日本書紀(四)』岩波書店(ワイド版岩波文庫)、2003年。
多田1995. 多田一臣「言挙げということ─『万葉集』巻十三・三二五三~四を手がかりにして」『日本文学』第44巻第6号、平成7年6月。
多田2009. 多田一臣『万葉集全解 3』筑摩書房、2009年。
多田2020. 多田一臣『古事記私解Ⅱ』花鳥社、2020年。
タルスキ1987. アルフレッド・タルスキ、飯田隆訳「真理の意味論的観点と意味論の基礎」坂本百大編『現代哲学基本論文集Ⅱ ムーア タルスキ クワイン ライル ストローソン』勁草書房、1987年。(Alfred Tarski, “The semantic conception of truth and the foundations of semantics”, in Leonard Linsky (ed.), “Semantics and the Philosophy of Language : a collection of readings”, Urbana : University of Illinois Press, 1952.)
次田1924. 次田潤『古事記新考』明治書院、大正13年。
中村2012. 中村秀吉『パラドックス─論理分析への招待─』講談社(講談社学術文庫)、2012年。
樋口2016. 樋口達郎「神の発話と神への発話─「言挙」に関する一考察─」『倫理学』32号、2016年3月。つくばリポジトリhttp://hdl.handle.net/2241/00143848(『言霊と日本─言霊論再考─』北樹出版、2017年、所収)
吉井1977. 吉井巌『ヤマトタケル』学生社、昭和52年。















