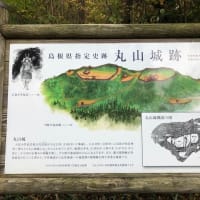1.2.5.明治初期の舟運
国土交通省が公表している「明治初期の舟運」を見ると、江の川は陰陽の大動脈として物資が行き通っていたことが分かる。
以下に上記のレポートから要点を抜き出して次に示す。
「明治初期の舟運」の抄録
明治2年に津留が解かれた後、 舟運は急激に発展した。

運航時間
江の川を上下する舟運は江津ー三次間を上り5日、下り2日で結んでいた(この時間は船着き場での駐船時間・宿泊の時間を含めている)。
実際の運行時間は、三次一粕淵間約62Kmを上りは24 時間強、下りは13時間弱で運航した。
江津ー粕淵間では川本大字川本今津舟着場や川越村田津舟着場(今の渡田)が比較的規模 の大きい舟着場となっていた。
また、江津の郷田川端舟着場には絶えず20~30 艘の川船がつながれ、この他に河口付近には、小規模な舟着場が多数設けられた。
運行回数
運航回数は口羽村から粕淵までは月平均54往復に達し、 特に都賀村大字都賀西渡り場舟着場から粕淵番所ノ沖舟着場間は70往復という頻繁な運航であった。
粕淵から江津村大字郷田川端舟着場間は平均50回弱である。
船の大きさ
また、舟の大きさは江の川本川では長さ6間 (約11m) 幅4尺 (約1.2m) の大船が使われ、 三次近辺では吃水の浅い長さ3間 (約 5.5m) 幅3尺 (約0.9m) の軽古舟が主に利用されていた。
積載量は下りが20~30駄 (1駄 = 約112.5kg)、 上りは10駄程度で、下りの3分の1程度にも満たないこともあった。
運賃
運賃は大正初年で米1升が15銭のころ、作木一江津間木材を運んで8〜9円であった。
船頭は通常1隻2人で、下 りは櫂や楨を巧みに操りながら急流を下っていったが、 上りになると順風であれば帆をはり、風がないときは船頭の一人が沿岸沿いの、いわゆる船頭道からロー プで舟を引いて遡航した。
鉄製品
江の川舟運は中国山地の 「たたら」 製鉄地帯を横断しており、鉄製品が米とともに移送物の中心を占めている。
幕末から明治20年代までがたたら製鉄の最盛期であり、 鉄・鉄鋼・祇・砂鉄などが大量に運搬されていた。
鉄製品の搬出の中心となっていたのは、 上流部では門田中原舟着場と東入君木呂舟着場で、それぞ れ西城川上流域と神野瀬川流域のたたらを背景としている。
これらは主に吉田方面へ運搬されたが、 吉田浜舟着場には江の川中流域で生産した製品も多く搬入さ れた。
中流域では、 作木港・下作木大津・下口亀ノ尾・上田青山・宇津井都賀西 渡り場・都賀本郷古市等の港から付近の鉄を搬出している。 また、 都賀西と都賀本郷には大量の砂鉄が搬入されている。
邑智郡粕淵より下流では鉄山地が数箇所に集中しており、 搬出港は粕淵番所ノ沖と坂本舟津、川越田津舟着場に限られる。
川越田津から搬出される鉄製品は邑智郡中・南部のものである。
これらの鉄製品は河口付近の港で大量に荷降されるため、 拠点港である郷田川端以外の港を多く利用している。
その取扱数量はほぼ郷田に匹敵する。
荷物取り扱い高と出荷方面
最も荷物取扱高が多いのは江の川舟運の発着地である河口の郷田川端舟着場であり、 粕淵番所ノ沖、 吉田浜舟着場、 三次五日市運上場 (五日市舟着場 松原舟着場を含む)、 川本今津舟着場とつづく。
遡航最終地の吉田浜舟着場に陸揚げされた荷物は、 馬で上根峠を越して可部に運び、 可部でまた舟積し、太田川本流を広島へ、あるいは太田川支流三篠川舟運で広島方面に送られた。
一方、郷田へ集められた物資は日本海を南北に航行する年2回 の廻船に積み込まれ、 北は北海道、南は北九州から釜山・仁川等へも輸送された。
舟留りは河口西側の幸島にあったが、 水深が浅いため一部の荷物は海へ出て艀で積み込まれていた。
筏下しは丸太や竹材で竹は80~120束を筏として荷造りし大貫付近の物が最も多く出荷された。
郷田川端舟着場における取り扱い荷物を金額でみると、移入は銅・鉄・鉄・扱苧・ 白炭・木材・格と続き、 移出は鉄・鉄・白炭・楮の順である。
銅は大森で産出したもので、 川本今津舟着場から送られてきたものである。
中流部の中継地点粕淵 番所ノ沖舟着場における移入は、 反物干草・ 金物・塩・砂糖など郷田川端とは 対照的に日用品が多くなっている。
また、 移出は牛馬が群を抜いており、繭・米・ 反物・金物 ・ 炭と続く。 上流部の三次五日市運上場では移出入とも鉄と雑貨である。
最上流部の吉田では移入は鋼・米・鉄が中心で、 日用雑貨の取り扱いがなく、 三次までとは異なった傾向を示す。 吉田浜と三次運上場間の小規模な舟着場及び馬洗川の舟着場はもっぱら米の搬出に利用されていた。
江の川水運の衰退
明治年代の後半から浜原一江津間に定期船が開通した。
これは三光社が経営していたので三光船と呼ばれた。 船の底部をペンキで塗装した4人張りの手漕ぎ船であったが、当時としては最新の快速船であった。
三光船は10艘位あったが、明治30 年代には姿を消した。
ついで大正期に入って飛行船といわれたプロペラ船が登場 した。
このプロペラ船は紀州熊野川で利用されていたものを移入し、1日2往復 50人ぐらいの客と荷物を積んで江津から粕淵まで行き来していた。
しかし、三江線が川越まで開通すると旅客も減少し採算がとれず、 昭和6年に廃業した。
<川舟 (三次市粟屋町荒瀬)>

<続く>