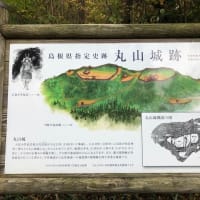1-2.江の川の水運
江の川の水運については、僅かな文献しか残されていないが、相当古くから江の川は交通手段として活用されていた様である。
邑智郡誌(昭和47年9月1日再発行、昭和12年12月20日初版発行)に
「江川に於ける河船のことが文献に記録されている最初のものは、口羽村上ヶ畑菅原神社の由来記に見もるものであろう。
それは天慶九年(946年)とあるから、今より約一千年位前のことである。
併しこれは此の時に船を初めて作ったのではあるまいから、恐らく舟運はこれより以前相當に古く行われていたとするのが正常な考え方であろう」
との記載がある。
口羽村上ヶ畑は現在の邑南町上田である。
この上田地区で「菅原神社」を探したが見当たらなかったが、「菅津彦神社」が村上ヶ畑集会所の近くに存在していた。
この神社が何らかの関係があるかもしれないが、それ以上は分からない。
江の川を行き交う舟
次の絵は、安永3年(1774年)に香川景隆と江村景憲によって著された「石見名所方角図解」のなかの「渡里山」の絵である。
この「渡里山」とはいまの甘南備寺山である。その山の麓を流れている江の川を人が舟で移動している図である。
船に乗っている人が旅人なのか地元の人なのかは不明であるが、江の川は交通路として使われていたことが見て取れる。

1.2.1. 桜井ノ津
古来より江の川と八戸川の合流点辺りを桜井ノ津と呼ばれ交易が盛んに行われていたという。
当時、川戸は現在のような平地は存在しておらず、一面に江の川の水を湛えた一大湖面の景観であった。
江の川の水量も豊富で、河床も現在より遥かに低かったので、日本海の湾の入り込み方もずっと、川戸近くまで寄っており、川戸・住郷の地は「桜井の津」と名付けて、邑智郡奥部の物資を積み出し、外海からの物産を輸入していたのである。
記録に残っているものとして、応仁2年(1468年)この地の土豪土屋吉久が朝鮮貿易を先駆けたとある。
朝鮮の「海道諸国記」に「石見州桜井津土屋修理大夫平朝臣賢宗が(1470年)に使いを派する」との記述があり、このことを裏付けている。
この土屋氏の先祖はかつて鏑腰城(川戸:八戸川と江の川に挟まれた山地)の城主であったが、応永21年(1414年)に都治家騒動を起こしたため、幕府によって征伐され領地を没収された歴史がある。
その後土屋氏は朝鮮交易などで蓄財し、次第に勢力を盛り返し、小地域ながらこの地域を支配するようになっていく。
古記録には、土屋賢宗は宝徳4年(1452年)6月、谷住郷の地に宇佐より住江八幡宮を勧請し、自らその大旦那となったり、応仁の乱後の皇居修復のための石見割当段銭600貫(現在の価値で6,000万円位と思われる)を諸豪族の代わりに全額負担したりした、との記載がある。
1.2.2. 軽枯船(かんこせん)
江の川は山陰・山陽連絡の大動脈として早くから利用されていた。
江戸幕藩体制下では直轄地を江の川以北としたが、特例として江の川の左岸にある、川本や郷田(江津)は天領に編入された。
これは、江の川の舟運の大動脈を幕府が掌握するためである。
江戸幕府は国境の要地・港湾河川などの要衝の地に口留番所を設け、物資の出入、 人の往来に監視の体制をとっており、江の川河畔では、川登口(現松川町)、住郷口、坂本口、 川本口、小原口 (現粕淵) 浜原口、都賀口、都賀行口に川船改番所を設け、灰吹銀抜売の監視、諸取引に対して歩一 (税) 取立のため、 同心を配置していた。
<坂本口番所跡碑>

備後国の「三上郡山野内高母」 から 「川本」までの約72Kmの急流部の運送は軽枯船(かんこせん)と呼ばれる舟が行っていた。
川本に着いた軽枯船はここで下流へ向かう川船に継荷した。また下流から上流に向う場合も川本が中継点となっていた。
この軽枯船の構造は、船首の方は「鳩の胸」形に反りかえり、長さは約9mから10m、幅は底が狭くなり約50cmほど、上部で1mから1.2mぐらいで、全体的に軽快に造形されていた。
軽枯船の操作は、登り積荷の際は二人が縄をひき一人が竿で横をとり、 下りは縄ひきをつけないで竿だけで船を操るというやり方であった。
こうした輸送の形態は大正初期まで細々ながらも継続されたが、大正10年(1921年)に三次に発電用ダムが出来たため、平水量の減少により貨物輸送路としての江の川舟運は大きな打撃を受け徐々に消えていった。
1.2.3. 定期船の開通
明治20年代の後半頃から浜原ー江津間に定期船が開通した。これは三光社が経営したので三光船とよばれた。
船の底部をペンキで塗装した四人張りの手漕ぎ船であったが、当時としては最新の快速船であった。三光船は十艘位あったが、 明治三十年代には姿を消した。
当時の記録によると、因原から江津まで4,5時間かかったそうである。
朝八時に出ると、昼過ぎに江津に着いた。上りは荷物を積んでいると川越で泊まるから1日かかった、という話が記録されている。
1.2.4. プロペラ船(飛行船)
大正期に入ってプロペラ船が登場した。 これは紀州熊野川で利用されていたものを浅利村の山根佐仲という人が江川で企業化したものであり、当時飛行機に利用した発動機を使用し、飛行機のプロペラを回して前進し飛ぶように速かったので飛行船ともいわれた。
しかし、増水すれば遅延し、操縦を誤って岩に接触したりする事故も数回発生したという。
三方ガラス張りで眺めもよく、風の寒さも感じず、なかなかの人気を集めていたという。
大正七、八年頃川本ー江津間が二円八十銭というから相当な運賃であった。
大正時代の小学校の教員の初任給は50円程度だったことから換算すると1円は現在の約4,000円の価値があったことになる
このプロ ペラ船は、一日四往復運行(後で二往復に減便)されていたが、昭和6年(1931年) 三江線が川越まで開通すると、汽車の速度、運行回数、安全、運賃のやすさには比較すべもなく、旅客が激減し採算が取れなくなり 昭和六年に惜しまれながらついに廃業となった。
<プロペラ船>

<続く>