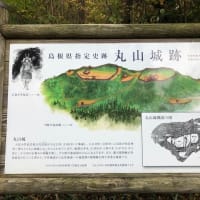戦国の石見−4(続き−5)
61.4. 尼子・毛利の対決(続き)
61.4.3.大内義隆とフランシスコ・ザビエル
フランシスコ・ザビエルは日本にキリスト教を伝え伝えた人物である。
このザビエルと大内義隆と関わりがあった。
横道にそれるが、少し触れたい。
ザビエルは1506年(永正3年)4月7日、スペインのナバラ王国で生まれた。
イエズス会の創設メンバーの一人である。
1541年4月7日にリスボン(ポルトガル)を出発しインドのゴアを目指した。
1542年5月6日にゴアに到着。
ここを拠点にインド各地で宣教活動を続けた。
1547年12月に出会った鹿児島出身の武士ヤジロウがザビエルに日本に来るようにすすめた、という。
1549年4月15日、イエズス会士コスメ・デ・トーレス神父、フアン・フェルナンデス修道士、マヌエルという中国人、アマドールというインド人、ゴアで洗礼を受けたばかりのヤジロウら3人の日本人とともにジャンク船でゴアを出発、日本を目指した。
549年4月15日、ヤジロウら3人の日本人とともにゴアを出発、日本を目指した。
天文18年(1549年)8月15日に現在の鹿児島市祇園之洲町に来着した。
9月、フランシスコ・ザビエルらは島津貴久の許可を得て布教を開始する。
しかし、その後、貴久が仏僧の助言を聞き入れ禁教に傾いたため、「京にのぼる」ことを理由に薩摩を去った。
天文19年8月、ザビエル一行は平戸(長崎)に入り、宣教活動を行った。
10月下旬、信徒の世話をトーレス神父に託し、ベルナルド、フェルナンデスと共に京を目指し平戸を出発する。
ザビエルたちは、周防(山口)で宣教活動し、大内義隆にも謁見する。
しかし、男色を罪とするキリスト教の教えが義隆の怒りを買い、周防を発って京に向かった。
ザビエルは京都で宣教活動を行う。
しかし京都での宣教活動はうまくいかず、平戸に帰り、平戸に置き残していた献上品を携え、山口に向かい、大内義隆に会いに行った。
献上品は、望遠鏡、洋琴、置時計、ギヤマンの水差し、鏡、眼鏡、書籍、絵画、小銃などであった。
ザビエルは、初めて日本に眼鏡を持ち込んだといわれる。
これらの品々に喜んだ義隆はザビエルに宣教を許可し、信仰の自由を認めた。
日本滞在が2年を過ぎ、ザビエルはインドからの情報がないことを気にしていた。
そして一旦インドに戻ることを決意する。
11月15日、日本人青年4人(鹿児島のベルナルド、マテオ、ジュアン、アントニオ)を選んで同行させ、トーレス神父とフェルナンデス修道士らを残して出帆した。
1552年2月15日、ゴアに到着すると、ザビエルはベルナルドとマテオを司祭の養成学校である聖パウロ学院に入学させた。
マテオはゴアで病死するが、ベルナルドは学問を修めてヨーロッパに渡った最初の日本人となった。
一方、ザビエルは中国での宣教を目指し、同年9月上川島(中国広東省)に到着した。
しかし中国への入境は思うようにいかず、ザビエルは病を発症した。
12月3日、上川島でこの世を去った。46歳であった。
<ザビエルの航路>

<平戸オランダ館 フランシスコ・ザビエル肖像画>

<平戸市 崎方公園 フランシスコ・ザビエル記念碑>

<平戸ザビエル記念協会>

余話
司馬遼太郎には紀行文集「街道をゆく」シリーズがある。
この第22巻「南蛮のみち」では、フランシスコ・ザビエルの故郷バスクを中心に司馬が旅をしている。
これは、平成10年(1998年)にNHKスペシャルでも放映されている。
61.4.4.周防大内氏滅亡
天文20年(1551年)9月山口において、大内義隆が重臣陶隆房に殺されるという事件が起きた。
これにより山陰の情勢は大きく変わり、 尼子対毛利の対立がさけられないものになったのである。
義隆を滅ぼした陶隆房(後晴賢と改名)は、大義名分を立てるため、義隆の姉の子で九州にある大友宗麟の弟義長を迎えて大内の家督を相続させた。
この変事により石見に君臨した義隆がなくなったので、地方勢力はその均衡を失い各地に小紛争が起きることになる。
従来、陶隆房が文学遊芸に耽る大内義隆と合わなかったのは一朝一夕のことではない。
天文18年(1549年)大内義隆滅亡8月、隆房から吉川元春に送った書状には、「義隆某間の儀、更らに赦免なく候ひし条、若子のこと、取立つべき心中に候の由、杉正重、内藤盛興と申談じ候、この節御入魂に預り候はば、本望たるべく候、仍って御望みの儀候においては、聊も疎略あるべからず候」
と述べており、すでにこの時点において、 義隆を隠退せ、その子義尊を立てて重臣政治を実現しようとする陰謀が進行しつつあったのであるが、この謀に加わりながら隆房と相良武任を併せ除いて、自分の有利を図ろうとした杉重政の策謀が、更らに事態を悪化拡大したようである。
天文19年(1550年)9月、かねて杉・内藤と語らい、まず義隆の寵臣相良武任を除こうと企てた陶隆房は、更に義隆をも斥けんとしているとの風評が立ったので、所領の周防都濃郡富田の若山城に退き、相良武任もまた山口を逃げ出した。
隆房は義隆に対抗するため、大友義鎮の援助を求め事変後義鎮の弟晴英を後嗣とする内諾を得、天文20年8月28日挙兵、富田を発して佐波郡徳地口より山口に進み、その部将江良・宮川らは佐波郡防府口より山口に入り、杉重政・内藤興盛らも隆房に協力参加したので、山口の動揺は極度に達した。
【大内晴英】
大内義隆の養嗣子。
父は大友義鑑、母は大内義興の娘(大内義隆の姉)。
晴英はあくまで養嗣子ではなく猶子であった。
これは義隆に将来実子が生まれなかった場合に家督相続人とする含みを持っていたが、大友氏ではこれを歓迎した。
しかし、天文14年(1545年)に義隆の実子・義尊が誕生したため、猶子関係を解消され帰国していた。
義隆は築山館を棄てて滝の法泉寺に退き、防戦につとめたが、衆寡敵せず、29日、嫡子義尊をはじめ左中将良豊らの公家・家臣らとともに長門に逃げる。
吉敷郡糸伊根、長門美祢郡綾木・秋吉を経て、9月1日、長門大津郡仙崎に至り、船に乗り石見の吉見を頼り再挙を図ろうとしたが、北風にあい船が進まないので、再び上陸し深川の大寧寺に入って自殺した。
2日、義尊もまた殺されて、大内家の正統はここに絶えた。
前に、肥後の同族を頼って山口を逃げ出した相良武任は、大内氏の筑前の守護代杉興連に抑留されていた。
かれは天文20年1月、興連に宛てて自分の冤罪を訴えた「相良武任申状写」によれば、隆房の権勢をねたんでいた杉は、一方義隆に讒訴して隆房の力を抑えるとともに、隆房らの勢力を利用して武任を除こうとしたものだというのである。
隆房はこの「中状」を見て後悔し、天文21年1月、佐波郡大崎に重政を攻めてこれを滅ぼした。
山口の動乱鎮定後、 隆房は大友義鎮に前約の履行を懇請したので、晴英は天文21年(1552年)2月、豊後大分都府内を発して山口に入り、大内氏の後を継いだ。
この時隆房は晴英の偏諱を受けて名を晴賢と改め、ついで晴英もまた義長と改名した。
この大内義長は弘治3年(1557年)毛利に攻められ自害し、周防大内氏が滅亡するのである。
陶隆房謀反
隠匿太平記巻18に陶隆房の陰謀についての記述がある。
例によって作者の創作部分も多いと思われるが、次に記述する。
隠匿太平記 巻18
陶隆房の陰謀の事
かくて陶尾張守隆房は、杉・内藤を呼び集め、密かに囁いた。
「相良遠江守が逐電したこと、よくよく聞いてみると、全く武任自身が考えついた方策ではないようだ。
義隆卿の命により、いったん武任を逃がしおき、隆房の怒りを静めてのち、時節を窺い、隆房を成敗しようとする企てである。其れがしが謀りごとを巡らしていることも、また御辺達がそれがしに一味しようとして、おることも、相良がことごとく告げ申し上げたとか。
こういうことでは、この後、我々かならずや死罪に処せられるであろう。
かかる暗君に仕えていては、われらの滅亡はもとより、やがて大内家断絶のもと、一刻も早く義隆卿を討ち、明主を据えて、国中の苛政を改めるべきであろう。
しかしながら隆房、このまま山口にいては、計略を巡らそうにも便宜を得ぬ。
それがしは隠居と称し、身の暇を申し受け、富田の若山に引きこもって、大友・毛利などに誘いをかけるようにしよう。
毛利隆元は興盛の聟、吉川元春はこの隆房が兄弟の契りを結んでいる以上、それと いいこれといい、元就はさだめて我々に一味せられよう。
それがしは若山にあり、元就と示し合わせて、諸所の城々を攻めるとなれば、富田と吉田の間にある諸城は、一日のうちに落ちることであろう。
大友もまた一味して、 豊筑の武士は、大友に攻められることを恐れ、みなこれを警戒して、一人も義隆卿を助ける者はないだろう。
そのとき、一族の二、三人も誘い入れたならば、兵は四、五千人にもなるであろう。
この外、他家にも力を合わせる兵はござろう。
さてそれがしが山口へ押し入ると聞けば、山口勢はさだめて途中に出て来て防戦するであろうが、そのときおのおのが山口の所々に火を放ち、後ろから旗を揚げられたならば、山口勢は前後の敵に行く道を失い、四方八方へ逃げ散ること疑いなし。
もしまた冷泉・天野らが屋形(大内義隆)に勧めて、富田へ攻め入ることになれば、さだめて 各々方に先陣を申し付けられるであろう。
そのときはただちにお受けして、屋形を富田へ誘い出し、心を合わせて討ち取るのに、何の難しいことがあろうか」
謀議はここに一決して、陰謀を犇犇と巡らした。
まず与力となるべき者を語らったところ、問田の一族は陶の一門であるから言うに及ばず、鷲頭の一党は屋形に恨みを含む者どもで、流れに棹を得たりと、喜んで同心した。
八本杉の者どもは一門の総領である重政の下知に従う。青景は、屋形と陶との間の讒者の主謀者であるから、最初から一味である。
その外、日ごろ相良を憎んでいた者どもは、みな屋形に対しての恨みは深いので、われもわれもと一味同心し、ここに寄り合い、かしこに集い、秘計密策に、それぞれ少しの暇もないようである。
いよいよ富田へ引き籠もろうと思い、 安富源内に近付いて、馬や太刀、 その外数々の財宝を、折につけては引き出物として与えた。
そしてその後、話をした。
「この隆房、かたじけなくも重臣の身として、国の政道を補佐申し、姦臣を遠ざけ、賢臣を取り立てんことを思い、相良(遠江守)を追い去ろうとした。
しかし彼への屋形のご寵愛甚だ深く、これではご当家敗頽のもとであろうと思い、わが身の後日の鼎鑊(人を煮る釜:刑罰の意)をも忘れ、相良を討とうとしたが、屋形憐みの心深く、『隆房、自害せよ』とさえ仰せ出されぬこと、これまったくもって亡父道麒が忠の限りを尽くされたによってのことと、ありがたき君恩、骨身に徹しております。
しかし、たとえ公(義隆)がお許しの心深うあらせられようとも、相良が逐電した上は、それがしとて、何のはばかりも恐れもなく、山口に留まっておりましては、いよいよもって不義不礼の至りとなる。
ならば、隆房は五郎に家を譲り、富田へ隠居し、座禅に専念し、念仏三昧を日課として、後世菩提の営みに身を捨て、俗世の交わりを絶ち、山野を友として世を送るが良策と思っている。
このよし屋形のもとへ、よろしくご披露なさってください。この儀ひとえにおとりなしのほどを」
と言いたてた。
安富はたびたびの引き出物が気を良くしており、また隆房に陰謀の企てがあるとはつゆ思いつかず、まことにそれがよかろうと思い、すぐに義隆卿へ披露すると、義隆卿も天運に見放されたと言うべきか、いささかの思案もなく、隆房の望むところに任せたのである。
隆房は謀り得たと喜んで、天文二十年十月七日を、隠居の暖乞いの出仕の日と定めた。
一方、冷泉(隆豊)判官はこのことを聞き、屋形をおおいに諌めて、
「隆房、富田へ隠居のこと、俗世の交わりを断ち、菩提を願うべき心中では、些かもありません。己の城にこもって、陰謀を企てる所存でございましょう。
彼が城に籠もってしまっては、いかにおぼし召されようとも、容易にご退治はなりがたく思われます。幸いに来たる七日、(隆房は)お暇乞いのため出仕するので、お許しがあれば、某が奏者(取り次ぎ役)して、刺し違えましょう。
そのとき、陶の郎党どもが、きっと殿中へ切り入ることでご ざいましょう。
かねて佐波・黒川・天野らに仰せ付けられ、その押さえとされ、またお側にもご側近の勇士どもを、ここかしこに隠しおかれ、ご用心なされるがよろしいかと存じまする。
いま彼をお討ちなされねば、後悔先に立つまいと存じます」
と献策した。
しかし屋形は、
「陶は近年、武任と婚姻の儀について、吾を恨んでおったと聞く。すでに武任逐電せし上は、日ごろの恨みも残ってはおるまい。
何で今さら逆意を抱こうか。謀反するというまさしき証拠がどこにある。
もし証拠もなしに成敗したならば、かえってこの義隆が自滅を招くこととなろう。
『国を亡ぼし家を破るは、人を失ふなり』という。陶は当家の柱であり、礎である。柱や礎が弱ければ家は崩れる。されば『主と臣と同じき者は昌え、主と臣と同じからざる者は亡ぶ』という。
この上は、たとえ、陶が反逆を起こすとも、この義隆においては、一旦は和を求め、君臣合体の道をこそ歩もうぞ。 ましてや、いま罪もなくして彼を成敗すること、まったくもって吾においては承知しないぞ」
と言った。
隆豊はその後は何も言わずに退出したのであるが、なんと頼りない義隆卿の仰せ言よ「明者は遠く未萌(ことが未だおこらないこと)に見、知者は危きを未形(形にならないこと)に避く」という、陶の謀反が露顕するまで時をおいては、なんとして退治なされ得ようぞ、彼が富田へ引きこもって反乱を起こせば、それがしも主君とともに死なねばならぬことは必定、『君辱しめらるるときは、すなわち臣死す』という、とても(どんなにしても)死ぬ命ならば、いま陶と刺し違えて、君の急難をお救いしよう。
陶がいかに心は猛くとも、力量においては、この隆豊の十分の一もあるまい、七日の出仕には、かならずや取って押し伏せ、刺し殺してくれようものを、と心一つに思い定め、二人の子供はまだ幼少で、この旨遺言することもできず、ただ事の始終を書置きにして、陶の出仕の日を待っていたのである。
去る程に、同十月七日、陶隆房は隠居の暇乞いのため、 築山へ出仕した。
かねて言い含めてあったのだろうか、宮川・深野・江良・野上ら二百余人、下の下の侍に至るまで、お屋形義隆公を一目拝み奉ってお暇乞い申したいと称して、おのおの一斉に小庭に押し入った。
これは隆豊の計画とは相違していた。
たとえ陶は討ち取ることができても、お屋形が何の用心もせずにおられたのでは、隆房の郎党がお屋形を討ってしまうことになろうと思い、 千度も百度も(幾度となく)刺し違えようと思ったが、致し方なく、怒りを押さえて踏み留まっていた。
しかし、今に謀反を起こし憎い敵となる者を討たずにおくことの無念さに、思わず両眼から涙がはらはらとこぼれたところ、隆房は目ざとい男で、隆豊の心中を察したのか、
「冷泉殿は今何が悲しゅうて落涙なされるぞ」
と、苦々しく詰問した。
隆豊は、
「さよう。 近年山口におられた間さえ、それがしもあなたも寸暇なきゆえ、たびたびの対面もならず、一尺の隔たりも千里のように思われ、不本意にうち過ごしておりました。ましてや 富田へご隠居と承ってござれば、この後は人を介して言葉を交わすこともまれになろうと、 お名残り惜しゅう存じて、覚えず落涙つかまつってござる」
と述べた。
隆房は、
「さてはそれほどまでに、それがしに名残りを惜しんでくだされるか。まことにありがたいお志でござる。しかしながら、「志合えばすなわち胡越も兄弟」と申します。いわんや山口・富田はわずか一日の道程です。たとえ隠居はしましても、折々は参ってお目にかかりましょう。
五郎長房(隆房の子)はここに留めておきまするほどに、万事よろしくお願いします」
と答え、暇乞いを終えて退出した。
こうして陶は富田の若山へ引きこもり、その後、筑前の麻生弥五郎が、当時義隆卿の勘気をこうむって豊後にいたが、彼を使いとして大友義鎮のもとへ遣わし、
「義隆公、 相良のつげ口によってこの隆房を討たんとなされましたによって、つげ口した人の真偽を明らかにせんため、武任の首をはねんといたしました。
これは、 義隆公に対し国政の誤りを正そうがためにしたもので、まったく私の恨みよりするところではござりませぬ。
しかるに義隆公、先のつげ口にとらわれ、とにもかくにも隆房を成敗せんとのおん企てに奔走されておりまするほどに、私も是非なく一矢報いて、自害つかまつる覚悟にござりまする。
この隆房にご哀憐をお垂れくださるならば、ご令弟八郎殿を申し受け、大内家を相続させ申し、隆房が後見となって、忠勤を励みましょうぞ」
と申し送った。
一方、義隆卿の側からも、
「陶が暴逆無道にして、君臣の礼に背き、謀反の心を懐いておりますので、 成敗します。 義鎮殿ご一味くだされるならば、隆房を降してのち、ご令弟五郎殿を養子に申し受け、家督を譲り、義隆は隠居いたします」
と言い送られたのであるが、 義鎮は深い考えでもあったのか、陶の方と一味して、義隆卿からの手紙は一つも残さず、すべて取り出して隆房に送ったのである。
<続く>