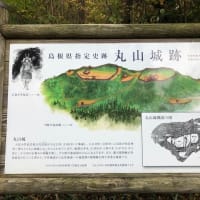26. 元寇
元寇とは、モンゴル帝国(元)の皇帝フビライが行った日本侵攻のことで、文永11年(1274年)と弘安4年(1281年)の二回行われた。
元寇という呼称が最初に使われたのは、歴史書「大日本史」(江戸時代、徳川光圀が編集を開始し、明治時代に完成)」である。
元や高麗の文献では「征東」「日本之役」などと表記しているという。
26.1. 蒙古(モンゴル)
蒙古はアジア大陸内部の草原で羊を追いながら移動していた遊牧民の一種族である。
西暦1206年この蒙古を統一したテムジンは、チンギス・ハンと称し、その不敗の騎兵集団をもって四方へ侵入し、ヨーロッパ、アジアの全大陸を恐怖のどん底へたたきこんだ。
侵入された都市は破壊され、多くの人々が殺戮されたのである。
その版図は第5代フビライ・ハンの時代に最大となり、欧亜にまたがる空前絶後の大帝国が建設された。
<チンギス・ハン肖像図>

西遼を1218年に占領し、1227年西夏を攻撃中にチンギス・ハンは死亡する。
このころ、中国大陸では、北方の女真族の金が強大となっていて、朱は江南に移って南宋とよばれていた。

1231年蒙古軍は朝鮮半島に侵入する。
高麗王朝は開城(現北朝鮮)から江華島(現韓国)にへ都を遷し避難した。
1234年華北に侵入した蒙古は、金を滅ぼす。
日本では、北条泰時が「御成敗式目」を制定 した二年後のことで、執権政治がわりにうまくいっていた時期であり、石見では福屋氏の分家した翌年にあたる。
26.1.1.フビライ・ハン
文応元年(1260年)にフビライが、蒙古帝国の皇帝にフビライが即位した。
<フビライ・ハン肖像図>

<蒙古帝国最大版図>

フビライ日本に関心を持つ
何かを始める時には、多くの場合きっかけというものがある。
フビライが日本に関心を持つようになったのもこの例である。
文永2年・至元2年(1265年)、高麗人である蒙古帝国の官吏・趙彝(ちょうい)等が日本との通交を進言したことが発端である、とされている。
趙彝は「日本は高麗の隣国であり、典章(制度や法律)・政治に賛美するに足るものがあります。また、漢・唐の時代以来、あるいは使いを派遣して中国と通じてきました」 と述べたという。
これを聞いたフビライは早速、招諭使(諸国・諸民族に朝貢を促すために派遣される使者)を派遣することにした。
第一回使節
文永3年(1266年)フビライは正使・黒的、副使・殷弘ら使節団を属国高麗の都へ使者を派遣した。
そして「爾の隣国日本は文化も政治も見るべきものがあるということである。それゆえ黒的らを派遣して通知しようと思うから、この使者を日本へ案内し、 東方を順化せしめよ。」と命じた。
「通知」といっても対等で互恵的なものではなく、朝貢を要求するのであった。
フビライの日本に対する「通知」の要求の目的は、朝鮮半島からチベット、インドシナ半島にわたって形成されていた雄大な包囲陣をさらに強化して南宋を孤立させる政策の一環であったろうと言われている。
使節団は11月に高麗に到着する。
高麗側は蒙古に服属して以来国力は疲弊しており、日本侵攻の軍事費の負担を恐れた。
そこで、使節団を朝鮮半島東南岸の巨済島まで案内すると、対馬を臨み、海の荒れ方を見せて航海が危険であることや、日本人は礼儀知らずなどと言い日本への進出は、利にならずと、蒙古の使節団に訴えた。
蒙古の人々は、陸地では天下無双であるが、航海の経験は殆どない。
広い海原の僅かな波風にも恐れをなして、使節団は日本に向かわず帰国した。
しかし、これを知ったフビライは怒り、高麗が責任を持って日本へ使節を派遣するよう命じ、日本側から要領を得た返答を得てくることを高麗国王元宗に約束させた。
第二回使節
文永4年(1267年)8月フビライは再び、黒的、殷弘らの使節団を派遣する。
しかし、今回は、高麗から先、日本への使者は高麗国の使者に頼むことにした。
そこで、高麗王は潘阜というものに、蒙古と高麗の国書を持たせて、9月23日に出発させた。
しかし、対馬に着いたのは11月で、九州の太宰府に到着したのは翌年の正月だという。
いかにも、日時がかかり過ぎている。
これは、当時の航海が困難であり、途中のどこかで波風が静まるのを待っていたものと思われる。
文永5年(1268年)正月、高麗の潘阜が九州の太宰府に到着した。
太宰府の長官は少弐の武藤資能であった。
国書は鎌倉に届けられ、幕府は国書を外交担当である朝廷に回送した。
蒙古国書への対応を巡る朝廷の評定は連日続けられたという。
何の反応も日本側から無かったため、潘阜は要領を得ぬまま7月に帰国する。
フビライには、使いが失敗だったとの、報告が届く。
<国書>
次の画像は、フビライが「日本国王」にあてた国書の写し(後世、東大寺の僧、宗性が写し取ったもの)である。
フビライが「日本国王」にあてた国書で、文永3年(1266年)第一回目の使節に持たせたもので、至元3年(1266年)8月の日付となっている。
この国書は、文永5年正月第二回目の使節で高麗の潘阜が日本に持参した。

「天の慈しみを受けている大蒙古国の皇帝が、書を日本国王に送る。
朕思うに、昔からたとえ小国であっても国境が接している隣国同士は、貿易や人の行き来など、互いに仲良くすることに努めている。
まして、我が祖宗は天の命によって天下を治めている。
その威を恐れ、徳を慕ってくる遠い異国のものたちは数えられないほどである。
朕が皇帝になってからも、高麗の無辜の民が久しく戦争に疲れていたので、兵を引き揚げ、国土を還し、老人子供を帰らせた。
高麗の君臣は感激して来朝した。
義は君と臣の関係ではあるが、父子のように仲が良い。
日本国王の君臣もすでに知っているであろうが、高麗は朕の東の領土である。
しかし、日本は昔から高麗と仲良くし、また中国とも貿易していたにもかかわらず、未だ一度も使いをもって和好を通ずことがない。
日本が我々のことを知らないとすると、困ったことなので、故に特に使いを送りこの国書を通じて朕の気持ちを伝える。
これからは友好を結び、以って親睦をしたい。
且つ、聖人は四海を以って家とする。
我々は全ての国を一つの家と考えている。
互いに通好しないことにどうして一家としての理があろうか。
兵を用いることは、好まない。
日本国王はこの気持ちを良く良く考えて返事をしてほしい。
不宣(不宣とは「すべてを述べ尽くしていない」という意味の止め句である)
至元三年八月
第三回使節
文永5年・至元5年(1269年)2月、フビライは3回目の使節団を日本へ派遣する。
使者はこれまでと同じで、黒的、殷弘達である。
例によって、高麗到着は11月で、高麗を出発したのは12月に入ってからであった。
翌年3月、一行は対馬に到着する。
高麗史によると、
高麗人の起居舎人・潘阜らの案内で総勢75名の使節団が対馬に上陸した。
使節らは日本側から拒まれたため対馬から先には進めず、日本側と喧嘩になった際に対馬島人の塔二郎と弥二郎という2名を捕らえて、これらと共に帰還した。
フビライはたいへんよろこんでこの二人に首都燕京(後の大都)の宮殿の中を見せた。
第四回使節
文永6年・至元6年(1269年)2月、捕えた対馬島人の塔二郎と弥二郎らを護送する名目で使者として高麗人の金有成・高柔らの使節が大宰府守護所に到来する。
今度の使節はフビライ本人の国書でなく、モンゴル帝国の中央機関・中書省からの国書と高麗国書を携えて到来した。
この中書省牒に対して、朝廷の評定では、蒙古帝国の服属の要求を拒否することに決め、さらに拒否の返書を出すこととした。
早速、文書博士・菅原長成が返書文を起草し、中書省牒に対して返書「太政官牒案」草案を作成した。
しかし、幕府は評定により「返牒遣わさるべからずの旨」を決し、朝廷に返書しないことを上奏した。
朝廷が幕府の提案を受け入れたため、蒙古帝国からの使節は返書を得ないまま帰還した。
第五回使節
文永8年・至元8年(1271年)9月、女真人の趙良弼らが蒙古帝国への服属を命じる国書を携えて5度目の使節として100人余りを引き連れて到来する。
趙良弼は自ら入洛して、直々に国書を朝廷に差し上げたいと、言ったが拒絶される。
日本側が大宰府以東への訪問を拒否したため、趙良弼はやむなく国書の写しを手渡し、11月末の回答期限を過ぎた場合は武力行使も辞さないと伝える。
これに対して朝廷は評定を行うが、結論は出なかった。
一方、大宰府では、ひとまず先に返書の代わりとして、日本の使節がフビライのもとへと派遣されることになった。
趙良弼は、この日本使とともに帰還の途に就いた。
同年11月、フビライは国号を新たに「大元」と定める。
日本使節の大都訪問
趙良弼は、このまま、おめおめと帰ることもできなかったと見えて、対馬から連れてきていた弥四郎等12人(元史には26人と記載)を、日本からの使者と偽って、フビライに合わせようとした、という逸話がある。
元史、高麗史によると
文永9年・至元9年(1272年)、12人の日本使は1月に高麗を経由し、元の首都・大都を訪問する。
元側は日本使の意図を元の軍備の偵察だと判断し、フビライへの謁見は許さなかった。
大都を後にした日本使は、4月に再び高麗を経由して帰国した。
思うに、返書も出さない日本が、ましてや使節などを送るはずがないのは明白である。
第六回使節
文永10年・至元10年(1273年)4月、元使である女真人の趙良弼らは、6度目の使節として日本に到来した。
しかし、趙良弼ら使節団は、返書を得ることなく帰国することになる。
フビライの決断
フビライは、途中で引き返すなど日本に未到着のものも含め合計6回、日本へ使節を派遣したが、服属させるどころか、返書さえも受け取ることができなかった。
さすがのフビライも本気で怒り出した。
「コイツらはなんと愚かな奴らだ。世の中のことがまるで分かっていない。
儂も船を造ってまで攻めていくのが面倒だから、中途半端に優しく出たのが間違いだった。
東の端の小さな島国に、本気になって相手をする気も湧かないが、しかしここは、やはり少し痛い目を与えて、分からすしかないか。
海を渡る船は高麗に造らせよう。
それに、我軍は水上戦は頗る苦手なので、訓練をさせとかんとイカンなぁ」
と、フビライは武力侵攻を決断する。
<続く>