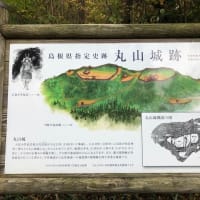26.1.2. 北条時宗
元寇について
この元寇は日本史上、一、二を争う重大な出来事である。
歴史にIFは無いといわれているが、元寇の結果が違っていたら(つまり、元の属国になっていたら)日本の歴史は大きく変わっているはずである。
元と戦い敗れた国はいづれも滅亡している。
元は、歯向かった敵に対して苛烈といえる制裁をしている。
一方最近、時宗が元の使者に返書しなかったことが、元寇の導火線となった、という意見も出てきているが、もし戦わずに属国となっても同じことである。
言葉の通じない者、伝統・習慣の異なる者が支配者になると、どうなるか?
まず、話し合いということは考えられない、支配者は力を以って恐怖心で民衆等を押さえつけるのである。
そうして、反乱の芽を摘んでおき、従わせるのである。
我が国で現在も2000年以上、国の中心として続いている、皇室の万世一系は途絶えていたであろう。
国の中心が無くなると、伝統や礼儀・礼節はその価値を失い、国は混迷し混乱する。
混迷の中で力によって生まれた国家は、だいたい数百年で入れ替わっていく。
人は何故伝統を崇め守るのか?
それは、例えば、1000年、2000年の大樹が神と崇められ大事に守られていることと、どこか似ている。
古ければ、古いほど、人智や日常を超えた、何か踏み込むことが出来ない偉大なものを感じるのである。
その偉大なものは、対面する時に、刹那ではあるが人を日常の煩わしさから開放してくれる。
元寇の結果が変わっていれば、現在生存している日本人の大半、或いは殆どが生まれておらず、別の人と置き換わっていることは、十分想像できる。
当然ながら、日本という国名もその時に無くなっているはずである。
日本の由来
日本という名前は7世紀ごろから使われてきたと考えられている。
607年(推古天皇15年)に第2回目の遣隋使派遣をした。
使節団代表の小野妹子は隋の煬帝に謁見し、聖徳太子からの書を渡す。
それには
「日出ずる処の天子、書を日没する処の天子に致す。恙(つつが)無きや」
と記載されていた。
煬帝はこの書を見て激怒し、「蛮夷からの手紙のくせに無礼だ。二度と奏上させるな」と鴻臚卿(外務大臣に相当)に命じたという、話がある。
この「日出ずる処」が日本の由来となっているという。
中国の歴史書に、初めて日本という名前が出てきたのは「旧唐書」という。
それまで日本は「倭」と記されている。
「日本国者倭国之別種也。以其国在日辺、故以日本為名。
或曰、倭国自悪其名不雅、改為日本。或云、日本舊小国、併倭国之地。
其人入朝者、多自矜大、不以實對、故中国疑焉。
・・・・」
日本国は倭国の別種なり。その国日辺にあるを以て、故に日本を以て名とす。
あるいはいう、倭国自らその名の雅ならざるを悪み、改めて日本となすと。
あるいはいう、日本は旧(もと)小国、倭国の地を併せたりと。
その人、入朝する者、多く自ら矜大、実を以て対(こた)えず。故に中国焉れを疑う。
元寇の結果によっては、国名が「倭」の国に逆戻りしていた可能性もある。
執権北条時宗

この日本史上最大級とも言える、大事件に立ち向かったのが、第8代鎌倉幕府執権若干17歳の北条時宗であった。
もちろん時代は違うが、現代で17歳と言えば、高校生である。
その17歳が、日本の運命を握らされたのである。
時宗は、弘安の役から3年後の弘安7年(1284年)4月4日に32歳で死没した。
かなりドラマチックに言えば、時宗は元寇に立ち向かうために生まれてきたのである。
その時宗の評価は時代を下って明治天皇によってなされた。
北条時宗が死没して720年後の明治37年(1904年)5月17日、北条時宗は従一位を贈られたのである。(それまでの時宗の位階は弘安4年に正五位下に昇叙)
さて、北条時宗は、第5代執権の北条得宗家時頼の三男として建長3年(1251年)5月15日に生まれ正寿丸と名付けられた。
北条時頼は有力御家人であった三浦一族を滅ぼした。
この後、北条氏・得宗家の独裁政治が始まることになる。

兄の二人は正室の子でないことから、嫡子は正寿丸となる。
康元2年(1257年)7歳という年齢でありながら、将軍御所にて征夷大将軍・宗尊親王の加冠により元服し、親王より「宗」の一字を賜り、相模太郎時宗と名乗る。
康元元年(1256年)病気になった時頼は執権の職を、義兄の北条長時に譲る。
これは、嫡子の時宗が5歳という若さであったためである。
この長時は文永元年(1264年)7月3日、病により執権職を辞任して出家する。
次の執権は、長時の叔父の北条政村(北条義時の子)が59歳で7代執権となる。
これも、得宗家嫡男の時宗が成人するまでの繋であった。
この時、時宗は13歳であり、連署となっている。
連署とは、執権の補佐役であり、執権とともに幕府の公文書に署判を加えることから連署といわれた。
元の国書に対する反応
文永5年(1268年)正月に元からの国書が届くと、鎌倉に送られた。
幕府は、直ぐに特使を京都に馳らせて、国書を朝廷に奏上した。
国書が朝廷に届いたのは、2月7日と言われている。
朝廷は驚愕した。
連日にわたって協議がなされるが、結論が出ぬまま日が過ぎ去っていく。
同年3月、執権北条政村(64歳)は、元寇という難局を前に権力の一元化を図るため、執権職を18歳の時宗に譲る。
なお、政村は再び連署として補佐し、侍所別当も務めた。
時宗は前執権の政村や義兄の安達泰盛、北条実時・平頼綱らに補佐され職務を遂行していく。
モンゴルの国書に対する返牒など対外問題を協議し、大田文(土地台帳)の作成、御家人の所領譲渡制限、異国警固体制の強化を行う。
また異国調伏の祈祷などが各地で行われた。
結局、時宗はモンゴルからの度々の国書には一切返事を与えず、また朝廷が作成した返牒案も採用しなかった。
文永7年(1270年)に書かれた返書案には次のように書かれていたとある。
贈蒙古国中書省牒 菅原長成
日本国太政官牒蒙古国中書省附高麗国使人牒送、
牒、得太宰府去年九月二十四日解状、去十七日申時、異国船一隻、来着対馬嶋伊奈浦、依例令存問来由之処、高麗国使人参来也、仍相副彼国并蒙古国牒、言上如件者、就解状案事情、蒙古之号、于今未聞、尺素無脛初来、寸丹非面僅察、原漢唐以降之蹤、観使介往還之道、緬依内外典籍之通義、雖成風俗融化之好礼、外交中絶、驪遷翰転、粤伝郷信、忽請隣睦、当斯節次、不得根究、然而呈上之命、縁底不容、音問縦雲霧万里之西巡、心夐忘胡越一体之前言、抑貴国曽無人物之通、本朝何有好悪之便、不顧由緒、欲用凶器、和風再報、疑冰猶厚、聖人之書、釈氏之教、以済生為素懐、以奪命為黒業、何称帝徳仁義之境、還開民庶殺傷之源乎、
凡自天照皇大神耀天統、至日本今皇帝受日嗣、聖明所覃、莫不属左廟右稷之霊、得一無弐之盟、百王之鎮護孔昭、四夷之脩靖無紊、故以皇土永号神国、非可以智競、非可以力争、難以一二、乞也思量、左大臣宣、奉敕、 彼到着之使、定留于対馬嶋、此丹青之信、宜伝自高麗国者、今以状、牒到准状、故牒、
文永七年正月日
(簡約)
「事情を考えても、我が邦は蒙古という国号等聞いた事も無い、初めて知った事である。
漢唐との外交の前例に従いって、通信を結ぶ事については親睦を深めて良いと思う。
だが、貴国とは一度も通行した事が無いので、我が邦にとっては何の好悪の感情を持ち合わせていないにも関わらず、突然、兵火を使うぞと述べている。春風が再びやって来ても、凍った氷はなお厚い(当方の疑念は大変深い)。
聖人や釈迦の教えでも、生命を尊び命を奪う事を悪としている。
帝徳仁義の境と誇りながら、かえって庶民を殺戮しようという風に向けているのでは無いのか?。
天照皇太神のおわしました古来より今に至るまで、日本皇帝は万世一系にして、国土にあまねく徳が行き渡り、内政が乱れて悪風が侵入する事も無い。だから我が邦は昔から神国と言うのである。
知恵をもって争う事も、武力をもって闘争する事も無用であるから、唯一の事として良く考えよ。
仮にこれが渡っていればフビライは激怒したことは想像に難くない。
これは、推古15年(607年)に、厩戸皇子( 後の聖徳太子)が随の煬帝に送った国書に差し出しにんである自分を「日出ずる国の天子」と述べた事とに通ずるものがある。
時宗の胸の内
時宗の胸の内を想像してみよう。
時宗は考えた。
フビライは国書の返書をイライラしながら待っているであろうなぁ。
しかし、なんと書けばいいのか?
「承知した」と書くことなど出来はしない。
それは、日本が元の属国になることである。
属国になったら、元から為政者がやってくる、或いは元の息のかかったものがこの国を治めることは目に見えている。
奴らは、日本で搾取し、それをフビライに送る。日本は益々疲弊する。
それよりもまず、そんなことをすれば、御家人たちは黙ってはいないだろう。
先祖たちが命を懸けて手に入れた領地を、見も知らない外国人に差し出すことなど、それこそ死にものぐるいで反対し、抵抗するに違いない。
それなら、「馬鹿を言うな」と書いて送り返すか?
そうすると、戦になる。
戦になれば、勝てるか?
元の兵士は、聞くところによると世界中を駆け巡って戦をし、連戦連勝だという。
どれだけ強いのか、想像し難い。
一方日本の武士は、国内の戦しか経験がない。
だが、心意気は誰にも負けない。日本の武士は、名誉のためなら死も恐れぬ。
しかし、フビライはいったい、何人の兵を送り込み、攻めてくるのだろうか?
蘭渓道隆(鎌倉時代中期の南宋から渡来した禅僧、鎌倉建長寺を開山)から、聞くところによると、元は南宋と紛争中であり、兵力はそんなに割けない筈だ。
とすると、寄せくる兵は10万ぐらいであろうか?
だが、まてよ。
奴らは、船に乗って海を渡って来る。
船で10万の兵を運ぶには、船は少なくとも2000〜2500隻は必要だ。
奴らは覇者でも騎馬による陸地の覇者であり、こんなに沢山の船を持っているはずはない。
今から造ると言っても、南宋との関係もあり、優に十年近くは掛かるだろう。
そうすると、いま元を怒らせて戦の準備をさせるのは得策でない。
ここは、「暫く梨の礫」で行くか。
その間、日本国内が挙国一致の体制を整え、また元についてもっと調べ対策を具体的な対策を立てよう。
日本の備え
この蒙古の再三の強要を受けても、返書を出さなかったことから、幕府は元の攻撃を当然予測して対応している。
西国御家人に「異敵」にそなえるよう指令を発した。
そして、挙国一致の体制を整えるため、反乱分子を一掃する(二月騒動)。
また文永9年(1272年)二月、蒙古の使者逍良弼が日本渡航から還った翌月、幕府は異国警固番役を設置した。
これは九州の御家人に大番役(地方の武士に京と鎌倉の警護を命じたもの)の代わりに、 筑前・肥前など九州沿岸の要害で、当番の日数を定めて警固に当たらせるようにしたのである。
しかし、こんな勤番の警護などでは、とてもまとまった軍勢に対処できるものではない。
このようにソフト面での対応は曲がりなりにも行った様子が伺える。
しかし、ハード面での対応をした様子がないのである。
例えば、兵を調練し、実践訓練するとか、城や防御壁などの、防御施設を築き準備した様子がないのである。
元が攻撃してくることは、まだ先のことであると鷹揚に構えていたのか?
或いは、元軍の戦法がどんなものか、まだ調べきれず、具体的な対応がまだできていなかったのか?
これらの理由は分らない。
<続く>