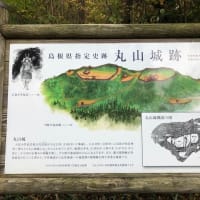34.足利尊氏叛乱
34.9.叡山の陣
34.9.4. 尊氏の誘い(和睦の提案)
叡山も坂本も益々兵糧が乏しくなって兵士たちの不安も増してきた。
孤立した官軍から抜けていく兵も増えてきていた。
このような時、尊氏から密かに後醍醐天皇に密使が来た。
「去々年の冬、近臣の讒に依て勅勘を蒙り候し時、身を法体に替て死を無罪賜らんと存候し処に、義貞・義助等、事を逆鱗に寄て日来の鬱憤を散ぜんと仕候し間、止事を不得して此乱天下に及候。
是全く君に向ひ奉て反逆を企てしに候はず。只義貞が一類を亡して、向後の讒臣をこらさんと存ずる許也。
若天鑒誠を照されば、臣が讒にをち罪を哀み思召て、竜駕を九重の月に被廻鳳暦を万歳の春に被複候へ。
供奉の諸卿、並降参の輩に至で、罪科の軽重を不云、悉本官本領に複し、天下の成敗を公家に任せ進せ候べし。」
と、「且は条々御不審を散ぜん為に、一紙別に進覧候也。」とて、大師勧請の起請文を副て、浄土寺の忠円僧正の方へぞ被進ける。
「一昨年の冬、近臣の讒言によって帝のお怒りを受けました時に、身を僧体にして死を無実のままに賜ろうと存じておりましたところに、義貞、義助等が逆鱗にかこつけて日頃の鬱憤を晴らそうと致しましたので、やむを得ずこの乱が天下に広がってしまいました。
これは全く帝に向かい申し上げて反逆を企てたのではありません。
ただ義貞の一門を滅ぼして今後讒言を行う臣を出さないようにしようと考えただけです。
もし帝が真実をご覧になるならば、私が讒言に遭って陥った罪をお哀れみになってお乗りものを都に回されて、御治世を末永い春の栄えにお返しください。
お供の公卿や降参した者たちに至るまで、罪の軽重を問わず、すべてもとの官位、もとの所領に復し、天下の執政を公家にお任せ申し上げます。」といって、
「さらに、一々の疑念をお晴らしするために、一枚の別紙をお目に掛けます」と言って、伝教大師に誓う起請文を添えて、浄土寺の忠円僧正の方に差し出された。
使者の忠円僧正は後醍醐天皇と関係があった僧である。
この僧は、以前にも書いたが、後醍醐天皇の統幕計画が露見した時に捉えられて鎌倉に送られた三人の僧のひとりである。
拷問されようとした忠円は、生まれつき臆病な人だったのか、まだ責めないうちに、帝が叡山と相談したことや、大塔宮の行い、俊基の陰謀など、あることないことすっかり白状して一巻に書いた。
そして越後国に流罪となっている。
後醍醐天皇は、近臣に相談することなく、これを受け入れた。
また、忠円僧正を介して、還幸は10月9日、下山の龍駕には、尊氏方から迎えの軍勢が途中まで出ていること。
等々の手筈まで、一切、諜しめし合せもつけていたという。
後醍醐天皇が、尊氏の、しかもいわくつきの忠円僧正が密使であるこの提案をすんなり受け入れたのは、やはり相当な窮状であったことが伺われる。
また、後醍醐天皇はこのことを、新田義貞には秘密にしておいた。
恐らく新田義貞に言うと猛反対されると思い、こっそり京に戻ろうとしたのかもしれない。
新田貞満
新田義貞は、この和睦を言伝に聞いた。
最初、義貞はこの話を全く信じなかった。
不安を感じた、新田一族である堀田貞満は様子を見てくる、と言って山を上っていった。
貞満が叡山の根本中堂についたとき、まさに後醍醐天皇は出発する寸前であった。
貞満は輿の前まで行き、轅を握りしめ、涙を流しながら叫んだ。
「陛下が帰還されるとの噂を聞きましたが、義貞が『知らぬ』と言っていたので、間違いであると思っていたが、本当だった。
一体何故、義貞を見捨てるのですか?
多年に及ぶ義貞の粉骨砕身の陛下への忠節、陛下はお忘れですか?
元弘の乱や、尊氏の叛乱に対して我が一族は、死線をかいくぐって奮戦した。
義を重んじて命を落とす一族は百三十二人、忠節を尽くすために死んだ郎党は八千余人です。
今回の今洛中での戦いでは、官軍がたびたび不利になっていることは、戦い方の罪ではなく、ただ帝の威徳に欠けるところがあると思えます。
だから、味方になってくれる軍勢が少ないのではないでしょうか。
結局、当家の累年に及ぶ忠義を捨てられて、京都へ御臨幸なさろうということであるのならば、ぜひに当家の一族五十余人を御前にお呼び出しになって、首を刎ねて伍子胥の罪に問われ、胸を裂いて比干の刑に処してください」
伍子胥
中国春秋時代(紀元前770年から紀元前403年)の呉国の政治家・軍人
呉のためにつくすが、晩年は呉王夫差に疎まれ、最後は夫差から自害するようにと授けられた剣で、自ら首をはねて死んだ。
比干
中国殷代(紀元前17世紀頃から 紀元前1046年)の王族
比干は、紂王の悪逆無道を止めようと諫言したが、かえって紂王の怒りを買ってしまう。
そして、紂王は「立派な人物の心臓には七つの穴がある」という伝説を確認するため、部下に命じて比干の胸を切り裂き、心臓を取り出させた、と言われている。
後醍醐天皇は黙っていたが、後悔している様子であった。
後醍醐天皇と新田義貞
しばらくして義貞は兵三千余騎を連れて後醍醐天皇に会いに来た。
義貞は怒りを抑えている様子であるが、礼儀を乱さず、階下の庭先に袖を並べて並び坐る。
後醍醐天皇は、義貞に申し訳無さそうに胸の内を話す。
「朕は新田一族の力を頼りに天下を治めようとしたが、まだ天運が訪れず、兵は疲れ衰えてしまった。
そこで、尊氏に一時和睦のことを話してしばらくの時を待とうと、還幸の事を言い出したのだ。
この事をあらかじめそなたに内々知らせたくはあったが、ことが広まってしまうとかえって難しいことにもなるだろうと
思われたので、時期を見て言おうと置いていたのを、貞満が恨み言を言うので、私の誤りに気がついた。
義貞、汝はこれから北陸に向かえ。
越前国へは川島維頼を先立って下しているので、その先は支障あるまいと思われる。
気比の社の神官などが敦賀の港に城を造って味方すると聞いているので、まずそこへ下ってしばらく兵の気力を養い、北国を討ち従えて再び大軍を起こして天下の守護役となって欲しい。
ただ、朕が京都へ出たならば、義貞が逆に朝敵と呼ばれると困るので、春宮(恒良親王)にこれから天子の位を譲るので、春宮と一緒に北国へ下ってくれ。
天下のことは何事も義貞の差配すべきものとして、私に変わらずこの君を取り立て申し上げて欲しい。
私はすでにそなたのために勾践の恥を甘受することにする。そなたは早く私のために范蠡の謀を巡らして欲しい」
范蠡と勾践
范蠡(はんかい)は越王勾践(こうせん)に仕え、勾践が天下に号令する「覇者」となるまで、20年余りも労苦をともにした重臣である。
勾践は「臥薪嘗胆」の故事成語で知られる呉越の抗争で最後の勝利者となり、賢君と呼ばれている。
と涙を抑えて話した。
あれほど怒っていた貞満も、道理に分からぬ東国の武将たちも、頭を下げて涙を流し、皆鎧の袖を濡らしたのだった。
10月9日は、忙しい新帝即位のこと、還幸の準備に一日があわただしく暮れていった。
34.9.5. 新田義貞日吉大権現に祈願
夜が更ける頃になって、新田左中将はひそかに日吉の大宮大権現に参拝して祈願し、家累代の重宝で鬼切りという太刀を社殿に奉納した。
臣苟も和光の御願を憑で日を送り、逆縁を結事日已に久し。
願は征路万里の末迄も擁護の御眸を廻らされて、再大軍を起し朝敵を亡す力を加へ給へ。
我縦不幸にして命の中に此望を不達と云共、祈念冥慮に不違ば、子孫の中に必大軍を起者有て、父祖の尸を清めん事を請ふ。此二の内一も達する事を得ば、末葉永く当社の檀度と成て霊神の威光を耀し奉るべし。
「私は、仮にも神仏のご加護を頼りに日を送り、神仏と逆の行いをしながら長く過ごしてきました。
願わくは、遠く出陣します果てまでも守護の御目をかけていただき、再び大軍を起こして朝敵を滅ぼす力をお与えください。
私がたとえ不幸にして寿命の内にこの願いを達しなくても、願いが神仏の心に沿っておれば、子孫の中に必ず大軍を起こす者が出て、先祖の屍を浄めてくれるよう願い上げます。
この二つの内の一つでも叶えることができれば子々孫々永く当社の信徒となって、権現の威光を輝かしもうしあげます」
日吉大社にこの事を記した石碑が建っている。
<表面>

<裏面>

<日吉大社 東本宮>

<続く>