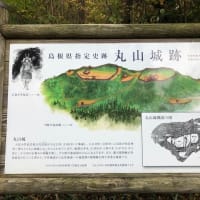39.観応の擾乱
39.6.尊氏の帰京と離京
とにかく、足利直義は南朝に降伏して、高師直・高師泰兄弟に対抗する勢力を築こうとした。
その直義は一旦、大和国越智(高市郡高取町)に構えた。
この直義の下に、大和、河内、和泉、紀伊の南朝方が集まってきた。
さらに、北朝方の畠山阿波将監国清もその手勢千余騎を連れて馳せ参じた。
39.6.1.尊氏京に引き返す
この噂は、当然京にも届く。
京都の警固担当だった足利義詮は早馬を立てて、備前の福岡にいる尊氏へ、急を知らせた。
報告を受けた尊氏は、特別驚いた様子はみせなかった。
「ほほぉ、直義はそうきたか!」と呟いた。
「南朝に逃げ込んだか」と少し安堵の表情をみせた。
尊氏は、直義の状態を心配していたのだ。
もちろん、周囲には心の内を漏らしてはいなかった。
『無事だったのか』と安心すると同時に『京に攻め込むとは、また面倒なことをやってくれるなぁ』と不愉快そうな顔つきになった。
周りの者はそれをみて、将軍は怒っている、と思った。
尊氏は、こうなった以上九州に向かうわけにはいくまい、と思った。
もし、京が南朝軍に占領されると、次にその軍勢は尊氏を襲ってくることが目に見えている。
そうなると、尊氏の軍は西から直冬軍、東から南朝軍に挟み撃ちにされる可能性があるからである。
尊氏はすぐさま京へ引き返し、南朝軍と対戦することとした。
そして、石見攻めをしている、高師泰を呼び戻すことにした。
だが、高師泰軍を待っている時間の余裕はなく、尊氏、高師直軍は先に京へ向かった。
39.6.2.直義京を攻める
観応2年/正平6年(1351年)京に向かった直義は、正月7日岩清水八幡宮(京都府八幡市、旧称男山八幡宮)に本陣を構えた。
一方、京を守備する足利義詮は東寺を本陣として対した。
そのうちに、直義の呼びかけに応じて正月8日に越中を発った越中守護桃井右馬権頭直常の軍勢が比叡山東坂本に着いた。
これを見た足利義詮は自軍の不利を悟り、西国から上洛してくる尊氏軍と合流するために、正月15日の早朝に京を脱出した。
義詮が脱出したその日の午後には、桃井軍が京に入った。
京を脱出した義詮は桂川を渡り、向日神社(京都府向日市向日町)を通り過ぎようとしたときに、上洛中の尊氏と師直軍に出会う。
義詮軍は尊氏等と早速引き返した。

戦は、四条河原を舞台に始まった。
情勢は互角で始まったが、桃井の背後を南から佐々木、北から尊氏らが突くという作戦が功を奏して、俄然足利の有利になってきた。
しかし、八幡の直義軍が何故か現れず、ついに桃井は粟田口から山科へ退いていった。
39.6.3.尊氏、京から逃亡する
桃井が戦闘に敗れ尊氏軍が有利な展開になると思われたが、状況は違った方向に進んだ。
尊氏軍の大半が寝返って、岩清水八幡に陣する直義の陣に加わったからである。
尊氏は、「これは一体どうしたことか」と困惑する。
残念ながら、何故こういう状況になったのかを、「太平記」は記していない。
尊氏は、「これでは洛中で再び戦いをするのは難しい。
しばらくは西国の方へ引き退いて、中国地方で軍勢を起こし、東国の者たちと連絡をして、引き返し敵を攻めよう」と思い、正月16日早朝に丹波路を西に下った。
尊氏は丹波国井原(兵庫県丹波市)まで来ると、義詮を石龕寺(岩屋寺とも)に留めてここを拠点にして防衛するように命じた。
この寺の衆徒は元来尊氏に対し非常な誠心を持っていたので、軍勢の兵糧、馬の藁や糠に至るまで山のように供出した。


義詮をここに留めて、尊氏らは南下して、書写山坂本(兵庫県姫路市)を目指した。
39.7.光明寺合戦
京都を脱した尊氏らは、石龕寺(兵庫県丹波市)に義詮を留めて、ここを防衛拠点の一つとした。
義詮を残して尊氏らは南下して、書写山坂本(兵庫県姫路市)に陣した。


観応2年/正平6年(1351年)2月になると石見から引き返した高師泰軍が合流する。
一方、直義軍は岩清水八幡から石塔右馬権頭を大将にして、愛曾伊勢守、矢野遠江守以下五千余騎で書写山坂本へ押し寄せようと下った。
しかし、書写山坂本へは越後守(高師泰)が大勢で着いたということを聞いて、播磨の光明寺に陣を取り、岩清水八幡の直義に加勢を求めた。
これを聞いた尊氏軍は、相手が勢いづく前に攻撃しようとして、2月3日書写山坂本を発って、光明寺(兵庫県加東市)を取り囲んだ。
翌4日から鏑矢を射合って戦闘が始まった。
攻め手の尊氏軍は、大軍であることの安心感があるせいか、戦闘意識は高くなかった。
徒に攻めるのではなく、相手が戦意を失うのを待っていた。
そのため、尊氏軍は攻めても攻めても毎日毎日、ただただ敗退を繰り返していくばかりであった。
このように毎日の戦は、攻め手城内側が健闘を続けていた。
そこに、尊氏側の赤松律師則祐が700余騎を率いて、到着した。
赤松は遠く城の様子を見て、「敵は無勢なのだから、一攻め攻めて見よ」と命じた。
赤松の配下の武将らは、極めて険阻な泣尾の尾根をよじ登り、防衛側の垣盾の際までたどりついた。
この時に他のいろいろな道からも寄せ手が同時に攻め上ったならば、城を一息に攻め落とせただろうが、数万の寄せ手は何もしないで見物していた。
このため、城に接近していった者たちは、味方の援護を受けらず、頭上からの矢の猛攻を受け、垣盾の下にうずくまるばかりで一歩も先に進めず、結局、山下の陣へ引き返してくるしかなかった。
<光明寺>

「太平記」によると、そんな時に一つの「怪異」と一つの夢のお告げが重なって、その大軍の楽観をあっさり打ち砕いてしまった。
一つの「怪異」とは
直義軍の伊勢の愛曾が使っていた子供が一人、急に気が変になって、十mほども飛び上がり跳ねて、
「私に伊勢大明神が乗りうつられて、この城を守るために、三本杉の上にお座りになっている。
寄せ手がたとえどんな大軍でも、私がここにいる間は、城を落とされることはないだろう。
悪行が身を責めて師直、師泰らは、あと七日の間に身を滅ぼすであろうことを知らないか。
何と熱いことだ、我慢ならぬ。はやく三熱の炎を冷まそう」
と言って、井戸の中へ跳び込んだところ、本当に井戸の水が沸き返って沸かした湯のようだった。
城中の人々はこのことを伝え聞いて、深く信じて頭を下げない者がいなかった。
寄せ手の赤松律師則祐も、このことを伝え聞いており、気にかけていた。
「一つの夢のお告げ」とは
赤松則祐の息子の肥前権守朝範が夢をみた。
その夢は、寄せ手一万余騎が同時に立てかけた楯の脇に攻め寄せて火を懸けたところ、八幡山と金峯山の方角から山鳩が数千羽飛んで来て翼を水に浸して、櫓や立て並べた楯に燃えつく火を消した、
という夢である。

朝範はすぐにこの夢を則祐に話す。
赤松則祐は、嫌な予感がし、『面倒なことになる前に引き上げたい』と思うようになった。
そういうところに、美作から敵が立ち上がって赤松へ寄せてくる、と云う知らせがきた。
則祐は、これぞ幸いと光明寺の陣を捨てて白旗城(兵庫県赤穂郡上郡町)へ帰っていったのだった。

光明寺に立て籠もる直義方軍の援軍として、新たに石清水八幡からの援軍が出発する。
この情報を得た尊氏軍は迎え討つため、光明寺から湊川に向かった。
<続く>