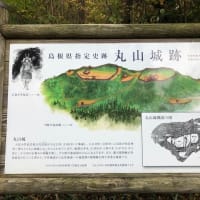39.観応の擾乱
39.8.打出浜の戦い
打出(うちで)は、兵庫県芦屋市東部、宮川流域、六甲山地南麓から大阪湾へかけての段丘・沖積地にあたる地域である。
足利尊氏は、ここ打出浜で2回合戦をしている。
1回目は建武3年(1336年)2月10日である。
鎌倉から上洛した尊氏は、京の合戦で破れ、丹波国篠村(京都府亀岡市)に逃れ、摂津国兵庫島(兵庫県神戸市兵庫区)に移った。
2月10日、後醍醐天皇の命を受け追撃してきた楠木正成と、ここ打出浜で合戦となり、尊氏は破れ、兵庫から船で九州へ落ち延びた。
この戦いの石碑、「大楠公戦跡」碑が兵庫県芦屋市楠町に建っている。

2回目が観応2年/正平6年(1351年)2月17日、つまり今回の戦いである。
打出浜の戦いは、「太平記」では小清水合戦(巻第二十九、小清水合戦事付瑞夢事)と記されている。
摂津国の守護赤松信濃守範資は、尊氏に使者を送った。
「八幡(岩清水)から石塔中務大輔と畠山阿波守国清、上杉蔵人大夫を大将として、七千余騎を光明寺方の敵の後ろを攻めるためということで差し下されたそうです。
このまま光明寺方の城を攻めていても、その守りは固く、もしこの状態で我が軍の後ろに新しい大軍の敵が攻めかかってきたならば、大変な事になる。
されば、今はこの城を措いて、新たに来る討手を神尾(神呪寺)、十林寺(鷲林寺)、小清水(越水)の辺りで待ち合戦すれば、敵の敗北は疑いないところです。(神呪寺、鷲林寺、越水いずれも兵庫県西宮市)
味方が一戦に勝ちましたら、敵はあちこちで戦をするとしても、いつまでも堪えられることはできないでしょう。
これこそが一挙に戦いを決して、あらゆる戦いに勝つ謀です」
と、次々に急使を発たせて、一日に三度も尊氏に申した。
尊氏も師直、師泰に至るまで、
「まことに、伝えられているとおりならば、敵は小勢であり、味方はこれの十倍である。
険しい山の城を攻めれば叶わないが、平場に出て向き合って勝負を決するならば、味方が必ず勝つだろう。
それならばこの城を措いて、まず向こうにいる敵に懸かろう」
ということで、2月13日、尊氏、高執事兄弟も、光明寺の麓を発って兵庫の湊川へ急ぎ向かったのである。

戦いは、2月17日に始まった。
戦いの結果は、尊氏軍の惨敗であった。
数の上では絶対的に優位にあった尊氏軍が破れたのは、戦意の差であったと、云われている。
恐らく、尊氏軍の個々の兵は数を頼みにして、緊張感がなかったものと思われる。
このような状態では、一旦何処かで劣勢になれば、簡単に兵は退いてしまう。
それが雪崩を打ったように広がってしまい、惨敗となったのであろう。
2万いた尊氏軍勢は脱走者も多く、最後は1000足らずまで減っていた。
39.9.尊氏と直義の和睦
尊氏は直義との和睦を考えた。
39.9.1.和睦
「太平記」では、敗北した尊氏らの軍の状況を次のように記している。
小清水の戦いに惨敗した尊氏軍二万余騎が、四方が四百mあまりほどもない松岡城(位置は不明)へ我も我もと入り込んだ。
しかし、中は少しも身動きならないようなありさまとなったので、主だった者以外は中へ入ってはいけないと、郎等や若党は皆外へ出して四方の城門を閉じた。
もともと戦う気の薄かった者たちは、これにことよせて連れだって逃げて行った。
あるものは漁師に紛れて破れた蓑を身に纏い、福良の渡しや淡路の瀬戸を舟で逃げる人もいる。
あるいは草刈り男に身をやつして竹の籠を肩に掛けて須磨の上野、生田の奥へ裸足で逃げる人もいる。
運が傾いたときの習いだが、臆病神の憑いた人ほど見苦しいものはない。
夜がすでに深いので、あれほど立て込んでいた城中は静まりかえって、全く人がいるとも見えなかった。
多くのものが逃げ、残っている軍勢は500騎に過ぎないと分かると、尊氏は「それでは、世の中は今夜限りであるようだ。
それぞれにその支度をするがいい」と言って、鎧を脱いで押しのけ、小手、脛当てなどだけになった。
これを見て高武蔵守師直ら主だった家来23人は十二間の客殿に二列に座を並べて諸々の神仏に焼香し、鎧、直垂の上を脱いで脱ぎ捨て、袴だけになって小さな袈裟を掛けて、尊氏が自害したらお供をしようと、腰の刀に手を掛けて静まりかえっていた。
その時、昨夜逃げたと思っていた饗庭命鶴丸(饗庭 氏直)のが現れた。
饗庭命鶴丸は
昨夜味方の軍勢の様子を見て、これでは戦っても勝てない、逃げても生き延びられることはできまいと思った。
そこで、鶴丸は敵将の畠山阿波将監のところに向かい、和睦のことを話したという。
すると、畠山も
『直義殿もただ一心にそのことばかりを仰っています。
執事兄弟(高師直・師泰)の不心得もただ一応思い知らせるだけのことですから、しつこく討伐なさるほどのこともないでしょう。
親以上に親しみがあるのは気の合う兄弟の仲である。
子供にも劣らず慕わしいのは長年の主従の縁である。
獣にもそういう気持ちがある。
まして人の道ではなおさらだ。
かりに合戦に及んでも、情け容赦ないことはするなと、八幡から戴きました手紙が数通あります』
と言って、取り出して鶴丸に見せたという。
鶴丸の話を聞いて、尊氏も執事兄弟も、それなら問題はないだろうと、その夜の自害は止めたのだった。
しかし、この話は創作ではないかと思われる。
いくら鶴丸が尊氏の寵臣だったにしろ、自らの判断で敵将の畠山に和睦の相談に行くことは考えられない。
また、尊氏が自決を覚悟したと云われているが、尊氏がそのようなメンタリティになるとは到底思えない。
一瞬そういうことが、尊氏の頭の中に浮かんだかもしれないが、すぐさま打ち消したであろう。
尊氏は、土壇場になっても活機が働くのである。
実際は尊氏が直義に和睦を提案したようである。
尊氏は直義との和睦を考えた。
尊氏は、自分は直義に対して恨まれることは何もしていないと思っていた。
直義もそう思っているに違いないと考えている。
かつて、直義の屋敷が高師直によって取り囲まれたときに、尊氏は、自分の屋敷に呼び入れ窮地を救い、師直と交渉したのは尊氏だった。
直義が兵を挙げたのは、尊氏への敵対でなく、高師直・師泰兄弟に対する恨みである、と思っている。
そこで、尊氏は和睦の命を鶴丸に授け、鶴丸は直義のいる岩清水八幡に馬を飛ばした。
また、この頃夢窓疎石が双方の調停に動き出していたようであり、尊氏と直義との和睦はすんなり決まった。
39.9.2.和睦の条件
饗庭は翌日に帰って来た。
直義は、和睦してもよいと言った、という。
当然、これには条件が提示されていた。
それは、師直、師泰の引渡しだった。
しかし、尊氏にはこれが呑めなかった。
引き渡すということは、殺されることを意味している、からである。
従って、その調整の使者の往来は三度、四度にもおよんだ。
結局、高師直、師泰は高野山へのぼらせて生涯を出家遁世に終らせることになった。
尊氏はこれなら、二人に告げて観念させることができると思ったのである。
直義もこれを容れ、
「さっそく、御自身、両名を伴ともなって、連れ上っていただきたい」と伝えた。
尊氏は、師直に直義との再三の交渉のすえに、辿り着いた和解の条件を話した。
師直は、首をうなだれ神妙にそれを聞き、尊氏の温情に泣いた。
師直は、弟の師泰を切になだめた。
ここは辱も我慢も忍ばねばなるまい、死一等を減じられただけでも僥倖とせねばならぬ、と。
師泰も諦めた。
二人は、すぐ連れだって近くの真光寺へ入り、髪をおろし、法衣に着がえた。
しかし、高一族の薬師寺公義が、それを聞きつけてやって来た。
薬師寺公義は二人をしきりに諫めた。
「約束したといっても、先へ行けば結局、敵手にお身をまかせるしかない。
はたして直義殿が心から憎しみを解いているかどうか、わからない。
さらには越後の流刑先で横死した畠山直宗や上杉重能の家来どももいることです。
彼らが怨みをすてるとは思われません。
(一年前の観応元年/正平4年(1350年)8月13日、師直が直義を攻めた。
その結末は、直義は出家し、畠山直宗と上杉重能は越後の流刑され、当地で死罪となった。
畠山直宗や上杉重能の家臣はその怨みがある。)
むしろここには、まだ千余のお味方は残っているので、花々しく一戦をとげ、武士は武士らしく、御運命を決すべきではないでしょうか。
そして大御所(尊氏)は、そのあいだにお姿を変えて、中国の赤松をたよってお落ちになるがよいかと存じまする」
だが、師直は容れず、師泰もまた、一笑に附して言った。
「公義、名よりは実だよ、当世ではな。
向うに二重の腹があるなら、こっちも三重腹になって、幾変化でもして見せるわさ。
生き抜いた方が最後の勝ちというものだ」
これを聞いた公義は、何もいわず、悄然と退がって行った。
だが、薬師寺公義の危惧は現実となる。
<続く>