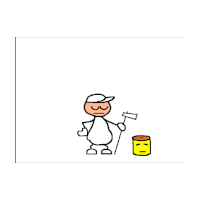レンガ敷き工事
庭先を芝生で一面に埋め尽くすぞ!! と意気込んでみましたが、技術、忍耐、植物愛に乏しい私には無理なことが解りました。
もともと、レンガの素焼きの質感に惹かれていたこともあり、芝生とレンガをミックスさせることに挑戦?しました。
庭先一杯にレンガを敷き詰め、その隙間(目地)を緑に…を狙いに。
レンガ工事は初めてなので、かなり自己流でしたが曲がりなりにも敷き終わりました。
後は目地の芝生が根付いてくれたら、すべて完了ということになりますが、節目を迎えたので掲載しました。
 |
 |
【 仕 様 】
| レンガ敷き込み面積 | 110㎡(約33坪) |
| 使用レンガ | ベルギーレンガ(赤、黄色) |
| レンガ寸法 | 110×110×H58mm |
| 使用レンガ数 | 黄 5,420枚、赤 1,380枚 合計6,800枚 |
| 目地幅 | 約6mm |
| 砕石層の厚さ | 約5cm |
| 砂層の厚さ | 約3cm |
| 目地 | 砂のみ充填 → いずれ芝生かコケに |
| 作業員 | ひとり漫才 |
| 車やバイクの乗り入れをしない歩行専用とする | |
【 レンガ敷きに使用した道具類 】
(ちょっと特殊な道具)
片手ハンマー、平タガネ、カナヅチ、ホウキ、剣スコップ、一輪車、水平器、水糸、一寸釘、
胴縁、木杭(長さ約20cm)、カケヤ、セメント、手袋、マスク、耳栓、プレート(転圧機)
【 事前工事 】
写真の上でクリックすると拡大します。
 |
玄関のアプローチに敷いていた枕木を剥ぎ取って、場外へ搬出します。1本50㎏くらいあるので、すべてフォークリフトで。 '05年9月6日作業開始です。 右へ続く。 |
 |
剥ぎ取り完了。 左下へ続く。 |
 |
左側の一段下がった砂利の道路は農道です。一列に枕木を並べて土留めとしていましたが、経年変化で乱れてしまったので、すべてやり直しです。 |  |
公道の路面とタイル面に段差ができるので、コンクリートを打ってスロープにしました。 |
 |
コンバインを改造したフォークリフトも活躍。 |  |
農道側に新たに枕木を敷設するため、コンクリートブロックを並べて基礎にします。 |
 |
枕木が農道側に倒れないように、専用に作ったアンカーを入れてコンクリートを打ちます。 |  |
コンクリートミキサーで打設。 |
 |
普通は、地中に埋めるアンカーにメッキをしないのですが、土に直接触れる部分も多いので、メッキを施しました。その前に枕木が腐ってしまうかな? 枕木を1/2"のコーチボルトで固定します。 |
 |
完成を想定したレンガの上面から、砂+砕石の厚みを考慮して整地します。 次に約1.5m間隔に、20cm程度の木杭を打ち込み、砕石上面の線を書きます。 歩行だけなので、砕石層は約5cmの厚さにしました。敷き込んだ後はプレートでしっかりと転圧します。 |
 |
現場の事前工事と平行して、レンガを搬入しました。4トンのロングトラックで運びます。レンガ1個が1.4㎏もあるので、なかなか大変です。 |  |
これですべて搬入完了です。置き場所と工事現場が離れていたので、運搬に苦労しました。 すべて木製のパレットに載せて納品です。 |
| 【レンガ敷き工事】 |
 |
プレートで転圧をした後は、いよいよ砂を敷き詰めます。砂を平らにしないと、レンガの表面が凸凹になるので注意が必要です。 私は鉄アングルを使って平らにしました。 その工程は、 モルタルでアングルの枕を作る→アングルを伏せる→砂を締める→砂をアングル上面にこすって削り取る となります。 (枕を作る) 枕の間隔は1.5m以内とし、砕石層にこぶし大の小穴を開けます。そこに固めのモルタルを盛り付けます。 次にモルタル上面のレベルを出します。 計画したレンガ上面からレンガの厚さ(58)と砂の厚さ(30)を差し引いた高さ(88)が、アングルを置く枕のレベルになります。レンガに水勾配を付ける場所は、アングルも傾斜を付けることになります。 (アングルを伏せる) アングルを伏せた上体で敷いた後に、アングルが枕から落ちないように、両サイドから砂で数箇所抑えます。 (砂を締める) 2本のアングルの間に砂を入れて、足でしっかりと踏み固めます。水はけの良い地盤の場合は、水締めする方が効果的かも知れません。 (削り取る) 1m以上の長い板を、両方のアングルに乗せて引っ張り、上面の砂を削り取ります。 |
 |
レンガを並べ終わったら、アングルを除去します。 良く見ないと判りませんが、レンガの中央に1本の水糸が写っています。 レンガの両脇に置いてある細長い2本の棒は、レンガ目地を書き込んだ棒ゲージです。 これらを頼りにレンガを並べてみましたが、なかなか縦横とも真っ直ぐに並んでくれませんでした。そこで…。 |
 |
そこで写真のように、水糸を網の目のように張り巡らせました。 遠くの壁に見えるように、目地の間隔で胴縁に釘を打って、それを壁などに固定しました。 しかし、長いスパンで水糸を張れる広い場所では有効ですが、張り替えが大変でした。 |
 |
水糸が正しく張れたら、あとはポンポンと並べて行くだけです。 ある程度レンガを置いたら、ちょっと離れて曲がりや凹凸がないことを確認し、良ければ砂を撒きます。そしてホウキ等で目地に砂を入れます。 これにより、レンガの動きが止まるので、普通に歩行できるようになります。 作業終了時には、サッと水を撒いて目地の砂をしっかり落ち着かせます。 ただし、目地砂が多すぎると、雨が降る都度砂がレンガ上面に広がってしまいます。 砂の量は、レンガ上面から1㎝くらい下げたほうが良いようです。足りなければ後で補充すれば良いわけですから。 モルタル目地にする方法もありますが、脱着が容易な砂にしました。 通路部分には赤レンガを、その他の部分は黄レンガを敷いてみました。 |
 |
左側には水糸を引っ掛ける胴縁等が見えます。玄関に向けて、緩い昇り勾配にしました。 |  |
以前から計画していたキンモクセイを、あわてて植えました。 |
 |
樹木根周りのレンガ敷きは最後の仕事です。 |  |
一日の作業が終わって、どのくらい進んだか振り返って見るのが楽しみです。 |
 |
枕木の除去工事から始めて2ヶ月、道路側からの眺めです。 |  |
建物に近づくにつれて、農道側へ緩い傾斜を付けてやる必要があります。水糸も思うように張れず、難航しました。 |
 |
そんな時に活躍してくれたのが、自作の木枠ゲージです。 |  |
11月も終わりに近づき、寒くなったため、翌春まで作業は中断です。 手前から2本目の枕木に「welcome」の掘り文字が見えます。 |
 |
5月になってようやく気分を一新して作業を再開。 すぐにカンを取り戻して数日後に殆ど敷き終わりました。 しかし、枕木や建物に接する部分に、レンガを切って入れる必要があります。 |
 |
手前の樹木(姫シャラ)も追加して、根元に姫高麗芝を貼り付けました。 枕木沿いにベゴニアを植えました。 |
 |
最後に小さなフェンスを、枕木の上に取り付け('06年6月23日)をして完成しました。その全景です。 右側が門で、ちょっと貧弱ですが、わが家のレベルから見れば、こんなもんでしょう。 (フェンスの仕様) 異形鉄筋D-25を、逆Uの字に曲げた後に帯鉄を溶接。亜鉛ドブ漬けメッキをした後に、油性ペンキで塗装。合計25個を枕木に木ネジで固定しました。 |
 |
境界枕木の油気がなくなってグレーになったうえ、表面が荒れてしまったので、オイルスティン(ウォールナット)を、スプレーガンで黒くしました。 作業時間と塗りやすさを考慮して、ハケ塗りを避けて大正解でした。 奥の方から撮影を。 |
 |
前庭を屋根の上から撮影。 黄色のゾーンに、赤レンガを数個散らばすと、もっとレンガに表情が出ると思いますが、いずれ近いうちに。 |
 |
裏側の庭を屋根の上から撮影。 |
【 付 録 】
 |
樹木の根周り部分は、レンガを丸くカットしました。 花壇のように、円周を2、3段積み上げることも考えましたが、全体に傾斜があるため、省略してしまいました。 樹木を支えている竹の棒は、完全に根が張ったらすかさず撤去する予定ですが、 風が強い場所なので、しばらくはこのままで。 |
 |
レンガを円周状にカットします。 根周りの直径を考慮して、レンガの目地に合わせて並べます。 ひもコンパスとチョークで円を書きます。 半端になったレンガは、ここでフルに使います。 |
 |
散水栓周りの収まりです。 |  |
弁ボックス周りの収まりです。小さな円形のため、コンクリートで仕上げました。 |
 |
ディスクグラインダーを、作業台に取り付けた自称レンガカッター(自作)です。 左の青い送風機は、あまり効果がなかったので取り外し、右の工場扇に変更しました。 |
 |
後ろに工場扇を置いて、埃を吹き飛ばします。 |
 |
カッター目を入れれば、レンガ割りは終わったも同然。 四面にちゃんとミゾを付けないで叩くと、思わぬところで割れてしまいます。 |
 |
レンガ用のヤットコ(自作)は、写真のようにして使います。100円ショップで買ったラジオペンチの先端を改造しました。 一旦敷いたレンガを1個だけ引き抜くときに便利です。 1、2回雨が降ると、レンガは完全に落ち着くので、周囲より低くなっているレンガを見つけたら平らに修正します。 (方法) レンガ1個を全部引き抜かず、ヤットコで掴んで低くなっている角方向を2、3回上下させて目地の砂を下に落とします。これでレンガが平らになります。ただし、大きく陥没している場合は、一旦引き抜いて砂を充填します。最後は目地に砂を補充します。 |
 |
写真のように、ベルギーレンガは角がボロボロに丸まっています。一見柔らかそうですが、場所によっては堅い部分もあり、裏表の色合いも異なって味わいがあります。 極寒時には、レンガに含まれた水分が凍結して、貝殻状に欠けることあります。 欠けが気になる場合は、レンガをひっくり返して使います。 |
 |
樹木を常時ライトアップ。 ソーラーパネルによる自家発電で蓄えた電気で照らします。 光源には車用の作業灯を転用し、ランプはレンガの中に埋めます。 カバーは素焼きの植木鉢を斜めにカットして被せました。 |
 |
洋芝の種を、6mm幅しかない目地に蒔いてみました。 手順は ①目地砂を深さ1cm以上を水道水のシャワーで流し飛ばします。 ②目土を入れて、散水してから種を蒔きます。 ③種が隠れる程度に目土を撒きます。 ④水道水を霧状にして種が飛ばないように時々散水します。 写真は、芽が出るまでの間、種が雨で流されないように、数cm浮かして乳白色のPP板を被せたところです。最初、レンガ表面から約1cm浮かせた状態で被せたところ、通気が悪くなり、中央部分が遅く発育してしまいした。 |
 |
約1週間で、レンガ表面まで伸びました。本当は、ここで背の高さはストップして、びっしりと横に殖えてくれるとありがたいのですが。 (目土の深さについて) 種を被せ終わった目土の深さは、深すぎても浅すぎてもまずいようです。 レンガの表面から1cm下がり程度にすると、芝生をレンガ表面で刈り込んでも、芝生の背は1cmということになり、最適かと思います。 成長したら芝刈機で時々刈ってやる必要がありますが、負けずにいつまで刈り続けられるかが問題です。 |
 |
この上の写真の奥に写っている芝生で、種蒔き後、半月を経過したものです。生育は順調でしたが、目土を浅くしたまま種を蒔いたため、芝を刈ると丸坊主になりそうなので、失敗でした。 考える前に手が動いているので、失敗の連続です。 |
 |
今のうちに、失敗した芝生を引き抜いて、深く植えなおすことにしました。 なんと、半月程度で根は5cmくらいまで伸びていました。これ以上放置しておくと、レンガの裏側まで根が伸びて、引き抜けなくなりそうです。 当然ですが、移植するよりも一面に直播きをする方が、断然速いですね。 |
 |
右上の苗を、目地の砂を低くしてから、レンガの交差点にだけ移植してみました。 これで自然に広がってくれれば、目的達成!!ということになりますが…。 この芝は、ホームセンターで買ったケンタッキー・ブルー・グラスという、タフな牧草芝です。 ゴルフ場においては、主にラフや法面に使うもので、成長すると膝くらいまで伸びるそうです。放置するとたちまちレンガが埋もれて見えなくなります。 最初、ここに使う芝は、グリーンに使うベントグラスを、と思ったのですが、病気に弱くて管理が難しいことと、種が高価なので不採用としました。ということで、芽が出揃ったのですが、残酷ながらも除草剤を散布してすべて枯らしてしまいました。 |
 |
芝生の作業とは別に、露地にあった砂ゴケを剥がし、試しに植えてみました。 しかし、ちょっと黄色みを帯びており、軽い感じの色になるため、一旦移植しましたが、全部引き抜きました。 次に見つけたコケは、色合いが良いため植えてみました。このコケは通行の頻繁な歩道のレンガの目地にでもビッシリと繁殖するハリコガネの仲間です。今後はこれ一筋で行くつもりです。 しかしコケの成長は極めて遅く、なかなか簡単に目地が緑に変わってくれそうもありません。 でも、コケなら除草剤を散布しても平気だし、芝生のようにレンガ表面より高く伸びてしまうこともなさそうなので、ベストなようです。 最初の頃に敷いたレンガの表面には、色んな汚れが付いて、風合い?が出てきました。目をこらして見ると、なんとハリコガネの仲間らしきコケが、あちこちに自然に生え始めているではありませんか。「今までのナヤミ?は何だったんだ」と苦笑い。 もう、これで私のレンガの緑化対策は打ち切りました。 何年掛かるか知れませんが、静かに全部の目地が緑色に染まってくれるまで、じっくりと待つことにしました。これが結論です。 |
 |
木の根本に張ってある芝が、だんだん四方のレンガ目地に広がってきました('07.9.16現在)。芝生の成長は早く、無精な私には手入れができません。 そこで右の写真のように、芝が広がらないように、小さな仕切り板を埋め込むことにしました。 まず目地の芝を剥ぎ取る作業から始めますが、このくらいまで伸びると、根の多くはレンガの下にまで伸びていました。 解っていたことですから、はじめから埋めておけば良かったと、しきりに後悔です。 写真は円周の半分近くの芝を除去し終わったところです。 |
 |
レンガの厚さ程度の仕切り板を、レンガ正面より1㎝程度飛び出して埋め込みました。 仕切りの材料には、切り裂いたサニーホースを使いました。放っておけば乗り越えてくるでしょうが、板の下をくぐって発芽するものか疑問です。 |