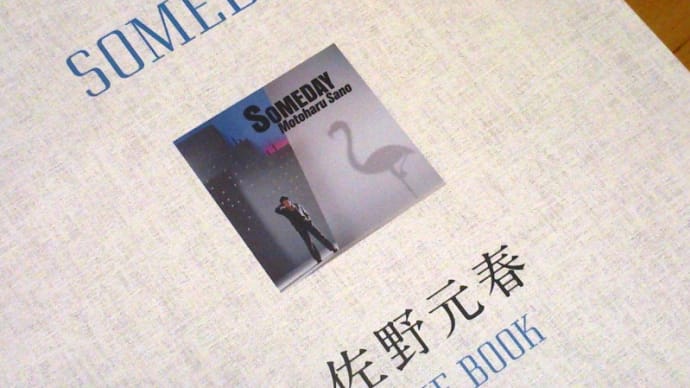
A's Gift
ことさらに大仰に言えば、 僕の人生の僥倖のひとつは、 多感なころ、16歳のとき、 佐野元春の...

一汁三菜
ユネスコ無形文化遺産に 「和食(日本人の伝統的な食文化)」が登録された。 むろん日本人とし...

狂想曲
今年は尾崎豊がデビューして30周年の節目に当たる年らしい。 デビュー記念日の12月1日、...

飽和状態
今月は、ブログの更新が滞ってる。 仕事が忙しいというのは言い訳に過ぎない。 四六時中、仕...

先輩後輩
夕べの酒は格別だった。 青年会議所(JC)の先輩後輩との飲み事。 気が置けない友人との時間は...

仕事納め雑感
表向きの仕事納めは28日の土曜日だったのだけど、 残務処理やら月末月初の資金繰りやらで、 ...
最近の記事
カテゴリー
- 旅行記(32)
- 桐箱ブログ(21)
- インポート(1)
- ギャンブル(1)
- まちづくり(130)
- 写真(42)
- オランダ・コラム(4)
- 音楽(23)
- テレビ番組(148)
- アート・文化(75)
- 佐野元春(76)
- うんちく・小ネタ(272)
- アニメ・コミック・ゲーム(71)
- 本と雑誌(12)
- 社会・経済(9)
- ブログ(49)
- 日記(0)
- 学問(13)
- 映画(9)
- 食・レシピ(18)
- 健康・病気(61)
- 国際・政治(54)
- 青年会議所(22)
- まち歩き(260)
- 悩み(52)
- ニュース(156)
- スポーツ(152)
- 日記・エッセイ・コラム(184)
- コスメ・ファッション(34)
- デジタル・インターネット(101)
- 旅行(9)
- グルメ(5)
バックナンバー
人気記事










