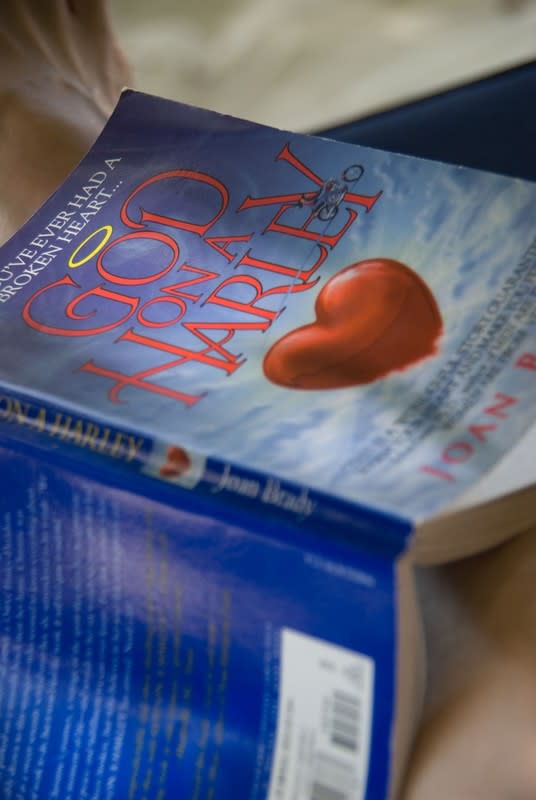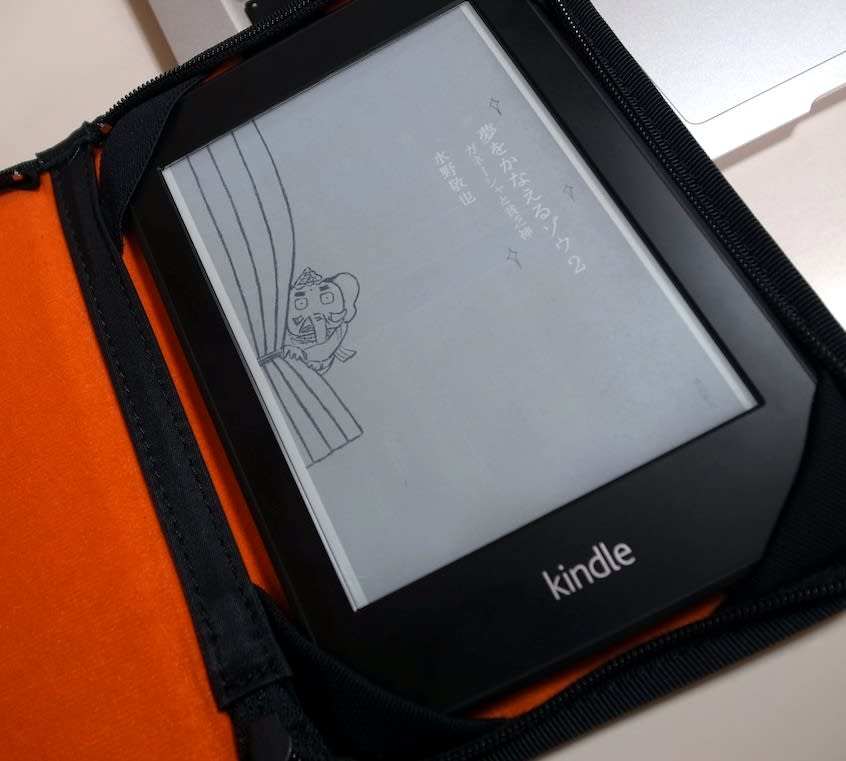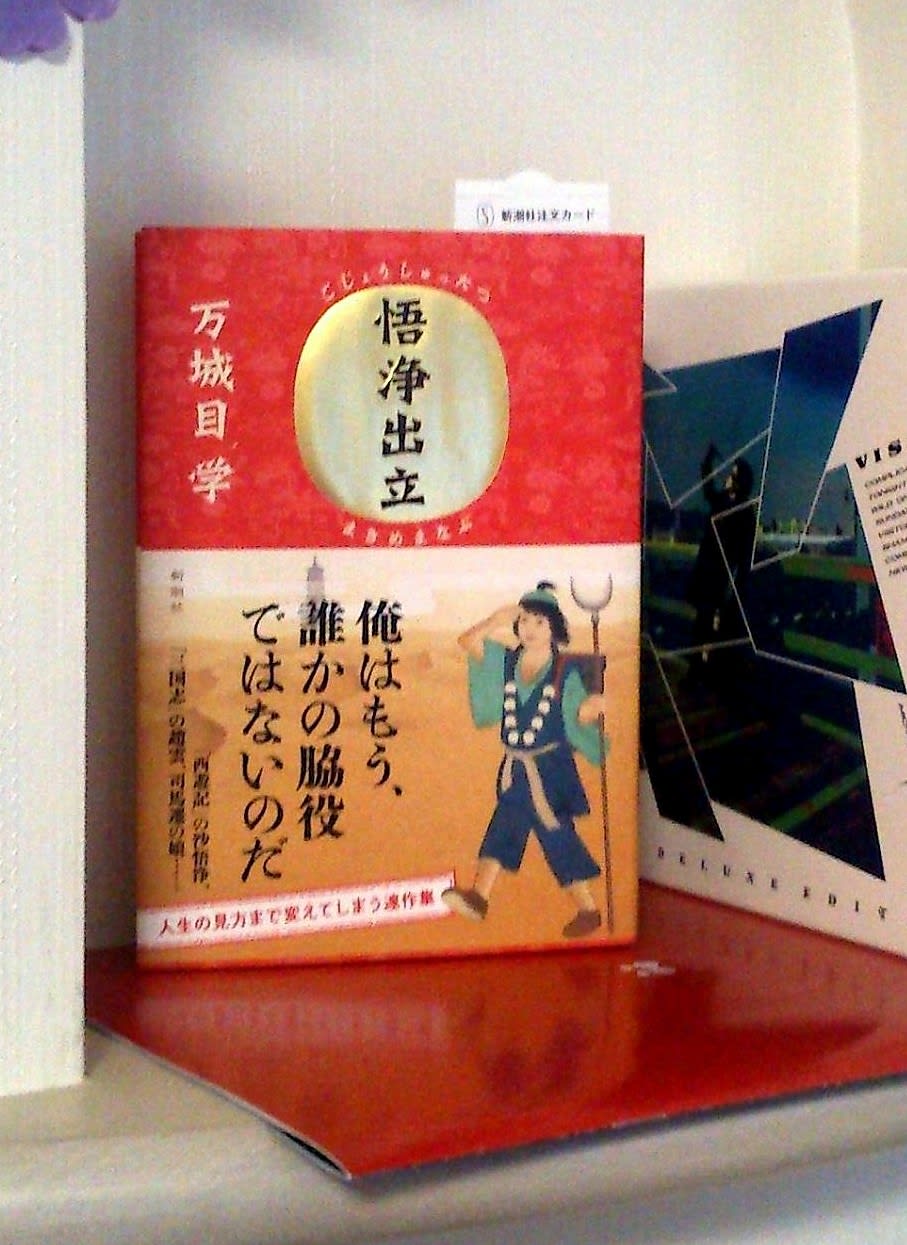若いころは歴史小説ばかり、
若いころは歴史小説ばかり、とりわけ司馬遼太郎作品を好んで読んでいた。
日本史好きということに加えて、
父親の影響が大きかったのかな?
家の書庫には歴史小説がずらりと並んでいた。
40歳を超えたあたりから、
他のジャンルも読み漁るようになった。
ある時期は、福井晴敏の作品ばかり読んでいた。
福井氏とは年齢がちかいから、
ガキのころ、同じような景色を見て育ったんだと思う。
読んでて、すごく共感できるんだよな。
『亡国のイージス』で知られる氏だが、
最近ではガンダム作品に深くコミットしている。
実際、彼自身、
自分は小説家ではなくアニメ作家だと規定しているらしい。
彼のガンダム作品は好きなんだけど、
もうちょい小説に軸足を置いてほしいんだよね。