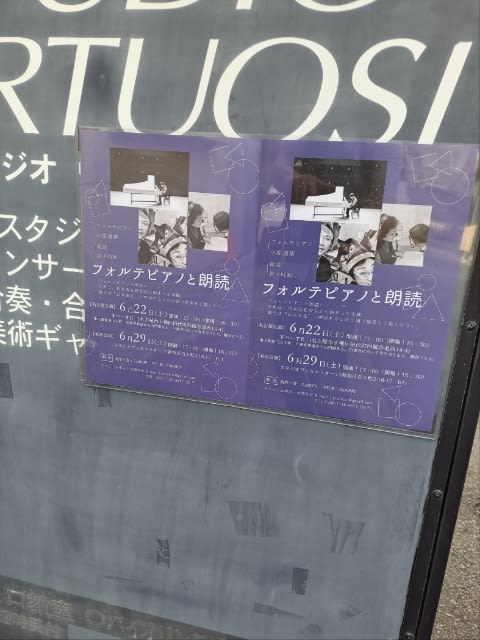

フォルテピアノ(レプリカではなく1817年のオリジナル!)と朗読によるコンサート。演奏は小原道雄さん。朗読は岩下時和さん。
感想としてはただただ楽しかった!色々な種類の「面白い」を味わったような感覚で、あっという間の2時間でした。
曲目も思わずニヤリとしてしまう選曲。特に1817年製の楽器でクレメンティ、ハイドンを聴けるというのはそれだけでワクワクです。今日聴かれるクレメンティとは違う、長調の優雅さや短調の耽美さはモダンピアノでは味わうことの難しい響き。それだけでも面白いのに、朗読とセット。
朗読→演奏という感じなのかなぁと思っていたのですが、朗読に合わせて演奏することもあり、その後にソロという流れでした。この朗読と合わせる、というのがすごく良かったのです。と言いますのも、普通であればBGMになってしまうか、逆に少し邪魔なったりしてしまうようなものですが、演奏が朗読の内容をぐっと引き出すのです。BGMではなく朗読のその場面をよりリアルに感じられるようになりました。そればかりは体感していただかないと伝わりにくいのですが💦
前半の最後はバッハのフランス組曲6番からアルマンド。想像しにくいかもしれませんが、アルマンドに朗読を乗せるのです。演奏前に「実験的」と話されていましたが、すでに確立されたような内容でした。これも聴いていただくしかないのですが(笑)
後半は笑える内容も。笑えるお話に合わせた選曲が実にピッタリで、BGMにもなるというのがまた面白かったです。
最後のお話は一番長く、他とは違うファンタジーな内容。しかしながら朗読と音楽が一体となりあっという間の時間でした。組み込まれたスカルラッティ、現代ではピアノで華やかなイメージが強いかもしれませんが、お話の影響と楽器の力があってなのか、とても哀愁のある音楽でした。スカルラッティを改めて見直さなければなりませんね。
朗読の会を見に行ったことはありませんでしたが、朗読だけの世界にも興味が芽生えました。
今回とても感動したのは、人の身体と楽器の力のみであれだけの世界が創れるということです。最近ではスクリーンに映像を投影するのもありますが、人の声と演奏というシンプルな構成なのに、その情景は(もちろん人それぞれでしょうが)しっかり浮かぶ。でもスクリーンに写してしまうとそのイメージは限定されてしまうため、自由度が下がってしまうのかもしれません。
終演後、時和さんに第2弾も楽しみにしてますとお伝えいたしました。本当に素晴らしい会でした。準備は大変かもしれませんが、本当に次回が楽しみです。


























※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます