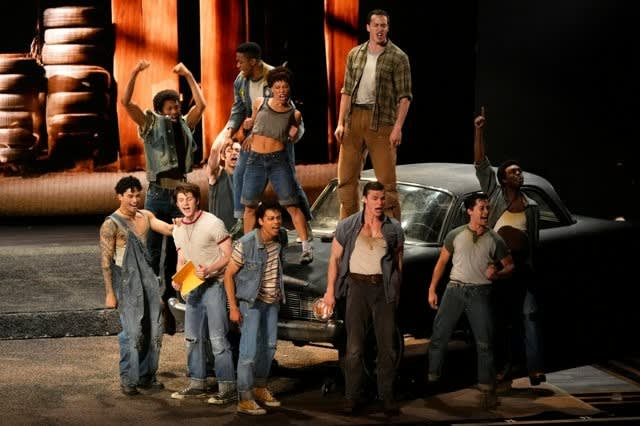3日ほど前、ここへ。

井の頭線で渋谷から2つ目の駒場東大前駅。

2022年11月にも来ていますが、
再訪したのは、
ここ↓に来るため。

↓1年半前と比べると、

店の前の木が大きくなっています。
11時半の開店前に4名行列。

目的は、これを食べるため。

生姜焼定食。
早乙女太一が来た店、ということで、
1年半前、娘の聖地巡礼に付き合いました。
このように、テレビ番組で誘われて来た店の中で、
もう一度、食べたい、と思わせた店の一つ。
大判の豚ロース肉を豪快に焼き、



添えたスパゲティも、
焼き汁がからんだキャベツも絶品。
ピーナッツの箸置き。

これを食べる人はいるのでしょうか。
このお店のある商店街は、
駒場東大前商店会といい、
愛称は「駒下」。


狭い道で自動車が最徐行で通ります。


この劇場は、「こまばアゴラ劇場」という小劇場。

昔の写真。

昔、友人の芝居を観に、よく通いました。

どうやら、5月末で閉館になったようです。
芸術総監督の平田オリザさんの挨拶文。

もともと、こまばアゴラ劇場は、
私の父平田穂生が銀行から多額の借金をして開業したものでした。
その後、私が23歳で支配人に就任し、
多くの方々のご支援もあり、
どうにかここまで経営を続けてきました。
しかしながら、現在も負債は多く残っており、
私の人生の残り時間を考えると、
健康上など不測の事態が起きた場合に、
債務不履行の状態に陥る懸念があります。
そこで、債務超過に至っていない今の段階で資産を処分することといたしました。

何だか寂しいですね。
商店街からこの階段を上り、


この踏切を越えたところに、

通称「矢内原門」(やないはらもん)があります。

いや、「ありました」ですね。

東大駒場キャンパスは、
↓の正門の他に、

↓のように、小さな通用口があります。

矢内原門もその一つで、
駒場商店会方面へ行くのに便利な位置に開けられた
幅1メートルほどの通用口。
学内にあった学生寮の学生たちがよく出入りしていました。
矢内原忠雄、後の第16代東大総長が
東京大学教養学部長の時代に、
学生の試験ボイコットで、
正門がピケにより通行できなくなった折、
学部長が自ら生垣を押し分けて通り、
以後公認の通路となったと伝えられています。
また、以前よりの抜け道であったが、
矢内原学部長がピケ対策として
「特別に門以外の場所を通行してよい」
旨の告知を行ったことから学生が公然と通行するに至ったものだとも言われています。
東京大学教養学部の前身である旧制第一高等学校では
正規の門以外は絶対に通らないという
「正門主義」があったこと、
矢内原がその後も学生のストライキ等には厳しい態度を貫き、
ストライキを指導した学生を退学とする
「矢内原三原則」を打ち出した人物であることなども
このエピソードの背景となっているようです。
矢内原門は、
私が学生の頃は、
存在していましたが、
後の駒場キャンパスの整備事業で、
柵の位置が大きく移動したため、消滅し、
石碑が残るのみとなりました。

現在、跡地付近は「矢内原公園」と呼ばれる小公園となっています。


このあたりは、緑が豊かで、
都内にいることを忘れさせてくれます。





これが学内のメインストリート。

緑が一杯です。
立て看板は政治的な色はなし。

ここは、当時、学生に占拠された教務課のあったところ。

私は右の高い所に立って、
占拠学生とやりあいました。
東大駒場キャンパスについては、
1年半前にブログで触れていますので、
今回はこれくらいにします。
興味のある方は、2022年11月13日のブログをご覧ください。
その後、渋谷に出て、映画を一本観ましたが、
途中で見た光景。

何だと思います?
解体中のBunkamuraです。

これも寂しい景色ですね。